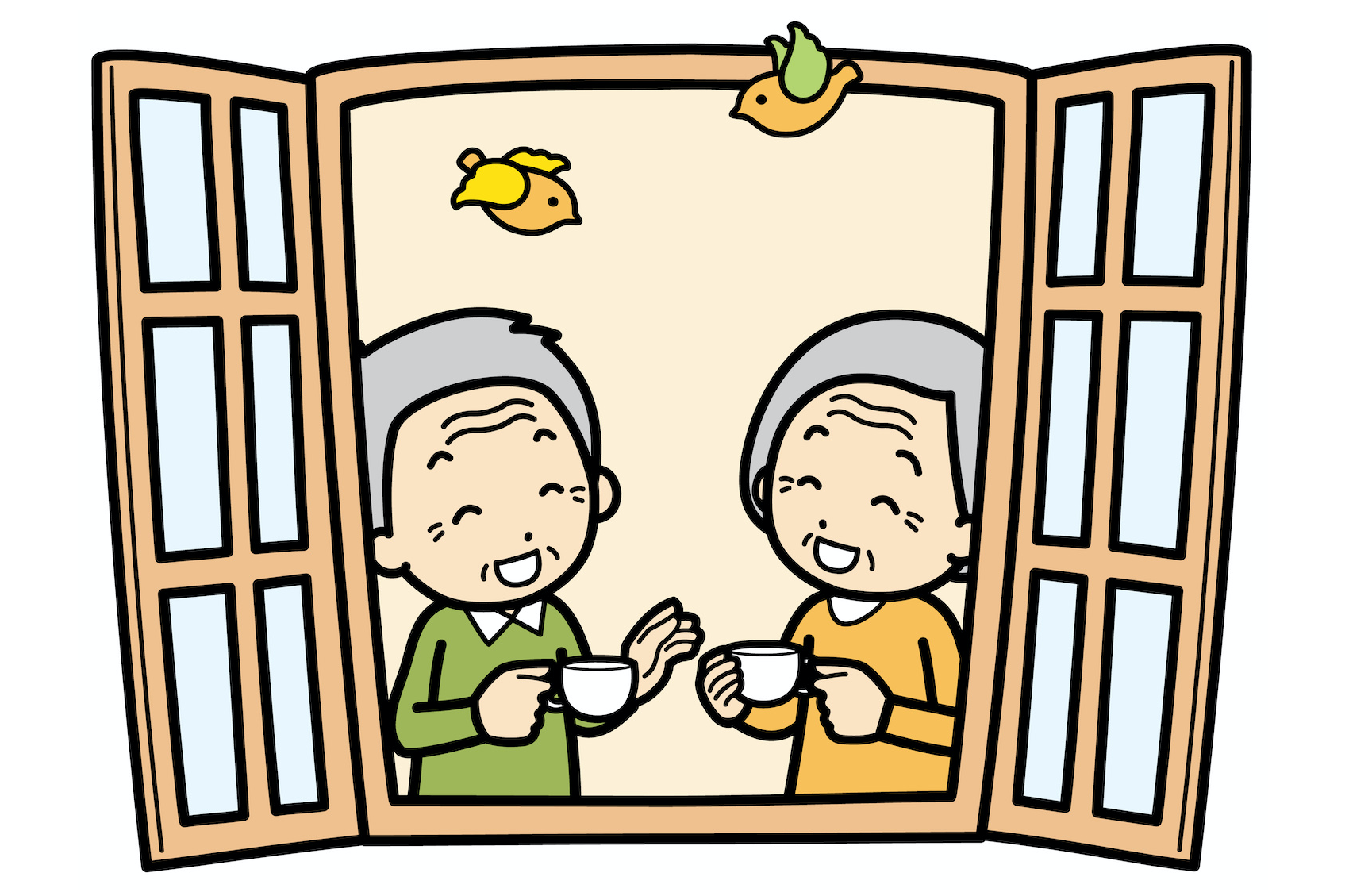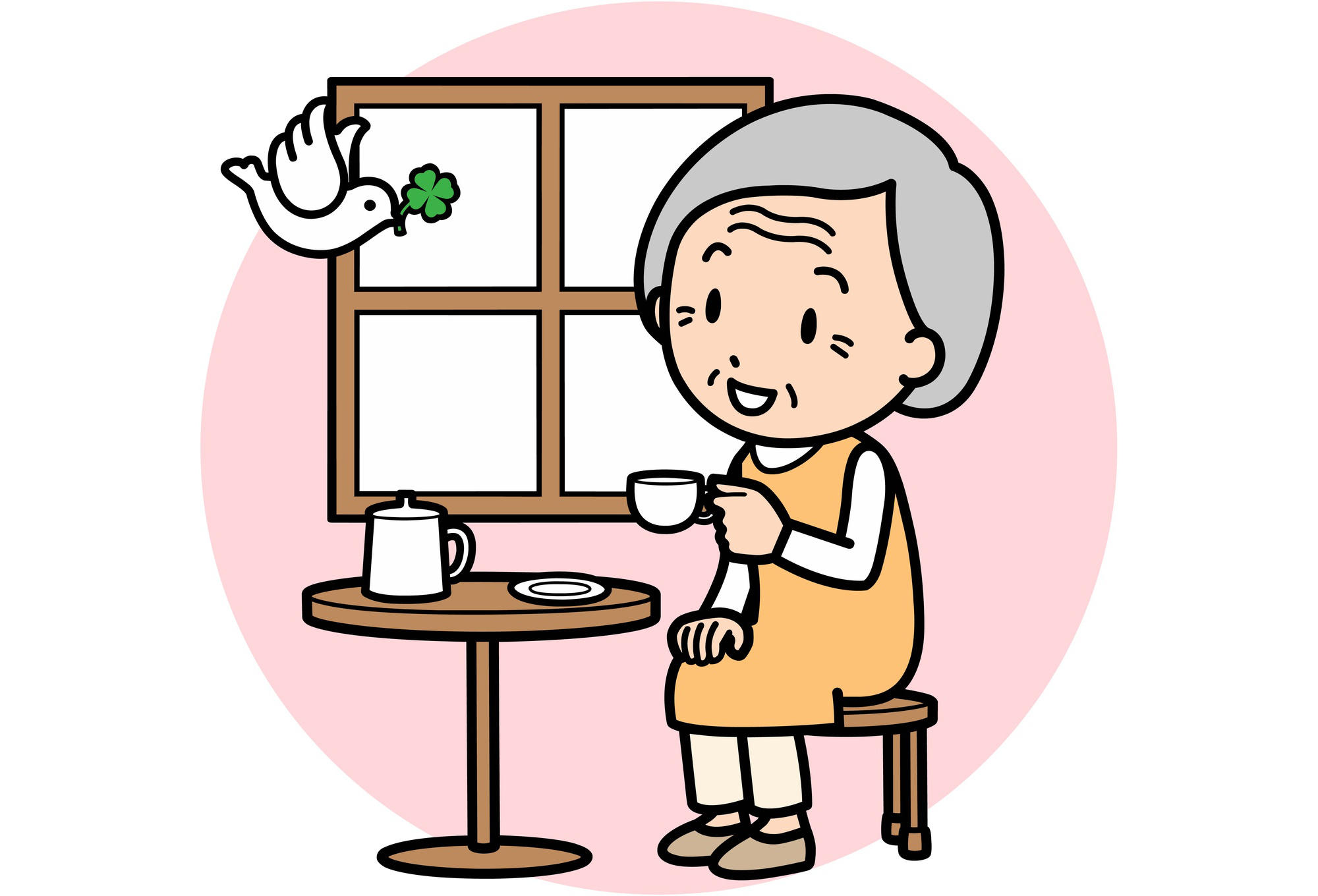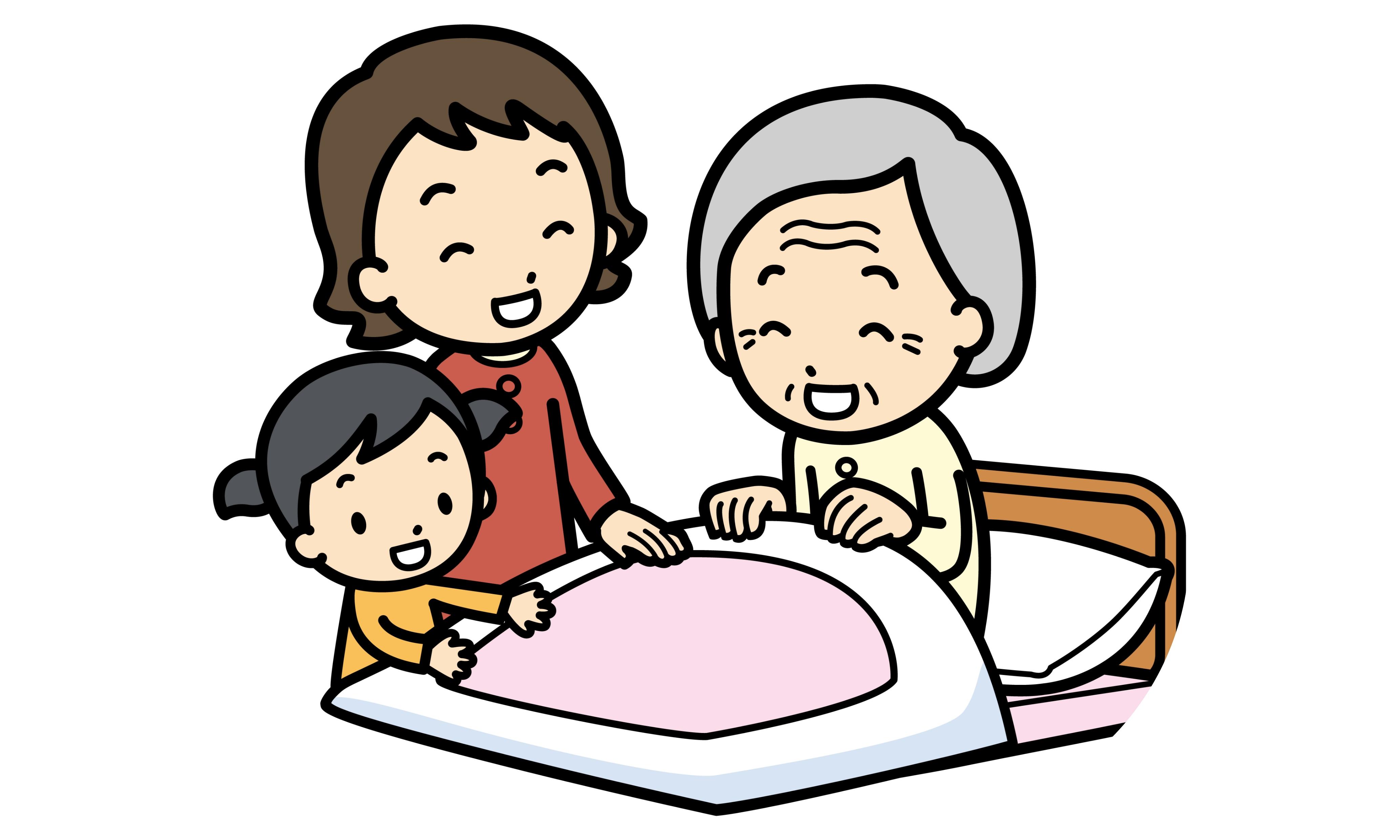дїЛи≠ЈгБЃдЊњеИ©еЄЦгГИгГГгГЧгБЄжИїгВЛ
йЂШ隥гБЃжЦєеРСгБСдљПгБЊгБДгБЃз®Ѓй°ЮгБ®еЃЙењГгБЧгБ¶йБОгБФгБЫгВЛдљПгБЊгБДйБЄгБ≥гБЃгГЭгВ§гГ≥гГИ
жЧ•жЬђгБЂгБѓгАМдїЛи≠ЈдњЭйЩЇеИґеЇ¶пЉИйЂШ隥иАЕгБ™гБ©гБЃдїЛи≠ЈгВТз§ЊдЉЪеЕ®дљУгБІжФѓгБИеРИгБЖдїХзµДгБњпЉЙгАНгБМгБВгВКгАБжФѓжПігВДдїЛи≠ЈгБМењЕи¶БгБЂгБ™гБ£гБ¶гВВгАБдљПгБњжЕ£гВМгБЯгБФиЗ™еЃЕгБІењЕи¶БгБ™дїЛи≠ЈгВµгГЉгГУгВєгВТеПЧгБСгБ™гБМгВЙжЪЃгВЙгБЧзґЪгБСгВЛгБУгБ®гВВеПѓиГљгБІгБЩгАВгБЧгБЛгБЧгАБгБХгБЊгБЦгБЊгБ™дЇЛжГЕгБЂгВИгВКиЗ™еЃЕгБІгБЃзФЯжіїгБМйЫ£гБЧгБПгБ™гВЛгБУгБ®гБМгБВгВКгБЊгБЩгАВ
гБЊгБЯгАБгБКеЕГж∞ЧгБ™гБЖгБ°гБЛгВЙиАБдЇЇгГЫгГЉгГ†гБ™гБ©гБЂдљПгБњжЫњгБИгБЯгБДгБ®гБКиАГгБИгБЃжЦєгВВгБДгВЙгБ£гБЧгВГгВЛгБІгБЧгВЗгБЖгАВдїКеЫЮгБѓгАБгБЭгБЃгВИгБЖгБ™е†іеРИгБЂеЕ•е±ЕгБІгБНгВЛйЂШ隥иАЕеРСгБСдљПгБЊгБДгБЂгБ§гБДгБ¶гБЊгБ®гВБгБЊгБЧгБЯгАВ
зЫЃжђ°
- гАР1гАСйЂШ隥гБЃжЦєеРСгБСдљПгБЊгБДгБЃз®Ѓй°Ю
- гАР2гАСйЂШ隥гБЃжЦєеРСгБСдљПгБЊгБДгБЃгВµгГЉгГУгВє
- гАР3гАСе±ЕдљПгБЂењЕи¶БгБ™и≤їзФ®
- гАР4гАСжЬЙжЦЩиАБдЇЇгГЫгГЉгГ†гБ®гБѓ
- гАР5гАСгВµгГЉгГУгВєдїШгБНйЂШ隥иАЕеРСгБСдљПеЃЕпЉИгВµйЂШдљПпЉЙгБ®гБѓ
- гАР6гАСзЙєеИ•й§Ки≠ЈиАБдЇЇгГЫгГЉгГ†пЉИдїЛи≠ЈиАБдЇЇз¶Пз•ЙжЦљи®≠пЉЙгБ®гБѓ
- гАР7гАСгБЭгБЃдїЦгБЃйЂШ隥иАЕеРСгБСдљПгБЊгБД
- гАР8гАСйЂШ隥гБЃжЦєеРСгБСдљПгБЊгБДгВТйБЄгБґгБ®гБНгБЃгГЭгВ§гГ≥гГИ
1.йЂШ隥гБЃжЦєеРСгБСдљПгБЊгБДгБЃз®Ѓй°Ю

йЂШ隥гБЃжЦєеРСгБСгБЃдљПгБЊгБДгБЂгБѓгАБгАМжЬЙжЦЩиАБдЇЇгГЫгГЉгГ†гАНгАБгАМгВµгГЉгГУгВєдїШгБНйЂШ隥иАЕеРСгБСдљПеЃЕпЉИгВµйЂШдљПпЉЙгАНгАБгАМзЙєеИ•й§Ки≠ЈиАБдЇЇгГЫгГЉгГ†пЉИдїЛи≠ЈиАБдЇЇз¶Пз•ЙжЦљи®≠пЉЙгАНгБ™гБ©гБМгБВгВКгБЊгБЩгАВгВµгГЉгГУгВєгБЃеЖЕеЃєгВДжПРдЊЫжЦєж≥ХгАБи®≠еВЩгАБи≤їзФ®гАБеЕ•е±ЕжЭ°дїґгБ™гБ©гБѓгАБжЦљи®≠гБЂгВИгБ£гБ¶зХ∞гБ™гВКгБЊгБЩгАВ
| жЦљи®≠гБЃз®Ѓй°Ю | дЄїгБ™зЙєеЊі |
|---|---|
| жЬЙжЦЩиАБдЇЇгГЫгГЉгГ† | е§ІгБНгБПеИЖгБСгБ¶гАМдїЛи≠ЈдїШжЬЙжЦЩиАБдЇЇгГЫгГЉгГ†гАНгАМдљПеЃЕеЮЛжЬЙжЦЩиАБдЇЇгГЫгГЉгГ†гАНгАМеБ•еЇЈеЮЛжЬЙжЦЩиАБдЇЇгГЫгГЉгГ†гАНгБЃ3гБ§гБМгБВгВКгБЊгБЩгАВеЕ•е±ЕжЭ°дїґгБѓгГЫгГЉгГ†гБЂгВИгБ£гБ¶зХ∞гБ™гВКгБЊгБЩгАВ |
| гВµгГЉгГУгВєдїШгБНйЂШ隥иАЕеРСгБСдљПеЃЕ | гАМйЂШ隥иАЕдљПгБЊгБДж≥ХгАНгБЃжФєж≠£гБЂгВИгВКеЙµи®≠гБХгВМгБЯгГРгГ™гВҐгГХгГ™гГЉжІЛйА†гБЃдљПгБЊгБДгБІгБЩгАВ |
| зЙєеИ•й§Ки≠ЈиАБдЇЇгГЫгГЉгГ† | жѓФиЉГзЪДеЃЙдЊ°гБІеЕ•е±ЕгБІгБНгВЛеЕђзЪДгБ™жЦљи®≠гБІгБЩгАВгБЭгБЃгБЯгВБеЊЕж©ЯиАЕгБМе§ЪгБПгАБжХ∞еєігБЃеЊЕж©ЯгБМењЕи¶БгБ®гБ™гВЛгБУгБ®гВВгБВгВКгБЊгБЩгАВе§ІгБНгБПеИЖгБСгБ¶гАМеЇГеЯЯеЮЛзЙєеИ•й§Ки≠ЈиАБдЇЇгГЫгГЉгГ†гАНгАМеЬ∞еЯЯеѓЖзЭАеЮЛзЙєеИ•й§Ки≠ЈиАБдЇЇгГЫгГЉгГ†гАНгАМеЬ∞еЯЯгВµгГЭгГЉгГИеЮЛзЙєеИ•й§Ки≠ЈиАБдЇЇгГЫгГЉгГ†гАНгБЃ3гБ§гБМгБВгВКгБЊгБЩгАВ |
гБЭгБЃдїЦгБЃдљПгБЊгБД
- гГїгВ±гВҐгГПгВ¶гВє
- гГїгВ∞гГЂгГЉгГЧгГЫгГЉгГ†пЉИи™НзЯ•зЧЗеѓЊењЬеЮЛеЕ±еРМзФЯжіїдїЛи≠ЈпЉЙ гГїдїЛи≠ЈеМїзЩВйЩҐгААгБ™гБ©
1.йЂШ隥гБЃжЦєеРСгБСдљПгБЊгБДгБЃгВµгГЉгГУгВє
| жЦљи®≠гБЃз®Ѓй°Ю | еПЧгБСгВЙгВМгВЛгВµгГЉгГУгВє |
|---|---|
| жЬЙжЦЩиАБдЇЇгГЫгГЉгГ† | гАМй£ЯдЇЛгБЃжПРдЊЫгАНгАМдїЛи≠ЈпЉИеЕ•жµігГїжОТгБЫгБ§гГїй£ЯдЇЛпЉЙгБЃжПРдЊЫгАНгАМжіЧжњѓгВДжОГйЩ§з≠ЙгБЃеЃґдЇЛгАНгАМеБ•еЇЈзЃ°зРЖгАНгБЃгВµгГЉгГУгВєгБЃгБЖгБ°гАБ1гБ§дї•дЄКгВТеПЧгБСгВЛгБУгБ®гБМгБІгБНгБЊгБЩгАВ |
| гВµгГЉгГУгВєдїШгБНйЂШ隥иАЕеРСгБСдљПеЃЕ | гАМеЃЙеж祯и™НгАНгБ®гАМзФЯжіїзЫЄиЂЗгАНгБЃгВµгГЉгГУгВєгБМењЕгБЪжПРдЊЫгБХгВМгБЊгБЩгАВдїЛи≠ЈдњЭйЩЇгВµгГЉгГУгВєгБѓгАБе§ЦйГ®гБЃдїЛи≠ЈдњЭйЩЇдЇЛж•≠иАЕз≠ЙгБ®е•СзіДгВТзµРгБґгБУгБ®гБІеИ©зФ®гБІгБНгБЊгБЩгАВ |
| зЙєеИ•й§Ки≠ЈиАБдЇЇгГЫгГЉгГ† | дїЛи≠ЈпЉИеЕ•жµігГїжОТгБЫгБ§гГїй£ЯдЇЛгБ™гБ©пЉЙгАБж©ЯиГљи®УзЈігАБзЩВй§КдЄКгБЃгВ±гВҐгБ™гБ©гВТеПЧгБСгВЛгБУгБ®гБМгБІгБНгБЊгБЩгАВ |
3.е±ЕдљПгБЂењЕи¶БгБ™и≤їзФ®
и≤їзФ®гБѓгАБдљПгБЊгБДгБЃз®Ѓй°ЮгАБжПРдЊЫгБХгВМгВЛгВµгГЉгГУгВєеЖЕеЃєгАБе±ЕеЃ§гВДеЕ±зФ®йГ®еИЖгБЃи®≠еВЩгБ™гБ©гБЂгВИгБ£гБ¶зХ∞гБ™гВКгБЊгБЩгАВ
ењЕи¶БгБ™и≤їзФ®
- гГїе±ЕеЃ§гВДеЕ±зФ®йГ®еИЖгВТеИ©зФ®гБЩгВЛгБЯгВБгБЃеЃґи≥Г
- гГїеЕ±зФ®йГ®еИЖгБЃзґ≠жМБгГїзЃ°зРЖгБЃгБЯгВБгБЂењЕи¶БгБ™еЕ±зЫКи≤їпЉИзЃ°зРЖи≤їпЉЙ
- гГїж∞ійБУеИ©зФ®жЦЩгВДйЫїж∞ЧеИ©зФ®жЦЩгБ™гБ©гБЃж∞іеЕЙзЖ±и≤ї
- гГїй£ЯдЇЛгБЃжПРдЊЫгВТеПЧгБСгВЛгБЯгВБгБЂењЕи¶БгБ™й£Яи≤ї
- гГїдїЛи≠ЈгАБзФЯжіїжФѓжПігАБеЃґдЇЛжПіеК©гБ™гБ©гВТеПЧгБСгВЛгБЯгВБгБЃгВµгГЉгГУгВєеИ©зФ®жЦЩ гБ™гБ©
вАї еЕ•е±ЕжЩВгБЂгАМжХЈйЗСгАНгБЃжФѓжЙХгБДгВТж±ВгВБгВЛгБ®гБУгВНгВВгБВгВКгБЊгБЩгАВ
4.жЬЙжЦЩиАБдЇЇгГЫгГЉгГ†гБ®гБѓ

жЬЙжЦЩиАБдЇЇгГЫгГЉгГ†гБѓгАБгАМиАБдЇЇз¶Пз•Йж≥Х зђђ29жЭ°гАНгБЂи¶ПеЃЪгБХгВМгБЯйЂШ隥гБЃжЦєеРСгБСгБЃдљПгБЊгБДгБІгБЩгАВйГљйБУеЇЬзЬМз≠ЙгБЄе±КгБСеЗЇгВЛгБУгБ®гБІи®≠зљЃгБМеПѓиГљгБ™жЦљи®≠гБІгАБжЬЙжЦЩиАБдЇЇгГЫгГЉгГ†гБЂеѓЊгБЩгВЛжМЗе∞ОгГїзЫ£зЭ£гВВйГљйБУеЇЬзЬМз≠ЙгБМи°МгБ£гБ¶гБДгБЊгБЩгАВ
еЕ•е±ЕжЭ°дїґ
еЕ•е±ЕгБІгБНгВЛ庳隥гАБи¶БдїЛи≠ЈеЇ¶гБ™гБ©гБЃи¶БдїґгБѓгАБгГЫгГЉгГ†гБЂгВИгБ£гБ¶зХ∞гБ™гВКгБЊгБЩгАВ
жЬЙжЦЩиАБдЇЇгГЫгГЉгГ†гБЃз®Ѓй°Ю
жЬЙжЦЩиАБдЇЇгГЫгГЉгГ†гБЂгБѓгАБгАМдїЛи≠ЈдїШжЬЙжЦЩиАБдЇЇгГЫгГЉгГ†гАНгАМдљПеЃЕеЮЛжЬЙжЦЩиАБдЇЇгГЫгГЉгГ†гАНгАМеБ•еЇЈеЮЛжЬЙжЦЩиАБдЇЇгГЫгГЉгГ†гАНгБЃ3гБ§гБМгБВгВКгБЊгБЩгАВ
гГїдїЛи≠ЈдїШжЬЙжЦЩиАБдЇЇгГЫгГЉгГ†дїЛи≠ЈгБ™гБ©гБЃгВµгГЉгГУгВєгБМдїШгБДгБЯжЬЙжЦЩиАБдЇЇгГЫгГЉгГ†гБІгБЩгАВ
дїЛи≠ЈгБМењЕи¶БгБЂгБ™гБ£гБ¶гВВгАБгГЫгГЉгГ†гБМжПРдЊЫгБЩгВЛгАМзЙєеЃЪжЦљи®≠еЕ•е±ЕиАЕзФЯжіїдїЛи≠ЈгАНгБ®гБДгБЖдїЛи≠ЈдњЭйЩЇгВµгГЉгГУгВєгВТеИ©зФ®гБЧгБ™гБМгВЙгАБжЪЃгВЙгБЧзґЪгБСгВЛгБУгБ®гБМгБІгБНгБЊгБЩгАВ
еЇГеСКгБ™гБ©гБЂгАМдїЛи≠ЈдїШгБНгАНгВДгАМгВ±гВҐдїШгБНгАНгБ®и°®з§ЇгБЩгВЛгБУгБ®гБМгБІгБНгВЛгБЃгБѓгАБгАМзЙєеЃЪжЦљи®≠еЕ•е±ЕиАЕзФЯжіїдїЛи≠ЈгАНгБЃжМЗеЃЪгВТеПЧгБСгБ¶гБДгВЛжЬЙжЦЩиАБдЇЇгГЫгГЉгГ†гБЃгБњгБІгБЩгАВ
дїЛи≠ЈдїШжЬЙжЦЩиАБдЇЇгГЫгГЉгГ†гБѓгАБгБХгВЙгБЂгАМдЄАиИђеЮЛзЙєеЃЪжЦљи®≠еЕ•е±ЕиАЕзФЯжіїдїЛи≠ЈгАНгБ®гАМе§ЦйГ®гВµгГЉгГУгВєеИ©зФ®еЮЛзЙєеЃЪжЦљи®≠еЕ•е±ЕиАЕзФЯжіїдїЛи≠ЈгАНгБЂеИЖгБЛгВМгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ
| дЄАиИђеЮЛзЙєеЃЪжЦљи®≠еЕ•е±ЕиАЕзФЯжіїдїЛи≠Ј | дїЛи≠ЈгВµгГЉгГУгВєгБѓгГЫгГЉгГ†гБЃиБЈеУ°гБМжПРдЊЫгБЧгБЊгБЩгАВ |
| е§ЦйГ®гВµгГЉгГУгВєеИ©зФ®еЮЛзЙєеЃЪжЦљи®≠еЕ•е±ЕиАЕзФЯжіїдїЛи≠Ј | дїЛи≠ЈгВµгГЉгГУгВєгБѓеІФи®ЧеЕИгБЃдїЛи≠ЈгВµгГЉгГУгВєдЇЛж•≠жЙАгБМжПРдЊЫгБЧгБЊгБЩгАВеЃЙеж祯и™НгВДи®ИзФїдљЬжИРгБ™гБ©гБѓгГЫгГЉгГ†гБЃиБЈеУ°гБМи°МгБДгБЊгБЩгАВ |
зФЯжіїжФѓжПігБ™гБ©гБЃгВµгГЉгГУгВєгБМдїШгБДгБЯжЬЙжЦЩиАБдЇЇгГЫгГЉгГ†гБІгБЩгАВдїЛи≠ЈгБМењЕи¶БгБЂгБ™гБ£гБЯе†іеРИгБѓгАБеЕ•е±ЕиАЕгБФиЗ™иЇЂгБЃйБЄжКЮгБЂгВИгВКгАБгГЗгВ§гВµгГЉгГУгВєгВДи®™еХПдїЛи≠ЈгБ™гБ©гБЃдїЛи≠ЈгВµгГЉгГУгВєгВТеИ©зФ®гБЧгБ™гБМгВЙжЪЃгВЙгБЧзґЪгБСгВЛгБУгБ®гБМеПѓиГљгБІгБЩгАВ
гГїеБ•еЇЈеЮЛжЬЙжЦЩиАБдЇЇгГЫгГЉгГ†й£ЯдЇЛгБ™гБ©гБЃгВµгГЉгГУгВєгБМдїШгБДгБЯжЬЙжЦЩиАБдЇЇгГЫгГЉгГ†гБІгБЩгАВ
гБЭгБЃеРНеЙНгБЃгБ®гБКгВКгАБиЗ™зЂЛгБЧгБЯйЂШ隥иАЕгВТеѓЊи±°гБ®гБЧгБ¶гБДгВЛгБЯгВБгАБдїЛи≠ЈгБМењЕи¶БгБЂгБ™гБ£гБЯе†іеРИгБѓгАБе•СзіДгВТиІ£йЩ§гБЧгБ¶йААеОїгБЩгВЛгБУгБ®гБЂгБ™гВКгБЊгБЩгАВ
е•СзіД嚥жЕЛ
| еИ©зФ®ж®©жЦєеЉП | е±ЕдљПйГ®еИЖгБ®гВµгГЉгГУгВєйГ®еИЖпЉИдїЛи≠ЈгВДзФЯжіїжФѓжПігБ™гБ©пЉЙгБЃе•СзіДгБМдЄАдљУгБ®гБ™гБ£гБ¶гБДгВЛжЦєеЉПгБІгБЩгАВ |
| еїЇзЙ©и≥Ги≤ЄеАЯжЦєеЉП | и≥Ги≤ЄдљПеЃЕгБЂгБКгБСгВЛе±ЕдљПгБЃе•СзіД嚥жЕЛгБІгАБе±ЕдљПйГ®еИЖгБ®гВµгГЉгГУгВєйГ®еИЖпЉИдїЛи≠ЈгВДзФЯжіїжФѓжПігБ™гБ©пЉЙгБЃе•СзіДгБМеИ•гАЕгБЂгБ™гБ£гБ¶гБДгВЛжЦєеЉПгБІгБЩгАВ |
| зµВиЇЂеїЇзЙ©и≥Ги≤ЄеАЯжЦєеЉП | гАМеїЇзЙ©и≥Ги≤ЄеАЯе•СзіДгАНгБЃзЙєеИ•гБ™й°ЮеЮЛгБІгАБйГљйБУеЇЬзЬМзЯ•дЇЛз≠ЙгБЛгВЙйЂШ隥иАЕгБЃе±ЕдљПгБЃеЃЙеЃЪ祯дњЭгБЂйЦҐгБЩгВЛж≥ХеЊЛгБЃи¶ПеЃЪгБЂеЯЇгБ•гБПзµВиЇЂеїЇзЙ©и≥Ги≤ЄеАЯдЇЛж•≠гБЃи™НеПѓгВТеПЧгБСгБЯгВВгБЃгБІгБЩгАВзµВиЇЂгБЂгВПгБЯгВКе±ЕдљПгБЩгВЛгБУгБ®гБМгБІгБНгБЊгБЩгАВ |
еИ©зФ®жЦЩгБЃжФѓжЙХгБДжЦєеЉП
| еЕ®й°НеЙНжЙХгБДжЦєеЉП | зµВиЇЂгБЂгВПгБЯгБ£гБ¶ењЕи¶БгБ™еЃґи≥ГгГїгВµгГЉгГУгВєи≤їзФ®гБЃеЕ®йГ®гВТгАМеЙНжЙХйЗСгАНгБ®гБЧгБ¶дЄАжЛђгБІжФѓжЙХгБЖжЦєеЉП |
| дЄАйГ®еЙНжЙХгБДгГїдЄАйГ®жЬИжЙХгБДжЦєеЉП | зµВиЇЂгБЂгВПгБЯгБ£гБ¶ењЕи¶БгБ™еЃґи≥ГгГїгВµгГЉгГУгВєи≤їзФ®гБЃдЄАйГ®гВТеЙНжЙХгБДгБЧгАБгБЭгБЃдїЦгБѓжЬИжЙХгБДгБЩгВЛжЦєеЉП |
| жЬИжЙХгБДжЦєеЉП | еЙНжЙХйЗСгБѓжФѓжЙХгВПгБЪгАБеЃґи≥ГгГїгВµгГЉгГУгВєи≤їзФ®гВТжЬИжЙХгБДгБЩгВЛжЦєеЉП |
| йБЄжКЮжЦєеЉП | еЕ•е±ЕиАЕгБМгАМеЕ®й°НеЙНжЙХгБДжЦєеЉПгАНгАМдЄАйГ®еЙНжЙХгБДгГїдЄАйГ®жЬИжЙХгБДжЦєеЉПгАНгАМжЬИжЙХгБДжЦєеЉПгАНгБЃгБДгБЪгВМгБЛгВТйБЄжКЮгБІгБНгВЛжЦєеЉПгАВ |
вЦЉйЦҐйА£и®ШдЇЛпЉЪ
жЬЙжЦЩиАБдЇЇгГЫгГЉгГ†гБ®гБѓпЉЯгБѓгБШгВБгБ¶гБФеЕ•е±ЕгВТгБКиАГгБИгБЃжЦєгБЂељєзЂЛгБ§жГЕ冱гВТгБФзієдїЛ
жЬЙжЦЩиАБдЇЇгГЫгГЉгГ†гБІе§ЦеЗЇгГїе§Цж≥КгБѓгБІгБНгВЛпЉЯе§ЦеЗЇгГїе§Цж≥КгВТеЄМжЬЫгБЩгВЛгБ®гБНгБЂгБѓ
5.гВµгГЉгГУгВєдїШгБНйЂШ隥иАЕеРСгБСдљПеЃЕпЉИгВµйЂШдљПпЉЙгБ®гБѓ
зХ•гБЧгБ¶гАМгВµйЂШдљПгАНгБ®гВВеСЉгБ∞гВМгВЛгВµгГЉгГУгВєдїШгБНйЂШ隥иАЕеРСгБСдљПеЃЕгБѓгАБйЂШ隥иАЕгБМеЃЙењГгБЧгБ¶зФЯжіїгБІгБНгВЛгГРгГ™гВҐгГХгГ™гГЉжІЛйА†гБЃдљПеЃЕгБІгБЩгАВ2011пЉИеє≥жИР23пЉЙеєігБЃгАМйЂШ隥иАЕдљПгБЊгБДж≥ХпЉИйЂШ隥иАЕгБЃе±ЕдљПеЃЙеЃЪ祯дњЭгБЂйЦҐгБЩгВЛж≥ХеЊЛпЉЙгАНгБЃжФєж≠£гБЂгВИгВКеЙµи®≠гБХгВМгБЊгБЧгБЯгАВ
зЩїйМ≤гВДжМЗе∞ОгГїзЫ£зЭ£гБѓгАБйГљйБУеЇЬзЬМгГїжФњдї§еЄВгГїдЄ≠ж†ЄеЄВгБЂгВИгБ£гБ¶и°МгВПгВМгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ
еЕ•е±ЕжЭ°дїґ
жђ°гБЃгБДгБЪгВМгБЛгБЂи©≤ељУгБЩгВЛеНШиЇЂгБЊгБЯгБѓе§Ђе©¶дЄЦеЄѓгБМеѓЊи±°гБІгБЩгАВ
- гГї60ж≠≥дї•дЄКгБЃжЦє
- гГїи¶БдїЛи≠ЈгБЊгБЯгБѓи¶БжФѓжПіи™НеЃЪгВТеПЧгБСгБ¶гБДгВЛ60ж≠≥жЬ™жЇАгБЃжЦє
гВµгГЉгГУгВєдїШгБНйЂШ隥иАЕеРСгБСдљПеЃЕгБЃзЙєеЊі
жЦљи®≠жГЕ冱гГїйБЛеЦґжГЕ冱гБМеЕђйЦЛгБХгВМгБ¶гБДгВЛе∞ВзФ®гВµгВ§гГИгБІи≤їзФ®гВДгВµгГЉгГУгВєгАБеЕ•е±ЕиАЕгБ™гБ©гБЂйЦҐгБЩгВЛжГЕ冱гБМйЦЛз§ЇгБХгВМгБ¶гБДгВЛгБЯгВБгАБеЕ•е±ЕеЄМжЬЫиАЕгБЃгГЛгГЉгВЇгБЂгБВгБ£гБЯдљПгБЊгБДгВТйБЄгБґгБУгБ®гБМеПѓиГљгБІгБЩгАВ
е±ЕдљПгБЃеЃЙеЃЪгБМеЫ≥гВЙгВМгБЯе•СзіДйХЈжЬЯеЕ•йЩҐгВТзРЖзФ±гБЂдЇЛж•≠иАЕгБЛгВЙдЄАжЦєзЪДгБЂиІ£зіДгБІгБНгБ™гБДгБ™гБ©гАБе±ЕдљПгБЃеЃЙеЃЪгБМеЫ≥гВЙгВМгБЯе•СзіДеЖЕеЃєгБЂгБ™гБ£гБ¶гБДгБЊгБЩгАВ
йЂШ隥гБЃжЦєгБЂйЕНжЕЃгБЧгБЯзТ∞еҐГжЙЛгБЩгВКгБЃи®≠зљЃгАБжЃµеЈЃиІ£жґИгАБеїКдЄЛеєЕгБЃзҐЇдњЭгБ™гБ©гАБгГРгГ™гВҐгГХгГ™гГЉгБЃеЯЇжЇЦгВТжЇАгБЯгБЧгБ¶гБДгБЊгБЩгАВгБЊгБЯгАБеРДе∞ВзФ®йГ®еИЖгБЃеЇКйЭҐз©НгБѓеОЯеЙЗ25гО°дї•дЄКгБІгАБеП∞жЙАгАБж∞іжіЧдЊњжЙАгАБеПОзіНи®≠еВЩгАБжіЧйЭҐи®≠еВЩгАБжµіеЃ§гВТеВЩгБИгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ
гАМи¶ЛеЃИгВКгВµгГЉгГУгВєгАНгБМжПРдЊЫгБХгВМгВЛгВ±гВҐгБЃе∞ВйЦАеЃґгБМе∞СгБ™гБПгБ®гВВжЧ•дЄ≠еЄЄйІРгБЧгАБгАМеЃЙеж祯и™НгАНгБ®гАМзФЯжіїзЫЄиЂЗгВµгГЉгГУгВєгАНгВТжПРдЊЫгБЧгБЊгБЩгАВгБЭгБЃдїЦгБЂгАБй£ЯдЇЛгБЃжПРдЊЫгАБеЃґдЇЛжПіеК©пЉИжЄЕжОГгГїжіЧжњѓз≠ЙпЉЙгАБдїЛи≠ЈпЉИдїЛи≠ЈдњЭйЩЇгВµгГЉгГУгВєгВТйЩ§гБПпЉЙгБ™гБ©гБЃгВµгГЉгГУгВєгВТжПРдЊЫгБЧгБ¶гБДгВЛгБ®гБУгВНгВВгБВгВКгБЊгБЩгАВ
гГїгВ±гВҐгБЃе∞ВйЦАеЃґз§ЊдЉЪз¶Пз•Йж≥ХдЇЇгГїеМїзЩВж≥ХдЇЇгГїжМЗеЃЪе±ЕеЃЕгВµгГЉгГУгВєдЇЛж•≠жЙАз≠ЙгБЃиБЈеУ°гАБдїЛи≠Јз¶Пз•Йе£ЂгАБз§ЊдЉЪз¶Пз•Йе£ЂгАБдїЛи≠ЈжФѓжПіе∞ВйЦАеУ°гАБй§КжИРз†ФдњЃдњЃдЇЖиАЕгААеМїеЄЂгАБзЬЛи≠ЈеЄЂгАБеЗЖзЬЛи≠ЈеЄЂ
гГїдїЛи≠ЈдњЭйЩЇгВµгГЉгГУгВєгБМеИ©зФ®гБІгБНгВЛдїЛи≠ЈгБМењЕи¶БгБ™е†іеРИгБѓгАБдљПеЃЕдЇЛж•≠иАЕгВДе§ЦйГ®гБЃдїЛи≠ЈдњЭйЩЇдЇЛж•≠иАЕгБ®е•СзіДгБЧгАБдїЛи≠ЈдњЭйЩЇгВµгГЉгГУгВєгВТеИ©зФ®гБЩгВЛгБУгБ®гБМгБІгБНгБЊгБЩгАВпЉИгАМзЙєеЃЪжЦљи®≠еЕ•е±ЕиАЕзФЯжіїдїЛи≠ЈгАНгБЃжМЗеЃЪгВТеПЧгБСгБ¶гБДгВЛгВµгГЉгГУгВєдїШгБНйЂШ隥иАЕеРСгБСдљПеЃЕгБЃе†іеРИгБѓгАБгБЭгБЃжЦљи®≠гБЛгВЙдїЛи≠ЈдњЭйЩЇгВµгГЉгГУгВєгВТеПЧгБСгВЛгБУгБ®гБЂгБ™гВКгБЊгБЩгАВпЉЙ
е•СзіД嚥жЕЛ
гАМеИ©зФ®ж®©жЦєеЉПгАНгБ®гАМеїЇзЙ©и≥Ги≤ЄеАЯжЦєеЉПгАНгБМгБВгВКгБЊгБЩгБМгАБдЄїгБ™е•СзіД嚥жЕЛгБѓгАМеїЇзЙ©и≥Ги≤ЄеАЯжЦєеЉПгАНгБІгБЩгАВ
еИ©зФ®жЦЩгБЃжФѓжЙХгБДжЦєеЉП
гАМеЙНжЙХгБДжЦєеЉПгАНгБ®гАМжЬИжЙХгБДжЦєеЉПгАНгБМгБВгВКгБЊгБЩгБМгАБе§ЪгБПгБЃгВµгГЉгГУгВєдїШгБНйЂШ隥иАЕеРСгБСдљПеЃЕгБѓгАМжЬИжЙХгБДжЦєеЉПгАНгВТжО°зФ®гБЧгБ¶гБДгБЊгБЩгАВгБ™гБКгАБгАМеЙНжЙХгБДжЦєеЉПгАНгБМжО°зФ®гБХгВМгБ¶гБДгВЛе†іеРИгБІгВВгАБеЙНжЙХйЗСгБЂеѓЊгБЧгБ¶ењЕи¶БгБ™дњЭеЕ®жО™зљЃгВТиђЫгБШгВЛгБУгБ®гБМзЊ©еЛЩдїШгБСгВЙгВМгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ
вЦЉйЦҐйА£и®ШдЇЛпЉЪ
гБФйЂШ隥иАЕгБМеЃЙењГгБЧгБ¶жЪЃгВЙгБЫгВЛгАМгВµгГЉгГУгВєдїШгБНйЂШ隥иАЕеРСгБСдљПеЃЕпЉИгВµйЂШдљПпЉЙгАН
6.зЙєеИ•й§Ки≠ЈиАБдЇЇгГЫгГЉгГ†пЉИдїЛи≠ЈиАБдЇЇз¶Пз•ЙжЦљи®≠пЉЙгБ®гБѓ
зХ•гБЧгБ¶гАМзЙєй§КгАНгБ®гВВеСЉгБ∞гВМгВЛзЙєеИ•й§Ки≠ЈиАБдЇЇгГЫгГЉгГ†пЉИдїЛи≠ЈиАБдЇЇз¶Пз•ЙжЦљи®≠пЉЙгБѓгАБдїЛи≠ЈгБМењЕи¶БгБ™йЂШ隥иАЕгБЃгБЯгВБгБЃзФЯжіїжЦљи®≠гБІгБЩгАВеЯЇжЬђзЪДгБЂгБѓгАБгАМеЬ∞жЦєеЕђеЕ±еЫ£дљУгАНгБ®гАМз§ЊдЉЪз¶Пз•Йж≥ХдЇЇгАНгБЂйЩРгБ£гБ¶и®≠зљЃйБЛеЦґгБМи™НгВБгВЙгВМгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ
еЕђзЪДгБ™жЦљи®≠гБІгБВгВЛгБЯгВБгАБеЕ•жЙАжЬЯйЦУгБЂеИґйЩРгБѓгБ™гБПгАБзµВиЇЂеИ©зФ®гБМеПѓиГљгБІгБЩгАВгБЯгБ†гБЧгАБж≤їзЩВгБМењЕи¶БгБ®гБ™гВКйХЈжЬЯеЕ•йЩҐгВТи¶БгБЩгВЛзКґжЕЛгБЂгБ™гБ£гБЯе†іеРИгБѓгАБйААжЙАгБ®гБ™гВЛгБУгБ®гБМгБВгВКгБЊгБЩгАВ
еЕ•е±ЕжЭ°дїґ
еОЯеЙЗгБ®гБЧгБ¶и¶БдїЛи≠ЈпЉУдї•дЄКгБЃйЂШ隥иАЕпЉИ65ж≠≥дї•дЄКпЉЙгБМеѓЊи±°гБІгБЩгАВ
гБЯгБ†гБЧгАБ40пљЮ64ж≠≥гБІзЙєеЃЪзЦЊзЧЕгБЂгВИгВКи¶БдїЛи≠ЈпЉУдї•дЄКгБ®и™НеЃЪгБХгВМгБЯжЦєгАБгВДгВАгВТгБИгБ™гБДдЇЛжГЕгБМгБВгВКзЙєдЊЛгБІеЕ•е±ЕгБМи™НгВБгВЙгВМгБЯи¶БдїЛи≠ЈпЉСпљЮпЉТгБЃжЦєгБѓеЕ•е±ЕгБІгБНгВЛгБУгБ®гБМгБВгВКгБЊгБЩгАВ
зЙєеИ•й§Ки≠ЈиАБдЇЇгГЫгГЉгГ†гБЃз®Ѓй°Ю
зЙєеИ•й§Ки≠ЈиАБдЇЇгГЫгГЉгГ†гБЂгБѓгАБе§ІгБНгБПеИЖгБСгБ¶гАМеЇГеЯЯеЮЛзЙєеИ•й§Ки≠ЈиАБдЇЇгГЫгГЉгГ†гАНгАМеЬ∞еЯЯеѓЖзЭАеЮЛзЙєеИ•й§Ки≠ЈиАБдЇЇгГЫгГЉгГ†гАНгАМеЬ∞еЯЯгВµгГЭгГЉгГИеЮЛзЙєеИ•й§Ки≠ЈиАБдЇЇгГЫгГЉгГ†гАНгБЃ3гБ§гБМгБВгВКгБЊгБЩгАВ
гГїеЇГеЯЯеЮЛзЙєеИ•й§Ки≠ЈиАБдЇЇгГЫгГЉгГ†жЬАгВВдЄАиИђзЪДгБ™гАБеЃЪеУ°гБМ30еРНдї•дЄКгБЃзЙєеИ•й§Ки≠ЈиАБдЇЇгГЫгГЉгГ†гБІгБЩгАВе±ЕдљПеЬ∞еЯЯгБЂеИґйЩРгБМгБ™гБПгАБгБ©гБЃеЬ∞еЯЯгБЂдљПгВУгБІгБДгБ¶гВВзФ≥гБЧиЊЉгВАгБУгБ®гБМгБІгБНгБЊгБЩгАВ
гГїеЬ∞еЯЯеѓЖзЭАеЮЛзЙєеИ•й§Ки≠ЈиАБдЇЇгГЫгГЉгГ†еЃЪеУ°гБМ29еРНдї•дЄЛгБЃе∞Пи¶Пж®°гБ™зЙєеИ•й§Ки≠ЈиАБдЇЇгГЫгГЉгГ†гБѓгАБгАМеЬ∞еЯЯеѓЖзЭАеЮЛзЙєеИ•й§Ки≠ЈиАБдЇЇгГЫгГЉгГ†гАНгБ®еСЉгБ∞гВМгБЊгБЩгАВ
еОЯеЙЗгБ®гБЧгБ¶гАБжЦљи®≠гБМгБВгВЛеЄВеМЇзФЇжЭСгБЂдљПгВУгБІгБДгВЛжЦєгБМзФ≥гБЧиЊЉгВБгБЊгБЩгАВ
еѓЊи±°еЬ∞еЯЯгБІеЬ®еЃЕдїЛи≠ЈгВТеПЧгБСгБ¶гБДгВЛйЂШ隥гБЃжЦєгВТеѓЊи±°гБЂгАБ24жЩВйЦУдљУеИґгБІи¶ЛеЃИгВКгВДзФЯжіїжПіеК©гАБзЫЄиЂЗж•≠еЛЩгБ™гБ©гВТи°МгБЖзЙєеИ•й§Ки≠ЈиАБдЇЇгГЫгГЉгГ†гБІгБЩгАВ
зЙєеИ•й§Ки≠ЈиАБдЇЇгГЫгГЉгГ†гБЃи≤їзФ®
дїЛи≠ЈдњЭйЩЇжЦљи®≠гБЃгБ≤гБ®гБ§гБІгБВгВЛзЙєеИ•й§Ки≠ЈиАБдЇЇгГЫгГЉгГ†гБѓгАБж∞СйЦУдЉБж•≠гБ™гБ©гБМйБЛеЦґгБЩгВЛжЦљи®≠гБ®гБѓзХ∞гБ™гВКгАБеЕ•е±ЕдЄАжЩВйЗСгБ™гБ©гБЃеИЭжЬЯи≤їзФ®гБѓгБЛгБЛгВКгБЊгБЫгВУгАВ
и≤†жЛЕгБЩгВЛгБЃгБѓеЕ•е±ЕеЊМгБЃжЬИй°НеИ©зФ®жЦЩгБЃгБњгБІгАБжЬИй°НеИ©зФ®жЦЩгБЂгБѓгАБжЦљи®≠гВµгГЉгГУгВєи≤їгАБе±ЕдљПи≤їгАБй£Яи≤їгАБжЧ•еЄЄзФЯжіїи≤їгБ™гБ©гБМеРЂгБЊгВМгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ
жЦљи®≠гВµгГЉгГУгВєи≤їгБѓгАБе±ЕеЃ§гБЃз®Ѓй°ЮпЉИеАЛеЃ§гГїе§ЪеЇКеЃ§гБ™гБ©пЉЙгВДжЦљи®≠гБЃељҐжЕЛгАБиБЈеУ°гБЃйЕНзљЃгБ™гБ©гБЂгВИгБ£гБ¶зХ∞гБ™гВКгБЊгБЩгАВ
вЦЉйЦҐйА£и®ШдЇЛпЉЪ
зЙєеИ•й§Ки≠ЈиАБдЇЇгГЫгГЉгГ†пљ£гАМдїЛи≠ЈиАБдЇЇдњЭеБ•жЦљи®≠гАНжЬЙжЦЩиАБдЇЇгГЫгГЉгГ†пљ£пљҐгВ∞гГЂгГЉгГЧгГЫгГЉгГ†пљ£гБЃйБХгБДгБ®гБѓпЉЯ
7.гБЭгБЃдїЦгБЃйЂШ隥иАЕеРСгБСдљПгБЊгБД
гГїгВ±гВҐгГПгВ¶гВєиЗ™зЂЛгБЧгБЯжЧ•еЄЄзФЯжіїгВТеЦґгВАгБУгБ®гБЂдЄНеЃЙгБМгБВгВЛгБ®и™НгВБгВЙгВМгБЯжЦєгАБгБФеЃґжЧПгБЂгВИгВЛжПіеК©гВТеПЧгБСгВЛгБУгБ®гБМеЫ∞йЫ£гБ™жЦєгБ™гБ©гБМгАБзД°жЦЩгБЊгБЯгБѓдљОй°НгБ™жЦЩйЗСгБІеЕ•е±ЕгБІгБНгВЛдљОжЙАеЊЧйЂШ隥иАЕгБЃгБЯгВБгБЃдљПгБЊгБДгБІгБЩгАВ
й£ЯдЇЛгБЃжПРдЊЫгАБеЕ•жµігБ™гБ©гБЃжЇЦеВЩгАБзЫЄиЂЗгБ®жПіеК©гАБз§ЊдЉЪзФЯжіїдЄКгБЃдЊњеЃЬгБЃдЊЫдЄОгБ™гБ©гБМжПРдЊЫгБХгВМгБЊгБЩгАВ
дїЛи≠ЈгБМењЕи¶БгБЂгБ™гБ£гБЯе†іеРИгБѓгАБе§ЦйГ®гБЃдїЛи≠ЈгВµгГЉгГУгВєгБЃеИ©зФ®гБМеПѓиГљгБІгБЩгАВ
гАМзЙєеЃЪжЦљи®≠еЕ•е±ЕиАЕзФЯжіїдїЛи≠ЈгАНгБЃжМЗеЃЪгВТеПЧгБСгБ¶гБДгВЛгВ±гВҐгГПгВ¶гВєгБІгБѓгАБи¶БжФѓжПігВДи¶БдїЛи≠ЈгБЃйЂШ隥иАЕгБЂдїЛи≠ЈгВµгГЉгГУгВєгВТжПРдЊЫгБЧгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ дїЛи≠ЈгВµгГЉгГУгВєгБМжПРдЊЫгБХгВМгБ™гБДе†іеРИгБѓгАБдљПгБњжЫњгБИгБМењЕи¶БгБЂгБ™гВЛгБУгБ®гВВгБВгВКгБЊгБЩгАВ
и™НзЯ•зЧЗгБЃжЦєгВТеѓЊи±°гБЂгБЧгБЯеЕ±еРМзФЯжіїдљПе±ЕгБІгБЩгАВ
е∞СдЇЇжХ∞гБЃи™НзЯ•зЧЗгБЃжЦєгБМгАБеЃґеЇ≠зЪДгБ™йЫ∞еЫ≤ж∞ЧгБЃдЄ≠гБІгАБдїЛи≠ЈгВєгВњгГГгГХгБЃе∞ВйЦАзЪДгБ™гВ±гВҐгВТеПЧгБСгБ™гБМгВЙжЪЃгВЙгБЩгБУгБ®гБМгБІгБНгБЊгБЩгАВ
жПРдЊЫгБХгВМгВЛгВµгГЉгГУгВєгБѓгАБдїЛи≠ЈпЉИеЕ•жµігГїжОТгБЫгБ§гГїй£ЯдЇЛгБ™гБ©пЉЙгВДжЧ•еЄЄзФЯжіїдЄКгБЃжФѓжПігАБж©ЯиГљи®УзЈігБ™гБ©гБІгБЩгАВ
и¶БжФѓжПіпЉТгБЊгБЯгБѓи¶БдїЛи≠ЈпЉСдї•дЄКгБЃи™НзЯ•зЧЗгБЃжЦєгБМеИ©зФ®гБІгБНгБЊгБЩгАВпЉИвАїи¶БжФѓжПіпЉТгБЃжЦєгБѓгАМдїЛи≠ЈдЇИйШ≤и™НзЯ•зЧЗеѓЊењЬеЮЛеЕ±еРМзФЯжіїдїЛи≠ЈгАНгБЃеИ©зФ®гБ®гБ™гВКгБЊгБЩгАВпЉЙ
дїЛи≠ЈгБМењЕи¶БгБ™жЦєгБЂгАМйХЈжЬЯзЩВй§КгБЃгБЯгВБгБЃеМїзЩВгАНгБ®гАМжЧ•еЄЄзФЯжіїдЄКгБЃдїЛи≠ЈгАНгВТдЄАдљУзЪДгБЂжПРдЊЫгБЩгВЛдїЛи≠ЈдњЭйЩЇжЦљи®≠гБІгБЩгАВ
гАМдљПгБЊгБДгАНгБ®гБЧгБ¶гБЃж©ЯиГљгВВйЗНи¶ЦгБХгВМгБ¶гБДгВЛгБЯгВБгАБгГЧгГ©гВ§гГРгВЈгГЉгБЂйЕНжЕЃгБЧгБЯзТ∞еҐГгБМжХігБ£гБ¶гБДгБЊгБЩгАВ
и®ЇеѓЯеЃ§гВДеЗ¶зљЃеЃ§гАБж©ЯиГљи®УзЈіеЃ§гБЃгБїгБЛгБЂгАБй£Яе†ВгАБжµіеЃ§гАБиЂЗи©±еЃ§гАБгГђгВѓгГ™гВ®гГЉгВЈгГІгГ≥гГЂгГЉгГ†гБ™гБ©гВВи®≠гБСгВЙгВМгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ
йХЈжЬЯзЪДгБ™еМїзЩВгБ®дїЛи≠ЈгБЃгГЛгГЉгВЇгВТдљµгБЫжМБгБ§и¶БдїЛи≠ЈпЉСпљЮпЉХгБЃжЦєгБМеѓЊи±°гБІгБЩгАВ
вЦЉйЦҐйА£и®ШдЇЛпЉЪ
гБФйЂШ隥иАЕгБЃзФЯжіїгВТжФѓжПігБЩгВЛиїљи≤їиАБдЇЇгГЫгГЉгГ†гБЃз®Ѓй°ЮгБ®гВµгГЉгГУгВє
дїЛи≠ЈдњЭйЩЇжЦљи®≠гАМдїЛи≠ЈеМїзЩВйЩҐгАНгБ®гБѓпЉЯгВµгГЉгГУгВєеЖЕеЃєгБ®и≤їзФ®гВТгБФзієдїЛгБЧгБЊгБЩ
гАМгВЈгГЂгГРгГЉгГПгВ¶гВЄгГ≥гВ∞гАНгБ®гБѓпЉЯеЕ•е±ЕеѓЊи±°иАЕгБ®жПРдЊЫгБХгВМгВЛгВµгГЉгГУгВє
8.йЂШ隥гБЃжЦєеРСгБСдљПгБЊгБДгВТйБЄгБґгБ®гБНгБЃгГЭгВ§гГ≥гГИ

йЂШ隥гБЃжЦєеРСгБСгБЃдљПгБЊгБДгБѓе§ЪжІШгБІгБВгВКгАБзЙєеЊігВДеЕ•е±ЕжЭ°дїґгАБи≤їзФ®гБ™гБ©гБМгБЭгВМгБЮгВМзХ∞гБ™гВКгБЊгБЩгАВгБЊгБЯгАБйБЛеЦґгБЩгВЛдЇЛж•≠иАЕгБЃиАГгБИжЦєгБМгВµгГЉгГУгВєз≠ЙгБЂеПНжШ†гБХгВМгБ¶гБДгВЛгБ®гБУгВНгВВгБВгВКгБЊгБЩгАВгБЭгБЃгБЯгВБгАБгБФиЗ™иЇЂгБЃеБ•еЇЈзКґжЕЛгВДеЄМжЬЫгАБгГ©гВ§гГХгВєгВњгВ§гГЂгБЂеРИгБ£гБЯдљПгБЊгБДгВТйБЄгБґгБУгБ®гБМе§ІеИЗгБІгБЩгАВ
и¶Ле≠¶гВДдљУй®УеЕ•е±ЕгВТгБЧгБ¶гБњгВЛ
ж∞ЧгБЂгБ™гВЛдљПгБЊгБДгБМи¶ЛгБ§гБЛгБ£гБЯгВЙгАБеЕ•е±ЕгВТж§Ьи®ОгБЩгВЛеЙНгБЂдљХеЇ¶гБЛи¶Ле≠¶гБЧгАБи≥ЗжЦЩгБ†гБСгБІгБѓеИЖгБЛгВЙгБ™гБДйЫ∞еЫ≤ж∞ЧгВДиБЈеУ°гБЃеѓЊењЬгАБгВµгГЉгГУгВєгБЃзі∞гБЛгБДйГ®еИЖгБ™гБ©гВТгГБгВІгГГгВѓгБЧгБ¶гБњгБЊгБЧгВЗгБЖгАВгБІгБНгВЛгБ†гБСгБФеЃґжЧПгБ®дЄАзЈТгБЂи§ЗжХ∞гБЃдљПгБЊгБДгБЂи¶Ле≠¶гБЂи°МгБНгАБеПѓиГљгБІгБВгВМгБ∞дљУй®УеЕ•е±ЕгВВгБЧгБ¶гБњгБЊгБЧгВЗгБЖгАВ
вЦЉйЦҐйА£и®ШдЇЛпЉЪ
иАБдЇЇгГЫгГЉгГ†гБЃи¶Ле≠¶гГїдљУй®УеЕ•е±ЕгБЃгБ®гБНгБЂгГБгВІгГГгВѓгБЧгБ¶гБКгБНгБЯгБДгГЭгВ§гГ≥гГИ
гВµгГЉгГУгВєжПРдЊЫдљУеИґгВТ祯и™НгБЩгВЛ
иБЈеУ°гБЃйЕНзљЃзКґж≥БгВДжМБгБ£гБ¶гБДгВЛи≥Зж†ЉгАБе§ЬеЛ§гБЃеЛ§еЛЩдљУеИґгАБдїЛи≠ЈгГїеМїзЩВгГЛгГЉгВЇгБЄгБЃеѓЊењЬгБ™гБ©гВТ祯и™НгБЧгБЊгБЧгВЗгБЖгАВ
еЕ•е±ЕеЊМгБЂдїЛи≠ЈгВДеМїзЩВгБМењЕи¶БгБЂгБ™гБ£гБЯе†іеРИгВДгАБдїЛи≠ЈеЇ¶гБМйЗНгБПгБ™гБ£гБЯе†іеРИгБЂгАБзФЯжіїгВТзґЩзґЪгБЩгВЛгБУгБ®гБМеПѓиГљгБЛгБ©гБЖгБЛгВВйЗНи¶БгБ™гГЭгВ§гГ≥гГИгБІгБЩгАВ
жЫЄй°ЮгВТгВИгБП祯и™НгБЩгВЛ
еЕ•е±ЕеЊМгВДйААеОїжЩВгБЃгГИгГ©гГЦгГЂгВТйШ≤гБРгБЯгВБгБЂгАБгАМйЗНи¶БдЇЛй†Еи™ђжШОжЫЄгАНгВДеЕ•е±Ее•СзіДжЫЄгБ™гБ©гБЃеРДз®ЃжЫЄй°ЮгБѓеНБеИЖгБЂзҐЇи™НгБЧгБЊгБЧгВЗгБЖгАВ
зЙєгБЂи≤їзФ®гАБйААеОїи¶БдїґгБѓе•СзіДеЊМгБЃгГИгГ©гГЦгГЂгБМе§ЪгБДгБЯгВБгАБж≥®жДПгБМењЕи¶БгБІгБЩгАВзЦСеХПзВєгБМгБВгБ£гБЯгВЙи™ђжШОгВТж±ВгВБгАБзРЖиІ£гАБзіНеЊЧгБЧгБ¶гБЛгВЙе•СзіДгБЧгБЊгБЧгВЗгБЖгАВ
йЂШ隥иАЕеРСгБСгБЃдљПгБЊгБДгВДдїЛи≠ЈгБ™гБ©гБЂгБ§гБДгБ¶еИЖгБЛгВЙгБ™гБДгБУгБ®гАБеЫ∞гБ£гБЯгБУгБ®гБМгБВгВЛе†іеРИгБѓгАБйЂШ隥иАЕгБЃгБЯгВБгБЃзЈПеРИзЫЄиЂЗз™УеП£гБІгБВгВЛгАМеЬ∞еЯЯеМЕжЛђжФѓжПігВїгГ≥гВњгГЉгАНгБЂзЫЄиЂЗгБЧгБ¶гБњгБЊгБЧгВЗгБЖгАВжЬАеѓДгВКгБЃеЬ∞еЯЯеМЕжЛђжФѓжПігВїгГ≥гВњгГЉгБѓгАБеОЪзФЯеКіеГНзЬБгБЃ гАМеЕ®еЫљгБЃеЬ∞еЯЯеМЕжЛђжФѓжПігВїгГ≥гВњгГЉгБЃдЄАи¶ІгАНгБІзҐЇи™НгБІгБНгБЊгБЩгАВ
гБЊгБЯгАБжЬЙжЦЩиАБдЇЇгГЫгГЉгГ†з≠ЙгБЂйЦҐгБЧгБ¶гБѓгАМеЕђзЫКз§ЊеЫ£ж≥ХдЇЇ еЕ®еЫљжЬЙжЦЩиАБдЇЇгГЫгГЉгГ†еНФдЉЪгАНгАБгВµгГЉгГУгВєдїШгБНйЂШ隥иАЕеРСгБСдљПеЃЕгБЂйЦҐгБЧгБ¶гБѓгАМдЄАиИђз§ЊеЫ£ж≥ХдЇЇйЂШ隥иАЕдљПеЃЕеНФдЉЪгАНгБМгАБзЫЄиЂЗз™УеП£гВТйЦЛи®≠гБЧгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ
вЦЉйЦҐйА£и®ШдЇЛпЉЪ
гАМеЬ∞еЯЯеМЕжЛђжФѓжПігВїгГ≥гВњгГЉгАНгБ£гБ¶гБ©гВУгБ™гБ®гБУгВНпЉЯ гБЭгБЃељєеЙ≤гБ®ж•≠еЛЩеЖЕеЃє
й†ЉгВМгВЛдїЛи≠ЈгБЃе∞ВйЦАеЃґгАМгВ±гВҐгГЮгГНгВЄгГ£гГЉгАНгБЃдїХдЇЛеЖЕеЃєгБ®гБѓпЉЯ
еЃґжЧПгБЃдїЛи≠ЈгВТгБНгБ£гБЛгБСгБЂдїЛи≠Јз¶Пз•Йе£ЂгГїз§ЊдЉЪз¶Пз•ЙдЄїдЇЛдїїзФ®и≥Зж†ЉгВТеПЦеЊЧгАВзПЊеЬ®гБѓгГ©гВ§гВњгГЉгАВжЧ•гАЕгБЃжЪЃгВЙгБЧгБЂељєзЂЛгБ§иЇЂињСгБ™жГЕ冱гВТгБКдЉЭгБИгБЩгВЛгБєгБПгАБдїЛи≠ЈгГїеМїзЩВгГїзЊОеЃєгГїгВЂгГЂгГБгГ£гГЉгБ™гБ©еєЕеЇГгБДгВЄгГ£гГ≥гГЂгБЃи®ШдЇЛгВТеЯЈз≠ЖдЄ≠гАВ

FacebookгГЪгГЉгВЄгБІ
жЬАжЦ∞и®ШдЇЛйЕНдњ°пЉБпЉБ
 гГђгВ™гГПгВЪгГђгВє21гВѓгВЩгГЂгГЉгГХгВЪгБЃдїЛи≠ЈгВµгГЉгГТгВЩгВє
гГђгВ™гГПгВЪгГђгВє21гВѓгВЩгГЂгГЉгГХгВЪгБЃдїЛи≠ЈгВµгГЉгГТгВЩгВє