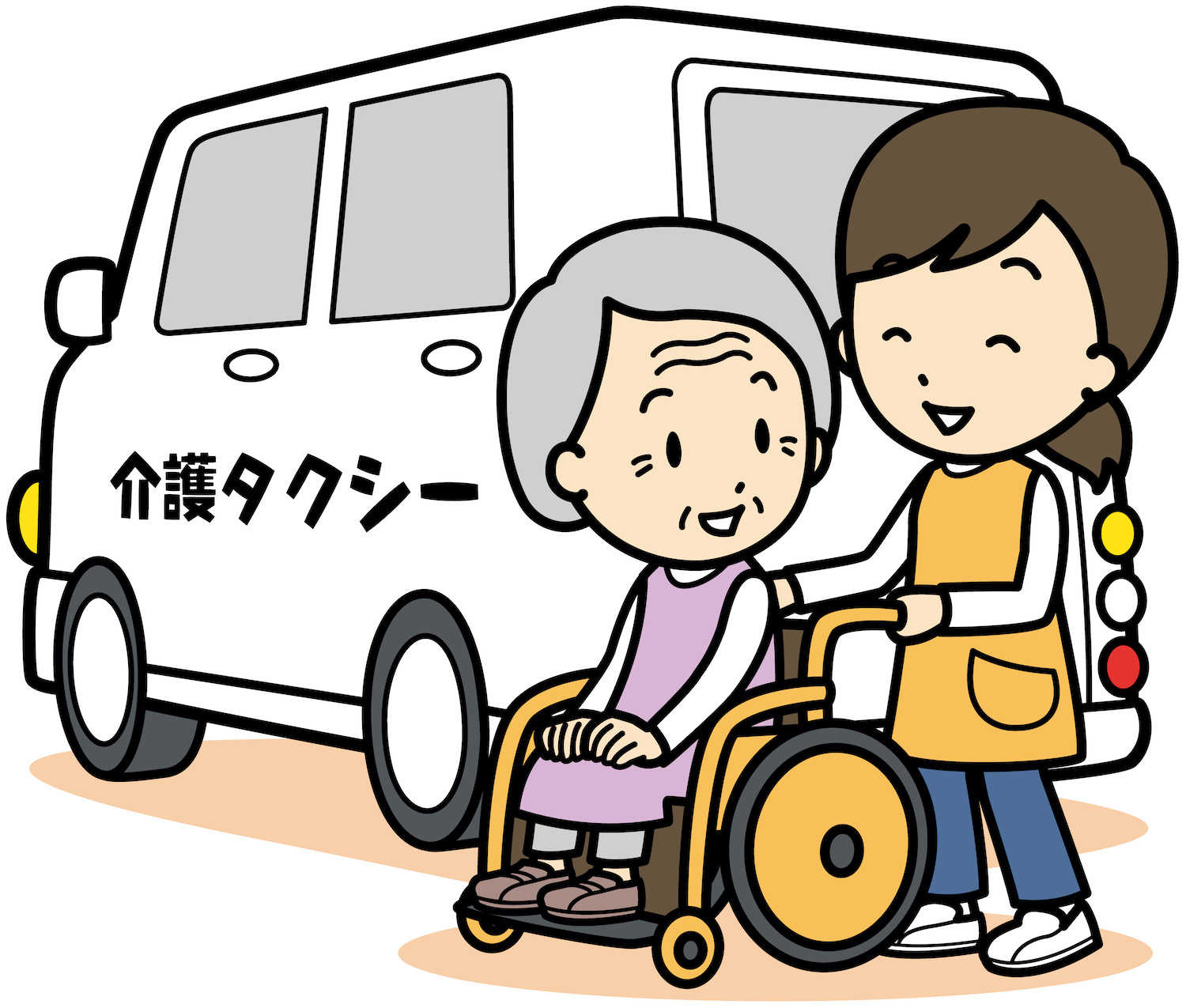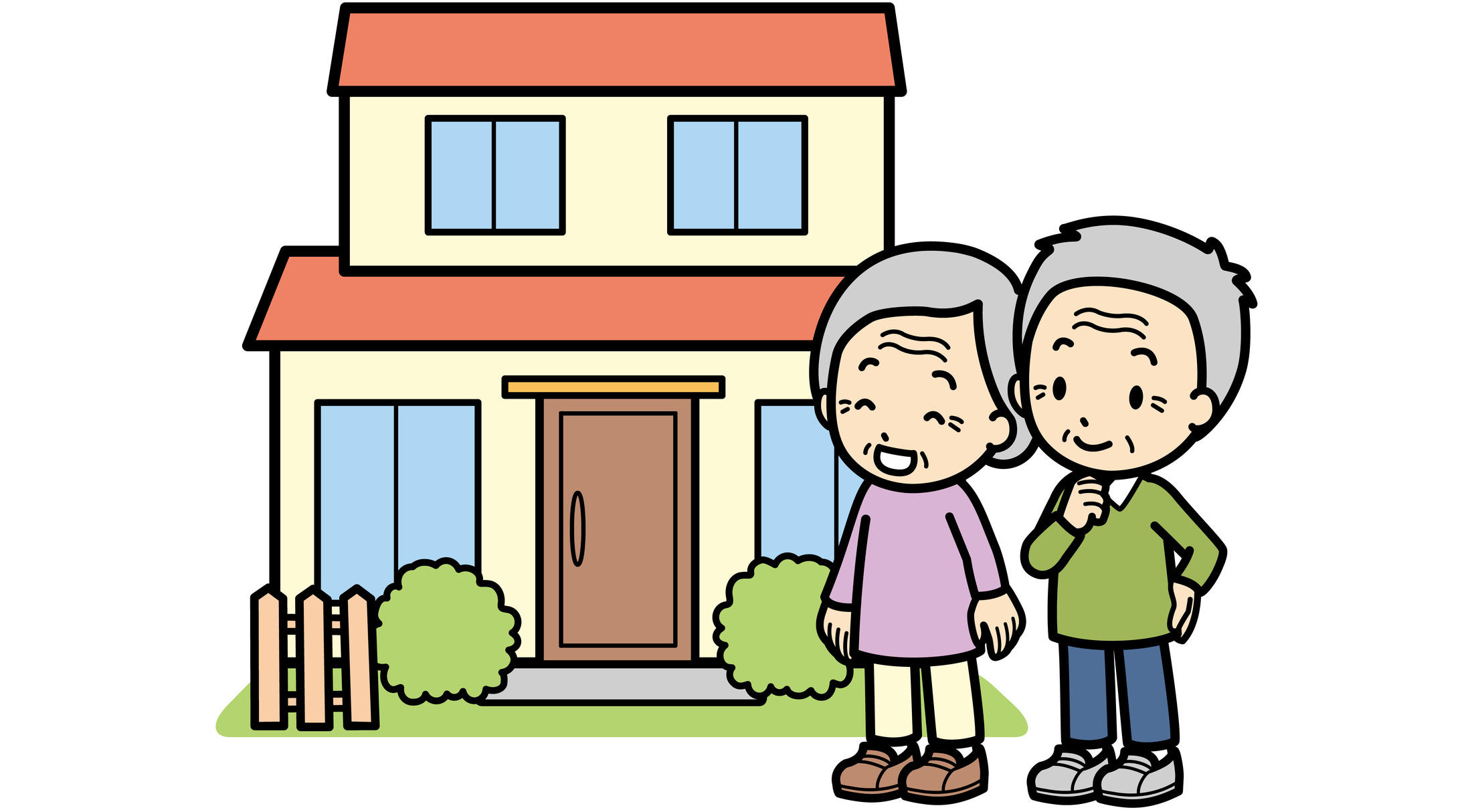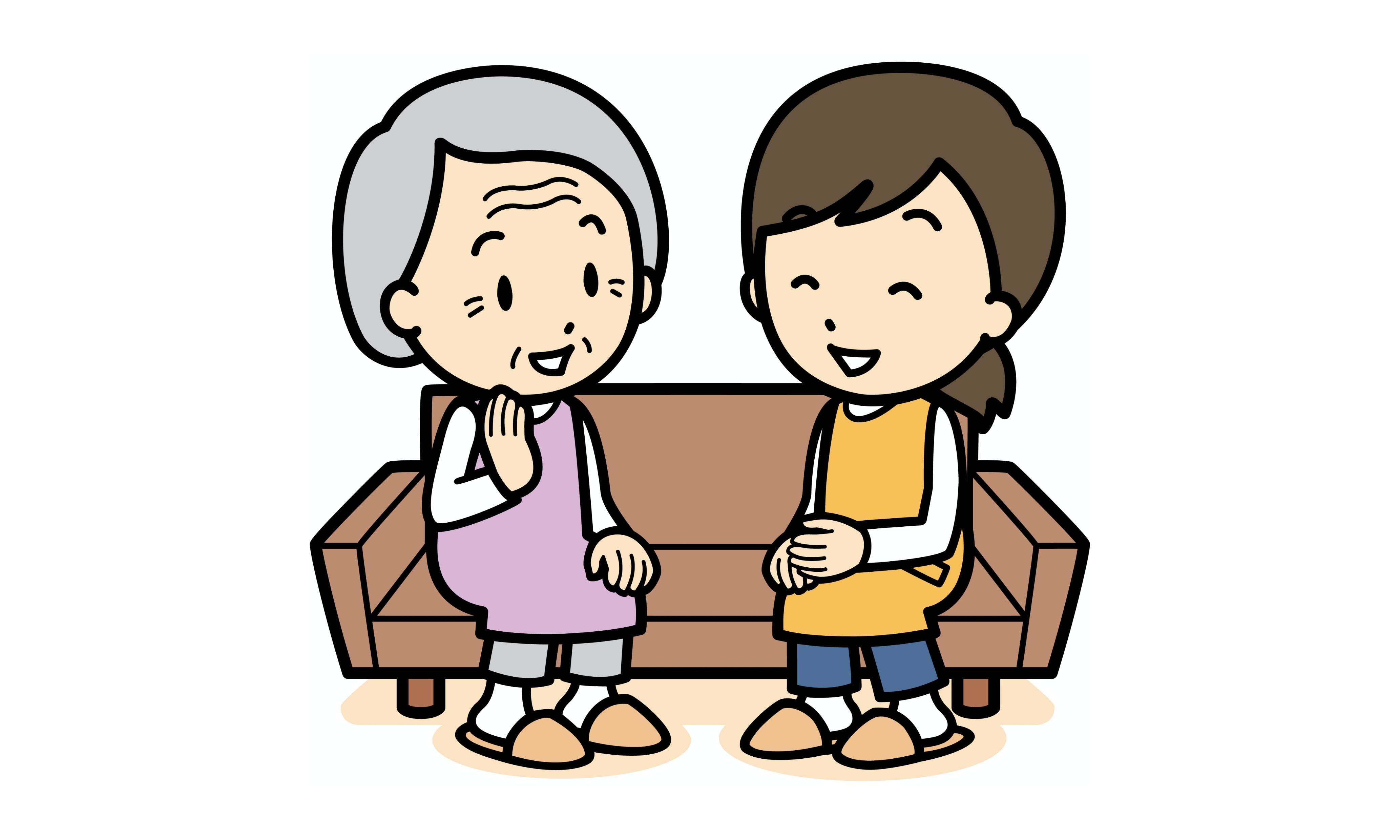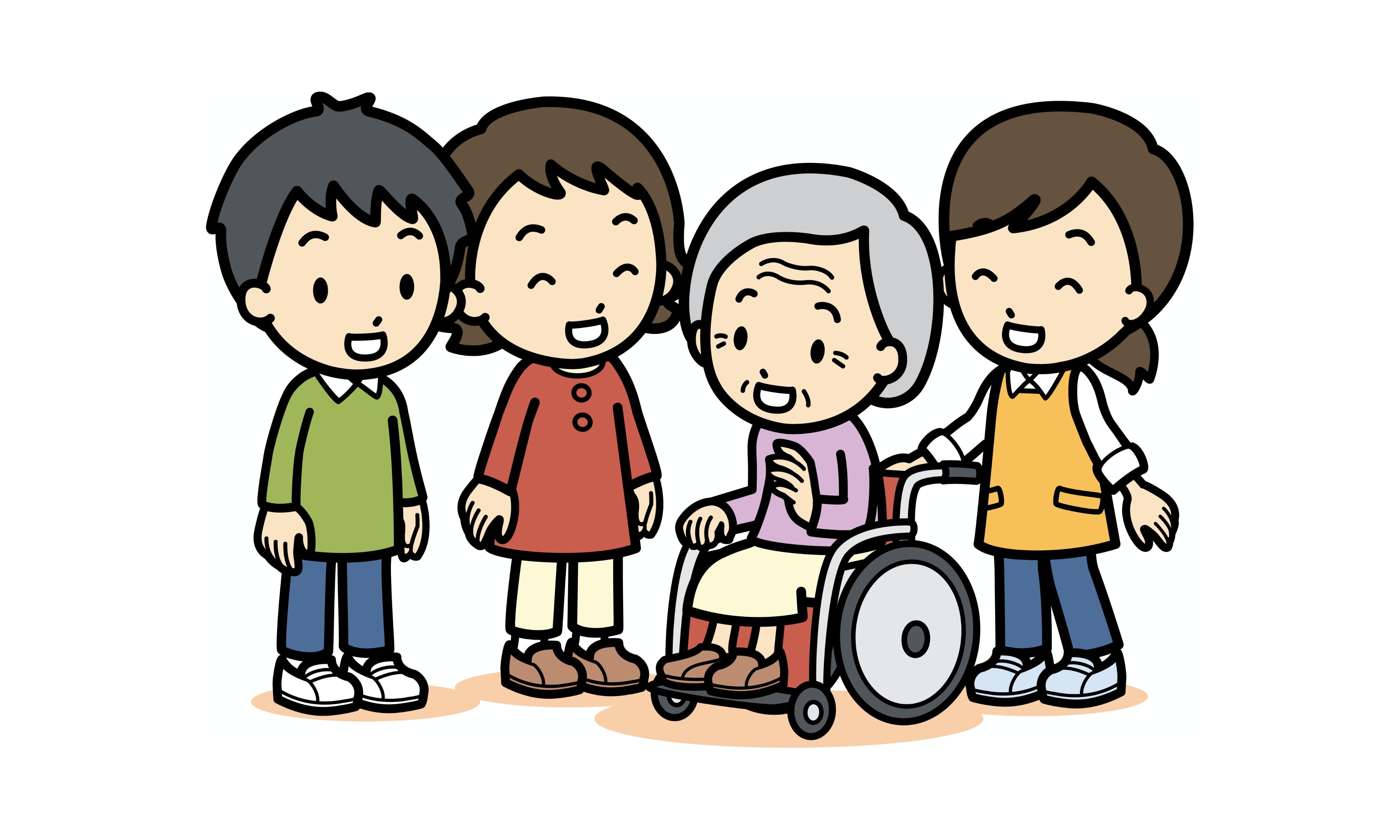д»Ӣиӯ·гҒ®дҫҝеҲ©её–гғҲгғғгғ—гҒёжҲ»гӮӢ
д»Ӣиӯ·дҝқйҷәгӮөгғјгғ“гӮ№гҒ®еҲ©з”ЁиҖ…иІ жӢ…гӮ’и»ҪгҒҸгҒҷгӮӢеҲ¶еәҰгҖҢй«ҳйЎҚд»Ӣиӯ·пјҲдәҲйҳІпјүгӮөгғјгғ“гӮ№иІ»гҖҚ
е…¬зҡ„д»Ӣиӯ·дҝқйҷәгҒ®гӮөгғјгғ“гӮ№гҒҜгҖҒиІ»з”ЁгҒ®пј‘еүІпҪһпј“еүІгӮ’ж”Ҝжү•гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§еҲ©з”ЁгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒ“гҒ®еҲ©з”ЁиҖ…иІ жӢ…гҒҢй«ҳйЎҚгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶе ҙеҗҲгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮд»ҠеӣһгҒҜгҖҒд»Ӣиӯ·дҝқйҷәгӮөгғјгғ“гӮ№гҒ®еҲ©з”ЁиҖ…иІ жӢ…гӮ’и»ҪгҒҸгҒҷгӮӢеҲ¶еәҰгҖҢй«ҳйЎҚд»Ӣиӯ·пјҲдәҲйҳІпјүгӮөгғјгғ“гӮ№иІ»гҖҚгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰи§ЈиӘ¬гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
й«ҳйЎҚд»Ӣиӯ·пјҲдәҲйҳІпјүгӮөгғјгғ“гӮ№иІ»гҒЁгҒҜ
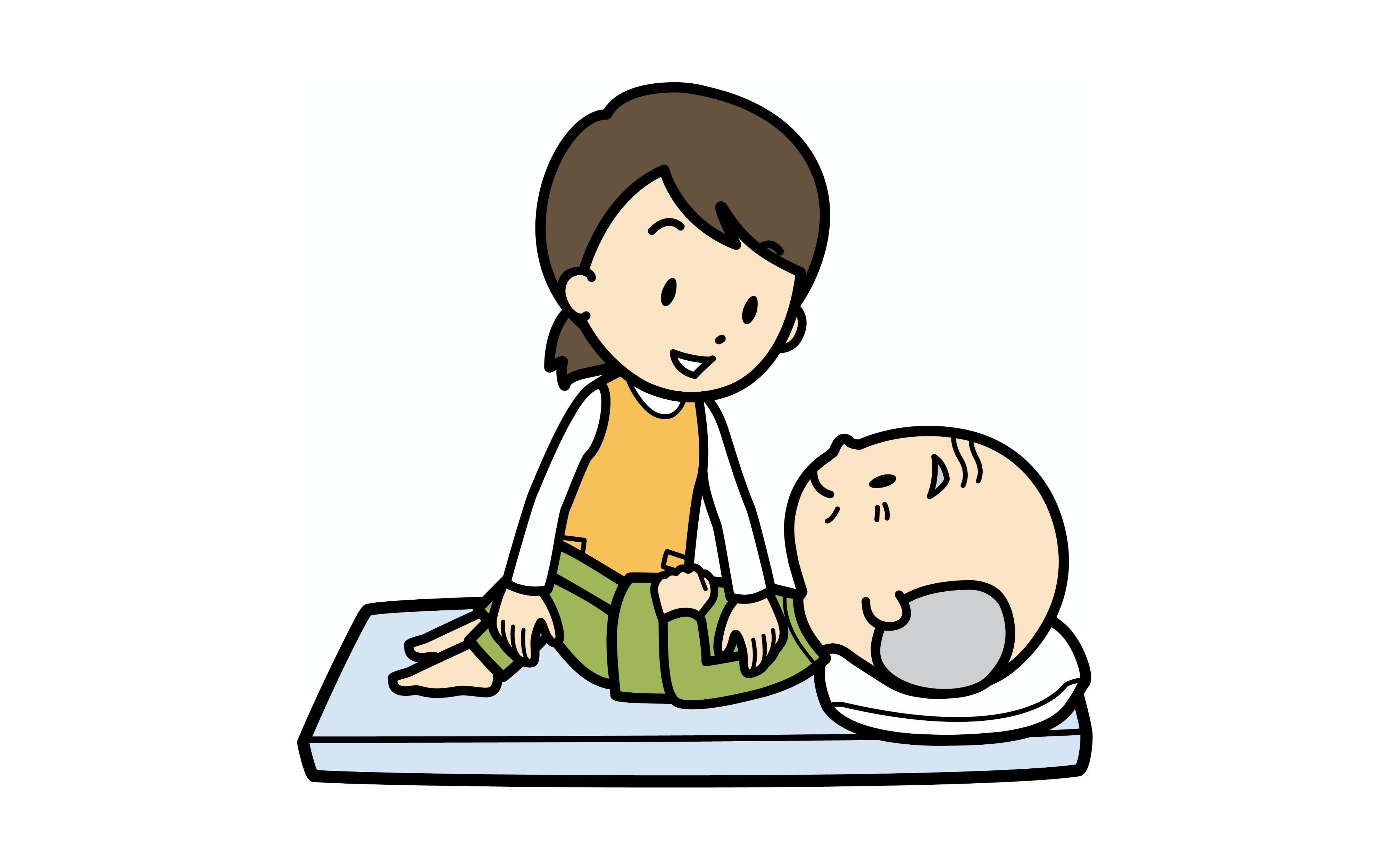
д»Ӣиӯ·дҝқйҷәгҒ®гӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’еҲ©з”ЁгҒ—гҒҹгҒЁгҒҚгҒҜгҖҒгҒӢгҒӢгҒЈгҒҹиІ»з”ЁгҒ®пј‘еүІпҪһпј“еүІгҒҢеҲ©з”ЁиҖ…иІ жӢ…гҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ®еҲ©з”ЁиҖ…иІ жӢ…гҒ«гҒҜгҖҒ1гӮ«жңҲгҒӮгҒҹгӮҠгҒ®дёҠйҷҗйЎҚгҒҢиЁӯе®ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ гҖҢй«ҳйЎҚд»Ӣиӯ·пјҲдәҲйҳІпјүгӮөгғјгғ“гӮ№иІ»гҖҚгҒҜгҖҒпј‘гӮ«жңҲгҒ«ж”Ҝжү•гҒЈгҒҹеҲ©з”ЁиҖ…иІ жӢ…гҒҢдёҖе®ҡгҒ®дёҠйҷҗйЎҚгӮ’и¶…гҒҲгҒҹе ҙеҗҲгҒ«гҖҒз”іи«ӢгҒ«гӮҲгӮҠи¶…гҒҲгҒҹеҲҶгҒҢжү•гҒ„жҲ»гҒ•гӮҢгӮӢеҲ¶еәҰгҒ§гҒҷгҖӮ
еҜҫиұЎгҒЁгҒӘгӮӢж–№
д»Ӣиӯ·пјҲд»Ӣиӯ·дәҲйҳІпјүгӮөгғјгғ“гӮ№гӮ„з·ҸеҗҲдәӢжҘӯгӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹж–№гҒ§гҖҒеҲ©з”ЁиҖ…иІ жӢ…йЎҚгҒҢжүҖеҫ—еҢәеҲҶгҒ”гҒЁгҒ«е®ҡгӮҒгӮүгӮҢгҒҹдёҠйҷҗйЎҚгӮ’и¶…гҒҲгҒҹж–№гҒ§гҒҷгҖӮ
пјҲз·ҸеҗҲдәӢжҘӯгӮөгғјгғ“гӮ№иІ»з”ЁгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒгҖҢй«ҳйЎҚд»Ӣиӯ·дәҲйҳІгӮөгғјгғ“гӮ№иІ»зӣёеҪ“дәӢжҘӯиІ»гҖҚгҒЁгҒ—гҒҰж”ҜзөҰгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮпјү
гҒӘгҒҠгҖҒеҗҢгҒҳдё–еёҜеҶ…гҒ«иӨҮж•°гҒ®гӮөгғјгғ“гӮ№еҲ©з”ЁиҖ…гҒҢгҒ„гӮӢе ҙеҗҲгҒҜгҖҒдё–еёҜеҗҲиЁҲйЎҚгҒҢеҜҫиұЎгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
й«ҳйЎҚд»Ӣиӯ·пјҲдәҲйҳІпјүгӮөгғјгғ“гӮ№иІ»гҒ®еҜҫиұЎгҒЁгҒӘгӮүгҒӘгҒ„иІ»з”Ё
й«ҳйЎҚд»Ӣиӯ·пјҲдәҲйҳІпјүгӮөгғјгғ“гӮ№иІ»гҒ®еҜҫиұЎгҒЁгҒӘгӮӢгҒ®гҒҜгҖҒпј‘гӮ«жңҲй–“гҒ«еҲ©з”ЁгҒ—гҒҹгӮөгғјгғ“гӮ№гҒ®еҲ©з”ЁиҖ…иІ жӢ…йЎҚгҒ®дҝқйҷәзөҰд»ҳеҲҶгҒ®гҒҝгҒ§гҒҷгҖӮж”ҜзөҰеҜҫиұЎгҒЁгҒӘгӮүгҒӘгҒ„иІ»з”ЁгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒдәӢеүҚгҒ«гҒ”зўәиӘҚгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ
| й«ҳйЎҚд»Ӣиӯ·пјҲдәҲйҳІпјүгӮөгғјгғ“гӮ№иІ»еҜҫиұЎеӨ–гҒ®иІ»з”Ё |
|---|
|
зҰҸзҘүз”Ёе…·иіје…ҘиІ»гҒ®еҲ©з”ЁиҖ…иІ жӢ…еҲҶ дҪҸе®…ж”№дҝ®иІ»гҒ®еҲ©з”ЁиҖ…иІ жӢ…еҲҶ иҰҒд»Ӣиӯ·зҠ¶ж…ӢеҢәеҲҶеҲҘгҒ®ж”ҜзөҰйҷҗеәҰйЎҚгӮ’и¶…гҒҲгҒҹгӮөгғјгғ“гӮ№иІ»пјҲе…ЁйЎҚиҮӘе·ұиІ жӢ…пјү е…ҘжүҖж–ҪиЁӯгҒ§гҒ®йЈҹиІ»гғ»еұ…дҪҸиІ»гғ»ж—Ҙеёёз”ҹжҙ»иІ»гҒӘгҒ© гҒқгҒ®д»–гҒ®д»Ӣиӯ·дҝқйҷәзөҰд»ҳеҜҫиұЎеӨ–гҒ®иІ»з”Ё |
й–ўйҖЈиЁҳдәӢпјҡ
гӮӮгҒ—д»Ӣиӯ·гҒҢеҝ…иҰҒгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгӮүпјҹгҒ“гӮҢгҒ гҒ‘гҒҜзҹҘгҒЈгҒҰгҒҠгҒҚгҒҹгҒ„пјҒгҖҢд»Ӣиӯ·дҝқйҷәгҖҚгҒ®еҹәзӨҺзҹҘиӯҳ
жҡ®гӮүгҒ—гӮ’гӮӮгҒЈгҒЁиұҠгҒӢгҒ«пјҒд»Ӣиӯ·дҝқйҷәгҒ®зҰҸзҘүз”Ёе…·гҒЁеҲ©з”ЁжүӢй Ҷ
гӮҲгӮҠжҡ®гӮүгҒ—гӮ„гҒҷгҒҸпјҒд»Ӣиӯ·дҝқйҷәгҒҢйҒ©з”ЁгҒ•гӮҢгӮӢдҪҸе®…ж”№дҝ®гҒЁгҒҜ
д»ҠгҒ•гӮүиҒһгҒ‘гҒӘгҒ„пјҒгҖҢд»Ӣиӯ·дәҲйҳІгғ»ж—Ҙеёёз”ҹжҙ»ж”ҜжҸҙз·ҸеҗҲдәӢжҘӯгҖҚгӮөгғјгғ“гӮ№гҒҜдҪ•гҒҢеӨүгӮҸгҒЈгҒҹпјҹ
й«ҳйЎҚд»Ӣиӯ·пјҲдәҲйҳІпјүгӮөгғјгғ“гӮ№иІ»гҒ®еҲ©з”ЁиҖ…иІ жӢ…дёҠйҷҗйЎҚ
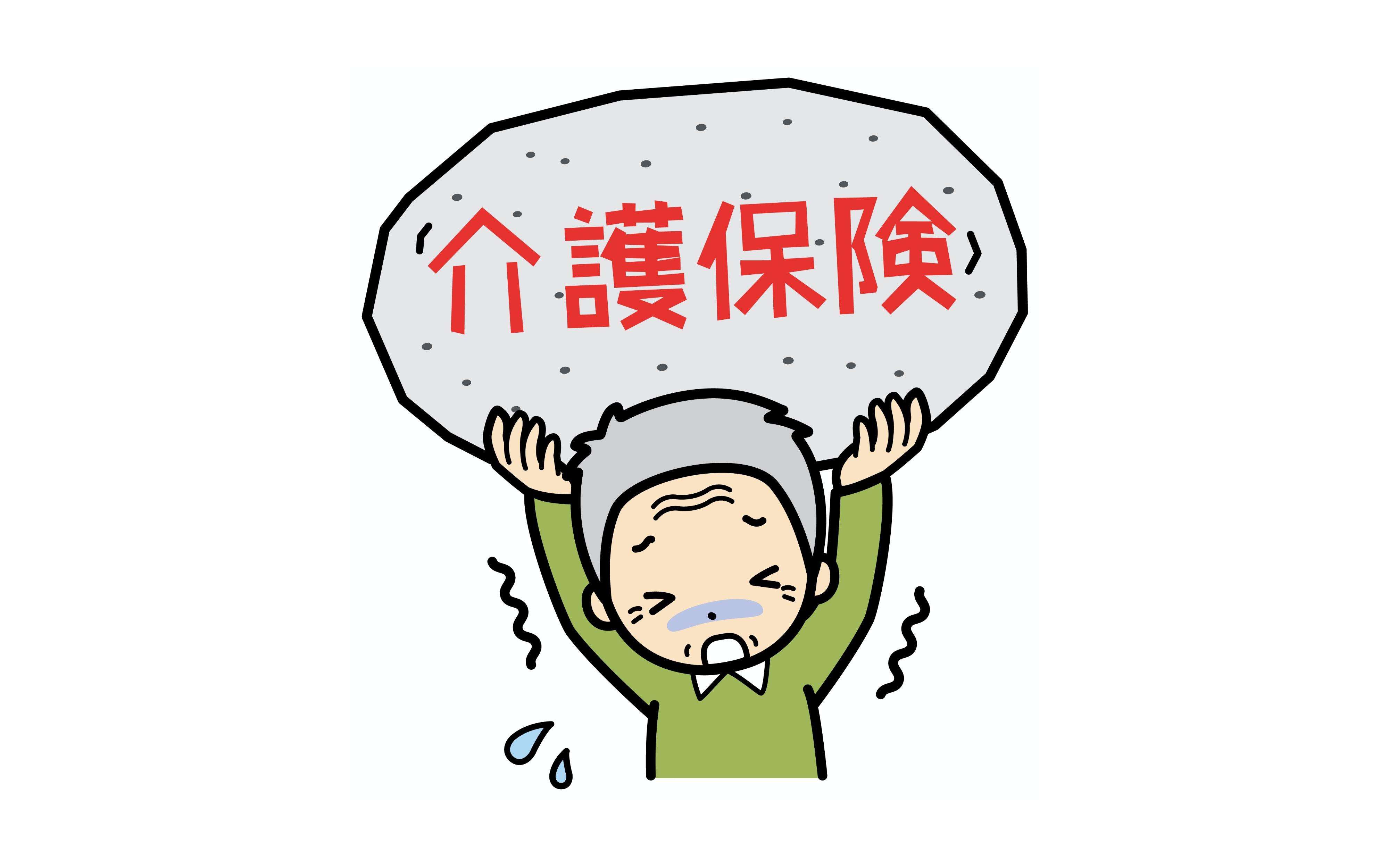
й«ҳйЎҚд»Ӣиӯ·пјҲдәҲйҳІпјүгӮөгғјгғ“гӮ№иІ»гҒ®еҲ©з”ЁиҖ…иІ жӢ…дёҠйҷҗйЎҚгҒҜжүҖеҫ—гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰз•°гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮдёҖиҲ¬зҡ„гҒӘжүҖеҫ—гҒ®ж–№гҒҜгҖҒжңҲйЎҚ44,400еҶҶпјҲдё–еёҜпјүгҒ§гҒҷгҖӮ
вҖ» 2021пјҲд»Өе’Ң3пјүе№ҙ8жңҲеҲ©з”ЁеҲҶгӮҲгӮҠгҖҒдёҖе®ҡе№ҙеҸҺд»ҘдёҠгҒ®й«ҳжүҖеҫ—иҖ…гҒ®иІ жӢ…дёҠйҷҗйЎҚгҒҢзҙ°еҲҶеҢ–гҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
еҲ©з”ЁиҖ…иІ жӢ…гҒ®дёҠйҷҗйЎҚ
| еҲ©з”ЁиҖ…иІ жӢ…ж®өйҡҺ | дёҠйҷҗйЎҚ пјҲжңҲйЎҚпјү |
|
| иӘІзЁҺжүҖеҫ—380дёҮеҶҶпјҲе№ҙеҸҺзҙ„770дёҮеҶҶпјүпҪһиӘІзЁҺжүҖеҫ—690дёҮеҶҶпјҲе№ҙеҸҺзҙ„1,160дёҮеҶҶпјүжңӘжәҖгҒ®ж–№ | 140,100еҶҶ пјҲдё–еёҜпјү |
|
| иӘІзЁҺжүҖеҫ—690дёҮеҶҶпјҲе№ҙеҸҺзҙ„1,160дёҮеҶҶпјүд»ҘдёҠгҒ®ж–№ | 93,000еҶҶ пјҲдё–еёҜпјү |
|
| еёӮз”әжқ‘ж°‘зЁҺиӘІзЁҺпҪһиӘІзЁҺжүҖеҫ—380дёҮеҶҶпјҲе№ҙеҸҺзҙ„770дёҮеҶҶпјүжңӘжәҖгҒ®ж–№ | 44,400еҶҶ пјҲдё–еёҜпјү |
|
| еёӮз”әжқ‘ж°‘зЁҺиӘІзЁҺпҪһиӘІзЁҺжүҖеҫ—380дёҮеҶҶпјҲе№ҙеҸҺзҙ„770дёҮеҶҶпјүжңӘжәҖгҒ®ж–№ | еүҚе№ҙгҒ®е…¬зҡ„е№ҙйҮ‘зӯүеҸҺе…ҘйЎҚпјӢгҒқгҒ®д»–гҒ®еҗҲиЁҲжүҖеҫ—йҮ‘йЎҚгҒҢ80дёҮеҶҶд»ҘдёҠгҒ®ж–№ | 24,600еҶҶ пјҲдё–еёҜпјү |
| еүҚе№ҙгҒ®е…¬зҡ„е№ҙйҮ‘зӯүеҸҺе…ҘйЎҚпјӢгҒқгҒ®д»–гҒ®еҗҲиЁҲжүҖеҫ—йҮ‘йЎҚгҒҢ80дёҮеҶҶд»ҘдёӢгҒ®ж–№иҖҒйҪўзҰҸзҘүе№ҙйҮ‘гӮ’еҸ—зөҰгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢж–№ | 24,600еҶҶпјҲдё–еёҜпјү 15,000еҶҶпјҲеҖӢдәәпјү |
|
| з”ҹжҙ»дҝқиӯ·гӮ’еҸ—зөҰгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢж–№гҒӘгҒ© | 15,000еҶҶ пјҲеҖӢдәәпјү |
|
й«ҳйЎҚд»Ӣиӯ·пјҲдәҲйҳІпјүгӮөгғјгғ“гӮ№иІ»гҒ®з”іи«Ӣж–№жі•
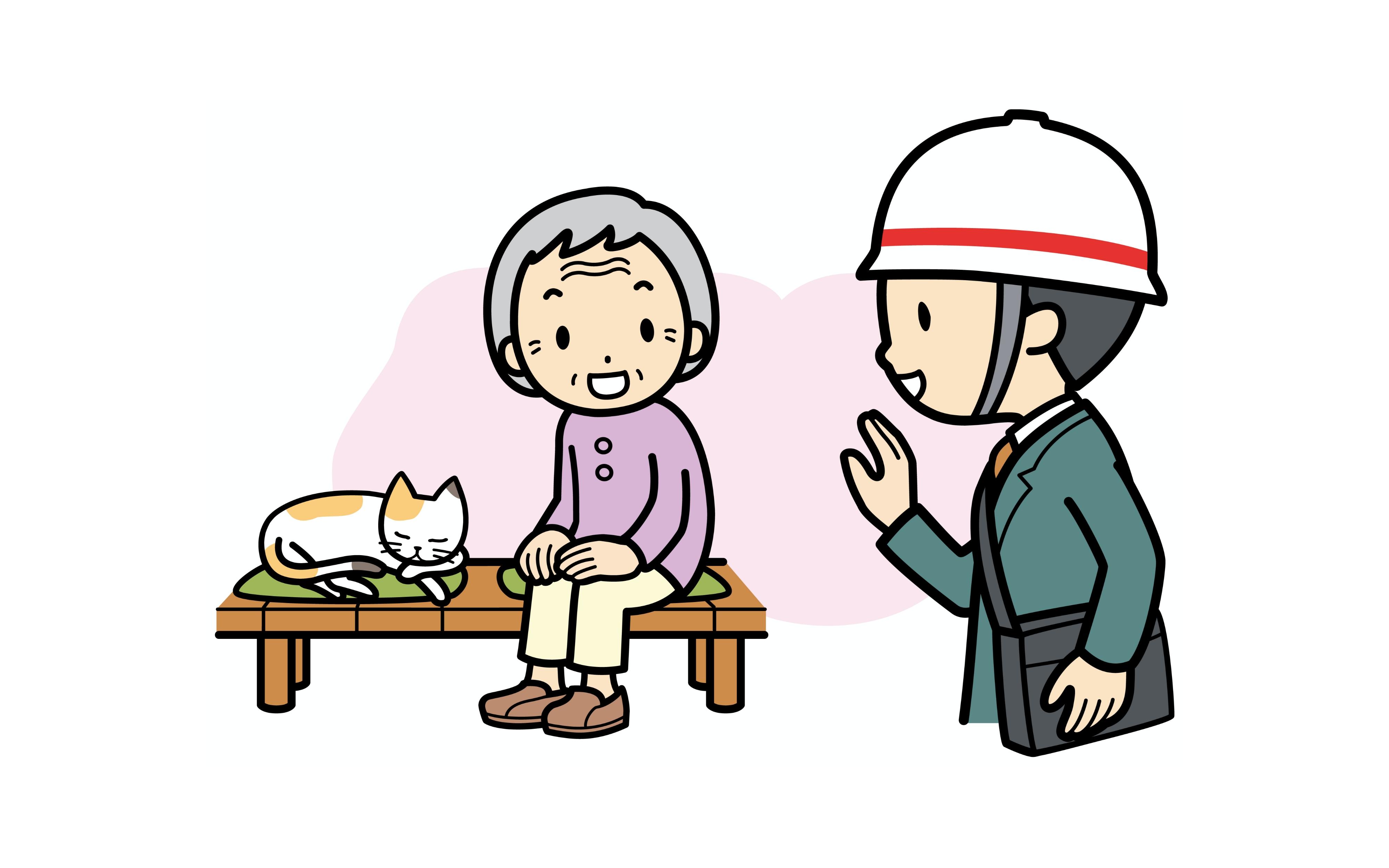
й«ҳйЎҚд»Ӣиӯ·пјҲдәҲйҳІпјүгӮөгғјгғ“гӮ№иІ»гҒ®ж”ҜзөҰгӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢгҒ«гҒҜгҖҒз”іи«ӢжүӢз¶ҡгҒҚгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҖӮ
з”іи«Ӣж–№жі•гҒҜиҮӘжІ»дҪ“гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеӨҡе°‘з•°гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒйҖҡеёёгҒҜеҜҫиұЎгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹж–№гҒ«иҮӘжІ»дҪ“гҒӢгӮүйҖҡзҹҘгҒҢжқҘгҒҫгҒҷгҖӮж”ҜзөҰз”іи«ӢжӣёгҒҢеұҠгҒ„гҒҹгӮүгҖҒеҝ…иҰҒдәӢй …гӮ’иЁҳе…ҘгҒ—гҖҒеҝ…иҰҒжӣёйЎһгӮ’ж·»д»ҳгҒ—гҒҰжҸҗеҮәгҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
еҲқеӣһгҒ®гҒҝз”іи«ӢжүӢз¶ҡгҒҚгӮ’иЎҢгҒ„гҖҒ2еӣһзӣ®д»ҘйҷҚгҒҜи©ІеҪ“гҒҷгӮҢгҒ°зҷ»йҢІгҒ—гҒҹеҸЈеә§гҒёиҮӘеӢ•зҡ„гҒ«ж”ҜзөҰйЎҚгҒҢжҢҜгӮҠиҫјгҒҫгӮҢгӮӢгҒ®гҒҢдёҖиҲ¬зҡ„гҒ§гҒҷгҖӮ
вҖ» д»Ӣиӯ·дҝқйҷәж–ҪиЁӯзӯүгҒ«е…ҘжүҖпјҲе…ҘйҷўпјүгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢж–№гҒҜгҖҒз”іи«ӢгҒ«гӮҲгӮҠгҖҢеҸ—й ҳ委任жү•гҒ„гҖҚгӮ’еҲ©з”ЁгҒ§гҒҚгӮӢе ҙеҗҲгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
й«ҳйЎҚд»Ӣиӯ·пјҲдәҲйҳІпјүгӮөгғјгғ“гӮ№иІ»гҒ®з”іи«ӢгҒҜгҖҒгӮөгғјгғ“гӮ№жҸҗдҫӣгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹжңҲгҒ®зҝҢжңҲ1ж—ҘгҒӢгӮү2е№ҙд»ҘеҶ…гҒ«иЎҢгҒҶеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ2е№ҙгӮ’зөҢйҒҺгҒҷгӮӢгҒЁз”іи«ӢгҒ§гҒҚгҒӘгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒгҒ§гҒҚгӮӢгҒ гҒ‘ж—©гӮҒгҒ«з”іи«ӢгҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
й«ҳйҪўгҒ«гҒӘгӮҠгҖҒд»Ӣиӯ·гӮ„ж”ҜжҸҙгҒҢеҝ…иҰҒгҒ«гҒӘгӮӢгҒЁгҖҒгҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒӘиІ»з”ЁгҒҢзҷәз”ҹгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮзөҢжёҲзҡ„гҒӘиІ жӢ…гӮ’е°‘гҒ—гҒ§гӮӮи»ҪгҒҸгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒе…¬зҡ„гҒӘеҲ¶еәҰгӮ’жҙ»з”ЁгҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
гҖҢй«ҳйЎҚд»Ӣиӯ·пјҲдәҲйҳІпјүгӮөгғјгғ“гӮ№иІ»гҖҚгҒ®гҒ»гҒӢгҒ«гӮӮгҖҒд»Ӣиӯ·иІ»з”ЁгҒ®иІ жӢ…гӮ’и»ҪгҒҸгҒҷгӮӢеҲ¶еәҰгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒгҖҢй«ҳйЎҚд»Ӣиӯ·еҗҲз®—зҷӮйӨҠиІ»еҲ¶еәҰпјҲе№ҙй–“гҒ®еҢ»зҷӮиІ»гҒЁд»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№иІ»гҒ®иҮӘе·ұиІ жӢ…еҗҲз®—йЎҚгҒҢйҷҗеәҰйЎҚгӮ’и¶…гҒҲгҒҹе ҙеҗҲгҒ«жү•гҒ„жҲ»гҒ•гӮҢгӮӢеҲ¶еәҰпјүгҖҚгӮ„гҖҢзү№е®ҡе…ҘжүҖиҖ…д»Ӣиӯ·пјҲдәҲйҳІпјүгӮөгғјгғ“гӮ№иІ»пјҲжүҖеҫ—гҒ®дҪҺгҒ„ж–№гҒ®д»Ӣиӯ·дҝқйҷәж–ҪиЁӯзӯүгҒ®йЈҹиІ»гғ»еұ…дҪҸиІ»гҒ®иІ жӢ…йЎҚгҒҢи»ҪжёӣгҒ•гӮҢгӮӢеҲ¶еәҰпјүгҖҚгҒӘгҒ©гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
в–јй–ўйҖЈиЁҳдәӢпјҡ
й«ҳйЎҚгҒӘеҢ»зҷӮгғ»д»Ӣиӯ·иІ»з”ЁгҒ®и»Ҫжёӣзӯ–гҖҢй«ҳйЎҚд»Ӣиӯ·еҗҲз®—зҷӮйӨҠиІ»еҲ¶еәҰгҖҚ
й«ҳйҪўеҢ–гҒҢйҖІгӮҖгҒӘгҒӢж–ҪиЎҢгҒ•гӮҢгҒҹгҖҢеҫҢжңҹй«ҳйҪўиҖ…еҢ»зҷӮеҲ¶еәҰгҖҚ
家ж—ҸгҒ®д»Ӣиӯ·гӮ’гҒҚгҒЈгҒӢгҒ‘гҒ«д»Ӣиӯ·зҰҸзҘүеЈ«гғ»зӨҫдјҡзҰҸзҘүдё»дәӢд»»з”ЁиіҮж јгӮ’еҸ–еҫ—гҖӮзҸҫеңЁгҒҜгғ©гӮӨгӮҝгғјгҖӮж—ҘгҖ…гҒ®жҡ®гӮүгҒ—гҒ«еҪ№з«ӢгҒӨиә«иҝ‘гҒӘжғ…е ұгӮ’гҒҠдјқгҒҲгҒҷгӮӢгҒ№гҒҸгҖҒд»Ӣиӯ·гғ»еҢ»зҷӮгғ»зҫҺе®№гғ»гӮ«гғ«гғҒгғЈгғјгҒӘгҒ©е№…еәғгҒ„гӮёгғЈгғігғ«гҒ®иЁҳдәӢгӮ’еҹ·зӯҶдёӯгҖӮ
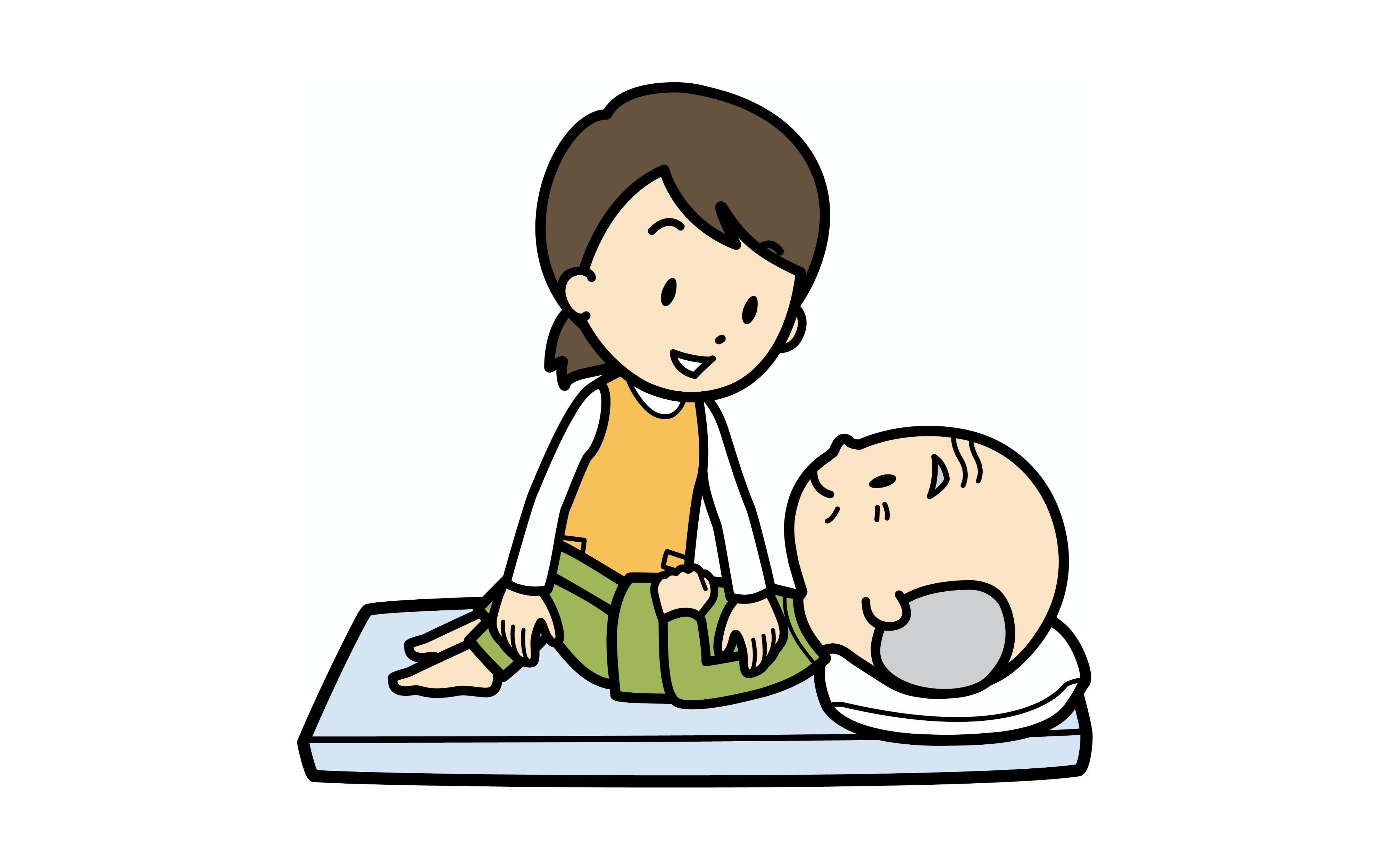
FacebookгғҡгғјгӮёгҒ§
жңҖж–°иЁҳдәӢй…ҚдҝЎпјҒпјҒ
 гғ¬гӮӘгғҸгӮҡгғ¬гӮ№21гӮҜгӮҷгғ«гғјгғ•гӮҡгҒ®д»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ’гӮҷгӮ№
гғ¬гӮӘгғҸгӮҡгғ¬гӮ№21гӮҜгӮҷгғ«гғјгғ•гӮҡгҒ®д»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ’гӮҷгӮ№