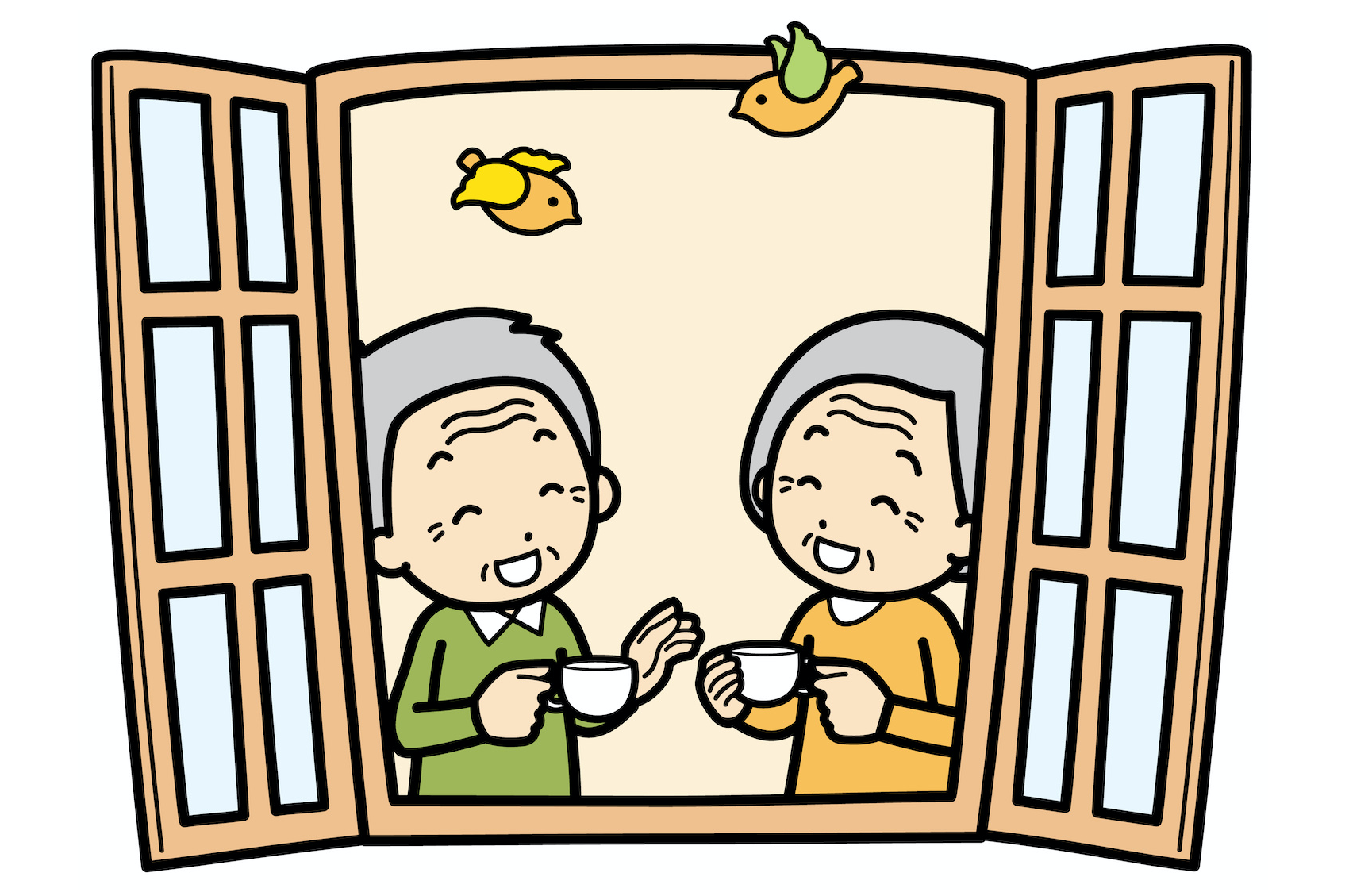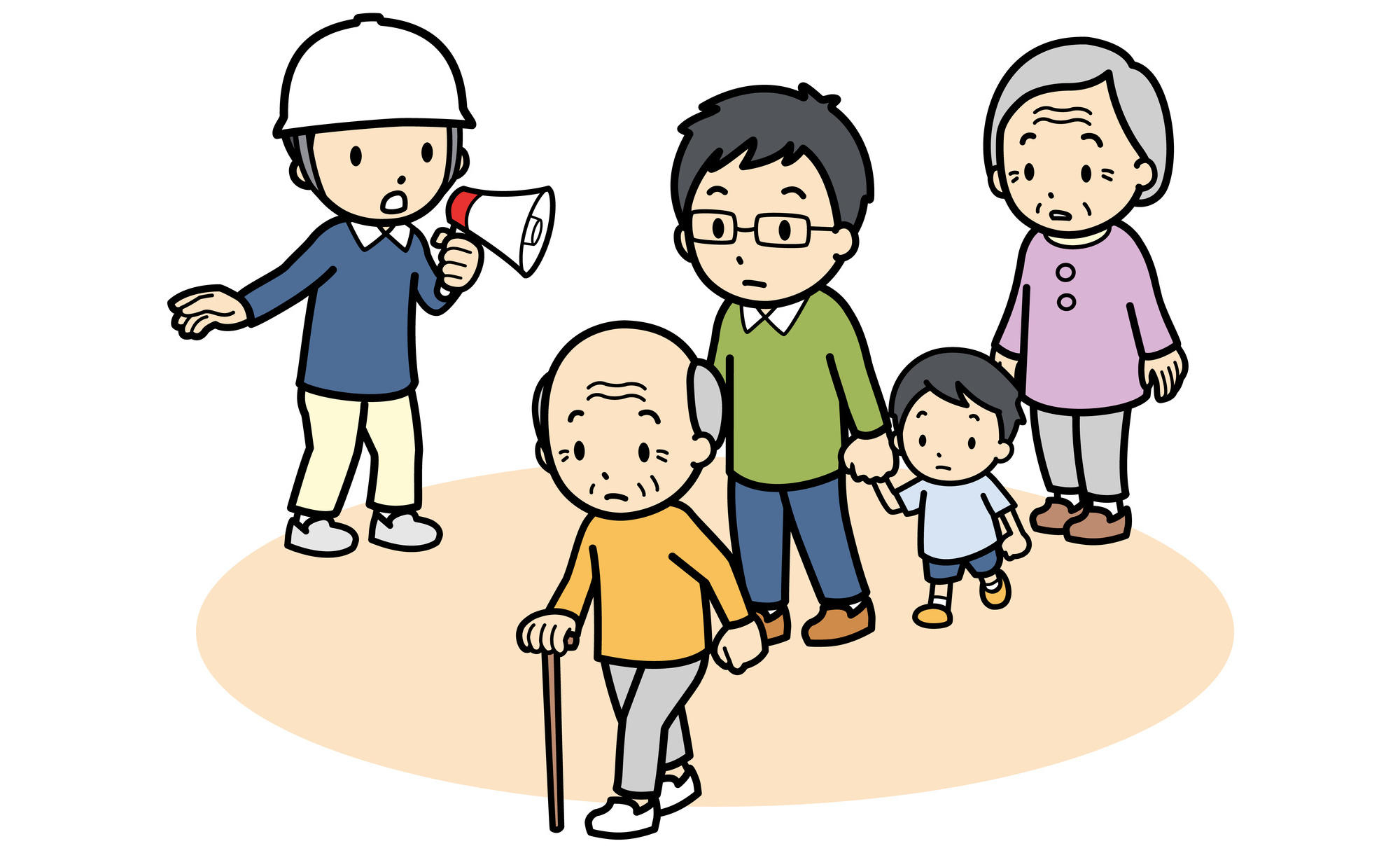д»Ӣиӯ·гҒ®дҫҝеҲ©её–гғҲгғғгғ—гҒёжҲ»гӮӢ
гҒ„гҒӨгҒҫгҒ§гӮӮиҮӘеҲҶгӮүгҒ—гҒҸжҡ®гӮүгҒ—з¶ҡгҒ‘гӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҖҢеҒҘеә·еҜҝе‘ҪгҖҚгӮ’延гҒ°гҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶпјҒ
гҒ”й«ҳйҪўиҖ…гҒ®з—…ж°—гӮ„и»ўеҖ’гҒӘгҒ©гҒ®дәӢж•…гҒҜгҖҒиҰҒд»Ӣиӯ·гӮ„еҜқгҒҹгҒҚгӮҠгҒ«гҒӨгҒӘгҒҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ„гҒӨгҒҫгҒ§гӮӮе…ғж°—гҒ§жҡ®гӮүгҒ—з¶ҡгҒ‘гӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҖҢеҒҘеә·еҜҝе‘ҪгҖҚгӮ’延гҒ°гҒҷгҒ“гҒЁгҒҢеӨ§еҲҮгҒ§гҒҷгҖӮд»ҠеӣһгҒҜгҖҒд»Ӣиӯ·гӮ„еҜқгҒҹгҒҚгӮҠгҒ®дәҲйҳІгҒЁгҒӘгӮӢйҒӢеӢ•зҝ’ж…ЈгӮ„йЈҹдәӢгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҝгҒҰгҒ„гҒҚгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
д»Ӣиӯ·гҒҢеҝ…иҰҒгҒЁгҒӘгӮӢдё»гҒӘеҺҹеӣ гҒҜпјҹ

еҺҡз”ҹеҠҙеғҚзңҒгҒ®з°Ўжҳ“з”ҹе‘ҪиЎЁгҒ«гӮҲгӮӢгҒЁгҖҒ2019пјҲд»Өе’Ңе…ғпјүе№ҙгҒ®ж—Ҙжң¬дәәгҒ®е№іеқҮеҜҝе‘ҪгҒҜгҖҒеҘіжҖ§гҒҢ87.45жӯігҖҒз”·жҖ§81.41жӯігҒ§гҖҒгҒ„гҒҡгӮҢгӮӮйҒҺеҺ»жңҖй«ҳгӮ’жӣҙж–°гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
дёҖж–№гҖҒгҖҢеҒҘеә·еҜҝе‘ҪпјҲеҒҘеә·дёҠгҒ®е•ҸйЎҢгҒ§ж—Ҙеёёз”ҹжҙ»гҒҢеҲ¶йҷҗгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒӘгҒҸз”ҹжҙ»гҒ§гҒҚгӮӢжңҹй–“пјүгҖҚгҒҜгҖҒ2016пјҲе№іжҲҗ28пјүе№ҙжҷӮзӮ№гҒ§еҘіжҖ§гҒҢ74.79жӯігҖҒз”·жҖ§гҒҢ72.14жӯігҒ§гҒ—гҒҹгҖӮ
д»Ӣиӯ·гҒҢеҝ…иҰҒгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹдё»гҒӘеҺҹеӣ гӮ’гҒҝгӮӢгҒЁгҖҒиҰҒд»Ӣиӯ·иҖ…гҒ§гҒҜгҖҢиӘҚзҹҘз—ҮгҖҚгҒҢ 24.3пј…гҒЁжңҖгӮӮеӨҡгҒҸгҖҒж¬ЎгҒ„гҒ§гҖҢи„іиЎҖз®Ўз–ҫжӮЈпјҲи„іеҚ’дёӯпјүгҖҚгҒҢ 19.2пј…гҖҒгҖҢйӘЁжҠҳгғ»и»ўеҖ’гҖҚгҒҢ 12.0пј…гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮпјҲ2019е№ҙ еӣҪж°‘з”ҹжҙ»еҹәзӨҺиӘҝжҹ»пјү
гҒ§гҒҜгҖҒиҰҒд»Ӣиӯ·гҒ«гҒӘгӮӢгғӘгӮ№гӮҜгӮ’жёӣгӮүгҒ—гҒҰгҖҢеҒҘеә·еҜҝе‘ҪгҖҚгӮ’延гҒ°гҒҷгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгҒ“гҒЁгӮ’еҝғгҒҢгҒ‘гӮҢгҒ°гӮҲгҒ„гҒ®гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖӮ
еҜқгҒҹгҒҚгӮҠгӮ’дәҲйҳІгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®зҝ’ж…ЈгӮ’гҒӨгҒ‘гӮҲгҒҶ
йҒӢеӢ•
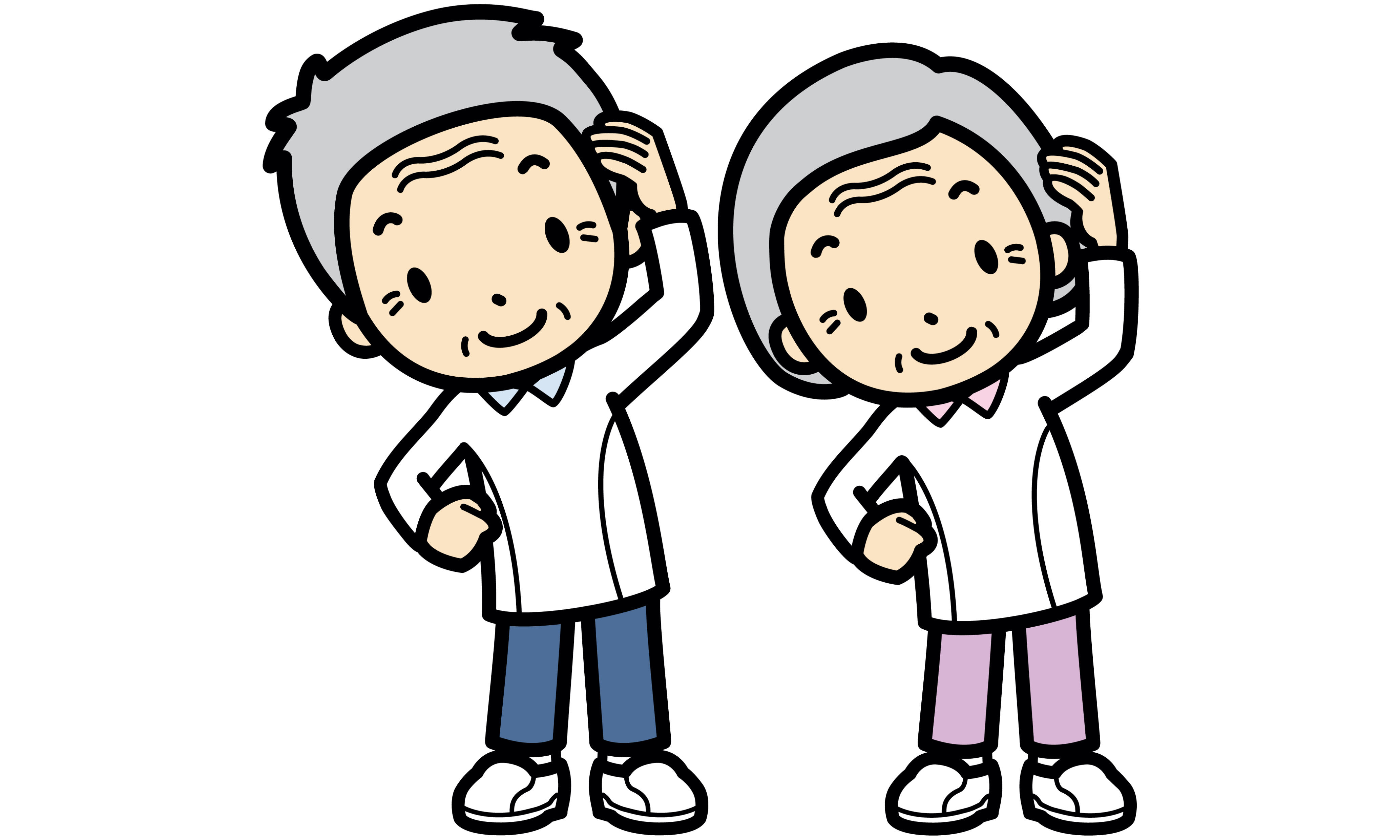
зӯӢиӮүгҒ«гҒҜгҖҢдҪ“гӮ’еӢ•гҒӢгҒҷгҖҚгҖҢгӮЁгғҚгғ«гӮ®гғјгӮ’гҒӨгҒҸгӮӢгҖҚгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹеғҚгҒҚд»ҘеӨ–гҒ«гӮӮгҖҒгҖҢи„ігҒ®еғҚгҒҚгҒ«еҪұйҹҝгӮ’дёҺгҒҲгӮӢгҖҚгҖҢгғӣгғ«гғўгғігӮ’еҲҶжіҢгҒҷгӮӢгҖҚгҒӘгҒ©гҒ®еғҚгҒҚгӮӮгӮӮгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгӮҸгҒӢгҒЈгҒҰгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
зӯӢиӮүгҒҜгҖҒдҪ•гӮӮгҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҖҒ20д»ЈгӮ’гғ”гғјгӮҜгҒ«жёӣе°‘гҒ—гҒҰгҒ„гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮгҒӮгӮӢж—ҘзӘҒ然жҖҘгҒ«жёӣгӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒқгҒ®иЎ°гҒҲгҒ«ж°—гҒҘгҒҚгҒ«гҒҸгҒ„гҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒдҪ•гӮӮгҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҖҒе°‘гҒ—гҒҡгҒӨгҒ§гҒҷгҒҢзқҖе®ҹгҒ«жёӣгӮҠз¶ҡгҒ‘гҒҰгҒ„гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒзӯӢиӮүгҒҜгҖҒ70жӯігӮ„80жӯігҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгӮӮеў—гӮ„гҒҷгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢйҒӢеӢ•еҷЁе®ҳгҒ§гҒҷгҖӮ
зӯӢеҠӣгӮўгғғгғ—гӮ„йӘЁгҒ®еј·еҢ–гҖҒгҒҫгҒҹиӘҚзҹҘз—ҮдәҲйҳІгҒ«гҖҒжүӢи»ҪгҒ«гҒ§гҒҚгҒҰзҝ’ж…ЈеҢ–гҒ—гӮ„гҒҷгҒ„йҒӢеӢ•гҒ®дёҖдҫӢгӮ’гҒ”зҙ№д»ӢгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
в—ӢзүҮи¶із«ӢгҒЎ
гғ»иғҢзӯӢгӮ’гҒҫгҒЈгҒҷгҒҗгҒ«дјёгҒ°гҒ—гҒҹгҒҫгҒҫгҖҒдёЎи¶ігӮ’гҒқгӮҚгҒҲгҒҰз«ӢгҒЎгҒҫгҒҷгҖӮ
гғ»еәҠгҒӢгӮүпј•cmгҒ»гҒ©жө®гҒӢгҒӣгҒҰзүҮи¶ігӮ’дёҠгҒ’гҒҫгҒҷгҖӮ
гғ»е·ҰеҸігҒқгӮҢгҒһгӮҢпј‘еҲҶй–“гҒҡгҒӨгӮ’пј‘гӮ»гғғгғҲгҒ§гҖҒпј‘ж—Ҙпј“гӮ»гғғгғҲиЎҢгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
и»ўеҖ’гҒ—гҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«гҒӨгҒӢгҒҫгӮӢгӮӮгҒ®гҒҢгҒӮгӮӢе ҙжүҖгҒ§иЎҢгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮж”ҜгҒҲгҒҢеҝ…иҰҒгҒӘдәәгҒҜгҖҒжңәгӮ„жүӢгҒҷгӮҠгҒ«жүӢгӮ’гҒӨгҒ„гҒҰиЎҢгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
в—ӢгӮ№гӮҜгғҜгғғгғҲ
гғ»иӮ©е№…гӮҲгӮҠе°‘гҒ—еәғгӮҒгҒ«дёЎи¶ігӮ’еәғгҒ’гҖҒгҒӨгҒҫе…ҲгӮ’30еәҰгҒҸгӮүгҒ„гҒ«й–ӢгҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
гғ»жҒҜгӮ’еҗҗгҒҚгҒӘгҒҢгӮүгӮҶгҒЈгҒҸгӮҠгҒҠе°»гӮ’дёӢгҒ’гҖҒеҗёгҒ„гҒӘгҒҢгӮүгӮҶгҒЈгҒҸгӮҠгҒЁе…ғгҒ«жҲ»гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гғ»пј‘гӮ»гғғгғҲпј•пҪһпј–еӣһгҒ§гҖҒпј‘ж—Ҙпј“гӮ»гғғгғҲиЎҢгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
и»ўеҖ’гҒ—гҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«гҒӨгҒӢгҒҫгӮӢгӮӮгҒ®гҒҢгҒӮгӮӢе ҙжүҖгҒ§иЎҢгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮж”ҜгҒҲгҒҢеҝ…иҰҒгҒӘдәәгҒҜгҖҒжңәгӮ„жүӢгҒҷгӮҠгҒ«жүӢгӮ’гҒӨгҒ„гҒҰиЎҢгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
в—ӢгҒІгҒЁгӮҠгӮёгғЈгғігӮұгғі
еҲ©гҒҚжүӢгҒ§гӮ°гғјгғ»гғҒгғ§гӮӯгғ»гғ‘гғјгҒЁй ҶгҒ«еҮәгҒ—гҖҒйҖҶгҒ®жүӢгҒҢеҝ…гҒҡиІ гҒ‘гӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гҒҰгҒҳгӮғгӮ“гҒ‘гӮ“гӮ’гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮпј‘ж—Ҙпј•еҲҶзЁӢеәҰиЎҢгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮж…ЈгӮҢгҒҹгӮүжүӢгӮ’йҖҶгҒ«гҒ—гҒҰгӮӮиЎҢгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
в—ӢгӮҰгӮ©гғјгӮӯгғігӮ°гӮ„гӮёгғ§гӮ®гғігӮ°
гӮҰгӮ©гғјгӮӯгғігӮ°гӮ„гӮёгғ§гӮ®гғігӮ°гҒӘгҒ©гҒ®жңүй…ёзҙ йҒӢеӢ•гҒҜгҖҒеҹәзӨҺд»Ји¬қйҮҸгҒ®з¶ӯжҢҒгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«гҖҒгғӘгғ•гғ¬гғғгӮ·гғҘгӮ„иЎҖиЎҢж”№е–„гҒӘгҒ©гҒ®еҠ№жһңгӮӮжңҹеҫ…гҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
в–јй–ўйҖЈиЁҳдәӢпјҡ
QOLпјҲз”ҹжҙ»гҒ®иіӘпјүгӮ’з¶ӯжҢҒгғ»еҗ‘дёҠгҒҷгӮӢгҒ”й«ҳйҪўиҖ…гҒ®зӯӢеҠӣгғҲгғ¬гғјгғӢгғігӮ°
йЈҹдәӢ

еҒҘеә·гӮ’дҝқгҒӨгҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҖҖж „йӨҠгғҗгғ©гғігӮ№гҒ®гҒЁгӮҢгҒҹйЈҹдәӢгӮ’гҒЁгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮеӨ§еҲҮгҒ§гҒҷгҖӮзӯӢиӮүгӮ„йӘЁгӮ’еј·гҒҸгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«еҝ…иҰҒгҒӘж „йӨҠзҙ гӮ’иҰӢгҒҰгҒҝгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
в—ӢгӮ«гғ«гӮ·гӮҰгғ
йӘЁйҮҸгҒ®жёӣе°‘гҖҒйӘЁзІ—гҒ—гӮҮгҒҶз—ҮгӮ’дәҲйҳІгҒҷгӮӢгҒ«гҒҜгҖҒгҒҫгҒҡгҖҒгӮ«гғ«гӮ·гӮҰгғ гӮ’еҚҒеҲҶгҒ«иЈңгҒҶгҒ“гҒЁгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҖӮгӮ«гғ«гӮ·гӮҰгғ гӮ’еӨҡгҒҸеҗ«гӮҖйЈҹе“ҒгҒ®д»ЈиЎЁгҒҜгҖҒзүӣд№ігҖҒд№іиЈҪе“ҒпјҲгғЁгғјгӮ°гғ«гғҲгҖҒгғҒгғјгӮәпјүгҒЁе°ҸйӯҡйЎһпјҲгҒ—гҒ—гӮғгӮӮгҖҒгҒЎгӮҠгӮҒгӮ“гҒҳгӮғгҒ“гҖҒгҒ—гӮүгҒҷе№ІгҒ—гҖҒгҒ„гӮҸгҒ—гҒӘгҒ©пјүгҒ§гҒҷгҖӮ
в—Ӣгғ“гӮҝгғҹгғіDгҖҒгғ“гӮҝгғҹгғіK
гғ“гӮҝгғҹгғіDгҒҜгҖҒгӮ«гғ«гӮ·гӮҰгғ гҒ®еҗёеҸҺзҺҮгӮ’й«ҳгӮҒгҒҫгҒҷгҖӮйӯҡд»ӢйЎһпјҲгҒ—гӮүгҒҷе№ІгҒ—гҖҒгӮөгғігғһгҖҒгӮөгӮұгҒӘгҒ©пјүгӮ„гҖҒгҒҚгҒ®гҒ“йЎһпјҲгғһгӮӨгӮҝгӮұгҖҒе№ІгҒ—гҒ—гҒ„гҒҹгҒ‘гҖҒгҒҚгҒҸгӮүгҒ’гҒӘгҒ©пјүгҒ«еӨҡгҒҸеҗ«гҒҫгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
гғ“гӮҝгғҹгғіKгҒҜгҖҒгӮ«гғ«гӮ·гӮҰгғ гҒҢйӘЁгҒ«жІҲзқҖгҒҷгӮӢгҒ®гӮ’дҝғгҒ—гҖҒгӮ«гғ«гӮ·гӮҰгғ гҒҢйӘЁгҒӢгӮүжөҒгӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒ®гӮ’жҠјгҒ•гҒҲгӮӢеғҚгҒҚгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮйҮҺиҸңйЎһпјҲгғӣгӮҰгғ¬гғігӮҪгӮҰгҖҒе°ҸжқҫиҸңгҖҒгғ–гғӯгғғгӮігғӘгғјгҒӘгҒ©пјүгӮ„зҙҚиұҶгҒӘгҒ©гҒ«еӨҡгҒҸеҗ«гҒҫгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
в—Ӣгғ“гӮҝгғҹгғіC
йӘЁгҒ®дё»жҲҗеҲҶгҒҜгӮігғ©гғјгӮІгғігҒЁгӮ«гғ«гӮ·гӮҰгғ гҒ§гҒҷгҖӮгғ“гӮҝгғҹгғіCгҒҢдёҚи¶ігҒҷгӮӢгҒЁгӮігғ©гғјгӮІгғігӮӮдёҚи¶ігҒ—гҖҒйӘЁгҒҢжӯЈгҒ—гҒҸеҪўжҲҗгҒ•гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©гҒ®йҮҺиҸңгҒЁжһңзү©гҒ«еҗ«гҒҫгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
в—ӢгҒҹгӮ“гҒұгҒҸиіӘ
гҒҹгӮ“гҒұгҒҸиіӘгҒҜгҖҒзӯӢиӮүгҒ®е…ғгҒ«гҒӘгӮӢж „йӨҠзҙ гҒ§гҒҷгҖӮеҹәзӨҺд»Ји¬қгӮ’дёҠгҒ’гӮӢеҠ№жһңгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮиӮүйЎһгҖҒйӯҡд»ӢйЎһгҖҒеҚөйЎһгҖҒеӨ§иұҶиЈҪе“ҒпјҲзҙҚиұҶгҖҒиұҶи…җгҒӘгҒ©пјүгҖҒд№іиЈҪе“ҒпјҲгғЁгғјгӮ°гғ«гғҲгҖҒгғҒгғјгӮәгҒӘгҒ©пјүгҒ«еӨҡгҒҸеҗ«гҒҫгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
в–јй–ўйҖЈиЁҳдәӢпјҡ
гҒ”й«ҳйҪўиҖ…гҒ®дҪҺж „йӨҠгӮ’йҳІгҒҗгҒҹгӮҒгҒ«жҙ»з”ЁгҒ—гҒҹгҒ„гҖҢйЈҹдәӢгғҗгғ©гғігӮ№гӮ¬гӮӨгғүгҖҚ
ж—©гӮҒгҒ®гғ•гғ¬гӮӨгғ«пјҲиҷҡејұпјүеҜҫзӯ–гҒ§еҒҘеә·й•·еҜҝгӮ’зӣ®жҢҮгҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶ
гғ•гғ¬гӮӨгғ«пјҲиҷҡејұпјүгҒ®иҰҒеӣ гҒ®гҒІгҒЁгҒӨгҖҢгӮөгғ«гӮігғҡгғӢгӮўгҖҚгӮ’йҳІгҒҺгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶ
еҒҘеә·еҜҝе‘ҪгӮ’延гҒ°гҒҷгҒҹгӮҒгҒ«пјҒгғӯгӮігғўгғҶгӮЈгғ–гӮ·гғігғүгғӯгғјгғ гӮ’дәҲйҳІгҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶ
зӯӢиӮүгӮ’гҒӨгҒ‘гҒҹгӮҠгҖҒйЈҹдәӢгҒ«ж°—гӮ’гҒӨгҒ‘гҒҹгӮҠгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҖҒд»Ӣиӯ·дәҲйҳІгҒ«гҒӨгҒӘгҒҢгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ„гҒӨгҒҫгҒ§гӮӮиҮӘеҲҶгӮүгҒ—гҒҸжҡ®гӮүгҒӣгӮӢз”ҹжҙ»гӮ’зӣ®жҢҮгҒ—гҒҰгҖҒе°ҸгҒ•гҒӘгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҒ§гӮӮгҒңгҒІе§ӢгӮҒгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
зӨҫдјҡзҰҸзҘүеЈ«иіҮж јдҝқжңүгҒ®гғ©гӮӨгӮҝгғјгҖӮгҖҢд»Ӣиӯ·гҖҚгӮ’дёӯеҝғгҒЁгҒ—гҒҹзҰҸзҘүеҲҶйҮҺгҒ§гҖҒеҹ·зӯҶжҙ»еӢ•гӮ’з¶ҡгҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

FacebookгғҡгғјгӮёгҒ§
жңҖж–°иЁҳдәӢй…ҚдҝЎпјҒпјҒ
 гғ¬гӮӘгғҸгӮҡгғ¬гӮ№21гӮҜгӮҷгғ«гғјгғ•гӮҡгҒ®д»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ’гӮҷгӮ№
гғ¬гӮӘгғҸгӮҡгғ¬гӮ№21гӮҜгӮҷгғ«гғјгғ•гӮҡгҒ®д»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ’гӮҷгӮ№