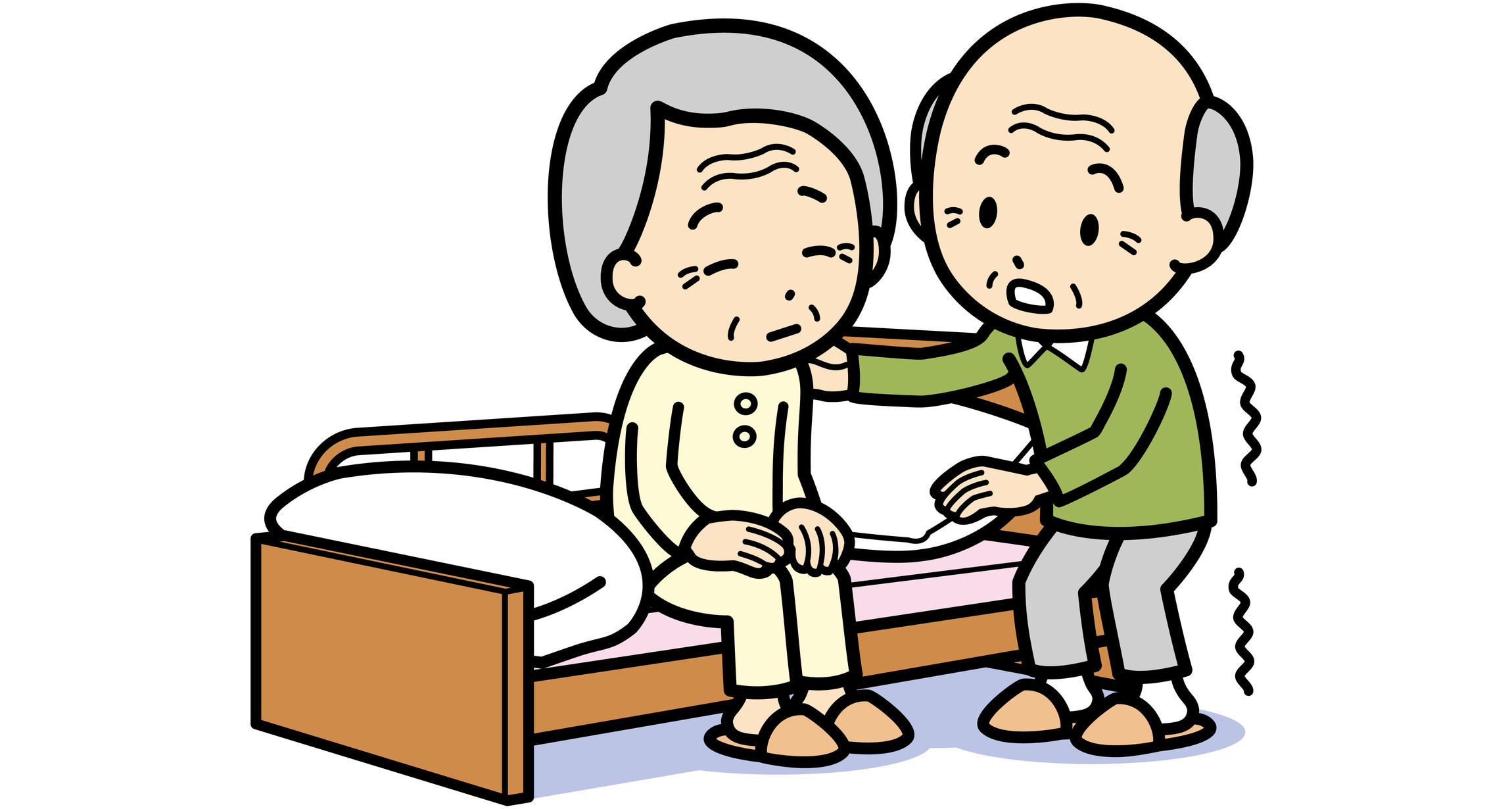дїЛи≠ЈгБЃдЊњеИ©еЄЦгГИгГГгГЧгБЄжИїгВЛ
1дЇЇгБІи§ЗжХ∞дЇЇгБЃдїЛи≠ЈгВТињЂгВЙгВМгВЛгАМе§ЪйЗНдїЛи≠ЈгАНгБЃеЃЯжЕЛгБ®иІ£ж±ЇгБЃгГТгГ≥гГИ
еЬ®еЃЕдїЛи≠ЈгВТгБХгВМгБ¶гБДгВЛжЦєгБЃдЄ≠гБЂгБѓгАБ1дЇЇгБІ2дЇЇдї•дЄКгБЃдїЛи≠ЈгВТгБЧгАБз≤Њз•ЮзЪДгГїиВЙдљУзЪДзЦ≤еКігБІйЩРзХМгВТжДЯгБШгБ¶гБДгВЛжЦєгВВгБДгВЙгБ£гБЧгВГгБДгБЊгБЩгАВдїКеЫЮгБѓгАБгБУгБЃгВИгБЖгБ™и§ЗжХ∞гБЃжЦєгВТеРМжЩВгБЂдїЛи≠ЈгБЩгВЛгАМе§ЪйЗНдїЛи≠ЈгАНгБЂгБ§гБДгБ¶гАБгБЭгБЃеЃЯжЕЛгБ®иІ£ж±ЇгБЃгГТгГ≥гГИгВТгБКдЉЭгБИгБЧгБЊгБЩгАВ
е§ЪйЗНдїЛи≠ЈгБ®гБѓ

гБФйЂШ隥иАЕгВДйЪЬгБМгБДгБМгБВгВЛжЦєгБ™гБ©и§ЗжХ∞дЇЇгВТеРМжЩВгБЂдїЛи≠ЈгБЩгВЛгБУгБ®гВТгАМе§ЪйЗНдїЛи≠ЈгАНгБ®гБДгБДгБЊгБЩгАВ
дЊЛгБИгБ∞гАБи¶БдїЛи≠ЈзКґжЕЛгБЃзȴ趙гБ®жѓН趙гВТ1дЇЇгБІдїЛи≠ЈгБЧгБ¶гБДгВЛе†іеРИгАБйЪЬгБМгБДгБМгБВгВЛе≠РгБ©гВВгБ®иЗ™еИЖгБЃзȴ趙гБЊгБЯгБѓжѓН趙гВТ1дЇЇгБІдїЛи≠ЈгБЧгБ¶гБДгВЛе†іеРИгБ™гБ©гБІгБЩгАВ
гБУгБЃгВИгБЖгБ™е†іеРИгАБдїЛи≠ЈгВµгГЉгГУгВєгВТеИ©зФ®гБЧгБ¶гБДгБ™гБДжЩВйЦУгБѓгАБдїШгБНгБ£гБНгВКгБЃзКґж≥БгБЂгБ™гВКгБЊгБЩгАВе§ЪйЗНдїЛи≠ЈгБѓдїЛи≠ЈгВТгБЩгВЛжЦєгБЃзФЯжіїгБЂе§ІгБНгБ™ељ±йЯњгВТдЄОгБИгВЛжЈ±еИїгБ™еХПй°МгБ™гБЃгБІгБЩгАВ
вЦЉйЦҐйА£и®ШдЇЛпЉЪ
иВ≤еЕРгБ®дїЛи≠ЈгБМйЗНгБ™гВЛгАМгГАгГЦгГЂгВ±гВҐгАНгБ®гБѓпЉЯгБЭгБЃеЃЯжЕЛгБ®еѓЊз≠Ц
е§ІдЇЇгБЃдї£гВПгВКгБЂеЃґдЇЛгВДгБФеЃґжЧПгБЃгВ±гВҐгБ™гБ©гВТжЛЕгБЖгАМгГ§гГ≥гВ∞гВ±гВҐгГ©гГЉгАН
е§ЪйЗНдїЛи≠ЈгБЃеЃЯжЕЛгБЂгБ§гБДгБ¶

дЇЇеП£гБЃжО®зІї
гАМе§ЪйЗНдїЛи≠ЈгАНгБЃиГМжЩѓгБЂгБѓе∞Се≠РйЂШ隥еМЦгБЃйА≤и°МгБМгБВгВКгБЊгБЩгАВ
жШФгБѓ1дЇЇгБЃе•≥жАІгБМгАБе≠РгБ©гВВгВТгБЯгБПгБХгВУеЗЇзФ£гБЧгБ¶гБДгБЊгБЧгБЯгАВеРИи®ИзЙєжЃКеЗЇзФЯзОЗпЉИ1дЇЇгБЃе•≥жАІгБМзФЯжґѓгБЂзФЯгВАгБ®и¶ЛиЊЉгБЊгВМгВЛе≠РгБ©гВВгБЃжХ∞гВТз§ЇгБЩжМЗж®ЩпЉЙгВТгБњгВЛгБ®гАБзђђ1жђ°гГЩгГУгГЉгГЦгГЉгГ†жЬЯгБѓ4.3гВТиґЕгБИгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ
гБЧгБЛгБЧгАБ2023пЉИдї§еТМ5пЉЙеєігБЃеРИи®ИзЙєжЃКеЗЇзФЯзОЗгБѓ 1.20 гБЊгБІдљОдЄЛгБЧгБ¶гБДгВЛгБЃгБІгБЩгАВдїКеЊМгБѓе∞Се≠РйЂШ隥еМЦгБМгБХгВЙгБЂжА•йАЯгБЂйА≤е±ХгБЩгВЛгБ®дЇИжЄђгБХгВМгБ¶гБДгВЛгБЯгВБгАБе§ЪйЗНдїЛи≠ЈгВВеҐЧгБИгВЛгБУгБ®гБМдЇИжГ≥гБХгВМгБЊгБЩгАВ
е§ЪйЗНдїЛи≠ЈгБЧгБ¶гБДгВЛжЦєгБЃзґЪжЯД
еОЪзФЯеКіеГНзЬБгБЃи™њжЯїпЉИ2022еєі еЫљж∞СзФЯжіїеЯЇз§Ои™њжЯїпЉЙгБІгБѓгАБдЄїгБ™дїЛи≠ЈиАЕгБѓи¶БдїЛи≠ЈиАЕз≠ЙгБ®еРМе±ЕгБЧгБ¶гБДгВЛжЦєгБМ45.9пЉЕгБ®жЬАгВВе§ЪгБПгБ™гБ£гБ¶гБДгБЊгБЩгАВ
еЖЕи®≥гВТгБњгВЛгБ®гАБйЕНеБґиАЕгБМ22.9пЉЕгАБйЂШ隥гБЃи¶™еЊ°гБХгВУгВТгВВгБ§е≠РгБМ16.2пЉЕгАБе≠РгБЃйЕНеБґиАЕгБМ5.4пЉЕгБ®гБ™гБ£гБ¶гБДгБЊгБЩгАВ
и¶БдїЛи≠ЈиАЕз≠ЙгБ®еРМе±ЕгБЧгБ¶гБДгВЛдЄїгБ™дїЛи≠ЈиАЕгБЃеєійљҐгБЂгБ§гБДгБ¶гБњгВЛгБ®гАБзФЈжАІгБІгБѓ75пЉЕгАБе•≥жАІгБІгБѓ76.5пЉЕгБМ60ж≠≥дї•дЄКгБІгБЧгБЯгАВгБ§гБЊгВКгАБгБФйЂШ隥иАЕгБМгБФйЂШ隥иАЕгВТдїЛи≠ЈгБЩгВЛгАМиАБиАБдїЛи≠ЈгАНгБЃгВ±гГЉгВєгВВе§ЪгБПгАБйЂШ隥еМЦгБЃйА≤и°МгБЂдЉігБ£гБ¶дїКеЊМгВВеҐЧеК†гБЧгБ¶гБДгБПгБ®и¶ЛиЊЉгБЊгВМгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ
вЦЉйЦҐйА£и®ШдЇЛпЉЪ
еҐЧеК†гБЧгБ¶гБДгВЛгАМиАБиАБдїЛи≠ЈгАНгБ®гБѓпЉЯзЯ•гБ£гБ¶гБКгБНгБЯгБДгВµгГЭгГЉгГИдљУеИґ
е§ЪйЗНдїЛи≠ЈгБЃеХПй°МзВє

дЊЛгБИгБ∞гАБ80ж≠≥гБЃгБФ姀婶2дЇЇгВТе≠РгБ©гВВ1дЇЇгБМдїЛи≠ЈгБЩгВЛгБУгБ®гВТжГ≥еЃЪгБЧгБ¶гБњгБЊгБЧгВЗгБЖгАВе≠РгБ©гВВгБМ50ж≠≥гБ†гБ®гБЩгВМгБ∞гАБгБЊгБ†гБЊгБ†еГНгБЛгБ™гБСгВМгБ∞гБ™гВКгБЊгБЫгВУгАВгБЧгБЛгБЧгАБеГНгБНгБ™гБМгВЙ趙匰гБХгВУ2дЇЇгБЃдїЛи≠ЈгБѓгБІгБНгБЪгАБдїХдЇЛгВТиЊЮгВБгБ™гБСгВМгБ∞гБ™гВЙгБ™гБДзКґж≥БгБЂгБ™гВЛгБУгБ®гВВгБВгВКгБЊгБЩгАВгБУгБУгБІгАМдїЛи≠ЈйЫҐиБЈгАНгБЃеХПй°МгВДзµМжЄИзЪДи≤†жЛЕгВВгБІгБ¶гБНгБЊгБЩгАВ
гБЊгБЯгАБе§ЪйЗНдїЛи≠ЈгВТгБЧгБ¶гБДгВЛжЦєгБЃењГзРЖзЪДгГїиЇЂдљУзЪДи≤†жЛЕгВВгБЛгБ™гВКе§ІгБНгБ™гВВгБЃгБ®гБ™гВКгБЊгБЩгАВеИЗињЂгБЧгБЯзКґжЕЛгБЂгБ™гВМгБ∞гАБгАМйЂШ隥иАЕиЩРеЊЕгАНгВДгАМеЕ±еАТгВМгАНгБЃеХПй°МгБМиµЈгБУгВЛеПѓиГљжАІгВВгБВгВЛгБЛгВВгБЧгВМгБЊгБЫгВУгАВгБУгБЃгВИгБЖгБЂгАМе§ЪйЗНдїЛи≠ЈгАНгБѓгАБгБХгБЊгБЦгБЊгБ™еХПй°МгВТеЉХгБНиµЈгБУгБЩгБНгБ£гБЛгБСгБ®гБ™гБ£гБ¶гБЧгБЊгБЖе†іеРИгБМгБВгВКгБЊгБЩгАВ
вЦЉйЦҐйА£и®ШдЇЛпЉЪ
дїЛи≠ЈйЫҐиБЈгВТйШ≤гБР пљЮдїХдЇЛгБ®дїЛи≠ЈгВТдЄ°зЂЛгБЩгВЛгБЯгВБгБЂгБІгБНгВЛгБУгБ®пљЮ
дїЦдЇЇдЇЛгБІгБѓгБ™гБДгАМйЂШ隥иАЕиЩРеЊЕгАНгВТжЬ™зДґгБЂйШ≤гБРгБЯгВБгБЂгБІгБНгВЛгБУгБ®
гБХгБЊгБЦгБЊгБ™и¶БеЫ†гБЂгВИгВЛгАМ8050пЉИгБѓгБ°гБЊгВЛгГїгБФгБЖгБЊгВЛпЉЙеХПй°МгАНгБЃзПЊзКґгБ®жФѓжПідљУеИґ
е§ЪйЗНдїЛи≠ЈгБЃиІ£ж±ЇгБЃгГТгГ≥гГИ
е§ЪйЗНдїЛи≠ЈгБѓгБДгБ§еІЛгБЊгВЛгБЛгАБдЇИжЄђгБІгБНгБЊгБЫгВУгАВе§ЪйЗНдїЛи≠ЈгБЃзКґж≥БгБЂгБ™гВКгАБдЄНеЃЙгБ™гБУгБ®гАБеЫ∞гБ£гБ¶гБДгВЛгБУгБ®гБ™гБ©гБМгБВгВЛе†іеРИгБѓгАБгБ≤гБ®гВКгБІжВ©гБЊгБЪе∞ВйЦАеЃґгБЂзЫЄиЂЗгБЧгАБйБ©еИЗгБ™ж©ЯйЦҐгБЂгБ§гБ™гБДгБІгВВгВЙгБДгБЊгБЧгВЗгБЖгАВ
еЬ∞еЯЯеМЕжЛђжФѓжПігВїгГ≥гВњгГЉгБѓгАБзЫіжО•зЪДдїЛи≠ЈгБ†гБСгБІгБ™гБПгАБеМїзЩВгВДз¶Пз•ЙгБЂйЦҐгБЩгВЛгБХгБЊгБЦгБЊгБ™зЫЄиЂЗгВДжВ©гБњгБЂгВВеѓЊењЬгБЧгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ
гБЊгБЯгАБгВєгГИгГђгВєгВДдЄНжЇАгВТзЩЇжХ£гБХгБЫгВЛгБЯгВБгБЂгАБе≠§зЂЛгБЫгБЪеС®еЫ≤гБЃжЦєгБЂзЫЄиЂЗгБЧгБ¶гБњгВЛгБЃгВВгБ≤гБ®гБ§гБЃжЦєж≥ХгБІгБЩгАВ
е∞Се≠РйЂШ隥еМЦгБЃеВЊеРСгБМзґЪгБПйЩРгВКгАБдїКеЊМгВВе§ЪйЗНдїЛи≠ЈгБѓгБЊгБЩгБЊгБЩеҐЧгБИгВЛгБУгБ®гБМдЇИжГ≥гБХгВМгБЊгБЩгАВе§ЪйЗНдїЛи≠ЈгБЛгВЙиµЈгБУгВЛеХПй°МгВТе∞СгБЧгБІгВВиІ£ж±ЇгБЩгВЛгБЯгВБгАБеЬ∞еЯЯеМЕжЛђжФѓжПігВїгГ≥гВњгГЉгБЂзЫЄиЂЗгВТгБЩгВЛгАБдїЛи≠ЈдњЭйЩЇгВµгГЉгГУгВєгВДеЬ∞еЯЯгБЃз§ЊдЉЪи≥ЗжЇРгВТдЄКжЙЛгБПжіїзФ®гБЩгВЛгБ™гБ©гБЧгБ¶гАБе§ЪйЗНдїЛи≠ЈгВТгБЧгБ¶гБДгВЛжЦєгБЃи≤†жЛЕгВТгБІгБНгВЛгБ†гБСжЄЫгВЙгБЩгВИгБЖгБЂгБЧгБЊгБЧгВЗгБЖгАВ
вЦЉйЦҐйА£и®ШдЇЛпЉЪ
еЬ∞еЯЯеМЕжЛђжФѓжПігВїгГ≥гВњгГЉгБ£гБ¶гБ©гВУгБ™гБ®гБУгВНпЉЯ гБЭгБЃж•≠еЛЩеЖЕеЃєгБ®ељєеЙ≤гБЂгБ§гБДгБ¶
вЦЉйЦҐйА£жГЕ冱пЉЪ
гБВгБЪгБњиЛСгБЃжЦљи®≠дЄАи¶ІгВТи¶ЛгВЛ
дїЛи≠Јз¶Пз•Йе£Ђй§КжИРгБЃе∞ВйЦАе≠¶ж†°гВТеНТж•≠еЊМгАБзЙєеИ•й§Ки≠ЈиАБдЇЇгГЫгГЉгГ†гБЂдїЛи≠ЈгВєгВњгГГгГХгБ®гБЧгБ¶7еєійЦУеЛ§еЛЩгБЩгВЛгАВжЦљи®≠гВ±гВҐгГЮгГНгВЄгГ£гГЉгВДзФЯжіїзЫЄиЂЗеУ°гБ™гБ©гВТзµМй®УгБЧгБ¶дїКгБЂиЗ≥гВЛгАВи≥Зж†ЉгБѓдїЛи≠Јз¶Пз•Йе£ЂгАБдїЛи≠ЈжФѓжПіе∞ВйЦАеУ°гАБз§ЊдЉЪз¶Пз•Йе£ЂгАБз§ЊдЉЪз¶Пз•ЙдЄїдЇЛдїїзФ®и≥Зж†ЉгБ™гБ©гВТеПЦеЊЧгБЧгБ¶гБДгВЛгАВ

FacebookгГЪгГЉгВЄгБІ
жЬАжЦ∞и®ШдЇЛйЕНдњ°пЉБпЉБ
 гГђгВ™гГПгВЪгГђгВє21гВѓгВЩгГЂгГЉгГХгВЪгБЃдїЛи≠ЈгВµгГЉгГТгВЩгВє
гГђгВ™гГПгВЪгГђгВє21гВѓгВЩгГЂгГЉгГХгВЪгБЃдїЛи≠ЈгВµгГЉгГТгВЩгВє