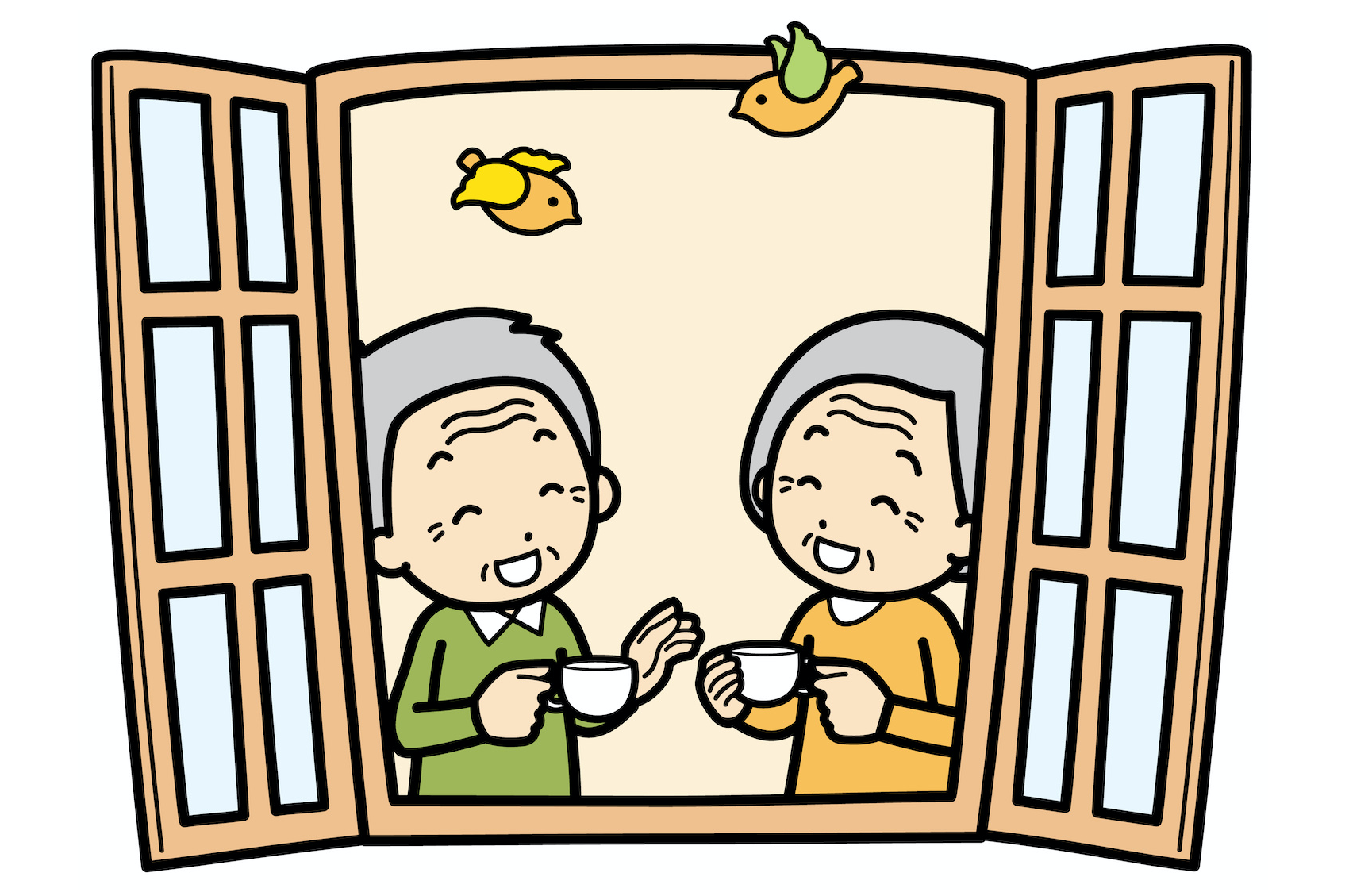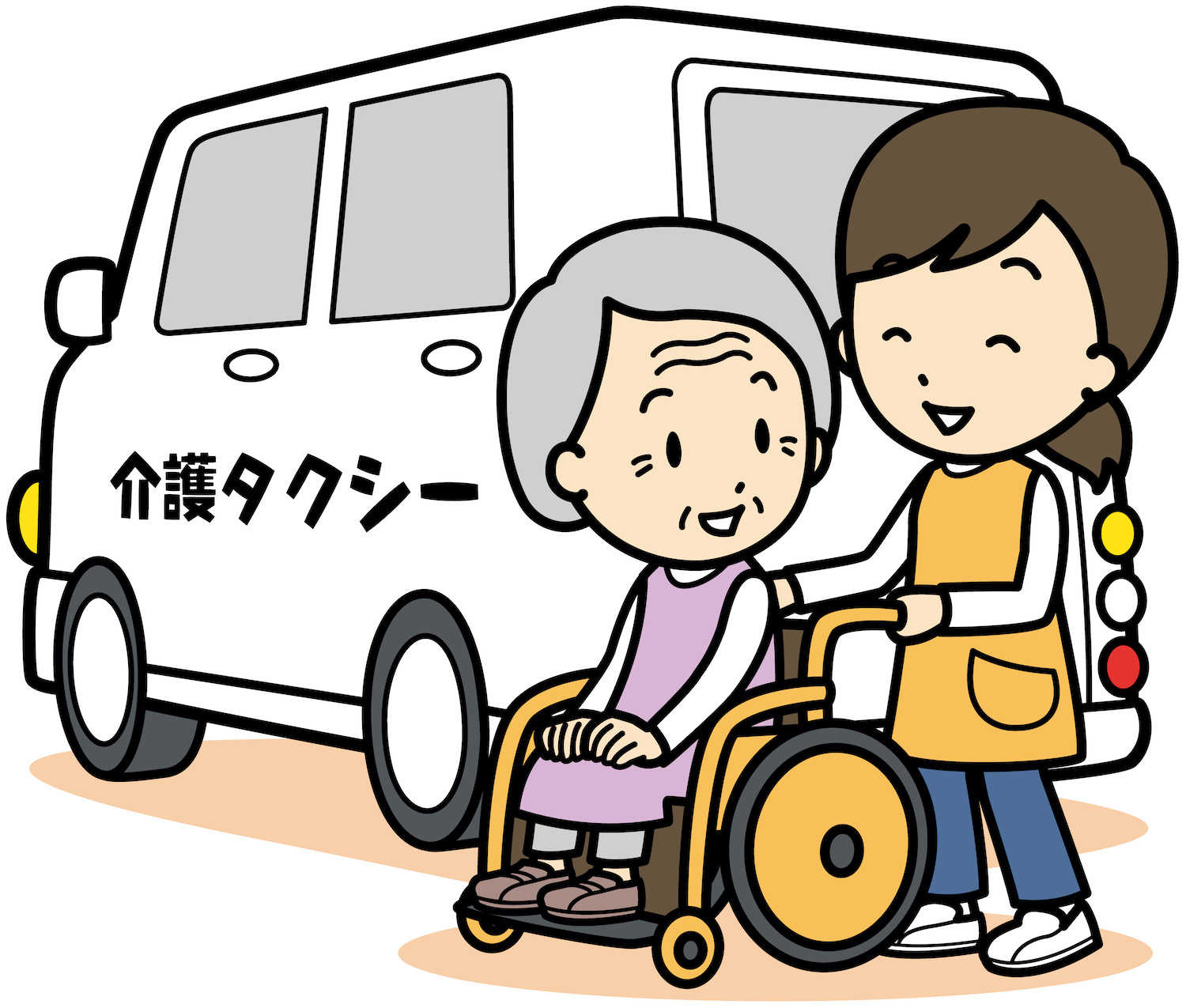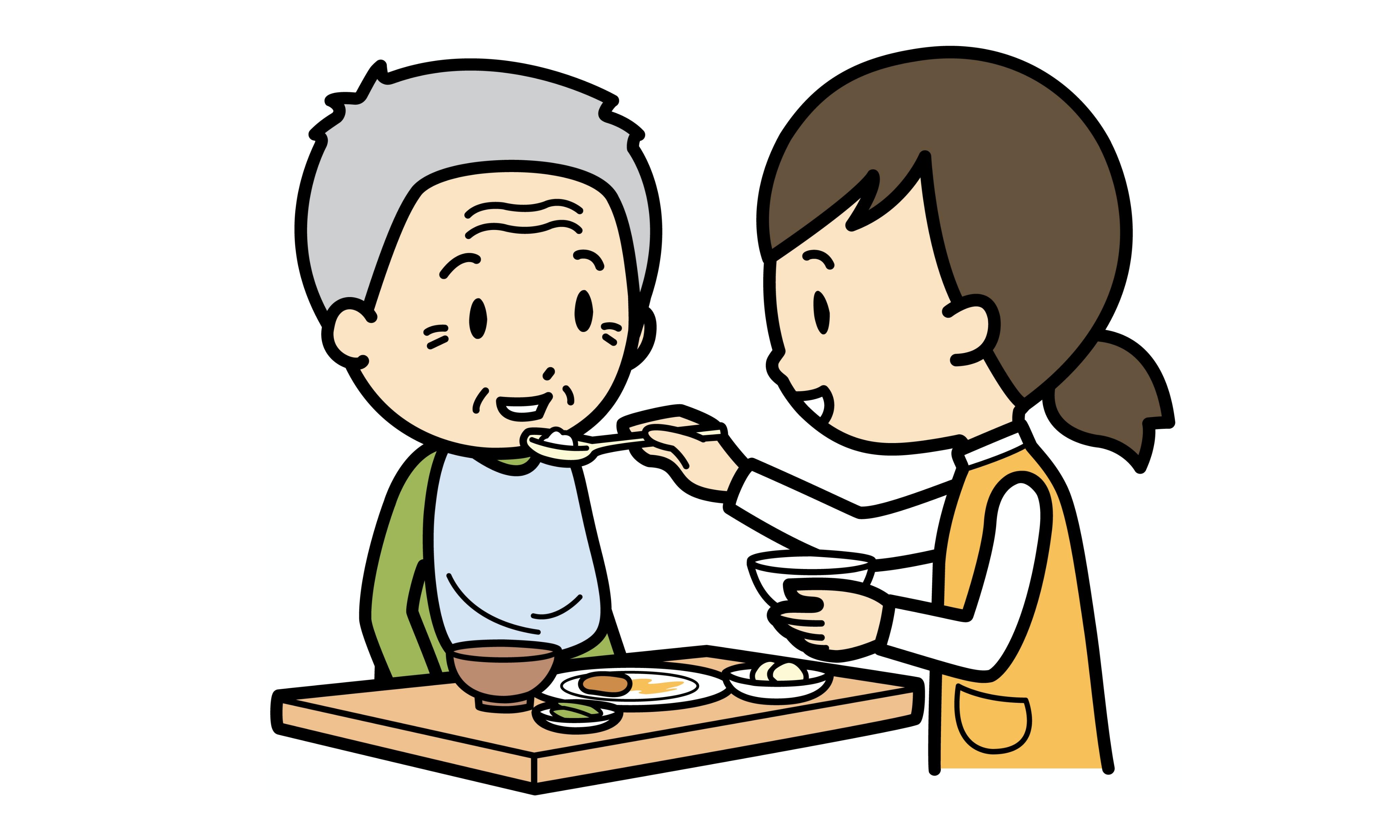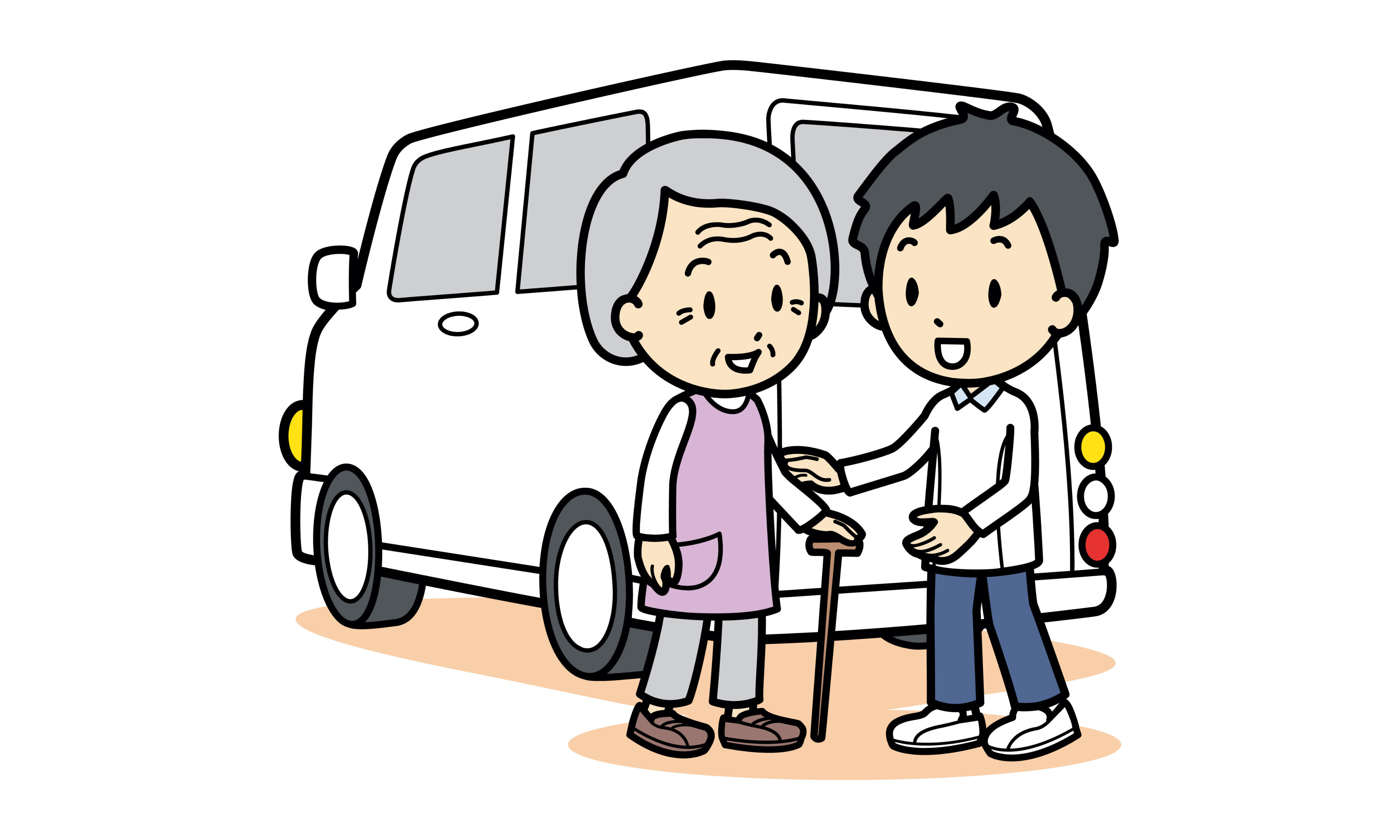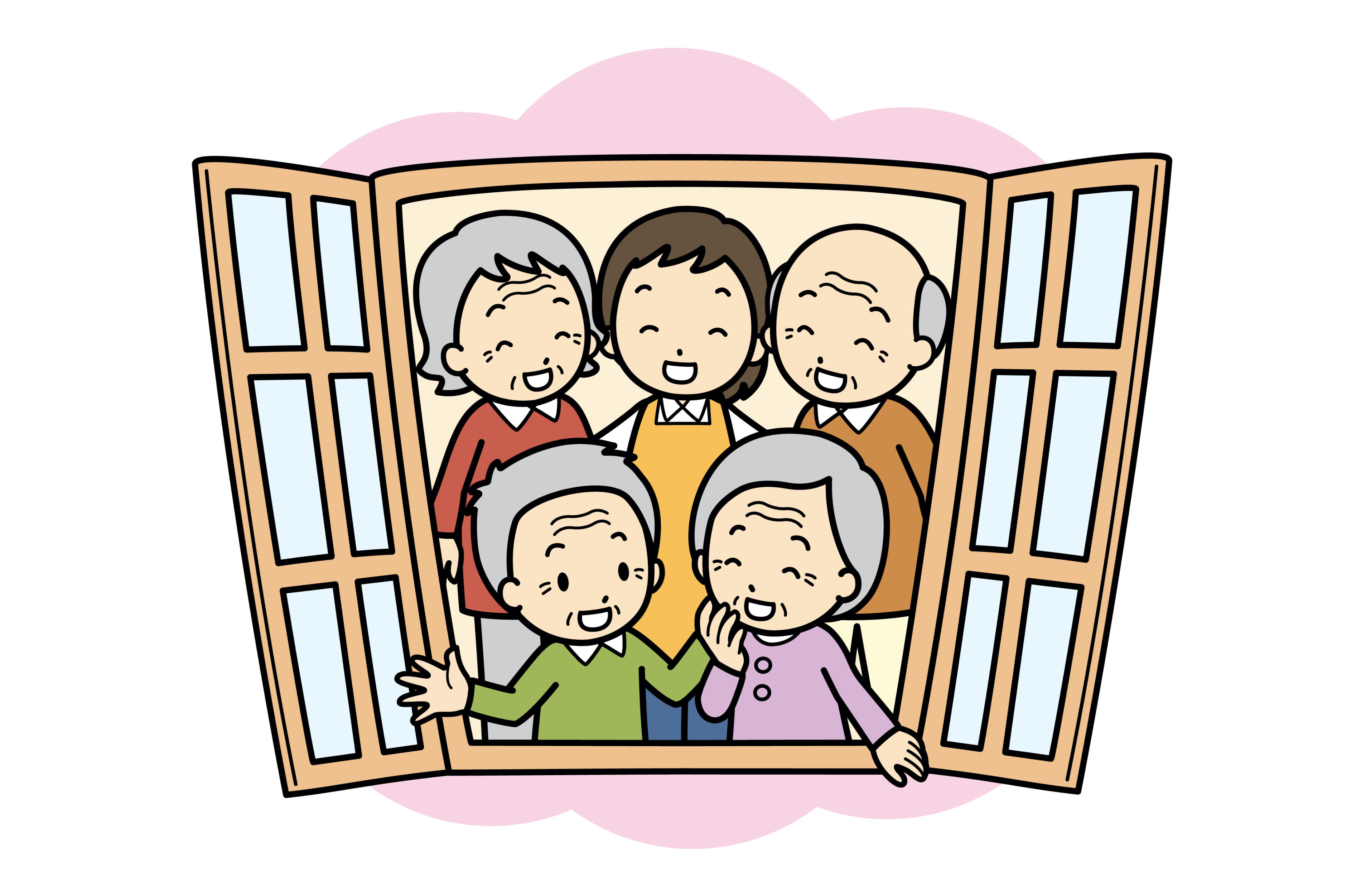д»Ӣиӯ·гҒ®дҫҝеҲ©её–гғҲгғғгғ—гҒёжҲ»гӮӢ
йҡңгҒҢгҒ„гҒ®гҒӮгӮӢж–№гҒ®гӮігғҹгғҘгғӢгӮұгғјгӮ·гғ§гғігӮ’ж”ҜжҸҙгҒҷгӮӢгҖҢж„ҸжҖқз–ҺйҖҡж”ҜжҸҙгҖҚгҒЁгҒҜ
гҖҢж„ҸжҖқз–ҺйҖҡж”ҜжҸҙгҖҚгҒҜгҖҒйҡңе®іиҖ…з·ҸеҗҲж”ҜжҸҙжі•гҒ«еҹәгҒҘгҒҸең°еҹҹз”ҹжҙ»ж”ҜжҸҙдәӢжҘӯгҒ®гҒІгҒЁгҒӨгҒ§гҒҷгҖӮж„ҸжҖқз–ҺйҖҡгҒҢеӣ°йӣЈгҒӘж–№гҒ®гҒҹгӮҒгҒ«гҖҒжүӢи©ұйҖҡиЁіиҖ…гӮ„иҰҒзҙ„зӯҶиЁҳиҖ…гҒӘгҒ©гӮ’жҙҫйҒЈгҒ—гҖҒгӮігғҹгғҘгғӢгӮұгғјгӮ·гғ§гғігҒ®еҶҶж»‘еҢ–гӮ’еӣігӮҠгҒҫгҒҷгҖӮд»ҠеӣһгҒҜгҖҒең°ж–№иҮӘжІ»дҪ“гҒҢе®ҹж–ҪгҒҷгӮӢгҖҢж„ҸжҖқз–ҺйҖҡж”ҜжҸҙгҖҚгҒЁгҖҒгӮігғҹгғҘгғӢгӮұгғјгӮ·гғ§гғіж”ҜжҸҙгӮ’иЎҢгҒҶгҖҢж„ҸжҖқз–ҺйҖҡж”ҜжҸҙиҖ…гҖҚгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰи§ЈиӘ¬гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҢж„ҸжҖқз–ҺйҖҡж”ҜжҸҙгҖҚгҒЁгҒҜ
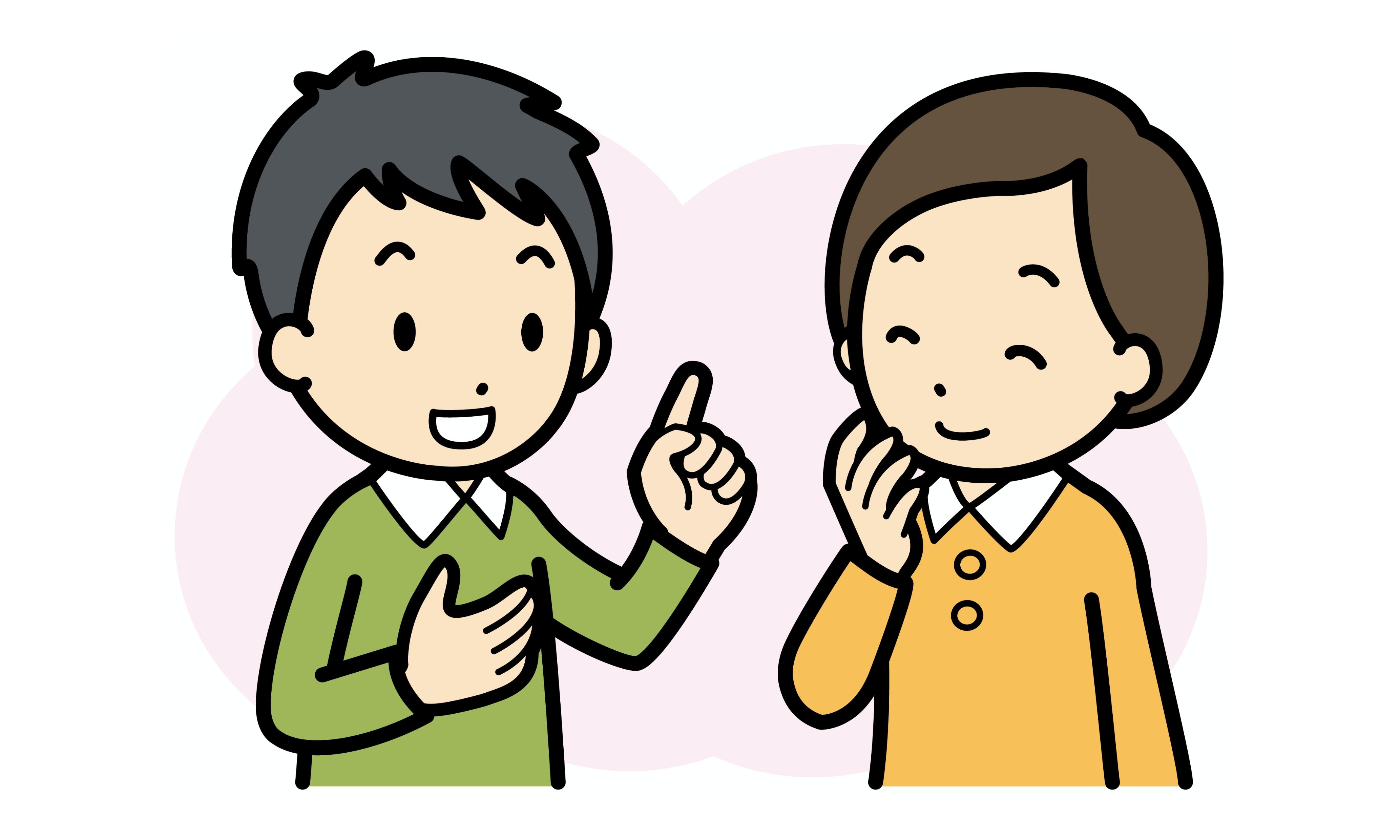
ж„ҸжҖқз–ҺйҖҡгӮ’еӣігӮӢгҒ“гҒЁгҒ«ж”ҜйҡңгҒҢгҒӮгӮӢж–№гҒ«гҖҒж„ҸжҖқз–ҺйҖҡж”ҜжҸҙиҖ…гҒ®жҙҫйҒЈзӯүгӮ’иЎҢгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
жүӢи©ұйҖҡиЁігӮ„иҰҒзҙ„зӯҶиЁҳгҒӘгҒ©гҒ®ж–№жі•гҒ«гӮҲгӮҠгҖҒеҶҶж»‘гҒӘгӮігғҹгғҘгғӢгӮұгғјгӮ·гғ§гғігӮ’еӣігӮҠгҖҒйҡңгҒҢгҒ„гҒ®гҒӮгӮӢж–№гҒ®зҰҸзҘүгҒ®еў—йҖІгҒЁзӨҫдјҡеҸӮеҠ гҒ®дҝғйҖІгҒ«иіҮгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӣ®зҡ„гҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
ж„ҸжҖқз–ҺйҖҡгҒҢеӣ°йӣЈгҒӘж–№гҒЁгҒқгҒ®д»–гҒ®ж–№гҒ®гӮігғҹгғҘгғӢгӮұгғјгӮ·гғ§гғігӮ’д»Ід»ӢгҒҷгӮӢгҒ®гҒҜгҖҒеҺҡз”ҹеҠҙеғҚзңҒд»ӨгҒ«еҹәгҒҘгҒҸиӘҚе®ҡиіҮж јгҒ«еҗҲж јгҒ—гҒҹж–№гӮ„гҖҒең°ж–№иҮӘжІ»дҪ“гҒҢе®ҹж–ҪгҒҷгӮӢйӨҠжҲҗз ”дҝ®гӮ’еҸ—и¬ӣгҒ—гҒҹж–№гҒ§гҒҷгҖӮ
| еҺҡз”ҹеҠҙеғҚзңҒд»ӨгҒ«еҹәгҒҘгҒҸиіҮж јиҖ… |
|---|
|
гғ»жүӢи©ұйҖҡиЁіеЈ« |
| еҺҡз”ҹеҠҙеғҚзңҒгҒҢйӨҠжҲҗгӮ«гғӘгӮӯгғҘгғ©гғ гӮ’е®ҡгӮҒгҒҰгҒ„гӮӢиҖ… |
|---|
|
гғ»жүӢи©ұйҖҡиЁіиҖ… гғ»жүӢи©ұеҘүд»•е“Ў гғ»иҰҒзҙ„зӯҶиЁҳиҖ… гғ»зӣІгӮҚгҒҶиҖ…еҗ‘гҒ‘йҖҡиЁігғ»д»ӢеҠ©е“Ў гғ»еӨұиӘһз—ҮиҖ…еҗ‘гҒ‘ж„ҸжҖқз–ҺйҖҡж”ҜжҸҙиҖ… |
еҜҫиұЎгҒЁгҒӘгӮӢж–№
иҒҙиҰҡгҖҒиЁҖиӘһж©ҹиғҪгҖҒйҹіеЈ°ж©ҹиғҪгҖҒиҰ–иҰҡгҖҒеӨұиӘһгҖҒзҹҘзҡ„гҖҒзҷәйҒ”гҖҒй«ҳж¬Ўи„іж©ҹиғҪгҖҒйҮҚеәҰгҒ®иә«дҪ“гҒӘгҒ©гҒ®йҡңгҒҢгҒ„гӮ„йӣЈз—…гҒ®гҒҹгӮҒгҖҒж„ҸжҖқз–ҺйҖҡгӮ’еӣігӮӢгҒ“гҒЁгҒ«ж”ҜйҡңгҒҢгҒӮгӮӢж–№
е®ҹж–Ҫдё»дҪ“
йҡңе®іиҖ…з·ҸеҗҲж”ҜжҸҙжі•пјҲйҡңе®іиҖ…гҒ®ж—Ҙеёёз”ҹжҙ»еҸҠгҒізӨҫдјҡз”ҹжҙ»гӮ’з·ҸеҗҲзҡ„гҒ«ж”ҜжҸҙгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®жі•еҫӢпјүгҒ®ең°еҹҹз”ҹжҙ»ж”ҜжҸҙдәӢжҘӯгҒ«еҹәгҒҘгҒ„гҒҰгҖҒеҗ„ең°ж–№иҮӘжІ»дҪ“гҒҢе®ҹж–ҪгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
| йғҪйҒ“еәңзңҢ |
|---|
|
гғ»зӣІгӮҚгҒҶиҖ…еҗ‘гҒ‘йҖҡиЁігғ»д»ӢеҠ©е“ЎгҒ®жҙҫйҒЈ гғ»еёӮз”әжқ‘гҒҢжҙҫйҒЈгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„е ҙеҗҲгҒӘгҒ©гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢжүӢи©ұйҖҡиЁіиҖ…гғ»иҰҒзҙ„зӯҶиЁҳиҖ…гғ»еӨұиӘһз—ҮиҖ…еҗ‘гҒ‘ж„ҸжҖқз–ҺйҖҡж”ҜжҸҙиҖ…гҒ®жҙҫйҒЈ гғ»еёӮеҢәз”әжқ‘еҹҹгӮ„йғҪйҒ“еәңзңҢеҹҹгӮ’и¶ҠгҒҲгҒҹеәғеҹҹзҡ„гҒӘжҙҫйҒЈгӮ’еҶҶж»‘гҒ«е®ҹж–ҪгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®еёӮеҢәз”әжқ‘й–“гҒ®жҙҫйҒЈиӘҝж•ҙ |
| еёӮеҢәз”әжқ‘ |
|---|
|
гғ»жүӢи©ұйҖҡиЁіиҖ…гғ»иҰҒзҙ„зӯҶиЁҳиҖ…гғ»еӨұиӘһз—ҮиҖ…еҗ‘гҒ‘ж„ҸжҖқз–ҺйҖҡж”ҜжҸҙиҖ…зӯүгҒ®жҙҫйҒЈ гғ»еёӮеҢәз”әжқ‘гҒ®зӘ“еҸЈгҒ«жүӢи©ұйҖҡиЁіиҖ…гӮ’иЁӯзҪ® |
еҲ©з”ЁиҖ…иІ жӢ…
ж„ҸжҖқз–ҺйҖҡж”ҜжҸҙиҖ…гҒ®жҙҫйҒЈзӯүгҒ«гҒӢгҒӢгӮӢеҲ©з”ЁиҖ…иІ жӢ…гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒең°ж–№иҮӘжІ»дҪ“гҒҢгҒқгӮҢгҒһгӮҢиҰҸе®ҡгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒеӨҡгҒҸгҒ®иҮӘжІ»дҪ“гҒ§з„Ўж–ҷгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
пјҲжҙҫйҒЈиҖ…гҒ®дәӨйҖҡиІ»гӮ„еҝ…иҰҒгҒӘе…Ҙе ҙж–ҷгҒӘгҒ©гҒҜеҲ©з”ЁиҖ…гҒ®иІ жӢ…гҒЁгҒӘгӮӢе ҙеҗҲгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮпјү
в–јй–ўйҖЈиЁҳдәӢ
гғ»йҡңгҒҢгҒ„гҒ®гҒӮгӮӢж–№гҒ®з”ҹжҙ»гӮ’ж”ҜжҸҙгҒҷгӮӢгҖҢйҡңгҒҢгҒ„зҰҸзҘүгӮөгғјгғ“гӮ№гҖҚгҒЁгҒҜ
гғ»йҡңгҒҢгҒ„гҒ®гҒӮгӮӢж–№гҒ®еӨ–еҮәж”ҜжҸҙгӮ„д»Ӣиӯ·гҒӘгҒ©гӮ’иЎҢгҒҶгҖҢгӮ¬гӮӨгғүгғҳгғ«гғ‘гғјгҖҚ
гҖҢж„ҸжҖқз–ҺйҖҡж”ҜжҸҙгҖҚгҒЁгҒҜ

гҖҢжүӢи©ұйҖҡиЁіеЈ«гҖҚгҖҢжүӢи©ұйҖҡиЁіиҖ…гҖҚгҖҢжүӢи©ұеҘүд»•е“ЎгҖҚ
иҒҙиҰҡйҡңгҒҢгҒ„гҒ®гҒӮгӮӢж–№гҒЁгҒқгҒ®д»–гҒ®ж–№гҒЁгҒҢеҶҶж»‘гҒ«гӮігғҹгғҘгғӢгӮұгғјгӮ·гғ§гғігӮ’еӣігӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҖҒжүӢи©ұгӮ’з”ЁгҒ„гҒҰж„ҸжҖқз–ҺйҖҡгӮ’ж”ҜжҸҙгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гғ»жүӢи©ұйҖҡиЁіеЈ«
еҺҡз”ҹеҠҙеғҚзңҒд»ӨгҒ«еҹәгҒҘгҒҸиӘҚе®ҡгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹгҖҢзӨҫдјҡзҰҸзҘүжі•дәәиҒҙиҰҡйҡңе®іиҖ…жғ…е ұж–ҮеҢ–гӮ»гғігӮҝгғјгҖҚгҒҢе®ҹж–ҪгҒҷгӮӢжүӢи©ұйҖҡиЁіжҠҖиғҪиӘҚе®ҡи©ҰйЁ“пјҲжүӢи©ұйҖҡиЁіеЈ«и©ҰйЁ“пјүгҒ«еҗҲж јгҒ—гҖҒзҷ»йҢІгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹж–№гҒ§гҒҷгҖӮ
ж”ҝиҰӢж”ҫйҖҒгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒжүӢи©ұйҖҡиЁігӮ’жӢ…еҪ“гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
гғ»жүӢи©ұйҖҡиЁіиҖ…
жүӢи©ұйҖҡиЁігҒ«еҝ…иҰҒгҒӘжүӢи©ұиӘһеҪҷпјҲгҒ”гҒ„пјүгҖҒжүӢи©ұиЎЁзҸҫжҠҖиЎ“гҖҒеҹәжң¬жҠҖиЎ“гӮ’зҝ’еҫ—гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢж–№гҒ§гҒҷгҖӮ
жүӢи©ұйҖҡиЁіиҖ…гҒ®йӨҠжҲҗз ”дҝ®гӮ’еҸ—и¬ӣгҒ—гҖҒйғҪйҒ“еәңзңҢгҒӘгҒ©гҒҢиЎҢгҒҶи©ҰйЁ“гҒ«еҗҲж јгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гғ»жүӢи©ұеҘүд»•е“Ў
еёӮеҢәз”әжқ‘гҒҠгӮҲгҒійғҪйҒ“еәңзңҢгҒҢе®ҹж–ҪгҒҷгӮӢжүӢи©ұеҘүд»•е“ЎйӨҠжҲҗз ”дҝ®дәӢжҘӯгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҢжүӢи©ұеҘүд»•е“ЎгҖҚгҒЁгҒ—гҒҰзҷ»йҢІгҒ•гӮҢгҒҹж–№гҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ
гҖҢиҰҒзҙ„зӯҶиЁҳиҖ…гҖҚ
иҰҒзҙ„зӯҶиЁҳгҖҚгҒҜгҖҒиҒҙиҰҡйҡңгҒҢгҒ„гҒ®гҒӮгӮӢж–№гҒёгҒ®дјқйҒ”жүӢж®өгҒ®гҒІгҒЁгҒӨгҒ§гҒҷгҖӮиҰҒзҙ„зӯҶиЁҳиҖ…гҒҜгҖҒдјҡи©ұгҒ®еҶ…е®№гӮ’гҒқгҒ®е ҙгҒ§иҰҒзҙ„гҒ—гҖҒгғҺгғјгғҲгӮ„гғ‘гӮҪгӮігғігҒӘгҒ©гҒ§ж–Үеӯ—гҒЁгҒ—гҒҰдјқгҒҲгҒҫгҒҷгҖӮ
иҰҒзҙ„зӯҶиЁҳиҖ…гҒ«гҒӘгӮӢгҒ«гҒҜгҖҒйӨҠжҲҗз ”дҝ®гӮ’еҸ—и¬ӣгҒ—гҖҒйғҪйҒ“еәңзңҢзӯүгҒҢиЎҢгҒҶи©ҰйЁ“гҒ«еҗҲж јгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҢзӣІгӮҚгҒҶиҖ…еҗ‘гҒ‘йҖҡиЁігғ»д»ӢеҠ©е“ЎгҖҚгҒЁгҒҜ

иҰ–иҰҡгҒЁиҒҙиҰҡгҒ®дёЎж–№гҒ«йҡңгҒҢгҒ„гҒҢгҒӮгӮӢж–№пјҲзӣІгӮҚгҒҶиҖ…пјүгҒ®иҖігҒЁзӣ®гҒ®д»ЈгӮҸгӮҠгҒЁгҒӘгӮҠгҖҒйҖҡиЁігҒӘгҒ©гҒ®гӮігғҹгғҘгғӢгӮұгғјгӮ·гғ§гғіж”ҜжҸҙгҖҒиҰ–иҰҡжғ…е ұгҒ®жҸҗдҫӣгҖҒеӨ–еҮәжҷӮгҒ®з§»еӢ•д»ӢеҠ©гҒӘгҒ©гӮ’иЎҢгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
в–јй–ўйҖЈиЁҳдәӢ
гғ»иҰ–иҰҡйҡңгҒҢгҒ„гҒ®гҒӮгӮӢгҒ”й«ҳйҪўиҖ…гҒёгҒ®й…Қж…®гҒЁгӮігғҹгғҘгғӢгӮұгғјгӮ·гғ§гғі
гҖҢеӨұиӘһз—ҮиҖ…еҗ‘гҒ‘ж„ҸжҖқз–ҺйҖҡж”ҜжҸҙиҖ…гҖҚгҒЁгҒҜ
еӨұиӘһз—ҮгҒ®з—ҮзҠ¶гӮ„еӣ°йӣЈгҒ•гӮ’зҗҶи§ЈгҒ—гҖҒгӮігғҹгғҘгғӢгӮұгғјгӮ·гғ§гғіж”ҜжҸҙгҖҒеӨ–еҮәгғ»еҗҢиЎҢж”ҜжҸҙгҖҒиә«дҪ“д»ӢеҠ©гҒӘгҒ©гӮ’иЎҢгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
в–јй–ўйҖЈиЁҳдәӢ
гғ»иЁҖиӘһйҡңгҒҢгҒ„гҒ®гҒӮгӮӢж–№гҒЁгҒ®гӮігғҹгғҘгғӢгӮұгғјгӮ·гғ§гғігҒ®гғқгӮӨгғігғҲ
ең°еҹҹз”ҹжҙ»ж”ҜжҸҙдәӢжҘӯгҒ«гҒҜгҖҒеҝ…гҒҡе®ҹж–ҪгҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖҢеҝ…й ҲдәӢжҘӯгҖҚгҒЁгҖҒеёӮеҢәз”әжқ‘гҒ®еҲӨж–ӯгҒ§иЎҢгҒҶгҖҢд»»ж„ҸдәӢжҘӯгҖҚгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҖҢж„ҸжҖқз–ҺйҖҡж”ҜжҸҙгҖҚгҒҜеҝ…й ҲдәӢжҘӯгҒ§гҒӮгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒгҒҷгҒ№гҒҰгҒ®иҮӘжІ»дҪ“гҒ§иЎҢгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгӮөгғјгғ“гӮ№гҒ®еҲ©з”ЁгӮ’еёҢжңӣгҒҷгӮӢж–№гҒҜгҖҒгҒҠдҪҸгҒҫгҒ„гҒ®еёӮеҢәз”әжқ‘гҒ«гҒҠе•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ
家ж—ҸгҒ®д»Ӣиӯ·гӮ’гҒҚгҒЈгҒӢгҒ‘гҒ«д»Ӣиӯ·зҰҸзҘүеЈ«гғ»зӨҫдјҡзҰҸзҘүдё»дәӢд»»з”ЁиіҮж јгӮ’еҸ–еҫ—гҖӮзҸҫеңЁгҒҜгғ©гӮӨгӮҝгғјгҖӮж—ҘгҖ…гҒ®жҡ®гӮүгҒ—гҒ«еҪ№з«ӢгҒӨиә«иҝ‘гҒӘжғ…е ұгӮ’гҒҠдјқгҒҲгҒҷгӮӢгҒ№гҒҸгҖҒд»Ӣиӯ·гғ»еҢ»зҷӮгғ»зҫҺе®№гғ»гӮ«гғ«гғҒгғЈгғјгҒӘгҒ©е№…еәғгҒ„гӮёгғЈгғігғ«гҒ®иЁҳдәӢгӮ’еҹ·зӯҶдёӯгҖӮ
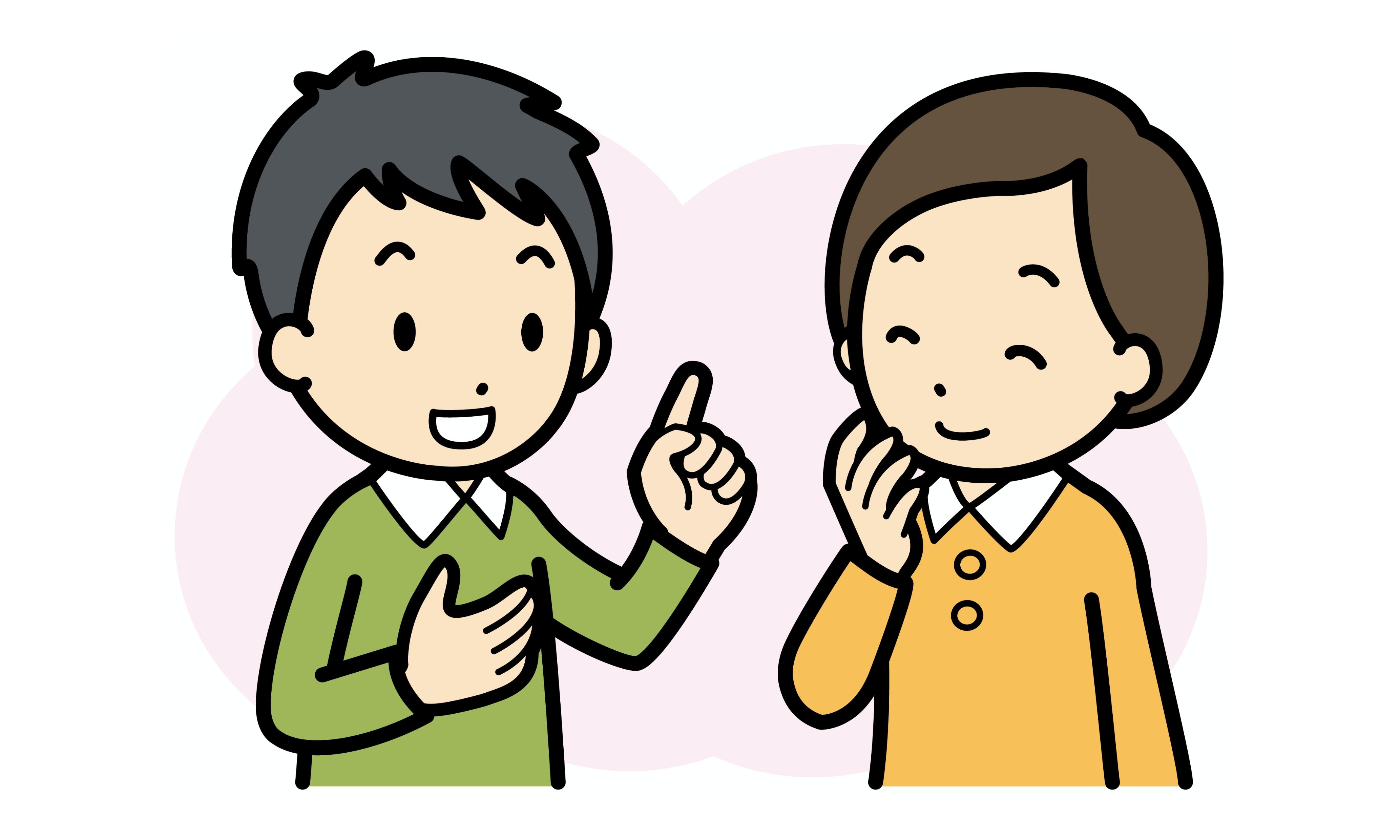
FacebookгғҡгғјгӮёгҒ§
жңҖж–°иЁҳдәӢй…ҚдҝЎпјҒпјҒ
 гғ¬гӮӘгғҸгӮҡгғ¬гӮ№21гӮҜгӮҷгғ«гғјгғ•гӮҡгҒ®д»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ’гӮҷгӮ№
гғ¬гӮӘгғҸгӮҡгғ¬гӮ№21гӮҜгӮҷгғ«гғјгғ•гӮҡгҒ®д»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ’гӮҷгӮ№