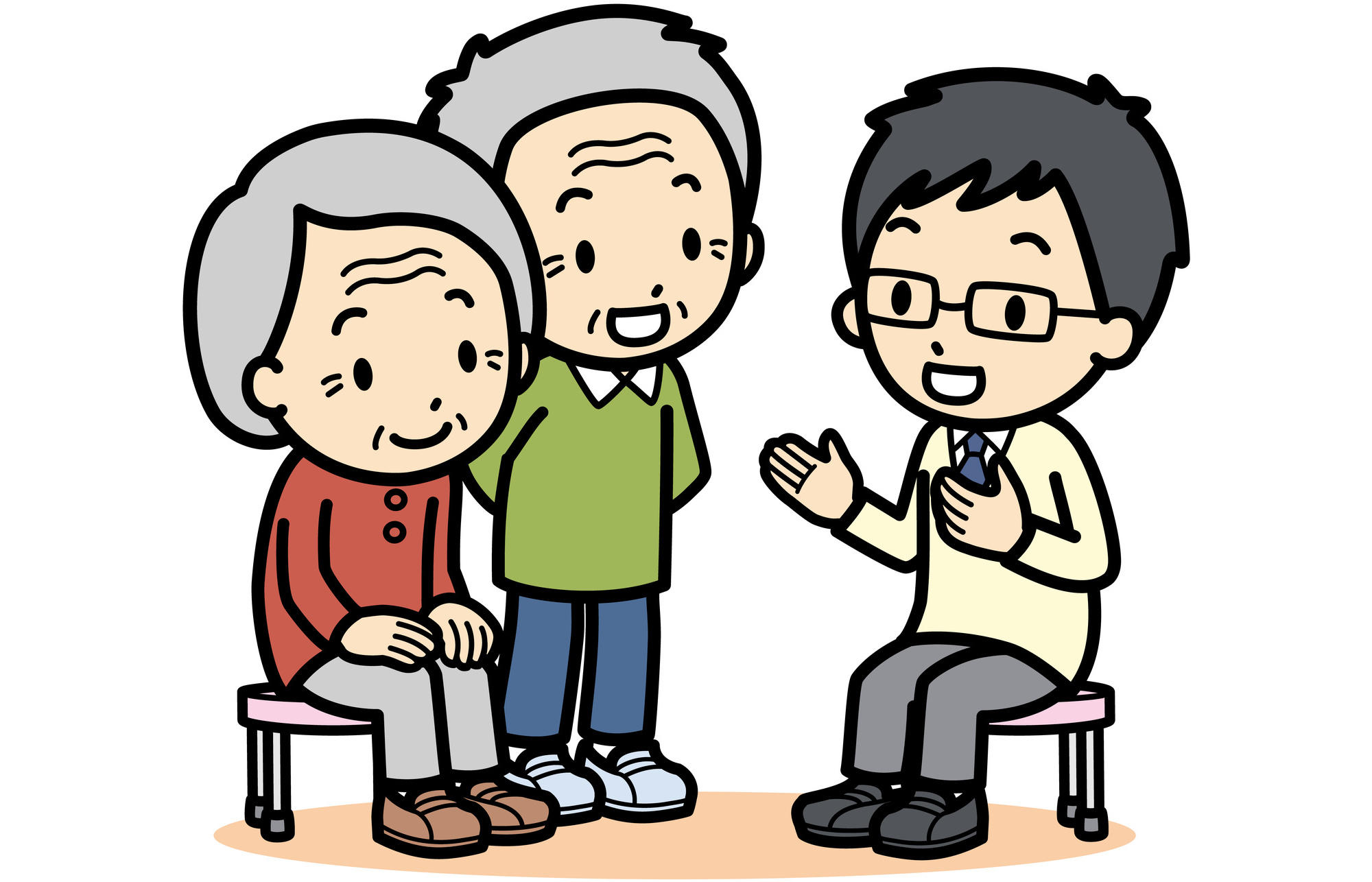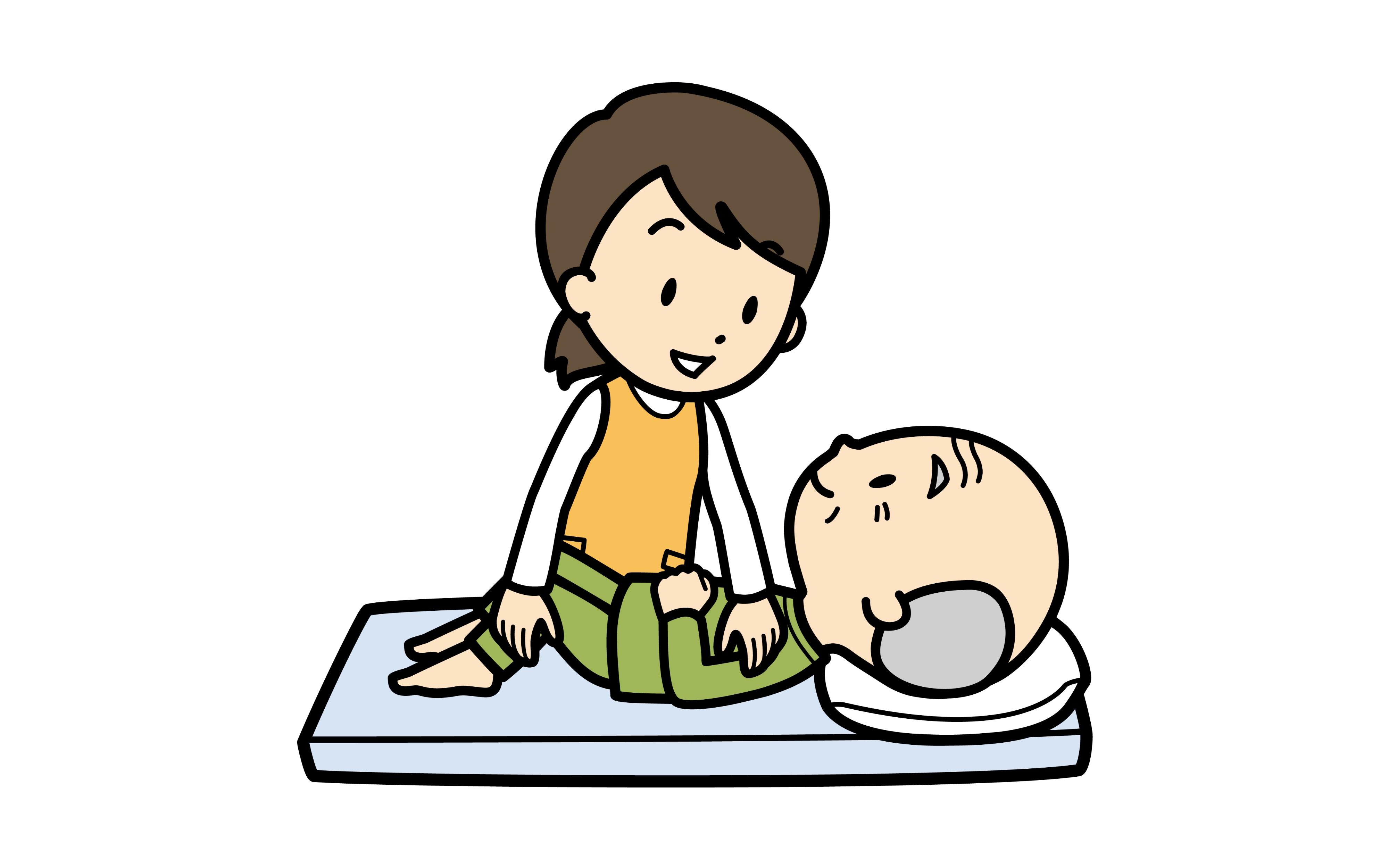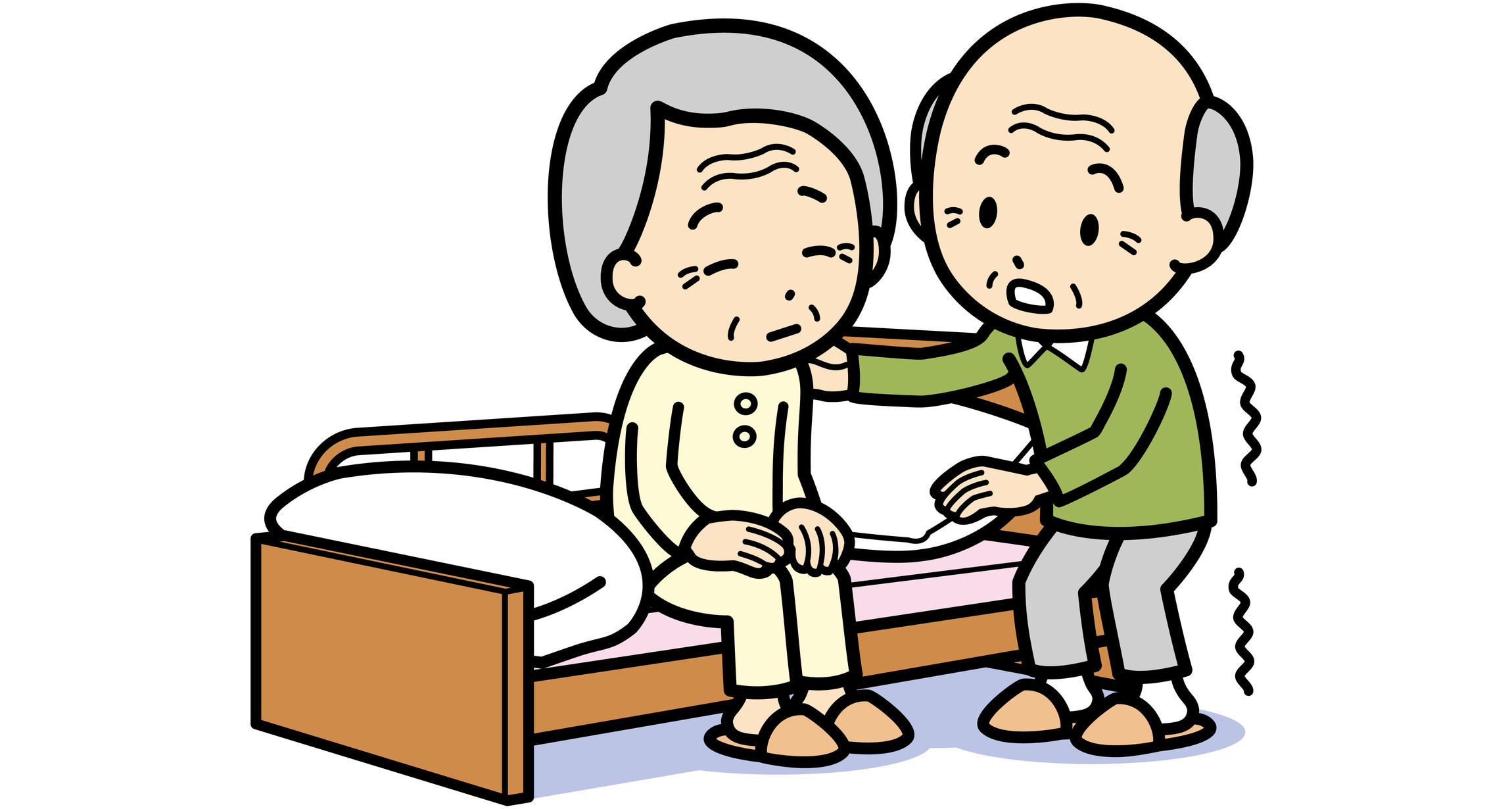д»Ӣиӯ·гҒ®дҫҝеҲ©её–гғҲгғғгғ—гҒёжҲ»гӮӢ
з”ҹжҙ»ж”ҜжҸҙгӮігғјгғҮгӮЈгғҚгғјгӮҝгғјпјҲең°еҹҹж”ҜгҒҲеҗҲгҒ„жҺЁйҖІе“ЎпјүгҒЁгҒҜпјҹзӣ®зҡ„гҒЁеҪ№еүІ
гҖҢең°еҹҹж”ҜгҒҲеҗҲгҒ„жҺЁйҖІе“ЎгҖҚгҒЁгӮӮе‘јгҒ°гӮҢгӮӢз”ҹжҙ»ж”ҜжҸҙгӮігғјгғҮгӮЈгғҚгғјгӮҝгғјгҖӮд»ҠеӣһгҒҜең°еҹҹгҒ§й«ҳйҪўгҒ®ж–№гӮ’ж”ҜжҸҙгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«иЁӯзҪ®гҒ•гӮҢгҒҹгҖҢз”ҹжҙ»ж”ҜжҸҙгӮігғјгғҮгӮЈгғҚгғјгӮҝгғјпјҲең°еҹҹж”ҜгҒҲеҗҲгҒ„жҺЁйҖІе“ЎпјүгҖҚгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҠдјқгҒҲгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
з”ҹжҙ»ж”ҜжҸҙгӮігғјгғҮгӮЈгғҚгғјгӮҝгғјгҒЁгҒҜ

з”ҹжҙ»ж”ҜжҸҙгӮігғјгғҮгӮЈгғҚгғјгӮҝгғјпјҲең°еҹҹж”ҜгҒҲеҗҲгҒ„жҺЁйҖІе“ЎпјүгҒЁгҒҜгҖҒй«ҳйҪўгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгӮӮдҪҸгҒҝж…ЈгӮҢгҒҹе ҙжүҖгҒ§е®үеҝғгҒ—гҒҰжҡ®гӮүгҒӣгӮӢгӮҲгҒҶгҖҒең°еҹҹгҒ§ж”ҜгҒҲеҗҲгҒҶдҪ“еҲ¶гҒҘгҒҸгӮҠгӮ’йҖІгӮҒгӮӢдәәгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ
й«ҳйҪўеҢ–гҒ®йҖІеұ•гҒ«дјҙгҒ„гҖҒгҒІгҒЁгӮҠжҡ®гӮүгҒ—гӮ„гҒ”еӨ«е©ҰгҒ®гҒҝгҒ®й«ҳйҪўиҖ…дё–еёҜгҖҒиӘҚзҹҘз—ҮгҒ®гҒ”й«ҳйҪўиҖ…гҒҢеў—еҠ гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
ең°еҹҹзӨҫдјҡгҒ§гҒ”й«ҳйҪўиҖ…гҒ®з”ҹжҙ»гӮ’ж”ҜгҒҲгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҖҒд»Ӣиӯ·дҝқйҷәеҲ¶еәҰгҒ®гӮөгғјгғ“гӮ№гҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒең°еҹҹеҢ…жӢ¬гӮұгӮўгӮ·гӮ№гғҶгғ пјҲдҪҸгҒҫгҒ„гғ»еҢ»зҷӮгғ»д»Ӣиӯ·гғ»дәҲйҳІгғ»з”ҹжҙ»ж”ҜжҸҙгҒ®гӮөгғјгғ“гӮ№гӮ’ең°еҹҹгҒ§дёҖдҪ“зҡ„гҒ«жҸҗдҫӣгҒҷгӮӢгӮ·гӮ№гғҶгғ пјүгҒ®ж§ӢзҜүгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒқгҒ“гҒ§гҖҒ2015пјҲе№іжҲҗ27пјүе№ҙгҒ®д»Ӣиӯ·дҝқйҷәжі•ж”№жӯЈгҒ«гӮҲгӮҠгҖҢз”ҹжҙ»ж”ҜжҸҙдҪ“еҲ¶ж•ҙеӮҷдәӢжҘӯгҖҚгҒҢеүөиЁӯгҒ•гӮҢгҖҒеёӮз”әжқ‘гҒ”гҒЁгҒ«з”ҹжҙ»ж”ҜжҸҙгӮігғјгғҮгӮЈгғҚгғјгӮҝгғјгҒЁеҚ”иӯ°дҪ“пјҲи©ұгҒ—еҗҲгҒ„гҒ®е ҙпјүгҒҢиЁӯзҪ®гҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
в–јй–ўйҖЈиЁҳдәӢ
ең°еҹҹгҒ§й«ҳйҪўиҖ…гҒ®жҡ®гӮүгҒ—гӮ’ж”ҜгҒҲгӮӢгҖҢең°еҹҹеҢ…жӢ¬гӮұгӮўгӮ·гӮ№гғҶгғ гҖҚгҒЁгҒҜпјҹ
з·ҸеҗҲдәӢжҘӯпјҲд»Ӣиӯ·дәҲйҳІгғ»ж—Ҙеёёз”ҹжҙ»ж”ҜжҸҙз·ҸеҗҲдәӢжҘӯпјүгҒЁгҒҜпјҹгӮөгғјгғ“гӮ№еҶ…е®№гҒЁеҲ©з”Ёж–№жі•
з”ҹжҙ»ж”ҜжҸҙгӮігғјгғҮгӮЈгғҚгғјгӮҝгғјгҒ®зӣ®зҡ„гҒЁеҪ№еүІ

з”ҹжҙ»ж”ҜжҸҙгӮігғјгғҮгӮЈгғҚгғјгӮҝгғјгҒ®зӣ®зҡ„
з”ҹжҙ»ж”ҜжҸҙгӮігғјгғҮгӮЈгғҚгғјгӮҝгғјпјҲең°еҹҹж”ҜгҒҲеҗҲгҒ„жҺЁйҖІе“ЎпјүгҒҜгҖҒең°еҹҹгҒ§гҒ”й«ҳйҪўиҖ…гҒ®з”ҹжҙ»ж”ҜжҸҙгғ»д»Ӣиӯ·дәҲйҳІгӮөгғјгғ“гӮ№гҒ®дҪ“еҲ¶гҒҘгҒҸгӮҠгӮ’йҖІгӮҒгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӣ®зҡ„гҒЁгҒ—гҒҰиЁӯзҪ®гҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гғңгғ©гғігғҶгӮЈгӮўгӮ„NPOжі•дәәгҖҒж°‘й–“дјҒжҘӯгҖҒзӨҫдјҡзҰҸзҘүжі•дәәгҖҒзӨҫдјҡзҰҸзҘүеҚ”иӯ°дјҡгҖҒд»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№дәӢжҘӯиҖ…гҖҒж°‘з”ҹ委員гҒӘгҒ©гҒЁйҖЈжҗәгҒ—гҒҰгҖҒгҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒӘж”ҜгҒҲеҗҲгҒ„гҒ®дҪ“еҲ¶гҒҘгҒҸгӮҠгҒ«еҸ–гӮҠзө„гӮ“гҒ§гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
з”ҹжҙ»ж”ҜжҸҙгӮігғјгғҮгӮЈгғҚгғјгӮҝгғјгҒ®дё»гҒӘеҪ№еүІ
з”ҹжҙ»ж”ҜжҸҙгӮігғјгғҮгӮЈгғҚгғјгӮҝгғјгҒ«гҒҜгҖҒ第1еұӨгҖҒ第2еұӨгҖҒ第3еұӨгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
| 第1еұӨ | еёӮз”әжқ‘еҢәеҹҹгҒҢеҜҫиұЎ дё»гҒ«иіҮжәҗй–ӢзҷәгҒҢдёӯеҝғ |
|---|---|
| 第2еұӨ | ж—Ҙеёёз”ҹжҙ»еңҸеҹҹпјҲдёӯеӯҰж ЎеҢәеҹҹзӯүпјүгҒҢеҜҫиұЎ 第1еұӨгҒ®ж©ҹиғҪгҒ®дёӢгҒ§е…·дҪ“зҡ„гҒӘжҙ»еӢ•гӮ’еұ•й–Ӣ |
| 第3еұӨ пјҲвҖ»дәӢжҘӯгҒ®еҜҫиұЎеӨ–пјү |
гӮөгғјгғ“гӮ№гҒ®жҸҗдҫӣдё»дҪ“ еҲ©з”ЁиҖ…гҒЁжҸҗдҫӣиҖ…гӮ’гғһгғғгғҒгғігӮ°гҒҷгӮӢж©ҹиғҪ |
гҖҮиіҮжәҗй–Ӣзҷә
гғ»ең°еҹҹгҒ«дёҚи¶ігҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгӮөгғјгғ“гӮ№гҒ®жҠҠжҸЎгҒЁеүөеҮә
гғ»гӮөгғјгғ“гӮ№гҒ®жӢ…гҒ„жүӢгҒ®зҷәжҺҳгҒЁйӨҠжҲҗ
гғ»е…ғж°—гҒӘгҒ”й«ҳйҪўиҖ…гҒӘгҒ©гҒҢжӢ…гҒ„жүӢгҒЁгҒ—гҒҰжҙ»еӢ•гҒҷгӮӢе ҙгҒ®зўәдҝқ
гҖҮгғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгҒ®ж§ӢзҜү
гғ»й–ўдҝӮиҖ…й–“гҒ®жғ…е ұе…ұжңү
гғ»гӮөгғјгғ“гӮ№жҸҗдҫӣдё»дҪ“й–“гҒ®йҖЈжҗәгҒ®дҪ“еҲ¶гҒҘгҒҸгӮҠ
гҖҮгғӢгғјгӮәгҒЁеҸ–гӮҠзө„гҒҝгҒ®гғһгғғгғҒгғігӮ°
гғ»ең°еҹҹгҒ®ж”ҜжҸҙгғӢгғјгӮәгҒЁгӮөгғјгғ“гӮ№жҸҗдҫӣдё»дҪ“гҒ®жҙ»еӢ•гӮ’гғһгғғгғҒгғігӮ°
з”ҹжҙ»ж”ҜжҸҙгӮігғјгғҮгӮЈгғҚгғјгӮҝгғјгҒ«гҒӘгӮӢгҒ«гҒҜ
з”ҹжҙ»ж”ҜжҸҙгӮігғјгғҮгӮЈгғҚгғјгӮҝгғјпјҲең°еҹҹж”ҜгҒҲеҗҲгҒ„жҺЁйҖІе“ЎпјүгҒ«гҒӘгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«еҝ…иҰҒгҒӘиіҮж јиҰҒ件гҒҜзү№гҒ«гҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒҢгҖҒеҺҡз”ҹеҠҙеғҚзңҒгҒҜгҖҢең°еҹҹгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢеҠ©гҒ‘еҗҲгҒ„гӮ„з”ҹжҙ»ж”ҜжҸҙгғ»д»Ӣиӯ·дәҲйҳІгӮөгғјгғ“гӮ№гҒ®жҸҗдҫӣе®ҹзёҫгҒ®гҒӮгӮӢиҖ…гҖҒгҒҫгҒҹгҒҜдёӯй–“ж”ҜжҸҙгӮ’иЎҢгҒҶеӣЈдҪ“зӯүгҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгҖҒең°еҹҹгҒ§гӮігғјгғҮгӮЈгғҚгғјгғҲж©ҹиғҪгӮ’йҒ©еҲҮгҒ«жӢ…гҒҶгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢиҖ…гҖҚгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒгҖҢеёӮж°‘жҙ»еӢ•гҒёгҒ®зҗҶи§ЈгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒеӨҡж§ҳгҒӘзҗҶеҝөгӮ’гӮӮгҒӨең°еҹҹгҒ®гӮөгғјгғ“гӮ№жҸҗдҫӣдё»дҪ“гҒЁйҖЈзөЎиӘҝж•ҙгҒ§гҒҚгӮӢз«Ӣе ҙгҒ®иҖ…гҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгҖҒеӣҪгӮ„йғҪйҒ“еәңзңҢгҒҢе®ҹж–ҪгҒҷгӮӢз ”дҝ®гӮ’дҝ®дәҶгҒ—гҒҹиҖ…гҒҢжңӣгҒҫгҒ—гҒ„гҖҚгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒӘгҒҠгҖҒз”ҹжҙ»ж”ҜжҸҙгӮігғјгғҮгӮЈгғҚгғјгӮҝгғјгҒ®й…ҚзҪ®е ҙжүҖгҒҜгҖҒеёӮз”әжқ‘гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰз•°гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮи©ігҒ—гҒҸгҒҜгҒҠдҪҸгҒҫгҒ„гҒ®иҮӘжІ»дҪ“гҒ®гғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҒӘгҒ©гҒ§гҒ”зўәиӘҚгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ
в–јй–ўйҖЈиЁҳдәӢ
ең°еҹҹзҰҸзҘүеҗ‘дёҠгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«гҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒӘжҙ»еӢ•гӮ’иЎҢгҒҶгҖҢзӨҫдјҡзҰҸзҘүеҚ”иӯ°дјҡпјҲзӨҫеҚ”пјүгҖҚ
гҖҢең°еҹҹеҢ…жӢ¬ж”ҜжҸҙгӮ»гғігӮҝгғјгҖҚгҒЈгҒҰгҒ©гӮ“гҒӘгҒЁгҒ“гӮҚпјҹ гҒқгҒ®еҪ№еүІгҒЁжҘӯеӢҷеҶ…е®№
家ж—ҸгҒ®д»Ӣиӯ·гӮ’гҒҚгҒЈгҒӢгҒ‘гҒ«д»Ӣиӯ·зҰҸзҘүеЈ«гғ»зӨҫдјҡзҰҸзҘүдё»дәӢд»»з”ЁиіҮж јгӮ’еҸ–еҫ—гҖӮзҸҫеңЁгҒҜгғ©гӮӨгӮҝгғјгҖӮж—ҘгҖ…гҒ®жҡ®гӮүгҒ—гҒ«еҪ№з«ӢгҒӨиә«иҝ‘гҒӘжғ…е ұгӮ’гҒҠдјқгҒҲгҒҷгӮӢгҒ№гҒҸгҖҒд»Ӣиӯ·гғ»еҢ»зҷӮгғ»зҫҺе®№гғ»гӮ«гғ«гғҒгғЈгғјгҒӘгҒ©е№…еәғгҒ„гӮёгғЈгғігғ«гҒ®иЁҳдәӢгӮ’еҹ·зӯҶдёӯгҖӮ

FacebookгғҡгғјгӮёгҒ§
жңҖж–°иЁҳдәӢй…ҚдҝЎпјҒпјҒ
 гғ¬гӮӘгғҸгӮҡгғ¬гӮ№21гӮҜгӮҷгғ«гғјгғ•гӮҡгҒ®д»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ’гӮҷгӮ№
гғ¬гӮӘгғҸгӮҡгғ¬гӮ№21гӮҜгӮҷгғ«гғјгғ•гӮҡгҒ®д»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ’гӮҷгӮ№