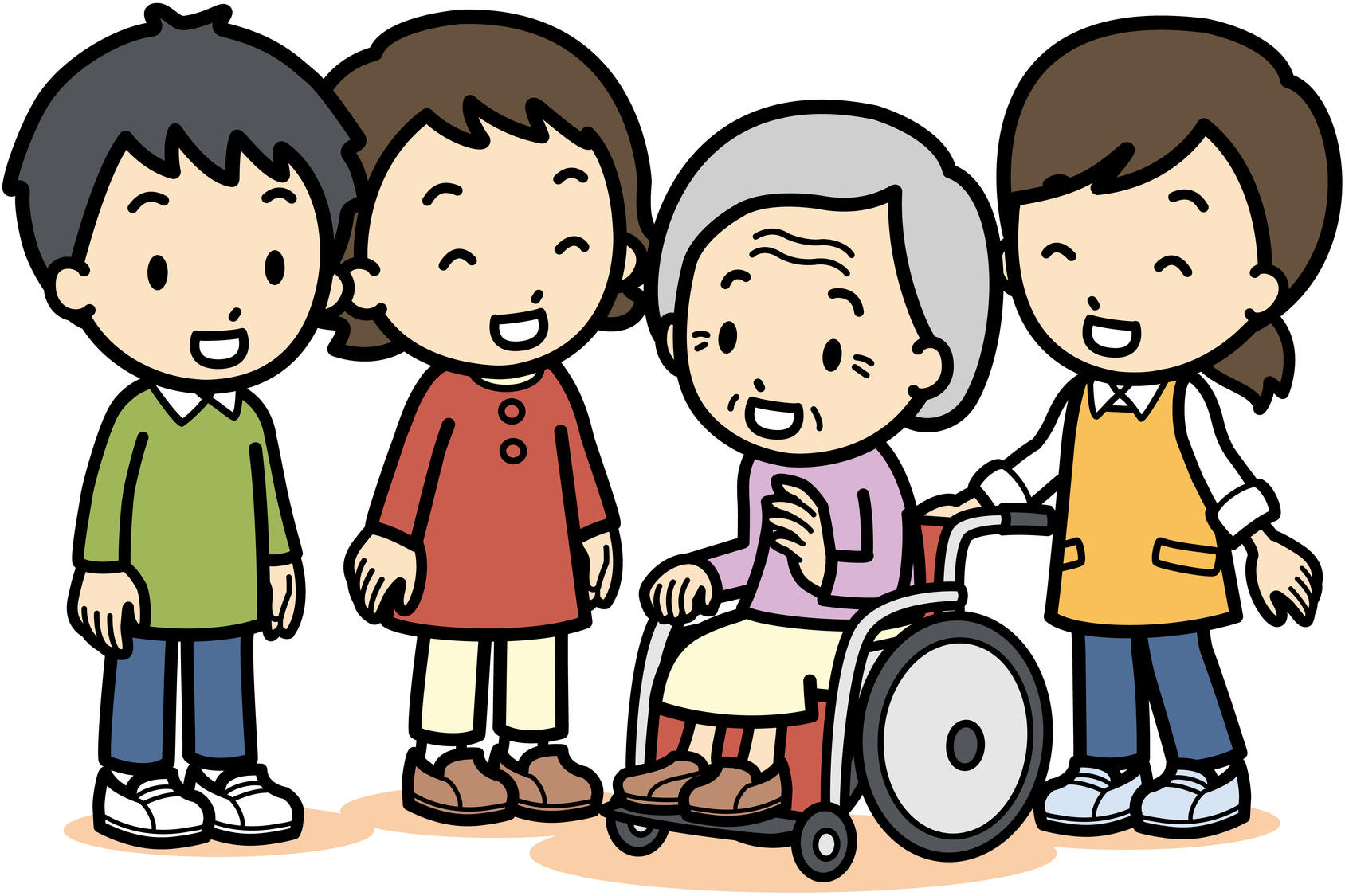д»Ӣиӯ·гҒ®дҫҝеҲ©её–гғҲгғғгғ—гҒёжҲ»гӮӢ
ж–°еһӢгӮігғӯгғҠгӮҰгӮӨгғ«гӮ№ж„ҹжҹ“з—ҮгҒ«й–ўгҒҷгӮӢеӣҪгӮ„иҮӘжІ»дҪ“зӯүгҒ®ж”ҜжҸҙзӯ–
еӣҪгӮ„иҮӘжІ»дҪ“гҒӘгҒ©гҒ§гҒҜгҖҒж–°еһӢгӮігғӯгғҠгӮҰгӮӨгғ«гӮ№ж„ҹжҹ“з—ҮгҒ®еҪұйҹҝгҒ§з”ҹжҙ»гҒ«еӣ°йӣЈгӮ’жҠұгҒҲгӮӢж–№гҖ…гҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҖҒгҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒӘж”ҜжҸҙгӮ’иЎҢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮд»ҠеӣһгҒҜгҖҒж–°еһӢгӮігғӯгғҠгӮҰгӮӨгғ«гӮ№ж„ҹжҹ“з—ҮгҒ«дјҙгҒҶдё»гҒӘж”ҜжҸҙзӯ–гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҫгҒЁгӮҒгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
з”ҹжҙ»гӮ’ж”ҜгҒҲгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®ж”ҜжҸҙ

дҪҸж°‘зЁҺйқһиӘІзЁҺдё–еёҜзӯүгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢиҮЁжҷӮзү№еҲҘзөҰд»ҳйҮ‘
дҪҸж°‘зЁҺеқҮзӯүеүІйқһиӘІзЁҺдё–еёҜгӮ„д»Өе’Ң3е№ҙ1жңҲд»ҘйҷҚгҒ«ж–°еһӢгӮігғӯгғҠгӮҰгӮӨгғ«гӮ№ж„ҹжҹ“з—ҮгҒ®еҪұйҹҝгҒ§е®¶иЁҲжҖҘеӨүгҒ®гҒӮгҒЈгҒҹдё–еёҜгӮ’ж”ҜжҸҙгҒҷгӮӢж–°гҒҹгҒӘзөҰд»ҳйҮ‘гҒ§гҒҷгҖӮдҪҸж°‘зЁҺйқһиӘІзЁҺдё–еёҜзӯүгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҖҒпј‘дё–еёҜеҪ“гҒҹгӮҠпј‘пјҗдёҮеҶҶгҒҢж”ҜзөҰгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
-
еҜҫиұЎ
в‘ дё–еёҜе…Ёе“ЎгҒ®д»Өе’Ң3е№ҙеәҰеҲҶгҒ®дҪҸж°‘зЁҺеқҮзӯүеүІгҒҢйқһиӘІзЁҺгҒ§гҒӮгӮӢдё–еёҜ
пјҲвҖ»дҪҸж°‘зЁҺгҒҢиӘІзЁҺгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢиҖ…гҒ®жү¶йӨҠиҰӘж—ҸзӯүгҒ®гҒҝгҒӢгӮүгҒӘгӮӢдё–еёҜгӮ’йҷӨгҒҸпјү
в‘Ў в‘ гҒ®гҒ»гҒӢгҖҒж–°еһӢгӮігғӯгғҠгӮҰгӮӨгғ«гӮ№ж„ҹжҹ“з—ҮгҒ®еҪұйҹҝгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰ家иЁҲгҒҢжҖҘеӨүгҒ—гҖҒв‘ гҒ®дё–еёҜгҒЁеҗҢж§ҳгҒ®дәӢжғ…гҒ«гҒӮгӮӢгҒЁиӘҚгӮҒгӮүгӮҢгӮӢдё–еёҜпјҲ家иЁҲжҖҘеӨүдё–еёҜпјүгҖӮ
ж”ҜзөҰйЎҚ
пј‘дё–еёҜеҪ“гҒҹгӮҠ10дёҮеҶҶ
зөҰд»ҳйҮ‘гҒ®ж”ҜзөҰжҷӮжңҹ
еёӮеҢәз”әжқ‘гҒ«гӮҲгӮҠз•°гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҠе•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣе…Ҳ
дҪҸж°‘зЁҺйқһиӘІзЁҺдё–еёҜзӯүгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢиҮЁжҷӮзү№еҲҘзөҰд»ҳйҮ‘гӮігғјгғ«гӮ»гғігӮҝгғј
гғ•гғӘгғјгғҖгӮӨгғӨгғ«0120пҪ°526пҪ°145пјҲ 9пјҡ00пҪһ20пјҡ00гҖҖ12/29пҪһ1/3гӮ’йҷӨгҒҸпјү
гҒҠз”іиҫјгҒҝе…Ҳ
гҒҠдҪҸгҒҫгҒ„гҒ®еёӮеҢәз”әжқ‘
еӣҪж°‘еҒҘеә·дҝқйҷәгҖҒеӣҪж°‘е№ҙйҮ‘гҖҒеҫҢжңҹй«ҳйҪўиҖ…еҢ»зҷӮгҒҠгӮҲгҒід»Ӣиӯ·дҝқйҷәгҒ®дҝқйҷәж–ҷгҒ®жёӣе…Қзӯү
ж–°еһӢгӮігғӯгғҠгӮҰгӮӨгғ«гӮ№ж„ҹжҹ“з—ҮгҒ®еҪұйҹҝгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰдёҖе®ҡзЁӢеәҰеҸҺе…ҘгҒҢдёӢгҒҢгҒЈгҒҹж–№гҒҜгҖҒеӣҪж°‘еҒҘеә·дҝқйҷәгғ»еӣҪж°‘е№ҙйҮ‘гғ»еҫҢжңҹй«ҳйҪўиҖ…еҢ»зҷӮеҲ¶еәҰгҒҠгӮҲгҒід»Ӣиӯ·дҝқйҷәгҒ®дҝқйҷәж–ҷпјҲзЁҺпјүгҒ®жёӣе…ҚгӮ„еҫҙеҸҺзҢ¶дәҲгҒӘгҒ©гҒҢиӘҚгӮҒгӮүгӮҢгӮӢе ҙеҗҲгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҠе•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣе…Ҳ
| еӣҪж°‘еҒҘеә·дҝқйҷәж–ҷпјҲзЁҺпјү | гҒҠдҪҸгҒҫгҒ„гҒ®еёӮеҢәз”әжқ‘гҒ®еӣҪж°‘еҒҘеә·дҝқйҷәжӢ…еҪ“иӘІ пјҲеӣҪж°‘еҒҘеә·дҝқйҷәзө„еҗҲгҒ«гҒ”еҠ е…ҘгҒ®ж–№гҒҜгҖҒеҠ е…ҘгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢзө„еҗҲпјү |
| еҫҢжңҹй«ҳйҪўиҖ…еҢ»зҷӮеҲ¶еәҰгҒ®дҝқйҷәж–ҷ | гҒҠдҪҸгҒҫгҒ„гҒ®еёӮеҢәз”әжқ‘гҒ®еҫҢжңҹй«ҳйҪўиҖ…еҢ»зҷӮжӢ…еҪ“иӘІ |
| д»Ӣиӯ·дҝқйҷәж–ҷ | гҒҠдҪҸгҒҫгҒ„гҒ®еёӮеҢәз”әжқ‘гҒ®д»Ӣиӯ·дҝқйҷәжӢ…еҪ“иӘІ |
| еӣҪж°‘е№ҙйҮ‘дҝқйҷәж–ҷ | гҒҠдҪҸгҒҫгҒ„гҒ®еёӮеҢәз”әжқ‘гҒ®еӣҪж°‘е№ҙйҮ‘жӢ…еҪ“иӘІ гҒҫгҒҹгҒҜе№ҙйҮ‘дәӢеӢҷжүҖ |
е…¬е…ұж–ҷйҮ‘зӯүгҒ®ж”Ҝжү•гҒ„зҢ¶дәҲгҖҖ
ж–°еһӢгӮігғӯгғҠгӮҰгӮӨгғ«гӮ№ж„ҹжҹ“з—ҮгҒ®еҪұйҹҝгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒйӣ»ж°—гғ»гӮ¬гӮ№гғ»йӣ»и©ұж–ҷйҮ‘гғ»NHKеҸ—дҝЎж–ҷгҒ®ж”Ҝжү•гҒ„гҒҢеӣ°йӣЈгҒӘж–№гҒ«гҒҜгҖҒж”Ҝжү•гҒ„зҢ¶дәҲгҒҢиӘҚгӮҒгӮүгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҠе•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣе…Ҳ
еҘ‘зҙ„гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢеҗ„дәӢжҘӯиҖ…
дҪҸеұ…зўәдҝқзөҰд»ҳйҮ‘пјҲ家иіғпјү
дј‘жҘӯзӯүгҒ«дјҙгҒҶеҸҺе…Ҙжёӣе°‘гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰдҪҸеұ…гӮ’еӨұгҒҶгҒҠгҒқгӮҢгҒҢз”ҹгҒҳгҒҰгҒ„гӮӢж–№гҒ«гҖҒдёҖе®ҡжңҹ間家иіғзӣёеҪ“йЎҚгҒҢж”ҜзөҰгҒ•гӮҢгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
3гҒӢжңҲй–“гҒ®еҶҚж”ҜзөҰгҒ®з”іи«Ӣжңҹй–“гҒҢд»Өе’Ң4е№ҙ6жңҲжң«ж—ҘгҒҫгҒ§е»¶й•·гҒ•гӮҢгӮӢдәҲе®ҡгҒ§гҒҷгҖӮ
д»Өе’Ң3е№ҙ1жңҲ1ж—Ҙд»ҘйҷҚгҒҜжңҖй•·гҒ§12гҒӢжңҲгҒҫгҒ§е»¶й•·гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҸҜиғҪгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷпјҲвҖ» д»Өе’Ң2е№ҙеәҰдёӯгҒ«ж–°иҰҸз”іи«ӢгҒ—гҒҰеҸ—зөҰгӮ’й–Ӣе§ӢгҒ—гҒҹж–№гҒ«йҷҗгӮӢпјүгҖӮ
-
еҜҫиұЎиҖ…
в‘ йӣўиҒ·гғ»е»ғжҘӯеҫҢпј’е№ҙд»ҘеҶ…гҒ®ж–№
в‘Ў еҖӢдәәгҒ®иІ¬д»»гғ»йғҪеҗҲгҒ«гӮҲгӮүгҒҡзөҰдёҺзӯүгӮ’еҫ—гӮӢж©ҹдјҡгҒҢгҖҒйӣўиҒ·гғ»е»ғжҘӯгҒЁеҗҢзЁӢеәҰгҒҫгҒ§жёӣе°‘гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢе ҙеҗҲгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒдёҖе®ҡгҒ®иҰҒ件гӮ’жәҖгҒҹгҒ—гҒҹе ҙеҗҲ
ж”ҜзөҰжңҹй–“
еҺҹеүҮ3гҒӢжңҲпјҲжңҖй•·9гҒӢжңҲпјү
вҖ» дҪҸеұ…зўәдҝқзөҰд»ҳйҮ‘гҒ®ж”ҜзөҰгҒҢзөӮдәҶгҒ—гҒҹж–№гҒ«еҜҫгҒ—гҖҒд»Өе’Ң4е№ҙ6жңҲжң«гҒҫгҒ§гҒ®й–“гҖҒ3гҒӢжңҲй–“гҒ®еҶҚж”ҜзөҰгҒҢеҸҜиғҪгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷпјҲд»Өе’Ң3е№ҙ2жңҲз”іи«ӢгҒӢгӮүпјүгҖӮ
ж”ҜзөҰйЎҚ
家иіғйЎҚпјҲгҒҹгҒ гҒ—дҪҸе®…жү¶еҠ©зү№еҲҘеҹәжә–йЎҚгӮ’дёҠйҷҗгҒЁгҒҷгӮӢпјү
ж”ҜзөҰиҰҒ件
гғ»еҸҺе…ҘиҰҒ件пјҡдё–еёҜеҸҺе…ҘеҗҲиЁҲйЎҚгҒҢгҖҒв‘ гҒЁв‘ЎгҒ®еҗҲиЁҲйЎҚгӮ’и¶ҠгҒҲгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁ
гҖҖв‘ еёӮз”әжқ‘ж°‘зЁҺеқҮзӯүеүІгҒҢйқһиӘІзЁҺгҒЁгҒӘгӮӢеҸҺе…ҘйЎҚгҒ®1/12
гҖҖв‘Ў 家иіғйЎҚпјҲдҪҸе®…жү¶еҠ©зү№еҲҘеҹәжә–йЎҚгҒҢдёҠйҷҗпјү
гғ»иіҮз”ЈиҰҒ件пјҡдё–еёҜгҒ®й җиІҜйҮ‘гҒ®еҗҲиЁҲйЎҚгҒҢгҖҒдёҠиЁҳв‘ гҒ®6жңҲеҲҶгӮ’и¶…гҒҲгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁпјҲгҒҹгҒ гҒ—100дёҮеҶҶгӮ’и¶…гҒҲгҒӘгҒ„йЎҚпјү
гғ»жұӮиҒ·жҙ»еӢ•зӯүиҰҒ件пјҡгғҸгғӯгғјгғҜгғјгӮҜгҒҫгҒҹгҒҜең°ж–№е…¬е…ұеӣЈдҪ“гҒҢиЁӯгҒ‘гӮӢе…¬зҡ„гҒӘз„Ўж–ҷиҒ·жҘӯзҙ№д»ӢгҒ®зӘ“еҸЈгҒ«жұӮиҒ·гҒ®з”іиҫј
гҒҠе•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣе…Ҳ
зӣёи«ҮгӮігғјгғ«гӮ»гғігӮҝгғјпјҲдёҖиҲ¬зҡ„гҒӘгҒҠе•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣпјү
гғ•гғӘгғјгғҖгӮӨгғӨгғ«0120пҪ°23пҪ°5572 пјҲ 9пјҡ00пҪһ17пјҡ00 е№іж—ҘгҒ®гҒҝпјү
гҒҠз”іиҫјгҒҝе…Ҳ
гҒҠдҪҸгҒҫгҒ„гҒ®еёӮеҢәз”әжқ‘гҒ®иҮӘз«Ӣзӣёи«Үж”ҜжҸҙж©ҹй–ў
е…ЁеӣҪйҖЈзөЎе…ҲдёҖиҰ§гҒҜгҒ“гҒЎгӮү
з·ҠжҖҘе°ҸеҸЈиіҮйҮ‘гғ»з·ҸеҗҲж”ҜжҸҙиіҮйҮ‘
ж–°еһӢгӮігғӯгғҠгӮҰгӮӨгғ«гӮ№ж„ҹжҹ“з—ҮгҒ®еҪұйҹҝгҒ§еҸҺе…ҘгҒҢжёӣе°‘гҒ—з”ҹжҙ»гҒ«еӣ°зӘ®гҒҷгӮӢж–№гҒёгҒ®зү№дҫӢиІёд»ҳгҒ§гҒҷгҖӮ
з·ҠжҖҘе°ҸеҸЈиіҮйҮ‘гҒЁз·ҸеҗҲж”ҜжҸҙиіҮйҮ‘ (еҲқеӣһиІёд»ҳ)гҒ®з”іи«Ӣжңҹй–“гҒҜ2022пјҲд»Өе’Ң4е№ҙпјү6жңҲжң«ж—ҘгҒҫгҒ§е»¶й•·гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ(вҖ»
2022е№ҙ5жңҲзҸҫеңЁ)
| з·ҠжҖҘе°ҸеҸЈиіҮйҮ‘пјҲдёҖжҷӮзҡ„гҒӘиіҮйҮ‘гҒҢеҝ…иҰҒгҒӘж–№пјү пј»дё»гҒ«дј‘жҘӯгҒ•гӮҢгҒҹж–№еҗ‘гҒ‘пјҪ |
|
|---|---|
|
еҜҫиұЎиҖ… ж–°еһӢгӮігғӯгғҠгӮҰгӮӨгғ«гӮ№ж„ҹжҹ“з—ҮгҒ®еҪұйҹҝгӮ’еҸ—гҒ‘гҖҒдј‘жҘӯгҒӘгҒ©гҒ«гӮҲгӮҠеҸҺе…ҘгҒ®жёӣе°‘гҒҢгҒӮгӮҠгҖҒз·ҠжҖҘгҒӢгҒӨдёҖжҷӮзҡ„гҒӘз”ҹиЁҲз¶ӯжҢҒгҒ®гҒҹгӮҒгҒ®иІёд»ҳгӮ’еҝ…иҰҒгҒЁгҒҷгӮӢдё–еёҜ пјҲж–°еһӢгӮігғӯгғҠгӮҰгӮӨгғ«гӮ№гҒ®еҪұйҹҝгҒ§еҸҺе…ҘгҒ®жёӣе°‘гҒҢгҒӮгӮҢгҒ°гҖҒдј‘жҘӯзҠ¶ж…ӢгҒ«гҒӘгҒҸгҒҰгӮӮеҜҫиұЎпјү иІёд»ҳдёҠйҷҗйЎҚ 20дёҮеҶҶд»ҘеҶ… вҖ»еҫ“жқҘгҒ®10дёҮеҶҶд»ҘеҶ…гҒЁгҒҷгӮӢеҸ–жүұгӮ’жӢЎеӨ§гҒ—гҖҒдёӢиЁҳгҒ«и©ІеҪ“гҒҷгӮӢдё–еёҜгҒҜгҖҒиІёд»ҳдёҠйҷҗйЎҚгӮ’20дёҮеҶҶд»ҘеҶ…гҒЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ гӮў. дё–еёҜе“ЎгҒ®дёӯгҒ«ж–°еһӢгӮігғӯгғҠгӮҰгӮӨгғ«гӮ№ж„ҹжҹ“з—ҮгҒ®зҪ№жӮЈиҖ…зӯүгҒҢгҒ„гӮӢгҒЁгҒҚгҖӮ гӮӨ. дё–еёҜе“ЎгҒ«иҰҒд»Ӣиӯ·иҖ…гҒҢгҒ„гӮӢгҒЁгҒҚгҖӮ гӮҰ. дё–еёҜе“ЎгҒҢ4дәәд»ҘдёҠгҒ„гӮӢгҒЁгҒҚгҖӮ гӮЁ. дё–еёҜе“ЎгҒ«ж–°еһӢгӮігғӯгғҠгӮҰгӮӨгғ«гӮ№ж„ҹжҹ“з—ҮжӢЎеӨ§йҳІжӯўзӯ–гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒ иҮЁжҷӮдј‘жҘӯгҒ—гҒҹеӯҰж ЎзӯүгҒ«йҖҡгҒҶеӯҗгҒ®дё–и©ұгӮ’иЎҢгҒҶгҒ“гҒЁгҒҢеҝ…иҰҒгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹеҠҙеғҚиҖ…гҒҢгҒ„гӮӢгҒЁгҒҚгҖӮ гӮӘ. дё–еёҜе“ЎгҒ«йўЁйӮӘз—ҮзҠ¶гҒӘгҒ©ж–°еһӢгӮігғӯгғҠгӮҰгӮӨгғ«гӮ№гҒ«ж„ҹжҹ“гҒ—гҒҹжҒҗгӮҢгҒ®гҒӮгӮӢгҖҒ е°ҸеӯҰж ЎзӯүгҒ«йҖҡгҒҶеӯҗгҒ®дё–и©ұгӮ’иЎҢгҒҶгҒ“гҒЁгҒҢеҝ…иҰҒгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹеҠҙеғҚиҖ…гҒҢгҒ„гӮӢгҒЁгҒҚгҖӮ гӮ«. дёҠиЁҳд»ҘеӨ–гҒ§дј‘жҘӯзӯүгҒ«гӮҲгӮӢеҸҺе…ҘгҒ®жёӣе°‘зӯүгҒ§з”ҹжҙ»иІ»з”ЁгҒ®иІёд»ҳгҒҢеҝ…иҰҒгҒӘгҒЁгҒҚгҖӮ жҚ®зҪ®жңҹй–“ пј‘е№ҙд»ҘеҶ… пјҲд»Өе’Ң4е№ҙ12жңҲжң«ж—Ҙд»ҘеүҚгҒ«е„ҹйӮ„гҒҢй–Ӣе§ӢгҒЁгҒӘгӮӢиІёд»ҳгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒд»Өе’Ң4е№ҙ12жңҲжң«ж—ҘгҒҫгҒ§жҚ®зҪ®жңҹй–“гҒҢ延長гҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮпјү е„ҹйӮ„пјҲиҝ”жёҲпјүжңҹйҷҗ пј’е№ҙд»ҘеҶ… пјҲе„ҹйӮ„жҷӮгҒ«гҖҒгҒӘгҒҠжүҖеҫ—гҒ®жёӣе°‘гҒҢз¶ҡгҒҸдҪҸж°‘зЁҺйқһиӘІзЁҺдё–еёҜгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜе„ҹйӮ„гӮ’е…ҚйҷӨгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷпјү иІёд»ҳеҲ©еӯҗгғ»дҝқиЁјдәә з„ЎеҲ©еӯҗгғ»дёҚиҰҒ |
|
| з·ҸеҗҲж”ҜжҸҙиіҮйҮ‘пјҲз”ҹжҙ»гҒ®з«ӢгҒҰзӣҙгҒ—гҒҢеҝ…иҰҒгҒӘж–№пјү пј»дё»гҒ«еӨұжҘӯгҒ•гӮҢгҒҹж–№зӯүеҗ‘гҒ‘пјҪ |
|
|---|---|
|
еҜҫиұЎиҖ… ж–°еһӢгӮігғӯгғҠгӮҰгӮӨгғ«гӮ№гҒ®еҪұйҹҝгӮ’еҸ—гҒ‘гҖҒеҸҺе…ҘгҒ®жёӣе°‘гӮ„еӨұжҘӯзӯүгҒ«гӮҲгӮҠз”ҹжҙ»гҒ«еӣ°зӘ®гҒ—гҖҒж—Ҙеёёз”ҹжҙ»гҒ®з¶ӯжҢҒгҒҢеӣ°йӣЈгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢдё–еёҜ пјҲж–°еһӢгӮігғӯгғҠгӮҰгӮӨгғ«гӮ№гҒ®еҪұйҹҝгҒ§еҸҺе…ҘгҒ®жёӣе°‘гҒҢгҒӮгӮҢгҒ°гҖҒеӨұжҘӯзҠ¶ж…ӢгҒ«гҒӘгҒҸгҒҰгӮӮеҜҫиұЎпјү иІёд»ҳдёҠйҷҗйЎҚ гғ»пјҲпј’дәәд»ҘдёҠдё–еёҜпјүжңҲ20дёҮеҶҶд»ҘеҶ… гғ»пјҲеҚҳиә«дё–еёҜпјү гҖҖ жңҲ15дёҮеҶҶд»ҘеҶ… иІёд»ҳжңҹй–“пјҡеҺҹеүҮ3гҒӢжңҲд»ҘеҶ… жҚ®зҪ®жңҹй–“ пј‘е№ҙд»ҘеҶ… пјҲд»Өе’Ң4е№ҙ12жңҲжң«ж—Ҙд»ҘеүҚгҒ«е„ҹйӮ„гҒҢй–Ӣе§ӢгҒЁгҒӘгӮӢиІёд»ҳгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒд»Өе’Ң4е№ҙ12жңҲжң«ж—ҘгҒҫгҒ§жҚ®зҪ®жңҹй–“гҒҢ延長гҒ—гҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮпјү е„ҹйӮ„пјҲиҝ”жёҲпјүжңҹйҷҗ 10е№ҙд»ҘеҶ… пјҲе„ҹйӮ„жҷӮгҒ«гҖҒгҒӘгҒҠжүҖеҫ—гҒ®жёӣе°‘гҒҢз¶ҡгҒҸдҪҸж°‘зЁҺйқһиӘІзЁҺдё–еёҜгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜе„ҹйӮ„гӮ’е…ҚйҷӨгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷпјү иІёд»ҳеҲ©еӯҗгғ»дҝқиЁјдәә з„ЎеҲ©еӯҗгғ»дёҚиҰҒ гҒҠе•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣе…Ҳ зӣёи«ҮгӮігғјгғ«гӮ»гғігӮҝгғјпјҲдёҖиҲ¬зҡ„гҒӘгҒҠе•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣпјү гғ•гғӘгғјгғҖгӮӨгғӨгғ«0120-46-1999пјҲжҜҺж—Ҙ 9пјҡ00пҪһ17пјҡ00гҖҖе№іж—ҘгҒ®гҒҝ пјү гҒҠз”іиҫјгҒҝе…Ҳ гҒҠдҪҸгҒҫгҒ„гҒ®еёӮеҢәз”әжқ‘гҒ®зӨҫдјҡзҰҸзҘүеҚ”иӯ°дјҡ пјҲйғөйҖҒгҒ§гҒ®гҒҠз”іиҫјгҒҝгӮӮеҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖӮпјү |
|
ж–°еһӢгӮігғӯгғҠгӮҰгӮӨгғ«гӮ№ж„ҹжҹ“з—Үз”ҹжҙ»еӣ°зӘ®иҖ…иҮӘз«Ӣж”ҜжҸҙйҮ‘
з·ҠжҖҘе°ҸеҸЈиіҮйҮ‘зӯүгҒ®зү№дҫӢиІёд»ҳгӮ’еҲ©з”ЁгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„дёҖе®ҡгҒ®дё–еёҜгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰж”ҜзөҰгҒ•гӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
-
еҜҫиұЎиҖ…
з·ҠжҖҘе°ҸеҸЈиіҮйҮ‘зӯүгҒ®зү№дҫӢиІёд»ҳгӮ’еҲ©з”ЁгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„дё–еёҜпјҲвҖ»пјүгҒ§гҖҒд»ҘдёӢгҒ®иҰҒ件гӮ’жәҖгҒҹгҒҷж–№пјҲвҖ»пјү
гғ»з·ҸеҗҲж”ҜжҸҙиіҮйҮ‘гҒ®еҶҚиІёд»ҳгӮ’еҖҹгӮҠзөӮгӮҸгҒЈгҒҹдё–еёҜ/д»Өе’Ң4е№ҙ6жңҲгҒҫгҒ§гҒ«еҖҹгӮҠзөӮгӮҸгӮӢдё–еёҜ
гғ»з·ҸеҗҲж”ҜжҸҙиіҮйҮ‘гҒ®еҶҚиІёд»ҳгҒҢдёҚжүҝиӘҚгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹдё–еёҜ
гғ»з·ҸеҗҲж”ҜжҸҙиіҮйҮ‘гҒ®еҶҚиІёд»ҳгҒ®зӣёи«ҮгӮ’гҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ®гҖҒз”ігҒ—иҫјгҒҝгҒ«иҮігӮүгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹдё–еёҜ
гғ»д»Өе’Ң4е№ҙ1жңҲд»ҘйҷҚгҒ«ж–°гҒҹгҒ«иҮӘз«Ӣж”ҜжҸҙйҮ‘гӮ’з”іи«ӢгҒҷгӮӢдё–еёҜгҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгҖҒз·ҠжҖҘе°ҸеҸЈиіҮйҮ‘гҒҠгӮҲгҒіз·ҸеҗҲж”ҜжҸҙиіҮйҮ‘гҒ®еҲқеӣһиІёд»ҳгӮ’еҖҹгӮҠзөӮгӮҸгҒЈгҒҹдё–еёҜ/д»Өе’Ң4е№ҙ6жңҲгҒҫгҒ§гҒ«еҖҹгӮҠзөӮгӮҸгӮӢдё–еёҜ
еҸҺе…ҘиҰҒ件
еҸҺе…ҘгҒҢв‘ в‘ЎгҒ®еҗҲз®—йЎҚгӮ’и¶…гҒҲгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁпјҲжңҲйЎҚпјү
в‘ еёӮз”әжқ‘ж°‘зЁҺеқҮзӯүеүІйқһиӘІзЁҺйЎҚгҒ®1/12
в‘Ўз”ҹжҙ»дҝқиӯ·гҒ®дҪҸе®…жү¶еҠ©еҹәжә–йЎҚ
иіҮз”ЈиҰҒ件
й җиІҜйҮ‘гҒҢв‘ гҒ®пј–еҖҚд»ҘдёӢгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁпјҲгҒҹгҒ гҒ—100дёҮеҶҶд»ҘдёӢпјү
жұӮиҒ·жҙ»еӢ•зӯүиҰҒ件
д»ҘдёӢгҒ®гҒ„гҒҡгӮҢгҒӢгҒ®иҰҒ件гӮ’жәҖгҒҹгҒҷгҒ“гҒЁ
гғ»гғҸгғӯгғјгғҜгғјгӮҜгҒҫгҒҹгҒҜең°ж–№е…¬е…ұеӣЈдҪ“гҒҢиЁӯгҒ‘гӮӢе…¬зҡ„гҒӘз„Ўж–ҷиҒ·жҘӯзҙ№д»ӢгҒ®зӘ“еҸЈгҒ«жұӮиҒ·гҒ®з”іиҫјгӮ’гҒ—гҖҒиӘ е®ҹгҒӢгҒӨзҶұеҝғгҒ«жұӮиҒ·жҙ»еӢ•гӮ’иЎҢгҒҶгҒ“гҒЁ
гғ»е°ұеҠҙгҒ«гӮҲгӮӢиҮӘз«ӢгҒҢеӣ°йӣЈгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒжң¬зөҰд»ҳзөӮдәҶеҫҢгҒ®з”ҹжҙ»гҒ®з¶ӯжҢҒгҒҢеӣ°йӣЈгҒЁиҰӢиҫјгҒҫгӮҢгӮӢе ҙеҗҲгҒ«гҒҜгҖҒз”ҹжҙ»дҝқиӯ·гҒ®з”іи«ӢгӮ’иЎҢгҒҶгҒ“гҒЁ
ж”ҜзөҰйЎҚпјҲжңҲйЎҚпјү
еҚҳиә«дё–еёҜпјҡпј–дёҮеҶҶ
2дәәдё–еёҜпјҡпјҳдёҮеҶҶ
3дәәд»ҘдёҠдё–еёҜпјҡпј‘пјҗдёҮеҶҶ
пјҲвҖ» дҪҸеұ…зўәдҝқзөҰд»ҳйҮ‘гҒЁгҒ®дҪөзөҰгҒҢеҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖӮпјү
ж”ҜзөҰжңҹй–“
д»Өе’Ң3е№ҙ7жңҲд»ҘйҷҚгҒ®з”іи«ӢжңҲгҒӢгӮүпј“гҒӢжңҲ
вҖ»ж–°еһӢгӮігғӯгғҠгӮҰгӮӨгғ«гӮ№з”ҹжҙ»еӣ°зӘ®иҖ…иҮӘз«Ӣж”ҜжҸҙйҮ‘гҒ®ж”ҜзөҰгҒҢзөӮдәҶгҒ—гҒҹж–№гҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҖҒпј“гҒӢжңҲй–“гҒ®еҶҚж”ҜзөҰгҒҢеҸҜиғҪгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮпјҲз”іи«ӢеҸ—д»ҳгҒҜд»Өе’Ң4е№ҙ6жңҲжң«гҒҫгҒ§пјү
гҒҠе•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣе…Ҳ
зӣёи«ҮгӮігғјгғ«гӮ»гғігӮҝгғјпјҲдёҖиҲ¬зҡ„гҒӘгҒҠе•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣпјү
гғ•гғӘгғјгғҖгӮӨгғӨгғ«0120-46-1999пјҲжҜҺж—Ҙ 9пјҡ00пҪһ17пјҡ00гҖҖе№іж—ҘгҒ®гҒҝ пјү
гҒҠз”іиҫјгҒҝе…Ҳ
гҒҠдҪҸгҒҫгҒ„гҒ®иҮӘжІ»дҪ“
в–јй–ўйҖЈгғӘгғігӮҜпјҡ
еҺҡз”ҹеҠҙеғҚзңҒгҖҢз”ҹжҙ»гӮ’ж”ҜгҒҲгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®ж”ҜжҸҙгҒ®гҒ”жЎҲеҶ…гҖҚ
еҺҡз”ҹеҠҙеғҚзңҒгҖҢз”ҹжҙ»ж”ҜжҸҙзү№иЁӯгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҖҚ
еҶ…й–Је®ҳжҲҝгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҖҢж–°еһӢгӮігғӯгғҠгӮҰгӮӨгғ«гӮ№ж„ҹжҹ“з—ҮгҒ«дјҙгҒҶеҗ„зЁ®ж”ҜжҸҙгҒ®гҒ”жЎҲеҶ…гҖҚ
ж–°еһӢгӮігғӯгғҠгӮҰгӮӨгғ«гӮ№ж„ҹжҹ“з—ҮгҒ«й–ўгҒҷгӮӢзӣёи«Ү

еҺҡз”ҹеҠҙеғҚзңҒгҒ®йӣ»и©ұзӣёи«ҮзӘ“еҸЈ
ж–°еһӢгӮігғӯгғҠгӮҰгӮӨгғ«гӮ№ж„ҹжҹ“з—Үзӣёи«ҮзӘ“еҸЈ
гғ•гғӘгғјгғҖгӮӨгғӨгғ«гҖҖпјҗпј‘пј’пјҗпјҚпј•пј–пј•пј–пј•пј“пјҲ 9пјҡ00пҪһ21пјҡ00 пјү
ж–°еһӢгӮігғӯгғҠгғҜгӮҜгғҒгғігӮігғјгғ«гӮ»гғігӮҝгғј
гғ•гғӘгғјгғҖгӮӨгғӨгғ«гҖҖпјҗпј‘пј’пјҗпјҚпј—пј–пј‘пј—пј—пјҗпјҲ 9пјҡ00пҪһ21пјҡ00 пјү
иҒҙиҰҡгҒ«йҡңе®ігҒ®гҒӮгӮӢж–№гҒҜгҖҢдёҖиҲ¬иІЎеӣЈжі•дәәе…Ёж—Ҙжң¬гӮҚгҒҶгҒӮйҖЈзӣҹгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮёгҖҚгӮ’гҒ”иҰ§гҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ
еҝғгҒ®еҒҘеә·гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰзӣёи«Ү
е…ЁеӣҪзІҫзҘһдҝқеҒҘзҰҸзҘүгӮ»гғігӮҝгғјдёҖиҰ§ж–°еһӢгӮігғӯгғҠгӮҰгӮӨгғ«гӮ№ж„ҹжҹ“з—ҮгҒ«дҝӮгӮӢеҝғгҒ®гӮұгӮўгҒ«й–ўгҒҷгӮӢиҮӘжІ»дҪ“зӣёи«ҮзӘ“еҸЈдёҖиҰ§
гҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒӘжӮ©гҒҝзӣёи«Ү
гӮҲгӮҠгҒқгҒ„гғӣгғғгғҲгғ©гӮӨгғіпјҲдёҖиҲ¬зӨҫеӣЈжі•дәә зӨҫдјҡзҡ„еҢ…ж‘ӮгӮөгғқгғјгғҲгӮ»гғігӮҝгғјпјү
гғ•гғӘгғјгғҖгӮӨгғӨгғ«0120-279-338
пјҲеІ©жүӢгғ»е®®еҹҺгғ»зҰҸеі¶зңҢгҒӢгӮүгҒҜгҖҒ0120-279-226пјү
в–јй–ўйҖЈгғӘгғігӮҜ
еҺҡз”ҹеҠҙеғҚзңҒгҖҢйӣ»и©ұзӣёи«ҮгҖҚ
йӣ»и©ұгғ»гӮӘгғігғ©гӮӨгғіиЁәзҷӮгҖҖ
ж–°еһӢгӮігғӯгғҠгӮҰгӮӨгғ«гӮ№ж„ҹжҹ“гҒ®жҮёеҝөгҒӢгӮүгҖҒйӣ»и©ұгӮ„гғ‘гӮҪгӮігғігҖҒгӮ№гғһгғӣгҒӘгҒ©гҒ§еҢ»зҷӮж©ҹй–ўгҒ«зӣёи«Үгғ»еҸ—иЁәгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҡгҒҜгҒӢгҒӢгӮҠгҒӨгҒ‘еҢ»гҒӘгҒ©гҒ«зӣёи«ҮгҒ—гҒҰгҒҝгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
еҜҫеҝңгҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„еҢ»зҷӮж©ҹй–ўгӮӮгҒӮгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒеҸ—иЁәгӮ’иҖғгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢеҢ»зҷӮж©ҹй–ўгҒҢйӣ»и©ұгғ»гӮӘгғігғ©гӮӨгғіиЁәзҷӮгӮ’иЎҢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢзўәиӘҚгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
еҺҡз”ҹеҠҙеғҚзңҒгҒ§гҒҜгҖҒйӣ»и©ұгғ»гӮӘгғігғ©гӮӨгғіиЁәзҷӮгҒ«еҜҫеҝңгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢеҢ»зҷӮж©ҹй–ўгғӘгӮ№гғҲгӮ’е…¬иЎЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
еҺҡз”ҹеҠҙеғҚзңҒгҖҢж–°еһӢгӮігғӯгғҠгӮҰгӮӨгғ«гӮ№ж„ҹжҹ“з—ҮгҒ®ж„ҹжҹ“жӢЎеӨ§гӮ’иёҸгҒҫгҒҲгҒҹгӮӘгғігғ©гӮӨгғіиЁәзҷӮгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҚ
и©җж¬әгҒ«гҒ”жіЁж„ҸгҒҸгҒ гҒ•гҒ„пјҒ

ж–°еһӢгӮігғӯгғҠгӮҰгӮӨгғ«гӮ№гҒ«дҫҝд№—гҒ—гҒҹжӮӘиіӘе•Ҷжі•гӮ„и©җж¬әгҒҢзҷәз”ҹгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҢж–°еһӢгӮігғӯгғҠгӮҰгӮӨгғ«гӮ№гҒ®йҷӨиҸҢгӮ’гҒҷгӮӢгҖҚгҖҢж–°еһӢгӮігғӯгғҠгӮҰгӮӨгғ«гӮ№ж„ҹжҹ“з—ҮгҒҢдәҲйҳІгҒ§гҒҚгӮӢгҖҚгҒӘгҒ©гҒЁгҒ„гҒЈгҒҹиЁӘе•ҸиІ©еЈІгҒ«гҒҜж°—гӮ’гҒӨгҒ‘гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒеҺҡз”ҹеҠҙеғҚзңҒгӮ„еҪ№жүҖгҒӘгҒ©гӮ’гҒӢгҒҹгӮҠгҖҒзҸҫйҮ‘гӮ’гҒ гҒҫгҒ—еҸ–гӮҚгҒҶгҒЁгҒҷгӮӢйӣ»и©ұгҖҒгғЎгғјгғ«гҒ«гҒҜжіЁж„ҸгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒҷгҖӮ
зөҰд»ҳйҮ‘гҒ«й–ўгҒ—гҒҰгҖҒеӣҪгӮ„иҮӘжІ»дҪ“гҒҢгҖҢATMгҒ®ж“ҚдҪңгӮ’гҒҠйЎҳгҒ„гҒҷгӮӢгҖҚгҖҢзөҰд»ҳгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«жүӢж•°ж–ҷгҒ®жҢҜгӮҠиҫјгҒҝгӮ’жұӮгӮҒгӮӢгҖҚгҒ“гҒЁгҒҜзө¶еҜҫгҒ«гҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
жҡ—иЁјз•ӘеҸ·гӮ„еҸЈеә§з•ӘеҸ·гҖҒеҖӢдәәжғ…е ұгӮ’ж•ҷгҒҲгҒҹгӮҠгҖҒгӮӯгғЈгғғгӮ·гғҘгӮ«гғјгғүгӮ„йҖҡеёігӮ’жёЎгҒ—гҒҹгӮҠгҒ—гҒӘгҒ„гҒ§гҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ
гҖҢеҠ©жҲҗйҮ‘гҒҢгҒӮгӮӢгҖҚгҖҢгҒҠйҮ‘гҒҢиҝ”гҒЈгҒҰгҒҸгӮӢгҖҚгҒӘгҒ©гҒ®жҖӘгҒ—гҒ„йӣ»и©ұгҒҜгҒҷгҒҗгҒ«еҲҮгӮҠгҖҒдёҚеҜ©гҒӘгғЎгғјгғ«гӮ„SMSгҒҢеұҠгҒ„гҒҹе ҙеҗҲгҒҜз„ЎиҰ–гҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
е°‘гҒ—гҒ§гӮӮдёҚе®үгӮ’ж„ҹгҒҳгҒҹгҒЁгҒҚгӮ„гғҲгғ©гғ–гғ«гҒ«гҒӮгҒЈгҒҹе ҙеҗҲгҒҜгҖҒиӯҰеҜҹгӮ„ж¶ҲиІ»з”ҹжҙ»гӮ»гғігӮҝгғјгҒӘгҒ©гҒ«иҝ·гӮҸгҒҡзӣёи«ҮгҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
зӣёи«ҮзӘ“еҸЈ
гғ»ж¶ҲиІ»иҖ…гғӣгғғгғҲгғ©гӮӨгғігҖҢ188пјҲгҒ„гӮ„гӮ„пјҒпјүгҖҚ
гғ»гҒҠдҪҸгҒҫгҒ„гҒ®еёӮеҢәз”әжқ‘
гғ»гҒҠиҝ‘гҒҸгҒ®иӯҰеҜҹзҪІ
гғ»иӯҰеҜҹзӣёи«Үе°Ӯз”Ёйӣ»и©ұгҖҢ#9110гҖҚ
в–јй–ўйҖЈиЁҳдәӢ
гҒ”家ж—ҸгӮ„ең°еҹҹгҒ§иҰӢе®ҲгӮӢпјҒгҒ”й«ҳйҪўиҖ…гӮ’гҒӯгӮүгҒҶи©җж¬әгҒ®жүӢеҸЈгҒЁеҜҫзӯ–
гҒ”й«ҳйҪўиҖ…гҒ®ж¶ҲиІ»иҖ…гғҲгғ©гғ–гғ«гӮ’жңӘ然гҒ«йҳІгҒҗгҒҹгӮҒгҒ®гғқгӮӨгғігғҲ
家ж—ҸгҒ®д»Ӣиӯ·гӮ’гҒҚгҒЈгҒӢгҒ‘гҒ«д»Ӣиӯ·зҰҸзҘүеЈ«гғ»зӨҫдјҡзҰҸзҘүдё»дәӢд»»з”ЁиіҮж јгӮ’еҸ–еҫ—гҖӮзҸҫеңЁгҒҜгғ©гӮӨгӮҝгғјгҖӮж—ҘгҖ…гҒ®жҡ®гӮүгҒ—гҒ«еҪ№з«ӢгҒӨиә«иҝ‘гҒӘжғ…е ұгӮ’гҒҠдјқгҒҲгҒҷгӮӢгҒ№гҒҸгҖҒд»Ӣиӯ·гғ»еҢ»зҷӮгғ»зҫҺе®№гғ»гӮ«гғ«гғҒгғЈгғјгҒӘгҒ©е№…еәғгҒ„гӮёгғЈгғігғ«гҒ®иЁҳдәӢгӮ’еҹ·зӯҶдёӯгҖӮ

FacebookгғҡгғјгӮёгҒ§
жңҖж–°иЁҳдәӢй…ҚдҝЎпјҒпјҒ
 гғ¬гӮӘгғҸгӮҡгғ¬гӮ№21гӮҜгӮҷгғ«гғјгғ•гӮҡгҒ®д»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ’гӮҷгӮ№
гғ¬гӮӘгғҸгӮҡгғ¬гӮ№21гӮҜгӮҷгғ«гғјгғ•гӮҡгҒ®д»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ’гӮҷгӮ№