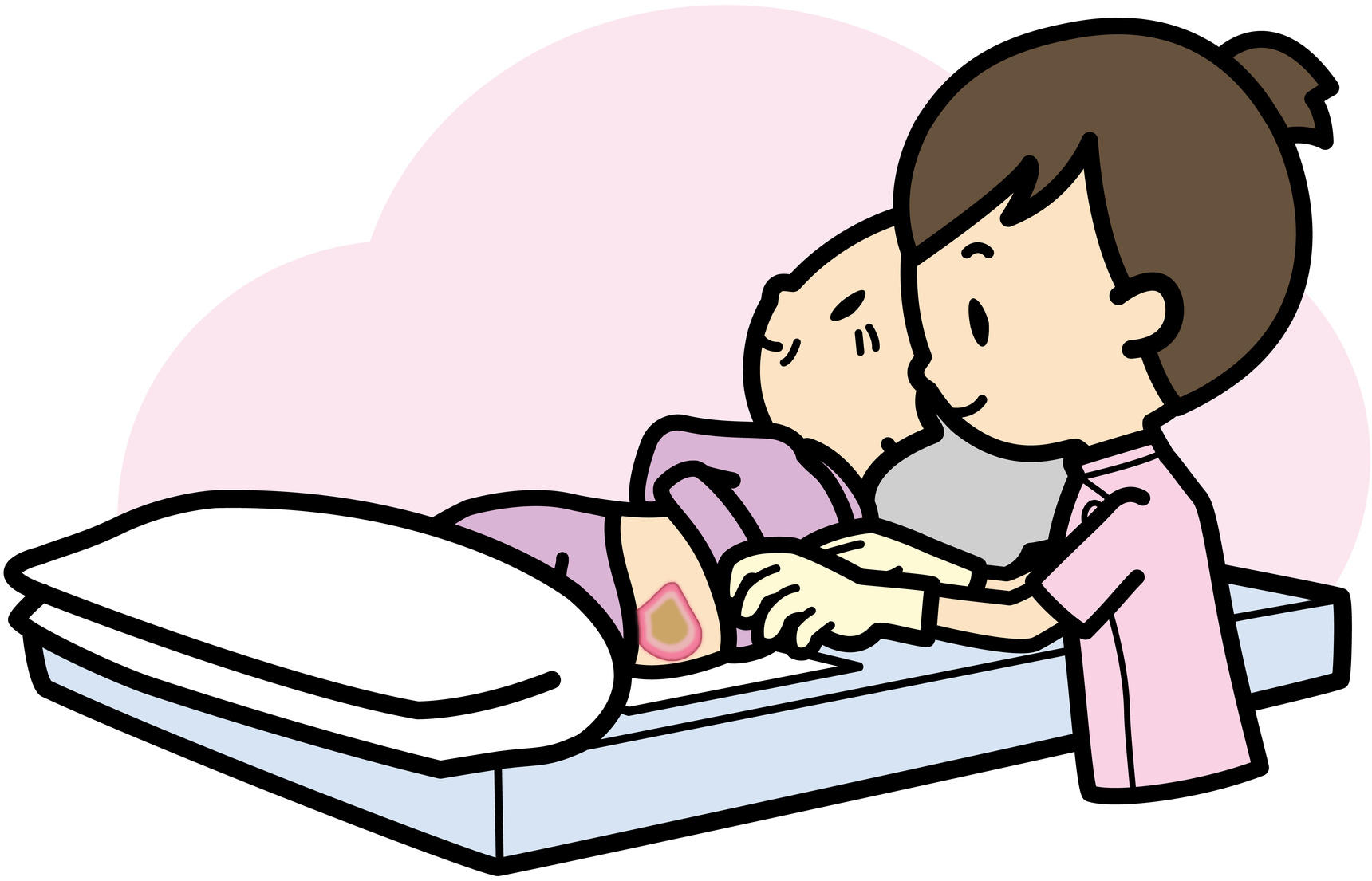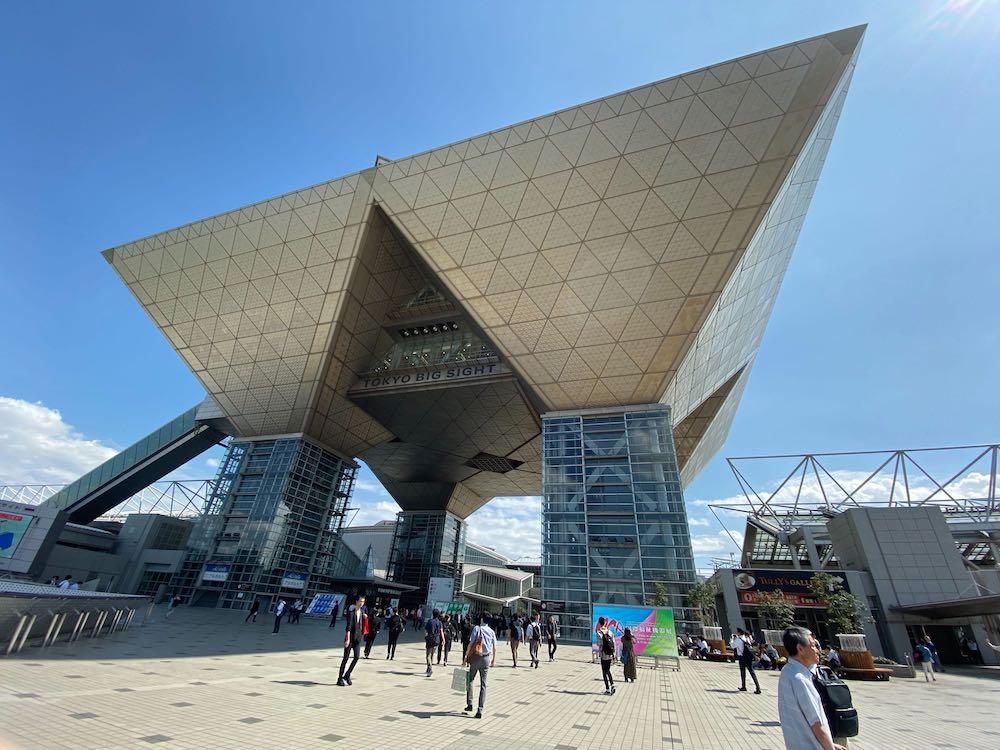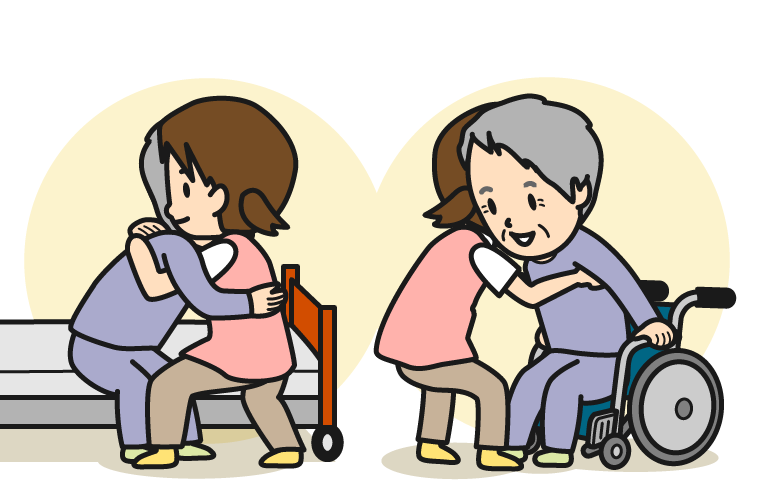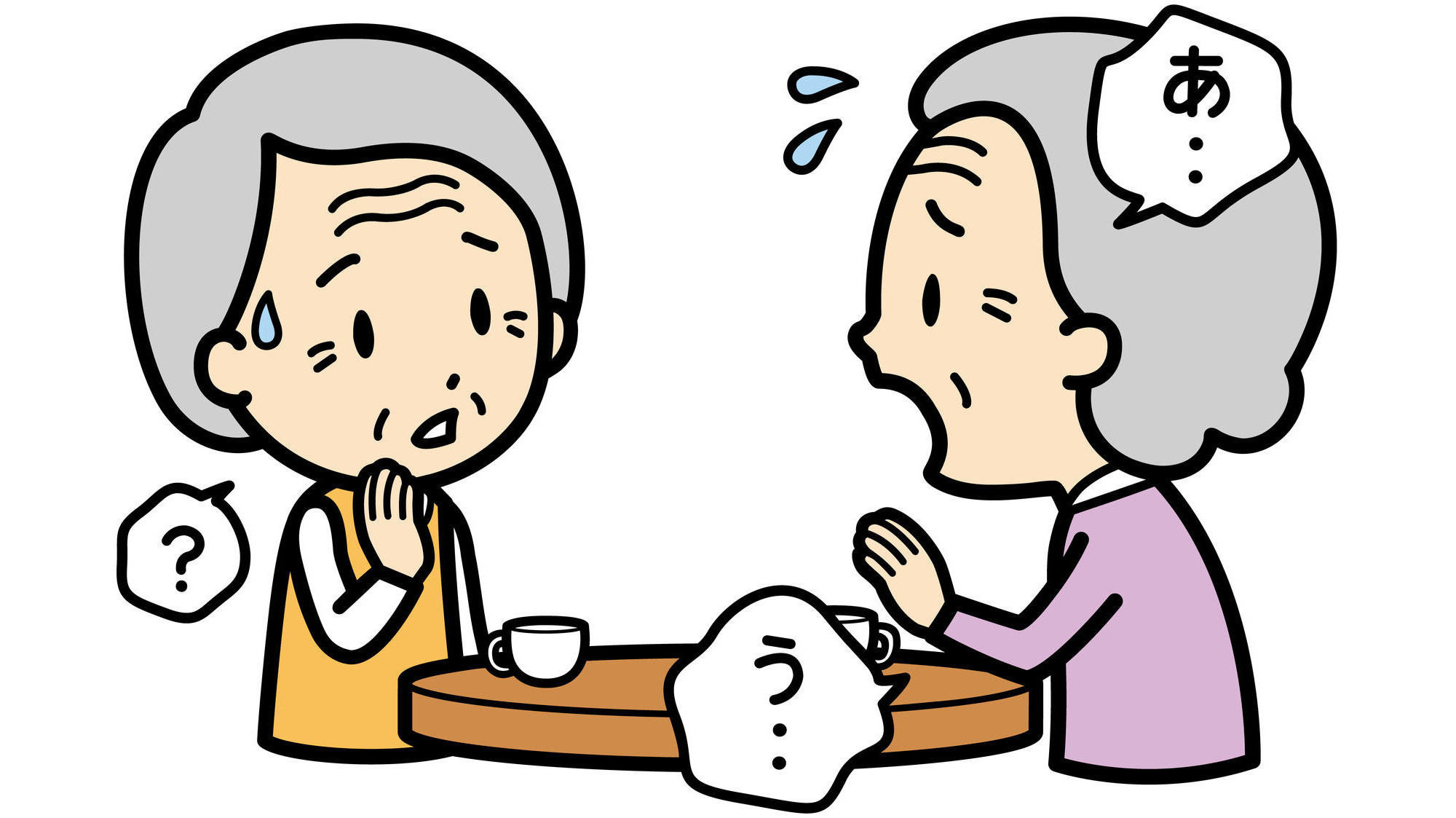д»Ӣиӯ·гҒ®дҫҝеҲ©её–гғҲгғғгғ—гҒёжҲ»гӮӢ
иІ жӢ…гҒҢе°‘гҒӘгҒҸз„ЎзҗҶгҒ®гҒӘгҒ„жӢҳзё®пјҲгҒ“гҒҶгҒ—гӮ…гҒҸпјүгӮұгӮўгҒ®гғқгӮӨгғігғҲ
й–ўзҜҖгҒ®еӢ•гҒҚгҒҢеҲ¶йҷҗгҒ•гӮҢгҒҹзҠ¶ж…ӢгҒ®гҒ“гҒЁгӮ’жӢҳзё®пјҲгҒ“гҒҶгҒ—гӮ…гҒҸпјүгҒЁгҒ„гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮжӢҳзё®гҒ®гҒӮгӮӢж–№гҒ®гӮұгӮўгҒ§гҒҜгҖҒгҒ”жң¬дәәгҒЁд»ӢеҠ©иҖ…гҒ®иІ жӢ…гӮ’гҒ§гҒҚгӮӢгҒ гҒ‘е°‘гҒӘгҒҸгҒ—гҖҒйҖІиЎҢгӮ’йҳІгҒҗгҒ“гҒЁгҒҢеӨ§еҲҮгҒ§гҒҷгҖӮд»ҠеӣһгҒҜгҖҒжӢҳзё®гҒ®еҹәзӨҺзҹҘиӯҳгӮ„гӮұгӮўгҒ®гғқгӮӨгғігғҲгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҠдјқгҒҲгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
жӢҳзё®пјҲгҒ“гҒҶгҒ—гӮ…гҒҸпјүгҒЁгҒҜ
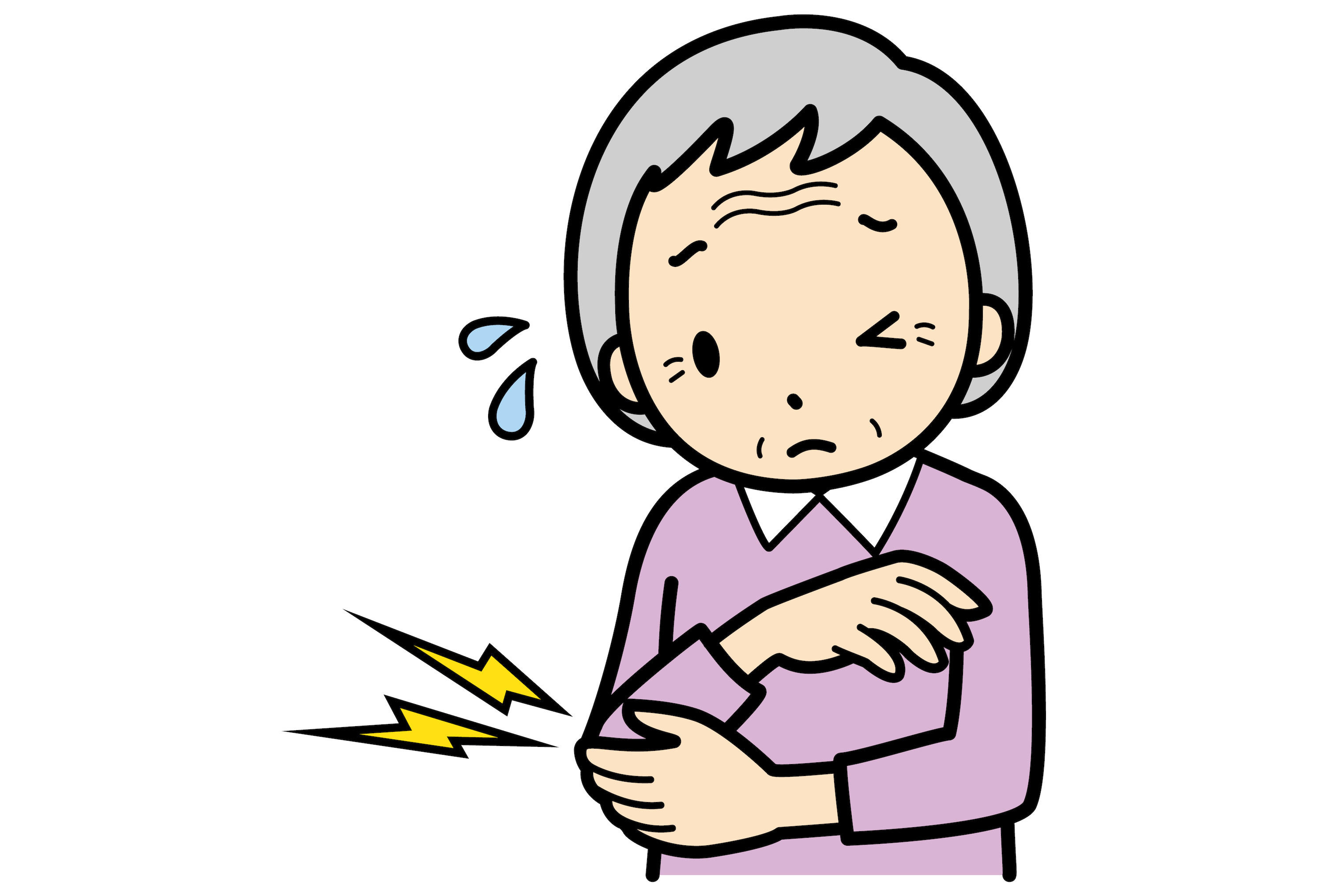
й–ўзҜҖпјҲйӘЁгҒЁйӘЁгҒЁгҒҢдә’гҒ„гҒ«еӢ•гҒ‘гӮӢзҠ¶ж…ӢгҒ§гҒӨгҒӘгҒҢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢйғЁеҲҶпјүгҒҢгҖҒгҒӘгӮ“гӮүгҒӢгҒ®еҺҹеӣ гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеӢ•гҒӢгҒ—гҒ«гҒҸгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹзҠ¶ж…ӢгҒ®гҒ“гҒЁгӮ’жӢҳзё®пјҲгҒ“гҒҶгҒ—гӮ…гҒҸпјүгҒЁгҒ„гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
й–ўзҜҖгҒ®е‘ЁгӮҠгҒ«гҒҜгҖҒзӯӢиӮүгӮ„и…ұпјҲгҒ‘гӮ“пјүгҖҒзҡ®иҶҡгҒӘгҒ©гҒ®и»ҹгӮүгҒӢгҒ„зө„з№”пјҲи»ҹйғЁзө„з№”пјүгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®и»ҹйғЁзө„з№”гҒҢеӣәгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгӮҠзҹӯзё®гҒ—гҒҹгӮҠгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгӮҠжӢҳзё®гҒҢз”ҹгҒҳгӮӢгҒЁгҖҒй–ўзҜҖгҒ®еҸҜеӢ•еҹҹпјҲеӢ•гҒӢгҒҷгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢзҜ„еӣІпјүгҒҢзӢӯгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
жӣІгҒҢгҒЈгҒҹгҒҫгҒҫгҒ§дјёгҒігҒӘгҒҸгҒӘгӮӢзҠ¶ж…ӢгӮ’еұҲжӣІпјҲгҒҸгҒЈгҒҚгӮҮгҒҸпјүжӢҳзё®гҒЁгҒ„гҒ„гҖҒдјёгҒігҒҹгҒҫгҒҫгҒ§жӣІгҒҢгӮүгҒӘгҒҸгҒӘгӮӢзҠ¶ж…ӢгӮ’дјёеұ•пјҲгҒ—гӮ“гҒҰгӮ“пјүжӢҳзё®гҒЁгҒ„гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
еӣәзё®пјҲгҒ“гҒ—гӮ…гҒҸпјүгҒЁгҒ®йҒ•гҒ„
еӣәзё®пјҲзӯӢеӣәзё®гҒЁгӮӮпјүгҒЁгҒҜгҖҒзӯӢз·ҠејөгҒҢдәўйҖІгҒ—гҖҒзӯӢиӮүгҒҢгҒ“гӮҸгҒ°гӮӢз—ҮзҠ¶гҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮеӣәзё®гҒ®гҒҹгӮҒгҒ«й–ўзҜҖгӮ’еӢ•гҒӢгҒҷж©ҹдјҡгҒҢе°‘гҒӘгҒҸгҒӘгӮӢгҒЁгҖҒжӢҳзё®пјҲгҒ“гҒҶгҒ—гӮ…гҒҸпјүгӮ’иө·гҒ“гҒ—гӮ„гҒҷгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
жӢҳзё®гҒҢиө·гҒ“гӮҠгӮ„гҒҷгҒ„йғЁдҪҚгҒЁеҪұйҹҝ
жӢҳзё®гҒҢиө·гҒ“гӮҠгӮ„гҒҷгҒ„гҒ®гҒҜгҖҒжүӢжҢҮгҖҒиӮ©гҖҒиӮҳпјҲгҒІгҒҳпјүгҖҒиҶқпјҲгҒІгҒ–пјүгҖҒи¶ігҖҒиӮЎгҒӘгҒ©гҒ®й–ўзҜҖгҒ§гҒҷгҖӮжӢҳзё®гҒҢгҒӮгӮӢгҒЁгҖҒгҒқгҒ®йғЁдҪҚгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰд»ҘдёӢгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘеҪұйҹҝгҒҢеҮәгҒҰгҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
жүӢгғ»жҢҮгҒ®й–ўзҜҖ
- гғ»жүӢжҢҮгҒҢжҸЎгҒЈгҒҹгҒҫгҒҫгҒ®зҠ¶ж…ӢгҒ«гҒӘгӮҠгҖҒзү©гҒҢгҒӨгҒӢгҒҝгҒ«гҒҸгҒ„
- гғ»зҲӘгҒҢжүӢгҒ®гҒІгӮүгҒ«йЈҹгҒ„иҫјгӮ“гҒ§з—ӣгҒ„гҖҒеӮ·гҒӨгҒ‘гӮ„гҒҷгҒ„
- гғ»жүӢгҒ®гҒІгӮүгҒ®жё…жҪ”гҒҢдҝқгҒЎгҒ«гҒҸгҒ„
иӮ©гғ»иӮҳпјҲгҒІгҒҳпјүгҒ®й–ўзҜҖ
- гғ»зқҖжӣҝгҒҲгҒҢгҒ—гҒ«гҒҸгҒҸгҒӘгӮҠгҖҒжҷӮй–“гҒҢгҒӢгҒӢгӮӢ
- гғ»иө·гҒҚдёҠгҒҢгӮӢгҖҒйЈҹдәӢгҒҷгӮӢгҒӘгҒ©гҒ®еӢ•дҪңгӮ„家дәӢгҒҢйӣЈгҒ—гҒҸгҒӘгӮӢ
- гғ»и„ҮгҒ®дёӢгҒ®жё…жҪ”гҒҢдҝқгҒЎгҒ«гҒҸгҒ„гҖҖ
иҶқпјҲгҒІгҒ–пјүгҒ®й–ўзҜҖ
- гғ»з«ӢгҒӨгҖҒеә§гӮӢгҖҒйҡҺж®өгӮ’дёҠгӮҠдёӢгӮҠгҒҷгӮӢгҒӘгҒ©гҒ®еӢ•дҪңгҒҢдёҚе®үе®ҡгҒ«гҒӘгӮӢ
- гғ»еә§дҪҚпјҲеә§гҒЈгҒҹе§ҝеӢўпјүгҒ®дҝқжҢҒгҒҢйӣЈгҒ—гҒҸгҒӘгӮӢ
- гғ»жӯ©гҒҚгҒ«гҒҸгҒҸгҒӘгӮҠгҖҒи»ўеҖ’гҒ—гӮ„гҒҷгҒҸгҒӘгӮӢ
- гғ»йқҙдёӢгӮ„йқҙгҒ®зқҖи„ұгҒҢеӣ°йӣЈгҒ«гҒӘгӮӢ
и¶ій–ўзҜҖ
- гғ»е°–и¶іпјҲгҒӣгӮ“гҒқгҒҸпјүвҖ» гҒ«гҒӘгӮҠгӮ„гҒҷгҒҸгҖҒжӯ©иЎҢгҒҢйӣЈгҒ—гҒҸгҒӘгӮӢ
- гғ»иғјиғқпјҲгҒҹгҒ“гғ»гҒ№гӮ“гҒЎпјүвҖ» гҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮӢ
- гғ»еә§дҪҚгҒҢдёҚе®үе®ҡгҒ«гҒӘгӮҠгӮ„гҒҷгҒ„
- гғ»и»ҠгҒ„гҒҷгҒ®гғ•гғғгғҲгӮөгғқгғјгғҲгҒ«и¶ігҒ®иЈҸгҒҢгҒӨгҒӢгҒӘгҒҸгҒӘгӮҠгҖҒдәӢж•…гҒҢиө·гҒ“гӮҠгӮ„гҒҷгҒ„
вҖ»е°–и¶іпјҲгҒӣгӮ“гҒқгҒҸпјүгҒЁгҒҜгҖҒи¶ігҒ®з”ІеҒҙгҒҢдјёгҒігҒҰгҖҒи¶іе…ҲгҒҢдёӢгӮ’еҗ‘гҒ„гҒҹгҒҫгҒҫгҒ®зҠ¶ж…Ӣ
вҖ»иғјиғқпјҲгҒҹгҒ“гғ»гҒ№гӮ“гҒЎпјүгҒЁгҒҜгҖҒзҡ®иҶҡгҒ®дёҖйғЁгҒҢеҺҡгҒҸзЎ¬гҒҸгҒӘгҒЈгҒҹзҠ¶ж…ӢгҒ®гҒ“гҒЁгҖӮ
иӮЎй–ўзҜҖ
- гғ»иЎЈйЎһгҒ®зқҖи„ұгҒҢеӣ°йӣЈгҒ«гҒӘгӮӢ
- гғ»еә§дҪҚгҒ®дҝқжҢҒгҖҒжҺ’гҒӣгҒӨгҒ®е§ҝеӢўгҒҢйӣЈгҒ—гҒҸгҒӘгӮӢ
- гғ»жӯ©гҒҚгҒ«гҒҸгҒҸгҒӘгӮҠгҖҒи»ўеҖ’гҒ—гӮ„гҒҷгҒҸгҒӘгӮӢ
- гғ»жөҙж§ҪгҒ«е…ҘгӮӢгҒ®гҒҢйӣЈгҒ—гҒҸгҒӘгӮӢ
жӢҳзё®гҒ®дё»гҒӘеҺҹеӣ
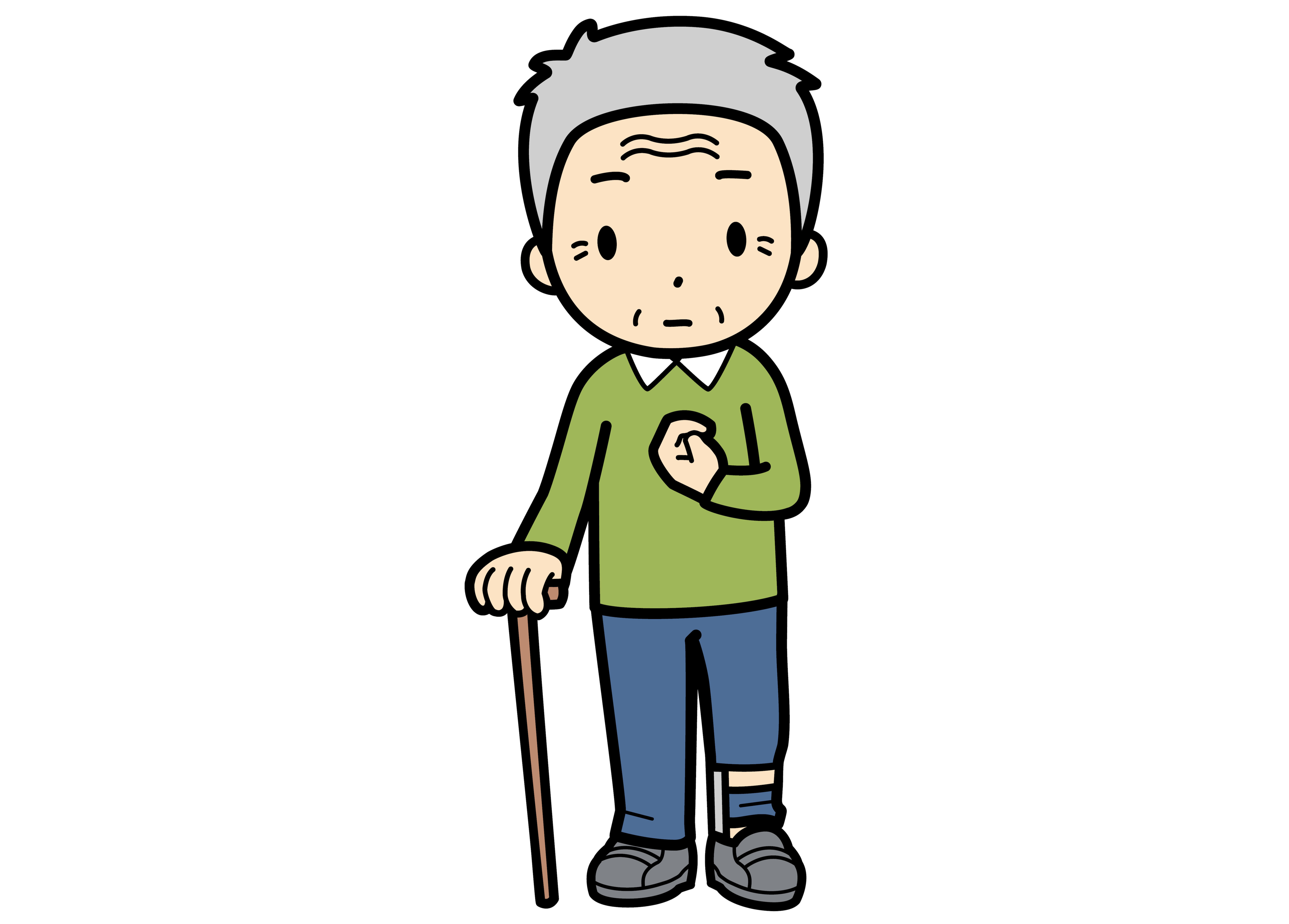
жӢҳзё®гҒҜдё»гҒ«гҖҒй–ўзҜҖгӮ’еӢ•гҒӢгҒҷж©ҹдјҡгҒҢжёӣгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰиө·гҒ“гӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
еҠ йҪўгҒ®еҪұйҹҝгӮ„гғ‘гғјгӮӯгғігӮҪгғіз—…зӯүгҒ®з—…ж°—гҖҒйә»з—әпјҲгҒҫгҒІпјүгҖҒз—ӣгҒҝгҖҒгӮҖгҒҸгҒҝгҖҒеҜқгҒҹгҒҚгӮҠгҒӘгҒ©гҒ®иҰҒеӣ гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒжҙ»еӢ•жҖ§гҒҢдҪҺдёӢгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒй–ўзҜҖгҒҢзЎ¬гҒҸгҒӘгӮҠгҖҒеҸҜеӢ•еҹҹгҒҢзӢӯгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгҒ—гҒҰгҖҢй–ўзҜҖгӮ’еӢ•гҒӢгҒӣгҒӘгҒ„гҖҚгҒҫгҒҹгҒҜгҖҢеӢ•гҒӢгҒ—гҒҹгҒҸгҒӘгҒ„гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶзҠ¶ж…ӢгҒҢз¶ҡгҒҸгҒЁгҖҒгҒ•гӮүгҒ«й–ўзҜҖеҸҜеӢ•еҹҹгҒҜзӢӯгҒҸгҒӘгӮҠгҖҒжӢҳзё®гҒҢйҖІиЎҢгҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
жӢҳзё®пјҲгҒ“гҒҶгҒ—гӮ…гҒҸпјүгӮұгӮўгҒ®гғқгӮӨгғігғҲ
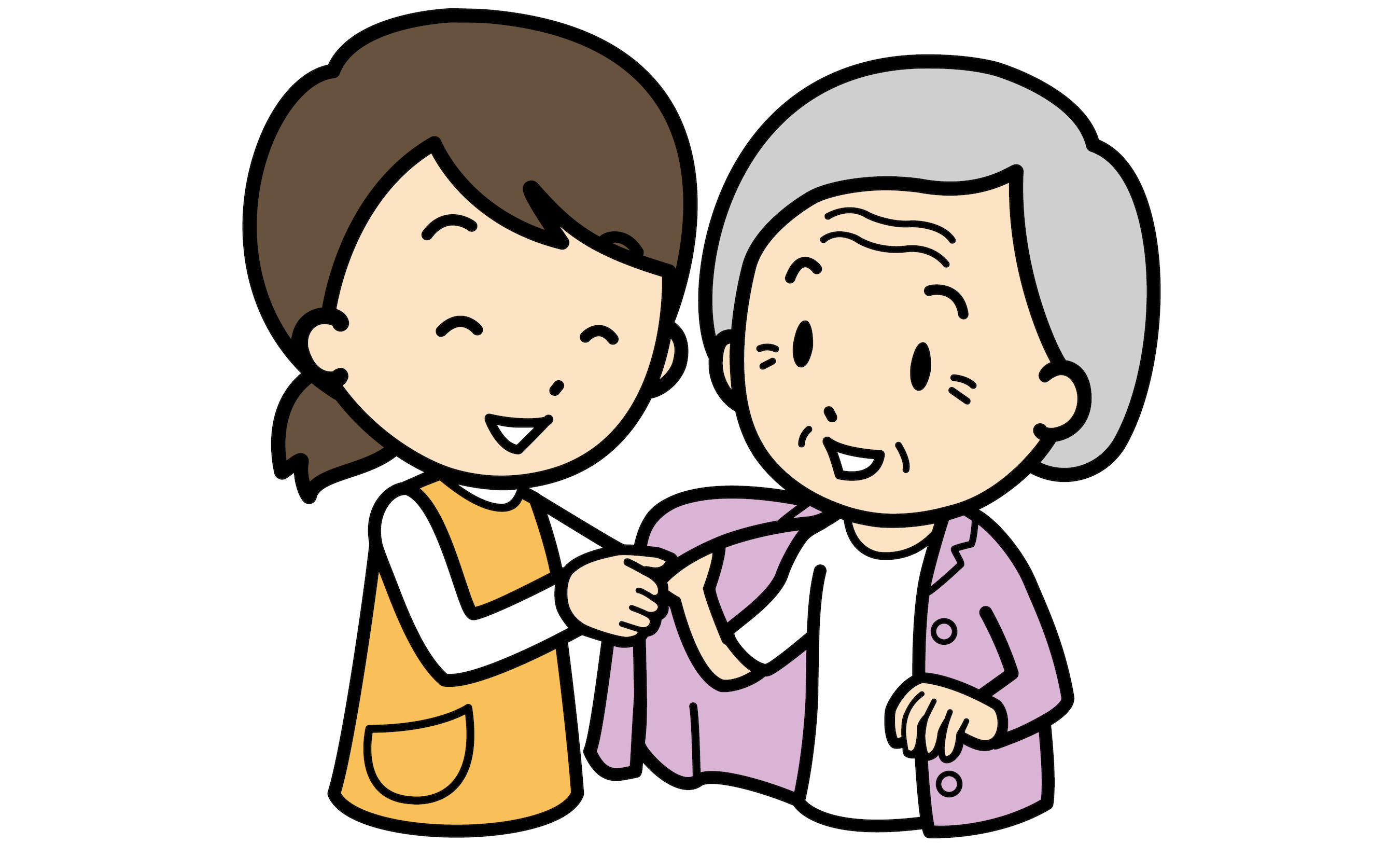
гӮҶгҒЈгҒҸгӮҠгҒЁд»ӢеҠ©гҒ—гҖҒз—ӣгҒҝгӮ’дёҺгҒҲгҒӘгҒ„
гӮўгӮӨгӮігғігӮҝгӮҜгғҲпјҲзӣ®гӮ’еҗҲгӮҸгҒӣгӮӢпјүгӮ’гҒЁгӮҠгҖҒи§ҰгӮҢгӮӢе ҙжүҖгҒЁж¬ЎгҒ«иЎҢгҒҶеӢ•дҪңпјҲдҫӢгҒҲгҒ°гҖҢи…•гӮ’еӨ–еҒҙгҒ«й–ӢгҒҚгҒҫгҒҷгҒӯгҖҚгҒӘгҒ©пјүгӮ’дјқгҒҲгҖҒгҒ“гҒҫгӮҒгҒ«еЈ°гӮ’гҒӢгҒ‘гҒӘгҒҢгӮүгҖҒгӮҶгҒЈгҒҸгӮҠдёҒеҜ§гҒ«д»ӢеҠ©гҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
д»ӢеҠ©иҖ…гҒ®жүӢгҒҢеҶ·гҒҹгҒ„гҒЁгҒҚгҒҜгҖҒжё©гӮҒгҒҰгҒӢгӮүи§ҰгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
жүӢгӮ„и¶ігӮ’еӢ•гҒӢгҒҷжҷӮгҒҜгҖҒдёҠгҒӢгӮүгҒӨгҒӢгӮҖгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸдёӢгҒӢгӮүж”ҜгҒҲгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гҖҒй–ўзҜҖгҒ«иҝ‘гҒ„йғЁеҲҶгӮ’жҢҒгҒЎгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒжүӢгҒ®гҒІгӮүгӮ„еүҚи…•е…ЁдҪ“гҒӘгҒ©гӮ’дҪҝгҒ„гҖҒжҺҘгҒҷгӮӢйқўгӮ’гҒ§гҒҚгӮӢгҒ гҒ‘еәғгҒҸгҒ—гҒҰж”ҜгҒҲгӮӢгҒЁе®үе®ҡж„ҹгҒҢеў—гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гғӘгғ©гғғгӮҜгӮ№гҒ§гҒҚгӮӢе§ҝеӢўгӮ’дҝқгҒӨ
жӢҳзё®гҒ®гҒӮгӮӢж–№гҒ®гӮұгӮўгҒ§гҒҜгҖҒйҒ©еҲҮгҒ§е®үжҘҪгҒӘе§ҝеӢўгӮ’дҝқгҒӨгҒ“гҒЁгҒҢйҮҚиҰҒгҒ§гҒҷгҖӮ
з—ӣгҒҝгӮ„дёҚе®үгҒӘгҒ©гӮ’ж„ҹгҒҳгӮӢгҒ“гҒЁгҒӘгҒҸгғӘгғ©гғғгӮҜгӮ№гҒ§гҒҚгӮӢиӮўдҪҚпјҲгҒ—гҒ„пјүгӮ’дҝқжҢҒгҒ—гҖҒиә«дҪ“гҒ«иІ жӢ…гҒҢгҒӢгҒӢгӮүгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гғқгӮӨгғігғҲгҒҜгҖҒжһ•гӮ„гӮҜгғғгӮ·гғ§гғігҒӘгҒ©гӮ’дҪҝгҒЈгҒҰгҖҒиә«дҪ“гҒЁгғҷгғғгғүгҒЁгҒ®гҒҷгҒҚй–“гӮ’жёӣгӮүгҒҷпјҲзӮ№гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸйқўгҒ§ж”ҜгҒҲгӮӢпјүгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгӮ·гғјгғ„гҒ®гҒ—гӮҸгӮ„жңҚгҒ®зё«гҒ„зӣ®гҒ«гӮӮж°—гӮ’гҒӨгҒ‘гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
еҗҢгҒҳе§ҝеӢўгӮ’й•·гҒҸз¶ҡгҒ‘гҒӘгҒ„
еҗҢгҒҳе§ҝеӢўгӮ’й•·жҷӮй–“з¶ҡгҒ‘гӮӢгҒЁгҖҒиә«дҪ“гҒ®дёҖйғЁеҲҶгҒ«ең§еҠӣгҒҢгҒӢгҒӢгӮҠгҖҒиә«дҪ“гҒҢгҒ“гӮҸгҒ°гҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
иӨҘзҳЎпјҲгҒҳгӮҮгҒҸгҒқгҒҶпјүгҒ®еҺҹеӣ гҒ«гӮӮгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒгӮҜгғғгӮ·гғ§гғігӮ„гӮЁгӮўгғһгғғгғҲгғ¬гӮ№зӯүгӮ’жҙ»з”ЁгҒ—гҒҰдҪ“ең§гӮ’еҲҶж•ЈгҒ—гҒҹгӮҠгҖҒдҪ“дҪҚеӨүжҸӣгӮ’иЎҢгҒЈгҒҹгӮҠгҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
в–јй–ўйҖЈиЁҳдәӢ
дәҲйҳІгғ»ж—©жңҹзҷәиҰӢгҒҢйҮҚиҰҒгҒӘеәҠгҒҡгӮҢпјҲиӨҘзҳЎгғ»гҒҳгӮҮгҒҸгҒқгҒҶпјүгҒ®дәҲйҳІжі•гҒЁеҜҫеҮҰжі•жӢҳзё®пјҲгҒ“гҒҶгҒ—гӮ…гҒҸпјүгҒ®дәҲйҳІ

жӢҳзё®гҒ®йҖІиЎҢгӮ’йҒ…гӮүгҒӣгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҖҒж—Ҙеёёз”ҹжҙ»еӢ•дҪңпјҲиө·еұ…еӢ•дҪңгғ»з§»д№—移еӢ•гғ»йЈҹдәӢгғ»жӣҙиЎЈгғ»жҺ’гҒӣгҒӨгғ»е…Ҙжөҙгғ»ж•ҙе®№пјүгҒ®дёӯгҒ§гҒӘгӮӢгҒ№гҒҸй–ўзҜҖгӮ’еӢ•гҒӢгҒҷгҒ“гҒЁгҒҢеӨ§еҲҮгҒ§гҒҷгҖӮ
еӢ•гҒӢгҒҷжҷӮгҒҜз„ЎзҗҶгӮ’гҒӣгҒҡгҖҒз—ӣгҒҝгӮ’ж„ҹгҒҳгҒӘгҒ„зЁӢеәҰгҒ«гӮҶгҒЈгҒҸгӮҠгҒЁеӢ•гҒӢгҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
иЎҖиЎҢдҝғйҖІгӮ„гғӘгғ©гғғгӮҜгӮ№еҠ№жһңгҒ®гҒӮгӮӢйғЁеҲҶжөҙгӮӮгҖҒжӢҳзё®гҒ®дәҲйҳІгғ»ж”№е–„гҒ«гҒӨгҒӘгҒҢгӮӢгҒЁгҒ„гӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
и¶іжөҙпјҲгҒқгҒҸгӮҲгҒҸпјүгӮ„жүӢжөҙпјҲгҒ—гӮ…гӮҲгҒҸпјүгӮ’иЎҢгҒҶжҷӮгҒҜгҖҒжүӢи¶ігӮ’жё©гӮҒгҒҰгҒӢгӮүгҖҒжӢҳзё®йғЁеҲҶгӮ’гӮҶгҒЈгҒҸгӮҠй–ӢгҒ„гҒҰжҙ—гҒ„гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
гҖҢгӮ·гғЈгғңгғігғ©гғғгғ”гғігӮ°гҖҚгӮ’еҸ–гӮҠе…ҘгӮҢгӮӢгҒЁгҖҒиІ жӢ…гӮ’и»ҪжёӣгҒ§гҒҚгӮӢе ҙеҗҲгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
в–јй–ўйҖЈиЁҳдәӢ
иЎҖиЎҢгӮ’иүҜгҒҸгҒ—гҒҰгғӘгғ©гғғгӮҜгӮ№еҠ№жһңгӮӮпјҒи¶іжөҙпјҲгҒқгҒҸгӮҲгҒҸпјүгҒ®еҠ№жһңгҒЁжүӢй ҶжүӢи»ҪгҒ«гғӘгғ•гғ¬гғғгӮ·гғҘпјҒгғһгғғгӮөгғјгӮёеҠ№жһңгӮӮгҒӮгӮӢжүӢжөҙпјҲгҒ—гӮ…гӮҲгҒҸпјүгҒ®жүӢй Ҷ
гҒ”иҮӘиә«гҒ§иә«дҪ“гӮ’еӢ•гҒӢгҒҷгҒ“гҒЁгҒҢеӣ°йӣЈгҒӘе ҙеҗҲгҒҜгҖҒйҖҡжүҖзі»гӮөгғјгғ“гӮ№пјҲйҖҡжүҖгғӘгғҸгғ“гғӘгғҶгғјгӮ·гғ§гғігӮ„йҖҡжүҖд»Ӣиӯ·пјүгҖҒиЁӘе•Ҹзі»гӮөгғјгғ“гӮ№пјҲиЁӘе•ҸгғӘгғҸгғ“гғӘгғҶгғјгӮ·гғ§гғігӮ„иЁӘе•ҸзңӢиӯ·гҖҒеҢ»зҷӮдҝқйҷәгҒ®иЁӘе•ҸгғһгғғгӮөгғјгӮёпјүгҒӘгҒ©гӮ’еҲ©з”ЁгҒ—гҖҒж©ҹиғҪиЁ“з·ҙгӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢгҒЁгӮҲгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
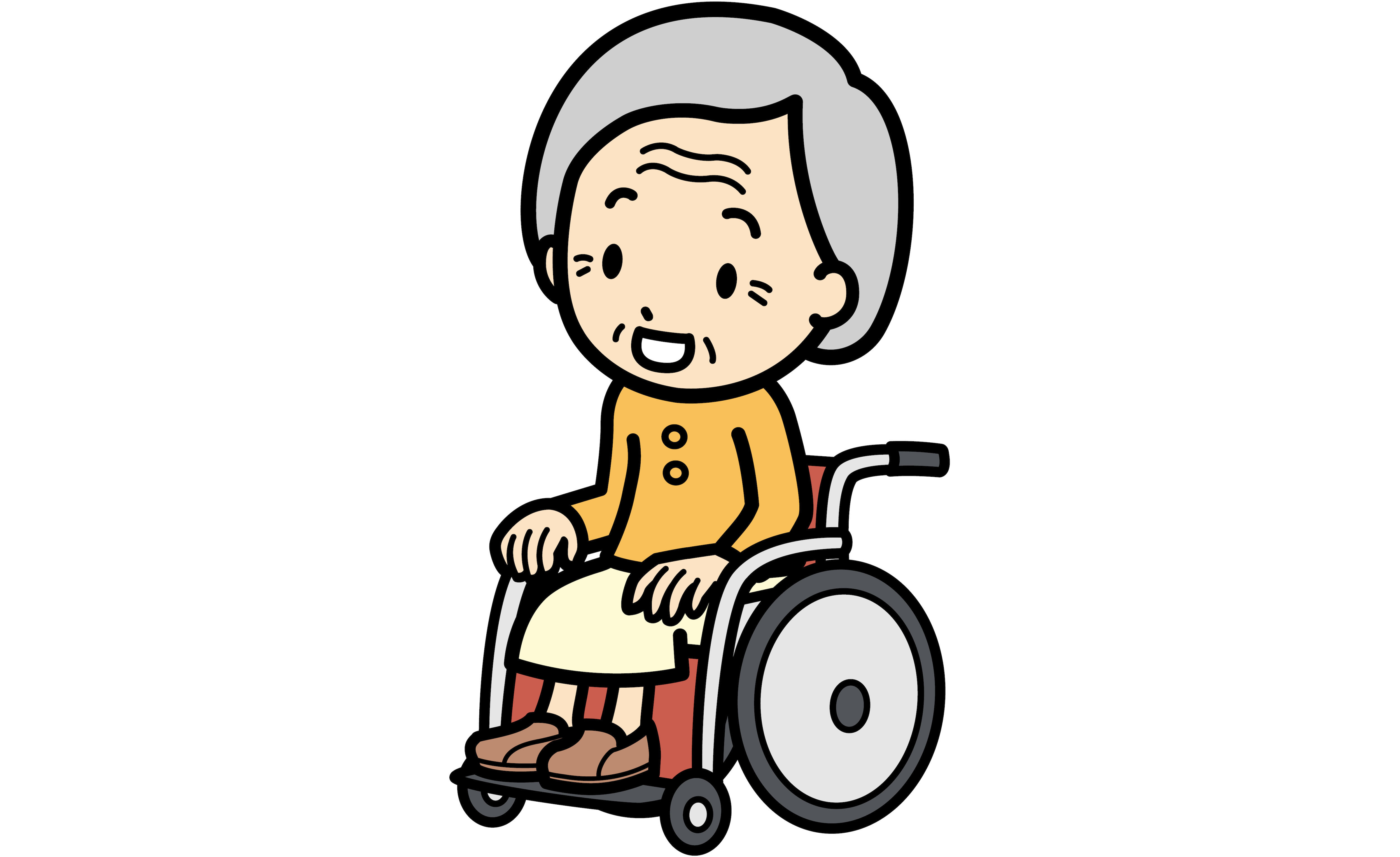
жӢҳзё®гҒ®гҒӮгӮӢж–№гҒ®еә§дҪҚгҒ®гғқгӮёгӮ·гғ§гғӢгғігӮ°
гҒ§гҒҚгӮӢгҒ гҒ‘йӣўеәҠгҒ—гҒҰжӯЈгҒ—гҒ„еә§дҪҚе§ҝеӢўгӮ’гҒЁгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒжӢҳзё®гӮ„е»ғз”ЁпјҲгҒҜгҒ„гӮҲгҒҶпјүз—ҮеҖҷзҫӨгҒ®дәҲйҳІгҒ«гҒӨгҒӘгҒҢгӮӢгҒЁгҒ„гӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒе§ҝеӢўгҒҢеҙ©гӮҢгҒҹгҒҫгҒҫеә§гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҖҒиә«дҪ“гҒ«жӮӘеҪұйҹҝгӮ’дёҺгҒҲгҒӢгҒӯгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
жӢҳзё®гҒ®гҒӮгӮӢж–№гҒҜгҖҒеә§гҒЈгҒҹгҒЁгҒҚгҒ«иә«дҪ“гҒҢжЁӘгӮ„еүҚгҒ«еӮҫгҒ„гҒҹгӮҠгҖҒгҒӯгҒҳгӮҢгҒҹгӮҠгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒеә§гӮҠж–№гҒ«е•ҸйЎҢгҒҢгҒӘгҒ„гҒӢзўәиӘҚгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеӨ§еҲҮгҒ§гҒҷгҖӮ
зҗҶжғізҡ„гҒӘеә§дҪҚе§ҝеӢў
жӯЈйқўгҒӢгӮүиҰӢгҒҹгҒЁгҒҚ
- гғ»е·ҰеҸігҒ®и¶ігҒҢеәҠпјҲи»ҠгҒ„гҒҷгҒ®е ҙеҗҲгҒҜгғ•гғғгғҲгӮөгғқгғјгғҲпјүгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢ
- гғ»и…•гҒҢж”ҜгҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢ
- гғ»йӘЁзӣӨгҖҒе·ҰеҸігҒ®гҒІгҒ–гҖҒе·ҰеҸігҒ®иӮ©гҒ®гғ©гӮӨгғігҒҢж°ҙе№ігҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢ
- гғ»пјҲи»ҠгҒ„гҒҷгҒ®е ҙеҗҲпјүгӮөгӮӨгғүгӮ¬гғјгғүгҒЁгҒ®гҒҷгҒҚй–“гҒҢе·ҰеҸігҒ§еҗҢгҒҳгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢ
жЁӘгҒӢгӮүиҰӢгҒҹгҒЁгҒҚ
- гғ»й ӯй ӮйғЁгҒӢгӮүйӘЁзӣӨгҒҢдёҖзӣҙз·ҡгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢ
- гғ»еӨӘгӮӮгӮӮгҒҢеә§йқўгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢ
- гғ»гҒІгҒ–гҒ®иЈҸгҒ«гҒҷгҒҚй–“гҒҢгҒӘгҒ„
зңҹдёҠгҒӢгӮүиҰӢгҒҹгҒЁгҒҚ
- гғ»иғҢгӮӮгҒҹгӮҢгҒЁгҒ®гҒҷгҒҚй–“гҒҢе·ҰеҸігҒ§еҗҢгҒҳгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢ
- гғ»е·ҰеҸігҒ®иӮ©гҒ®дҪҚзҪ®гҒҢеүҚеҫҢгҒ«гҒҡгӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„пјҲгҒӯгҒҳгӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„пјү
- гғ»е·ҰеҸігҒ®гҒІгҒ–гҒ®дҪҚзҪ®гҒҢеүҚеҫҢгҒ«гҒҡгӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„
вҖ»йҒ©еҲҮгҒӘйҒӢеӢ•гӮ„еә§гӮҠж–№гҖҒзҰҸзҘүз”Ёе…·гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜзҗҶеӯҰзҷӮжі•еЈ«гҒӘгҒ©гҒ®е°Ӯй–ҖиҒ·гҒ«зӣёи«ҮгҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
в–јй–ўйҖЈиЁҳдәӢ
第46еӣһпјҲ2019е№ҙпјү еӣҪйҡӣзҰҸзҘүж©ҹеҷЁеұ•гғ¬гғқгғјгғҲпјҲпј’пјүжҡ®гӮүгҒ—гӮ’гӮөгғқгғјгғҲгҒҷгӮӢзҰҸзҘү用具家ж—ҸгҒ®д»Ӣиӯ·гӮ’гҒҚгҒЈгҒӢгҒ‘гҒ«д»Ӣиӯ·зҰҸзҘүеЈ«гғ»зӨҫдјҡзҰҸзҘүдё»дәӢд»»з”ЁиіҮж јгӮ’еҸ–еҫ—гҖӮзҸҫеңЁгҒҜгғ©гӮӨгӮҝгғјгҖӮж—ҘгҖ…гҒ®жҡ®гӮүгҒ—гҒ«еҪ№з«ӢгҒӨиә«иҝ‘гҒӘжғ…е ұгӮ’гҒҠдјқгҒҲгҒҷгӮӢгҒ№гҒҸгҖҒд»Ӣиӯ·гғ»еҢ»зҷӮгғ»зҫҺе®№гғ»гӮ«гғ«гғҒгғЈгғјгҒӘгҒ©е№…еәғгҒ„гӮёгғЈгғігғ«гҒ®иЁҳдәӢгӮ’еҹ·зӯҶдёӯгҖӮ
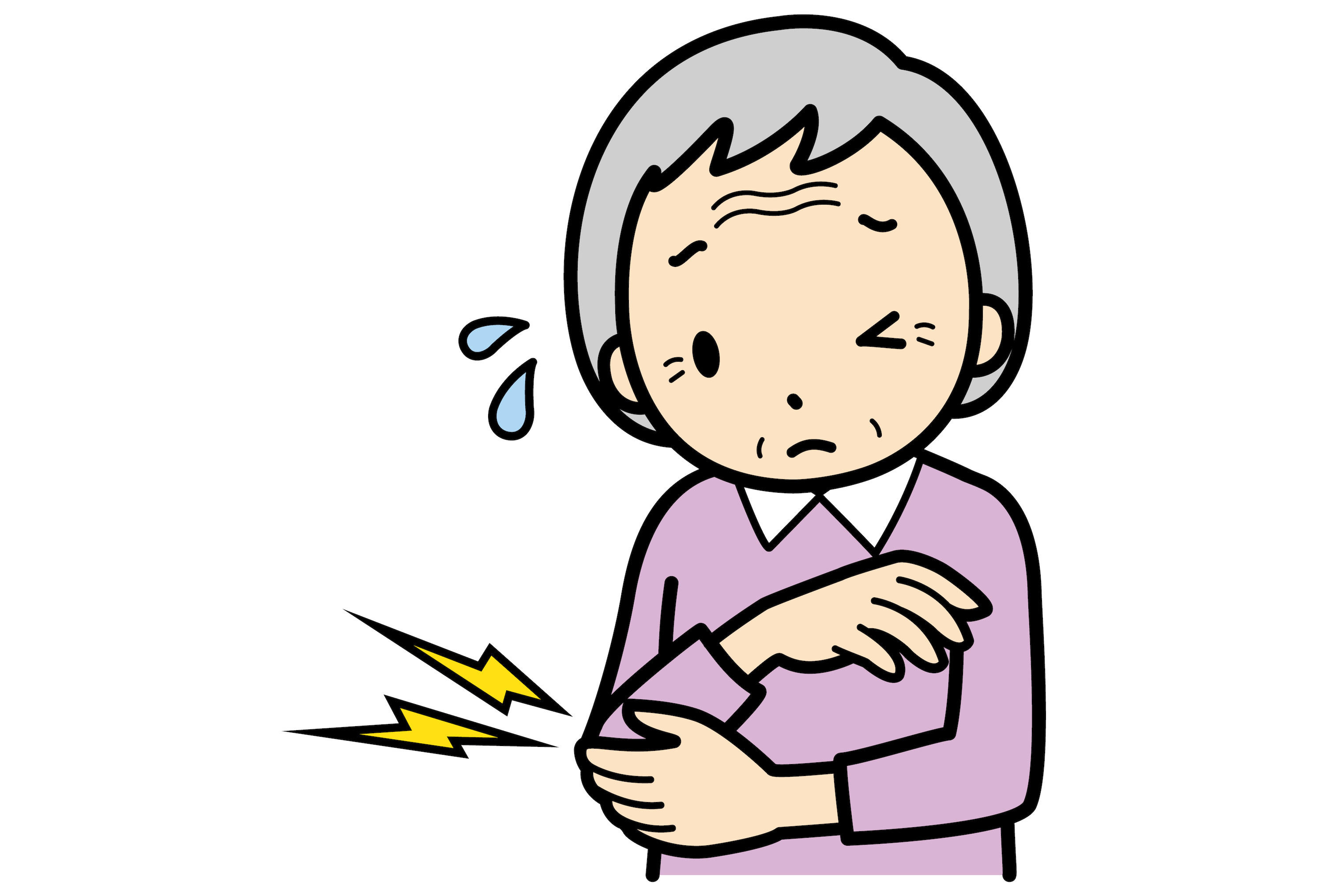
FacebookгғҡгғјгӮёгҒ§
жңҖж–°иЁҳдәӢй…ҚдҝЎпјҒпјҒ
 гғ¬гӮӘгғҸгӮҡгғ¬гӮ№21гӮҜгӮҷгғ«гғјгғ•гӮҡгҒ®д»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ’гӮҷгӮ№
гғ¬гӮӘгғҸгӮҡгғ¬гӮ№21гӮҜгӮҷгғ«гғјгғ•гӮҡгҒ®д»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ’гӮҷгӮ№