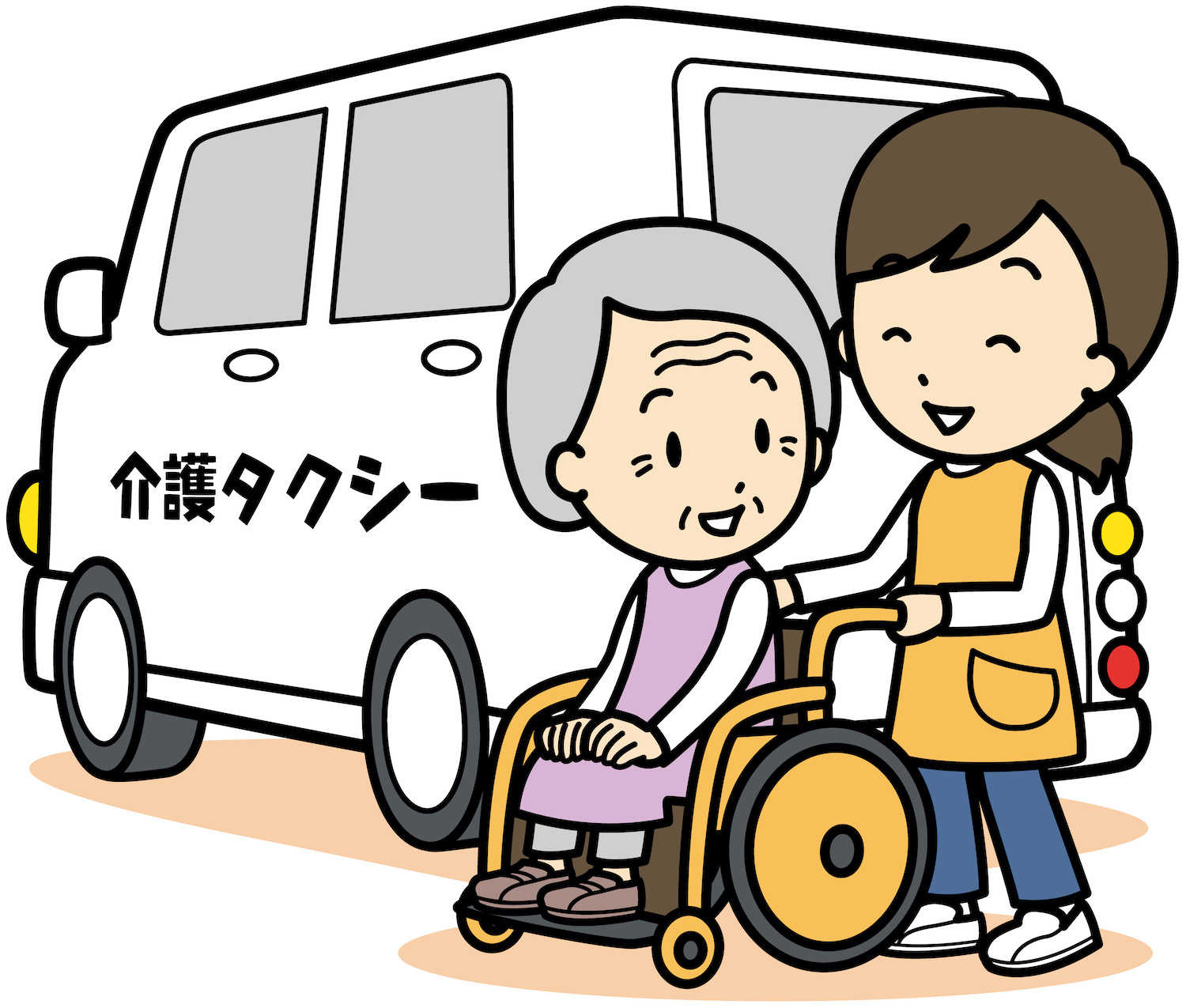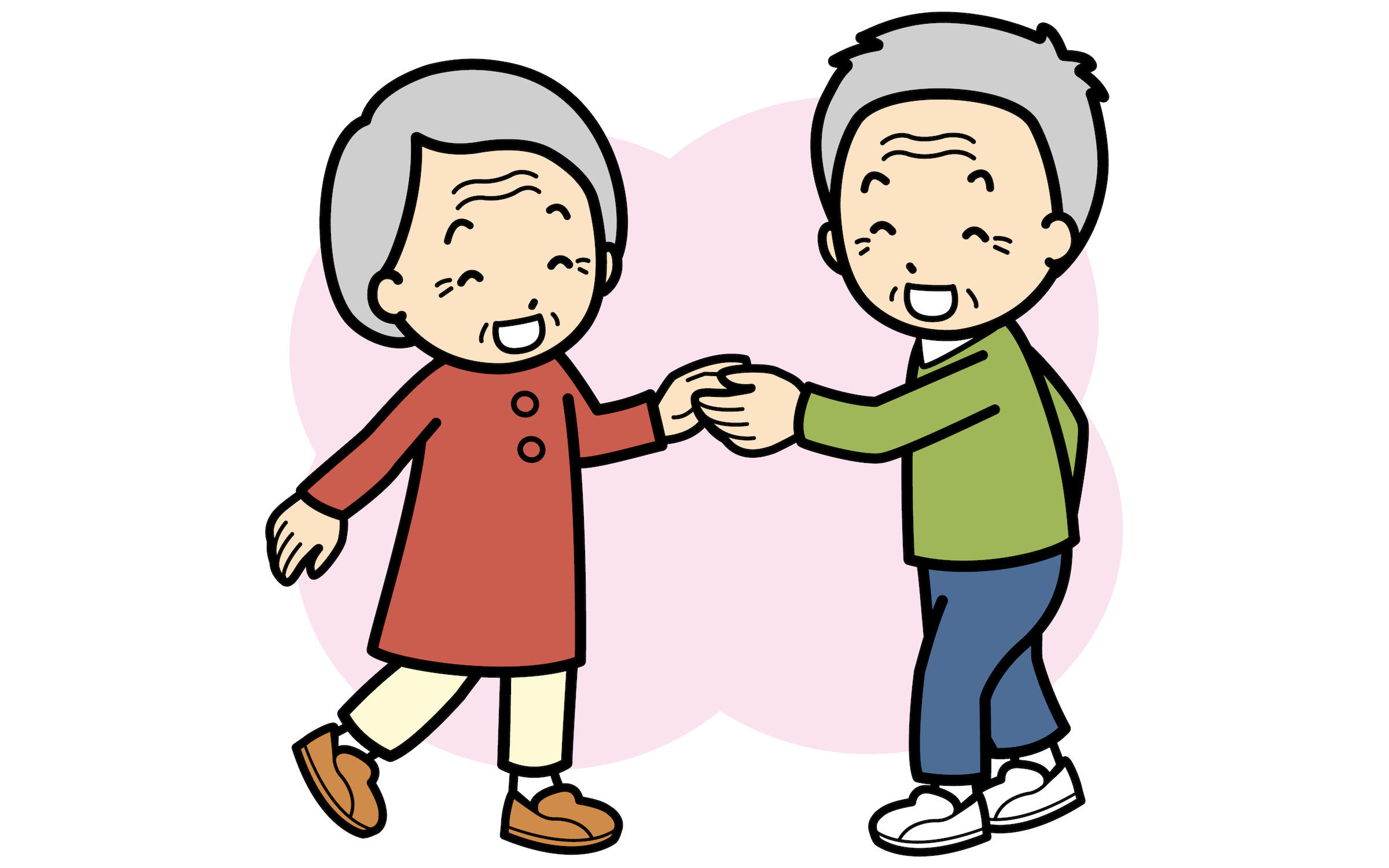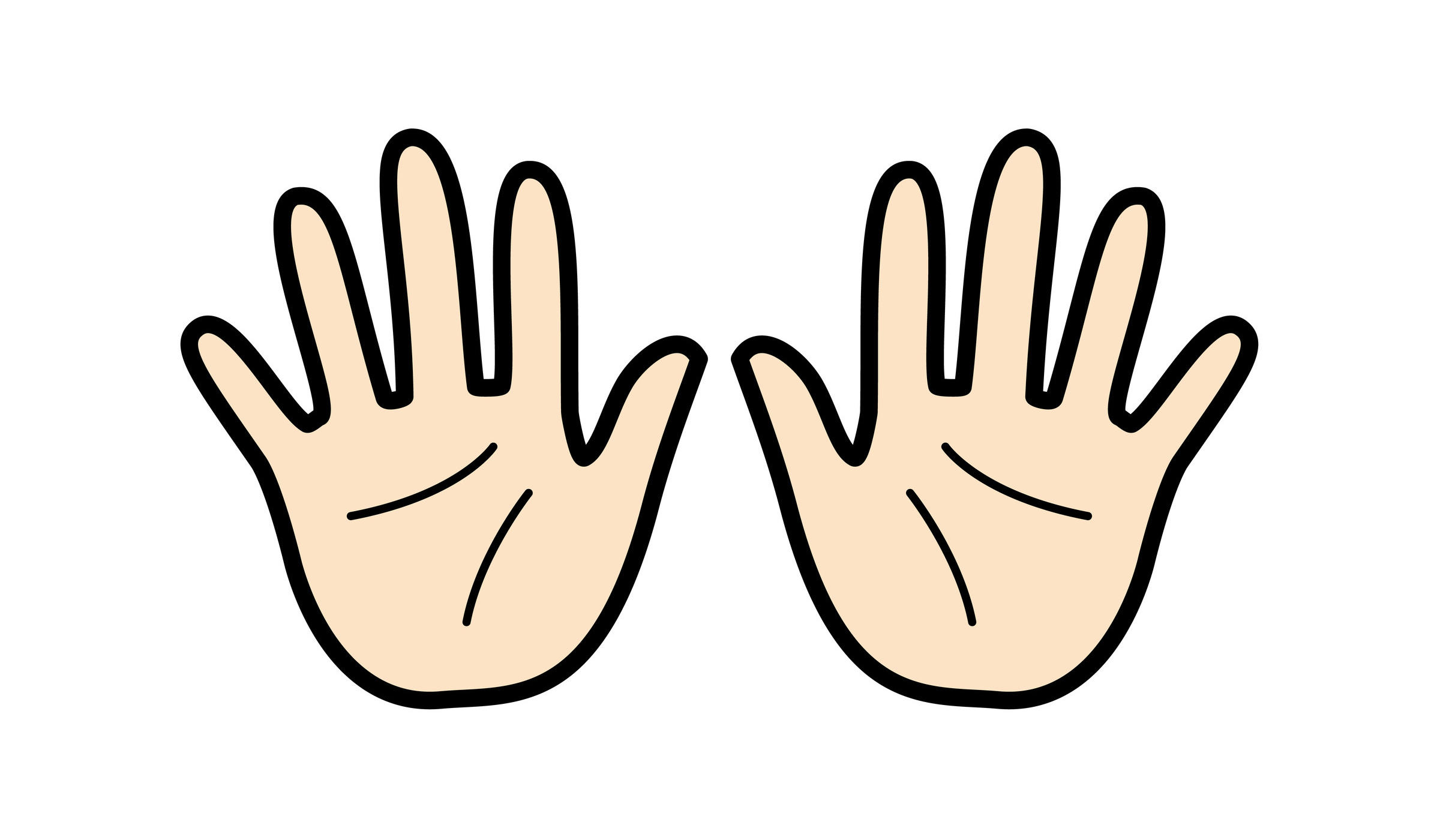С╗ІУГисЂ«СЙ┐тѕЕтИќсЃѕсЃЃсЃЌсЂИТѕ╗сѓІ
сЂЋсЂЙсЂќсЂЙсЂфті╣ТъюсЂїТюЪтЙЁсЂДсЂЇсѓІсЂћжФўжйбУђЁсЂ«сЃгсѓ»сЃфсѓесЃ╝сѓисЃДсЃ│
тцџсЂЈсЂ«С╗ІУГиТќйУеГсЂДсЂ»сђЂсЂЋсЂЙсЂќсЂЙсЂфуе«жАъсЂ«сЃгсѓ»сЃфсѓесЃ╝сѓисЃДсЃ│сѓњтЈќсѓітЁЦсѓїсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓсЂДсЂ»сђЂСйЋсЂ«сЂЪсѓЂсЂФсЃгсѓ»сЃфсѓесЃ╝сѓисЃДсЃ│сѓњУАїсЂБсЂдсЂёсѓІсЂ«сЂДсЂЌсѓЄсЂєсЂІ№╝ЪтЁиСйЊуџёсЂфТ┤╗тІЋтєЁт«╣сѓњСЙІсЂФсђЂсЃгсѓ»сЃфсѓесЃ╝сѓисЃДсЃ│сѓњУАїсЂєТёЈуЙЕсѓњУђЃсЂѕсЂдсЂёсЂЇсЂЙсЂЌсѓЄсЂєсђѓсЂЙсЂЪсђЂсЂћУЄфт«ЁсЂДсѓѓтЈќсѓітЁЦсѓїсѓЅсѓїсѓІу░АтЇўсЂфсЃгсѓ»сЃфсѓесЃ╝сѓисЃДсЃ│сѓѓсЂћу┤╣С╗ІсЂЌсЂЙсЂЎсђѓ
сЃгсѓ»сЃфсѓесЃ╝сѓисЃДсЃ│сЂ«уЏ«уџёсЂеті╣Тъю
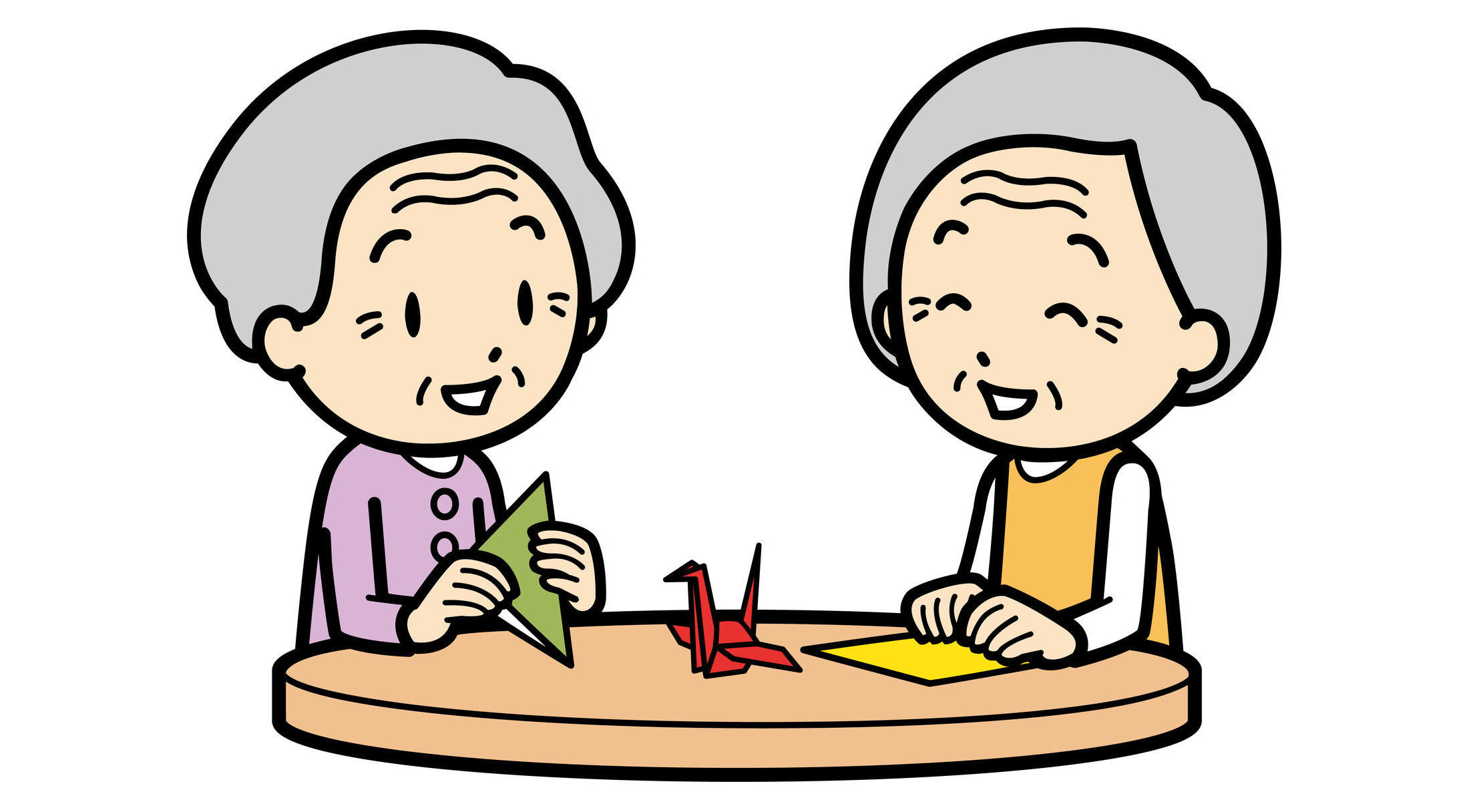
сЃгсѓ»сЃфсѓесЃ╝сѓисЃДсЃ│сЂ«ті╣ТъюсЂФсЂ»СИ╗сЂФС╗ЦСИІсЂ«3уѓ╣сЂїсЂѓсѓісЂЙсЂЎсђѓ
У║ФСйЊТЕЪУЃйсЂ«уХГТїЂсЃ╗тљЉСИі
С║║сЂ»Уф░сЂЌсѓѓсђЂТГ│сѓњжЄЇсЂГсЂдсЂЈсѓІсЂеУ║ФСйЊсЂ«ТЕЪУЃйсЂїСйјСИІсЂЌсЂдсЂёсЂЇсЂЙсЂЎсђѓсђїУђЂтїќуЈЙУ▒АсђЇсЂДсЂЎсђѓсЂесЂЊсѓЇсЂїсђЂУ┐Љт╣┤сђЂуГІУѓЅсЂФуЮђуЏ«сЂЌсђЂуГІтіЏсѓњжФўсѓЂсѓІсЂесђЂТћ╣тќёсЂїУдІУЙ╝сѓЂсЂфсЂёсЂесЂЋсѓїсЂдсЂёсЂЪУђЂтїќуЈЙУ▒АсЂ«жђ▓УАїсѓњТћ╣тќёсЂДсЂЇсѓІсЂЊсЂесЂїсѓЈсЂІсЂБсЂдсЂЇсЂЙсЂЌсЂЪсђѓ
сђїжФўжйбсЂасЂІсѓЅсђЇсђїуЌЁТ░ЌсЂасЂІсѓЅсђЇсЂежЂІтІЋсЂФТХѕТЦхуџёсЂфсЂћжФўжйбУђЁсЂ»тцџсЂёсЂДсЂЎсЂїсђЂтІЋсЂІсЂфсЂёсЂДсЂёсѓІсЂесђЂжфесѓёуГІУѓЅсЂ»сЂЕсѓЊсЂЕсѓЊу┤░сЂЈсЂфсЂБсЂдсђЂжќбу»ђсѓѓтЏ║сЂЈсЂфсѓісђЂсѓѕсѓіжЂІтІЋжЄЈсЂїТИЏсЂБсЂдсЂЌсЂЙсЂєсЂесЂёсЂєТѓфтЙфуњ░сЂФжЎЦсЂБсЂдсЂЌсЂЙсЂёсЂЙсЂЎсђѓ
жЂЕт║дсЂфжЂІтІЋсѓњтЈќсѓітЁЦсѓїсѓІсЂесЂёсЂєТёЈтЉ│сЂДсђЂсЃгсѓ»сЃфсѓесЃ╝сѓисЃДсЃ│сЂФсЂ»тцДсЂЇсЂфті╣ТъюсЂїсЂѓсѓісЂЙсЂЎсђѓ
Уё│сЂ«Т┤╗ТђДтїќ
ТЅІтЁѕсѓёжаГсѓњСй┐сЂєсЃгсѓ»сЃфсѓесЃ╝сѓисЃДсЃ│сЂДУё│сѓњТ┤╗ТђДтїќсЂЎсѓІсЂЊсЂесЂДсђЂУфЇуЪЦуЌЄсЂ«С║ѕжў▓сѓёуЌЄуіХсЂ«жђ▓УАїсѓњжЂЁсѓЅсЂЏсѓІті╣ТъюсЂїТюЪтЙЁсЂДсЂЇсЂЙсЂЎсђѓ
сЂЙсЂЪсђЂтЇўУф┐сЂФсЂфсѓісЂїсЂАсЂфТЌЦтИИућЪТ┤╗сЂ«СИГсЂДсђЂсђїжЮъТЌЦтИИсђЇсЂфсЃгсѓ»сЃфсѓесЃ╝сѓисЃДсЃ│сЂ«ТЎѓжќЊсѓњсѓѓсЂцсЂЊсЂесЂФсѓѕсѓісђЂТЌЦсђЁсЂ«ућЪТ┤╗сЂФтѕ║Т┐ђсѓњСИјсЂѕсђЂт┐ЃсѓњТўјсѓІсЂЈсЂЎсѓІті╣ТъюсѓѓсЂѓсѓісЂЙсЂЎсђѓ
тцџсЂЈсЂ«С╗ІУГиТќйУеГсЂДсЂ»сђЂт╣┤СИГУАїС║ІсѓётГБу»ђТёЪсѓњтЈќсѓітЁЦсѓїсЂЪсѓісђЂсЃЌсЃГсѓ░сЃЕсЃасѓњсѓбсЃгсЃ│сѓИсЂЌсЂЪсѓісЂЌсЂдсђЂсЃъсЃ│сЃЇсЃфтїќсЂЌсЂфсЂёсѓѕсЂєсЂФсЂЌсЂЙсЂЎсђѓ
сѓ│сЃЪсЃЦсЃІсѓ▒сЃ╝сѓисЃДсЃ│сЂ«С┐Ѓжђ▓
сЂћжФўжйбУђЁсЂіСИђС║║сЂісЂ▓сЂесѓісЂ«сђїтђІсђЇсѓњтцДтѕЄсЂФсЂЌсЂфсЂїсѓЅсђЂС╗ќсЂ«С║║сЂесЂ«сѓ│сЃЪсЃЦсЃІсѓ▒сЃ╝сѓисЃДсЃ│сѓњућЪсЂ┐сђЂС┐Ѓжђ▓сЂЎсѓІсЂ«сЂїсЃгсѓ»сЃфсѓесЃ╝сѓисЃДсЃ│сЂДсЂЎсђѓ
ТЎѓсЂФсЂ»сЃюсЃЕсЃ│сЃєсѓБсѓбсЂ«Тќ╣сЂФтЇћтіЏсЂЌсЂдсѓѓсѓЅсЂБсЂЪсѓісђЂтю░тЪЪсЂ«жЏєсЂЙсѓісЂФтЈѓтіасЂЌсЂЪсѓісЂЎсѓІсЂ«сѓѓсѓѕсЂёсЂДсЂЌсѓЄсЂєсђѓ
сЂЪсЂЈсЂЋсѓЊсЂ«С║║сЂїжЏєсЂЙсѓІсЂеТ┤╗Т░ЌсЂїтЄ║сЂдсђЂсЂёсЂцсѓѓсЂежЂЋсЂєжЏ░тЏ▓Т░ЌсѓњтѕєсЂІсЂАтљѕсЂєсЂЊсЂесЂїсЂДсЂЇсЂЙсЂЎсђѓсЂЮсЂЌсЂдсђЂТќ░сЂЌсЂётЄ║С╝џсЂёсѓёсЂцсЂфсЂїсѓісЂїућЪсЂЙсѓїсЂЙсЂЎсђѓ
С║║сЂесЂ«сЂхсѓїсЂѓсЂёсЂ»сђЂсЂћжФўжйбУђЁсЂФсЂесЂБсЂдућЪсЂЇсЂїсЂёсѓњтЅхтЄ║сЂЎсѓІсЂЇсЂБсЂІсЂЉсЂесЂфсѓісђЂУфЇуЪЦуЌЄС║ѕжў▓сЂФсѓѓсЂцсЂфсЂїсѓІсЂесЂёсѓЈсѓїсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓ
сЃгсѓ»сЃфсѓесЃ╝сѓисЃДсЃ│сЂ«уе«жАъ

У║ФСйЊсѓњтІЋсЂІсЂЎсЃгсѓ»сЃфсѓесЃ╝сѓисЃДсЃ│
СИ╗сЂФУ║ФСйЊсѓњСй┐сЂБсЂЪсѓ▓сЃ╝сЃасѓёсЃђсЃ│сѓ╣сЂфсЂЕсЂїсЂѓсѓісЂЙсЂЎсђѓ
сЂіСИђС║║сЂісЂ▓сЂесѓісЂ«У║ФСйЊТЕЪУЃйсЂФтљѕсѓЈсЂЏсЂЪсѓёсѓіТќ╣сЂДжЂЕт║дсЂфжЂІтІЋсѓњУАїсЂєсЂЊсЂесЂДсђЂУђЂтїќуЈЙУ▒АсЂ«жђ▓УАїсЂ«Тћ╣тќёсђЂт»ЮсЂЪсЂЇсѓісЂ«жў▓ТГбсЂфсЂЕсЂ«ті╣ТъюсЂїТюЪтЙЁсЂДсЂЇсЂЙсЂЎсђѓ
СЙІсЂѕсЂ░сЃ╗сЃ╗сЃ╗
сЃ╗жбеУѕ╣сЃљсЃгсЃ╝
№╝њсЂцсЂ«сЃЂсЃ╝сЃасЂФтѕєсЂІсѓїсЂдтљЉсЂІсЂётљѕсЂБсЂдт║ДсѓісЂЙсЂЎсђѓ1сЂцсЂ«жбеУѕ╣сѓњсЂєсЂАсѓЈсЂДсЂѓсЂісЂјсђЂуЏИТЅІсЃЂсЃ╝сЃасЂ«т║ісЂФжбеУѕ╣сѓњУљйсЂесЂЌсЂЪсЃЂсЃ╝сЃасЂ«тІЮсЂАсЂДсЂЎсђѓ
сЃ╗у┤Ўсѓ│сЃЃсЃЌсЃюсЃ╝сЃФсѓисЃЦсЃ╝сЃѕ
Т«хсЃюсЃ╝сЃФу«▒сЂ«СИГсЂФСИдсЂ╣сЂЪу┤Ўсѓ│сЃЃсЃЌсЂФсђЂсЃЂсЃ╝сЃасЂћсЂесЂФУЅ▓сѓњтѕєсЂЉсђЂсЂЮсЂ«УЅ▓сЂ«сЃюсЃ╝сЃФуГЅсѓњТіЋсЂњтЁЦсѓїсѓІсѓ▓сЃ╝сЃасЂДсЂЎсђѓсЂЪсЂЈсЂЋсѓЊтЁЦсЂБсЂЪсЃЂсЃ╝сЃасЂїтІЮсЂАсЂДсЂЎсђѓ
сЃ╗тюњУіИсѓёт«Хт║ГУЈютюњ
тГБу»ђсЂ«Уі▒сђЁсђЂжЄјУЈюсђЂТъюуЅЕсЂфсЂЕсѓњУѓ▓сЂдсЂдсЂёсЂЇсЂЙсЂЎсђѓт▒ІтцќсЂДТЌЦтЁЅсѓњТх┤сЂ│сЂфсЂїсѓЅТ░ЌТїЂсЂАсѓѕсЂЈУ║ФСйЊсѓњтІЋсЂІсЂЌсђЂТцЇуЅЕсЂФУДдсѓїсЂдУѓ▓сЂдсѓІтќюсЂ│сѓётЈјуЕФсЂЎсѓІТЦйсЂЌсЂЋсѓњт«ЪТёЪсЂЌсЂдсЂёсЂЪсЂасЂЇсЂЙсЂЎсђѓ
ТЅІтЁѕсѓњСй┐сЂБсЂЪсЃгсѓ»сЃфсѓесЃ╝сѓисЃДсЃ│
т«ЪжџЏсЂФТЅІсѓњтІЋсЂІсЂЌсЂдсЂёсЂЪсЂасЂЈсђЂт░ЈуЅЕсЂЦсЂЈсѓісѓёУф┐уљєсЃгсѓ»сЂфсЂЕсЂїсЂѓсѓісЂЙсЂЎсђѓ
ТЅІтЁѕсЂ«жЂІтІЋсЂ«сЂ╗сЂІсђЂсђїсЂцсЂЈсѓІтќюсЂ│сђЇсђїсЂДсЂЇсѓІтќюсЂ│сђЇсЂесЂёсЂБсЂЪжЂћТѕљТёЪсЂФсѓѓсЂцсЂфсЂїсѓісЂЙсЂЎсђѓ
СЙІсЂѕсЂ░сЃ╗сЃ╗сЃ╗
сЃ╗Тіўсѓіу┤Ў
сЂћжФўжйбУђЁсЂФсѓѓсЂфсЂўсЂ┐Ти▒сЂёсђїТіўсѓіу┤ЎсђЇсѓњСй┐сЂБсЂдсђЂт«џуЋфсЂ«жХ┤сѓётІЋуЅЕсђЂтГБу»ђсЂФжќбжђБсЂЌсЂЪсѓѓсЂ«сЂфсЂЕсѓњсЂцсЂЈсѓісЂЙсЂЎсђѓсЂцсЂЈсЂБсЂЪСйютЊЂсЂ»сђЂТќйУеГтєЁсѓёсЂіжЃет▒ІсЂФжБЙсЂБсЂдсЂёсЂЪсЂасЂЉсЂЙсЂЎсђѓ
сЃ╗сЂіУЈЊтГљсѓёУ╗йжБЪсЂЦсЂЈсѓі
тњїУЈЊтГљсѓёТ┤ІУЈЊтГљсђЂсЃЉсЃ│сђЂсЂЪсЂЊуё╝сЂЇсЂфсЂЕсѓњТЅІСйюсѓісЂЌсђЂсЂісѓёсЂцсЂесЂЌсЂдсЂёсЂЪсЂасЂЇсЂЙсЂЎсђѓ

жаГсѓњСй┐сЂєсЃгсѓ»сЃфсѓесЃ╝сѓисЃДсЃ│
сѓ»сѓцсѓ║сѓ▓сЃ╝сЃасѓёсЃЉсѓ║сЃФсѓ▓сЃ╝сЃасЂфсЂЕсЂїсЂѓсѓісЂЙсЂЎсђѓ
УфЇуЪЦуЌЄС║ѕжў▓сѓёсђЂУфЇуЪЦуЌЄсЂ«жђ▓УАїсѓњжЂЁсѓЅсЂЏсѓІті╣ТъюсЂїТюЪтЙЁсЂДсЂЇсЂЙсЂЎсђѓ
СЙІсЂѕсЂ░сЃ╗сЃ╗сЃ╗
сЃ╗жаГТќЄтГЌсЂЋсЂїсЂЌ
50жЪ│сЂїТЏИсЂІсѓїсЂЪсѓФсЃ╝сЃЅсЂІсѓЅ№╝ЉТъџт╝ЋсЂЇсђЂсЂЮсЂЊсЂФТЏИсЂІсѓїсЂЪТќЄтГЌсЂІсѓЅтДІсЂЙсѓІУеђУЉЅсѓњТЏИсЂЇтЄ║сЂЎсѓ▓сЃ╝сЃасЂДсЂЎсђѓсѓѓсЂБсЂесѓѓтцџсЂЈУеђУЉЅсѓњТЏИсЂЇтЄ║сЂЌсЂЪсЃЂсЃ╝сЃасЂ«тІЮсЂАсЂДсЂЎсђѓ
сЃ╗жђєТќЄтГЌсѓ▓сЃ╝сЃа
СИіСИІтидтЈ│сѓњсЂЋсЂІсЂЋсЂЙсЂФсЂЌсЂЪсЂ▓сѓЅсЂїсЂфсЂДТЏИсЂІсѓїсЂЪсѓФсЃ╝сЃЅсѓњУдІсЂдсђЂТЏИсЂІсѓїсЂЪтЇўУфъсѓњтйЊсЂдсѓІсѓ▓сЃ╝сЃасЂДсЂЎсђѓ
сЃ╗сЂісЂесЂфсЂ«тГдТаА
сѓ╣сѓ┐сЃЃсЃЋсЂїтЁѕућЪсЂесЂфсѓісђЂтЏйУфъсђЂу«ЌТЋ░сђЂуљєуДЉсђЂуцЙС╝џсђЂСйЊУѓ▓уГЅсЂ«сѓѕсЂєсЂФТјѕТЦГсЂФтЈѓтіасЂЌсђЂТ»јТюѕтцЅсѓЈсѓІТЋЎуДЉТЏИсѓњСй┐ућесЂЌсЂдсђїтЏъТЃ│Т│ЋсђЇуГЅсѓњућесЂёсЂЪ"тГдТаА"сЂ«сѓѕсЂєсЂфсЃгсѓ»сЃфсѓесЃ╝сѓисЃДсЃ│сЂДсЂЎсђѓсЂіСИђС║║сЂісЂ▓сЂесѓісЂ«сЃџсЃ╝сѓ╣сЂДсђЂТЦйсЂЌсЂ┐сЂфсЂїсѓЅтГдсЂХсЂЊсЂесЂїсЂДсЂЇсЂЙсЂЎсђѓ
т▓љжўюуюїсђїсЂѓсЂџсЂ┐УІЉтцДтъБ№╝ѕсЃЄсѓцсѓхсЃ╝сЃЊсѓ╣сЃ╗сѓисЃДсЃ╝сЃѕсѓ╣сЃєсѓц№╝ЅсђЇсЂ«сЃЄсѓцсѓхсЃ╝сЃЊсѓ╣сЂДсЂ»сђЂсђїсЂісЂесЂфсЂ«тГдТаАсђЇсѓњт«ЪТќйсЂЌсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓ
сЂѓсЂџсЂ┐УІЉтцДтъБсЂ«1ТЌЦуёАТќЎСйЊжеЊсЂ»сЂЊсЂАсѓЅсЂІсѓЅ
тЈБУЁћТЕЪУЃйсѓњжФўсѓЂсѓІсЃгсѓ»сЃфсѓесЃ╝сѓисЃДсЃ│
сѓ╣сЃѕсЃГсЃ╝сѓёсђЂТўћТЄљсЂІсЂЌсЂёсЂісѓѓсЂАсѓЃсЂ«у┤ЎсЂхсЂєсЂЏсѓЊсђЂти╗сЂЇугЏ№╝ѕТІГсЂЇТѕ╗сЂЌ№╝ЅсЂфсЂЕсѓњСй┐сЂєсЃгсѓ»сЃфсѓесЃ╝сѓисЃДсЃ│сЂ»сђЂсЂітЈБсЂ«ТЕЪУЃйтљЉСИісЂФсЂцсЂфсЂїсѓісЂЙсЂЎсђѓ
СЙІсЂѕсЂ░сЃ╗сЃ╗сЃ╗
сЃ╗сѓ╣сЃѕсЃГсЃ╝сЂДудЈугЉсЂё
у┤ЎсЂФжАћсЂ«У╝фжЃГсѓњТЈЈсЂЇсЂЙсЂЎсђѓтјџу┤ЎсЂФуЏ«сЃ╗ж╝╗сЃ╗тЈБсЂфсЂЕсЂ«сЃЉсЃ╝сЃёсѓњТЈЈсЂёсЂдтѕЄсѓіТіюсЂёсЂдсЂісЂЇсЂЙсЂЎсђѓтЦйсЂЇсЂфсЃЉсЃ╝сЃёсѓњсѓ╣сЃѕсЃГсЃ╝сЂДтљИсЂёСИісЂњсЂдтІЋсЂІсЂЌсђЂжАћсЂ«У╝фжЃГсЂ«СИісЂФуй«сЂёсЂдсЂёсЂЇсЂЙсЂЎсђѓ
Рќ╝жќбжђБУеўС║І
ТЦйсЂЌсЂЈтЈќсѓіухёсѓЊсЂДУфцтџЦ№╝ѕсЂћсЂѕсѓЊ№╝Ѕсѓњжў▓сЂљ№╝ЂсЂіжБЪС║ІтЅЇсЂ«ті╣ТъюуџёсЂфсЂітЈБсЂ«СйЊТЊЇ
УфЇуЪЦуЌЄсЂ«Тќ╣сѓѓТЦйсЂЌсѓЂсѓІсЃгсѓ»сЃфсѓесЃ╝сѓисЃДсЃ│
сЂћУЄфУ║ФсЂ«сЃџсЃ╝сѓ╣сЂДтЈќсѓіухёсѓЂсѓІсЃгсѓ»сЃфсѓесЃ╝сѓисЃДсЃ│сЂфсЂЕсЂ»сђЂУфЇуЪЦуЌЄсЂ«Тќ╣сѓѓТЦйсЂЌсѓЂсЂЙсЂЎсђѓ
СЙІсЂѕсЂ░сЃ╗сЃ╗сЃ╗
сЃ╗сѓГсЃБсЃЃсЃЌСИдсЂ╣
сЃџсЃЃсЃѕсЃюсЃѕсЃФ№╝ѕ350ml№╝ЅсѓњсЃєсЃ╝сЃЌсЂД3тђІсЂцсЂфсЂёсЂасѓѓсЂ«сѓњ3сЂцућеТёЈсЂЌсЂЙсЂЎсђѓсЃџсЃЃсЃѕсЃюсЃѕсЃФсЂ«сѓГсЃБсЃЃсЃЌсЂФсђЂ3УЅ▓№╝ѕУхцсЃ╗жЮњсЃ╗ж╗ё№╝ЅсЂ«сѓисЃ╝сЃФсѓњУ▓╝сѓісЂЙсЂЎсђѓСИђжЮбсѓњтѕЄсѓітЈќсЂБсЂЪуЅЏС╣│сЃЉсЃЃсѓ»3сЂцсѓњсЂцсЂфсЂёсЂДтюЪтЈ░сѓњсЂцсЂЈсѓісђЂсЃџсЃЃсЃѕсЃюсЃѕсЃФсѓњтЁЦсѓїсЂЙсЂЎсђѓС╗ІУГиУђЁсЂїсЃЏсЃ»сѓцсЃѕсЃюсЃ╝сЃЅсЂФсѓГсЃБсЃЃсЃЌсЂ«СИдсЂ╣Тќ╣сѓњТЈЈсЂЇсђЂсЂћжФўжйбУђЁсЂ»сѓГсЃБсЃЃсЃЌсѓњТїЄуц║сЂЕсЂісѓісЂФсЂЌсѓЂсЂдсЂёсЂЇсЂЙсЂЎсђѓ
уцЙС╝џУ▓буї«сЂ«сЃгсѓ»сЃфсѓесЃ╝сѓисЃДсЃ│
СИ╗сЂФтю░тЪЪсЂесЂ«С║цТхЂсѓёсђЂТЅІСйюсѓісЂ«тЊЂсѓњсЃљсѓХсЃ╝сЂДУ▓ЕтБ▓сЂЎсѓІсЂЊсЂесЂфсЂЕсЂїсЂѓсѓісЂЙсЂЎсђѓ
сЂДсЂЇсЂфсЂёсЂЊсЂесЂїтбЌсЂѕсЂдсЂЈсѓІсЂесђЂсђїУЄфтѕєсЂ»СйЋсѓѓсЂДсЂЇсЂфсЂёсЃ╗сЃ╗сЃ╗сђЇсЂеУђЃсЂѕсЂдсЂЌсЂЙсЂєсЂћжФўжйбУђЁсѓѓсЂёсѓЅсЂБсЂЌсѓЃсЂёсЂЙсЂЎсђѓсђїсЂДсЂЇсѓІсЂЊсЂесѓњсЂ┐сЂцсЂЉсЂдсѓѓсѓЅсЂєсђЇсђїсѓёсѓісЂїсЂёсѓњТёЪсЂўсЂдсѓѓсѓЅсЂєсђЇсѓѕсЂєсЂФсЂЎсѓІсЂесђЂУЄфти▒Уѓ»т«џТёЪсѓњжФўсѓЂсѓІсЂЊсЂесЂФсЂцсЂфсЂїсѓісЂЙсЂЎсђѓ
СЙІсЂѕсЂ░сЃ╗сЃ╗сЃ╗
сЃ╗уЋ░СИќС╗БС║цТхЂ
ТюђУ┐ЉсЂДсЂ»сђЂсЂћжФўжйбУђЁсЂетГљсЂЕсѓѓсЂ«УДдсѓїтљѕсЂёсѓњуЏ«уџёсЂФсђЂтюњтЁљсЂесЂћжФўжйбУђЁсЂїжќбсѓЈсѓІсѓцсЃЎсЃ│сЃѕсѓњУАїсЂБсЂдсЂёсѓІТќйУеГсѓѓтбЌсЂѕсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓсЂћжФўжйбУђЁсЂїтГљсЂЕсѓѓсЂЪсЂАсЂФТЄљсЂІсЂЌсЂёжЂісЂ│сѓњТЋЎсЂѕсЂдсЂѓсЂњсЂЪсѓісђЂтГљсЂЕсѓѓсЂЪсЂАсЂїтѕЮсѓЂсЂдУЂъсЂЈсѓѕсЂєсЂфТўћУЕ▒сѓњсЂЌсЂЪсѓісЂЌсЂдсђЂсЂіС║њсЂёсЂФТЦйсЂЌсЂёТЎѓжќЊсѓњжЂјсЂћсЂЌсЂЙсЂЎсђѓ
ТгАсЂ«сЃџсЃ╝сѓИ№йюсЃгсѓ»сЃфсѓесЃ╝сѓисЃДсЃ│сЂ«сЃЮсѓцсЃ│сЃѕсђђсђђ
уцЙС╝џудЈуЦЅтБФУ│ЄТа╝С┐ЮТюЅсЂ«сЃЕсѓцсѓ┐сЃ╝сђѓсђїС╗ІУГисђЇсѓњСИГт┐ЃсЂесЂЌсЂЪудЈуЦЅтѕєжЄјсЂДсђЂтЪиуГєТ┤╗тІЋсѓњуХџсЂЉсЂдсЂёсѓІсђѓ
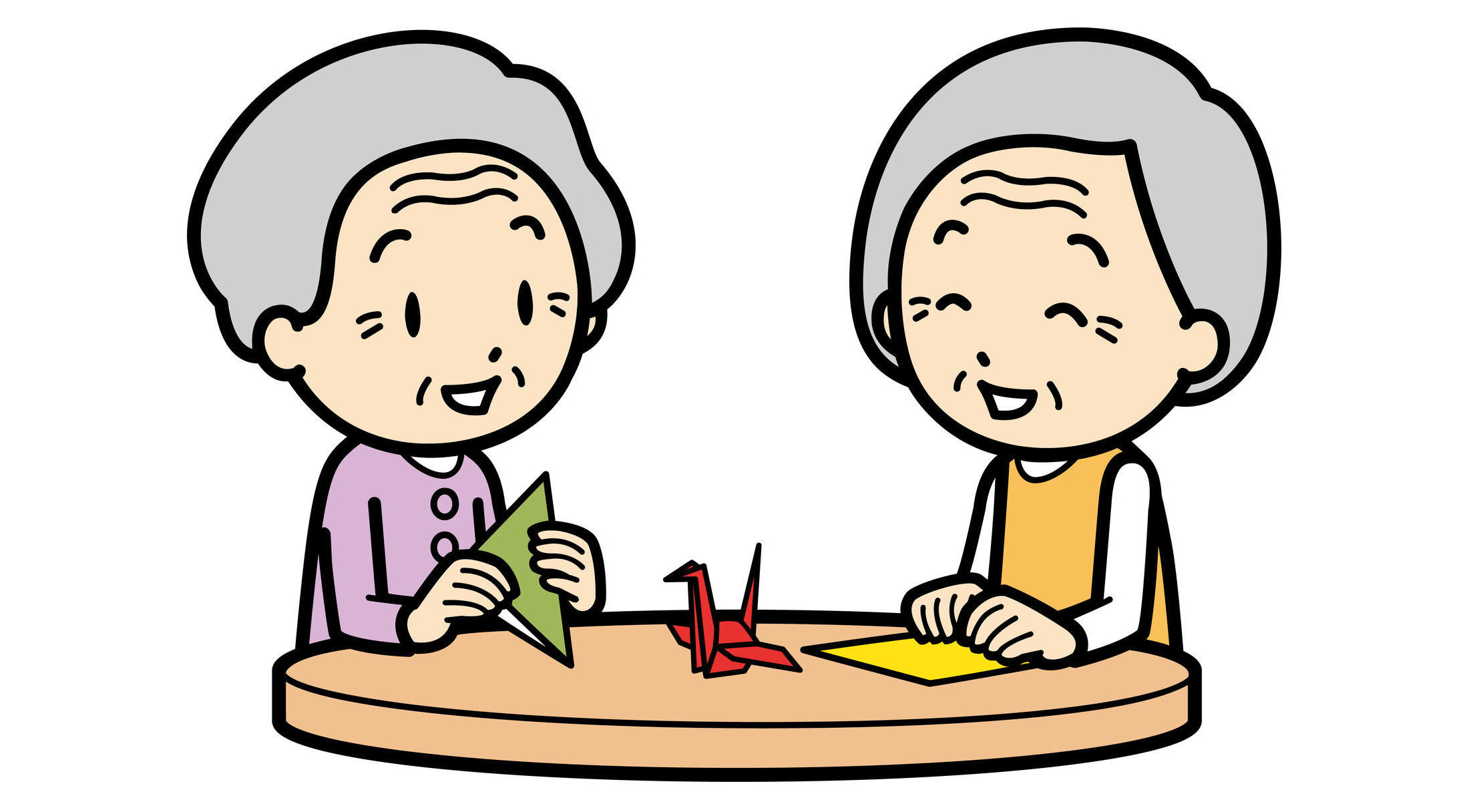
FacebookсЃџсЃ╝сѓИсЂД
ТюђТќ░УеўС║ІжЁЇС┐А№╝Ђ№╝Ђ
 сЃгсѓфсЃЈсѓџсЃгсѓ╣21сѓ»сѓЎсЃФсЃ╝сЃЋсѓџсЂ«С╗ІУГисѓхсЃ╝сЃњсѓЎсѓ╣
сЃгсѓфсЃЈсѓџсЃгсѓ╣21сѓ»сѓЎсЃФсЃ╝сЃЋсѓџсЂ«С╗ІУГисѓхсЃ╝сЃњсѓЎсѓ╣