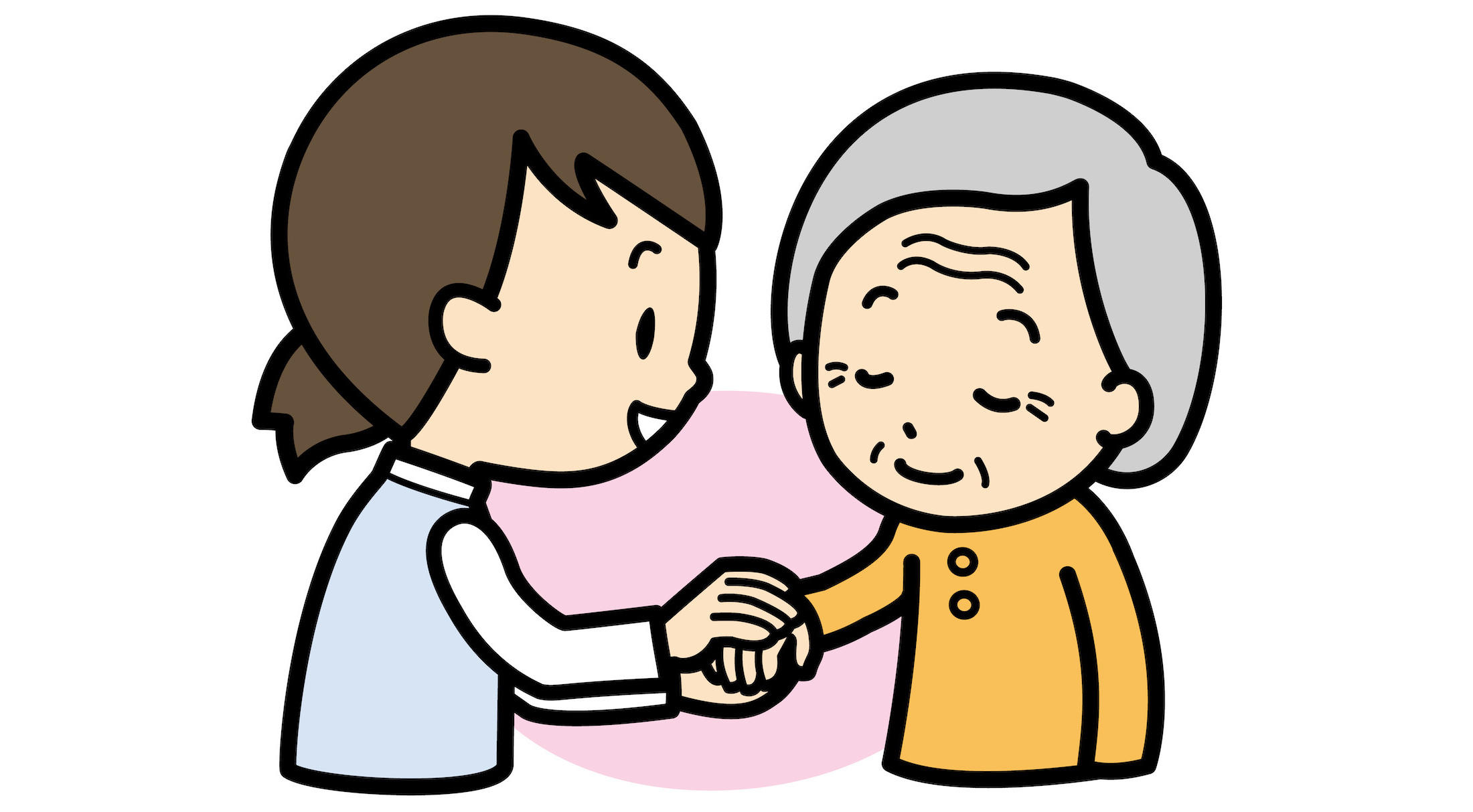д»Ӣиӯ·гҒ®дҫҝеҲ©её–гғҲгғғгғ—гҒёжҲ»гӮӢ
гҖҢиӘҚзҹҘз—ҮгғҗгғӘгӮўгғ•гғӘгғјгҖҚгҒЁгҒҜпјҹиӘ°гӮӮгҒҢжҡ®гӮүгҒ—гӮ„гҒҷгҒ„зӨҫдјҡгӮ’гӮҒгҒ–гҒ—гҒҰ
гҖҢиӘҚзҹҘз—ҮгғҗгғӘгӮўгғ•гғӘгғјгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶиЁҖи‘үгӮ’иҖігҒ«гҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒҜгҒӮгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖӮиӘҚзҹҘз—ҮгҒ®ж–№гҒЁгҒ”家ж—ҸгҒҢе®үеҝғгҒ—гҒҰжҡ®гӮүгҒ—з¶ҡгҒ‘гӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҖҒдә’гҒ„гҒ«ж”ҜгҒҲеҗҲгҒҶең°еҹҹгҒҘгҒҸгӮҠгӮ’йҖІгӮҒгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮд»ҠеӣһгҒҜгҖҒиӘҚзҹҘз—ҮгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгӮӮе°ҠеҺігҒЁеёҢжңӣгӮ’гӮӮгҒЈгҒҰз”ҹжҙ»гҒ§гҒҚгӮӢзӨҫдјҡгӮ’гӮҒгҒ–гҒҷгҖҢиӘҚзҹҘз—ҮгғҗгғӘгӮўгғ•гғӘгғјгҖҚгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҠдјқгҒҲгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҢиӘҚзҹҘз—ҮгғҗгғӘгӮўгғ•гғӘгғјгҖҚгҒЁгҒҜ

иӘҚзҹҘз—ҮгҒҜгҖҒиӘ°гҒ§гӮӮгҒӢгҒӢгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒ®гҒӮгӮӢиә«иҝ‘гҒӘз—…ж°—гҒ§гҒҷгҖӮ
2025е№ҙгҒ«гҒҜ65жӯід»ҘдёҠгҒ®гҒ”й«ҳйҪўиҖ…гҒ®зҙ„5дәәгҒ«1дәәгҒҢиӘҚзҹҘз—ҮгҒ«гҒӘгӮӢгҒЁжҺЁиЁҲгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒеғҚгҒҚзӣӣгӮҠгҒ®е№ҙд»ЈгҒ§гӮӮгҖҢиӢҘе№ҙжҖ§иӘҚзҹҘз—ҮгҖҚгҒ«гҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
иӘҚзҹҘз—ҮгҒ®ж–№гҒ®еӨҡгҒҸгҒҜгҖҒдёҚе®үгӮ„еӣ°йӣЈгӮ’жҠұгҒҲгҒӘгҒҢгӮүжҡ®гӮүгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгӮҢгҒҫгҒ§гҒ§гҒҚгҒҹгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгӮҠгҖҒгӮігғҹгғҘгғӢгӮұгғјгӮ·гғ§гғігҒҢйӣЈгҒ—гҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгӮҠгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҖҒеӨ–еҮәгӮ„дәӨжөҒгӮ’жҺ§гҒҲгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶж–№гӮӮгҒ„гӮүгҒЈгҒ—гӮғгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒиӘҚзҹҘз—ҮгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒӢгӮүгҒЁгҒ„гҒЈгҒҰдҪ•гӮӮгҒ§гҒҚгҒӘгҒҸгҒӘгӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒ—гҖҒгҖҢгҒқгҒ®дәәгӮүгҒ—гҒ•гҖҚгҒҢеӨұгӮҸгӮҢгӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
е‘ЁеӣІгҒ®зҗҶи§ЈгӮ„й…Қж…®гҖҒгҒЎгӮҮгҒЈгҒЁгҒ—гҒҹжүӢеҠ©гҒ‘гҒҢгҒӮгӮҢгҒ°гҖҒиҮӘеҲҶгӮүгҒ—гҒ„з”ҹжҙ»гӮ’з¶ҡгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҸҜиғҪгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгҒ“гҒ§жұӮгӮҒгӮүгӮҢгӮӢгҒ®гҒҢгҖҒиӘҚзҹҘз—ҮгҒ®ж–№гӮ’еҗ«гӮҒгҒҹгҖҢе…ұз”ҹгҖҚгҒ®зӨҫдјҡгҒҘгҒҸгӮҠгҒ§гҒҷгҖӮ
иӘҚзҹҘз—ҮгҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгӮӮгҒӘгҒҸгҒҰгӮӮе°ҠеҺігҒЁеёҢжңӣгӮ’гӮӮгҒЈгҒҰе…ұгҒ«з”ҹгҒҚгҒҰгҒ„гҒ‘гӮӢзӨҫдјҡгҒ®е®ҹзҸҫгӮ’зӣ®жҢҮгҒ—гҒҰгҖҒгҖҢж—Ҙжң¬иӘҚзҹҘз—Үе®ҳж°‘еҚ”иӯ°дјҡгҖҚгҒҜгҖҒз”ҹжҙ»гҒ®гҒӮгӮүгӮҶгӮӢе ҙйқўгҒ§йҡңеЈҒпјҲгғҗгғӘгӮўпјүгӮ’жёӣгӮүгҒ—гҒҰгҒ„гҒҸгҖҢиӘҚзҹҘз—ҮгғҗгғӘгӮўгғ•гғӘгғјгҖҚгҒ®еҸ–гӮҠзө„гҒҝгӮ’йҖІгӮҒгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
й–ўйҖЈиЁҳдәӢ
ж—©жңҹзҷәиҰӢгғ»еҜҫеҝңгҒҢйҮҚиҰҒпјҒ65жӯіжңӘжәҖгҒ®дәәгҒҢзҷәз—ҮгҒҷгӮӢгҖҢиӢҘе№ҙжҖ§иӘҚзҹҘз—ҮгҖҚ
гҖҢе…ұз”ҹгҖҚгҒЁгҖҢдәҲйҳІгҖҚгӮ’дёЎијӘгҒЁгҒҷгӮӢгҖҢиӘҚзҹҘз—Үж–Ҫзӯ–жҺЁйҖІеӨ§з¶ұгҖҚгҒ®5гҒӨгҒ®жҹұ
гҖҢж—Ҙжң¬иӘҚзҹҘз—Үе®ҳж°‘еҚ”иӯ°дјҡгҖҚгҒЁгҒҜ
иЎҢж”ҝгҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒзөҢжёҲеӣЈдҪ“гҖҒеҢ»зҷӮгғ»зҰҸзҘүеӣЈдҪ“гҖҒеӯҰдјҡгҒӘгҒ©гҒӢгӮүзҙ„100еӣЈдҪ“гҒҢеҸӮз”»гҒ—гҖҒ2019пјҲе№іжҲҗ31пјүе№ҙ4жңҲгҒ«гҖҢж—Ҙжң¬иӘҚзҹҘз—Үе®ҳж°‘еҚ”иӯ°дјҡгҖҚгҒҢиЁӯз«ӢгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
иӘҚзҹҘз—ҮгғҗгғӘгӮўгғ•гғӘгғјгӮ’жҺЁйҖІгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒиӘҚзҹҘз—ҮгҒ®ж–№гҒЁжҺҘгҒҷгӮӢж©ҹдјҡгҒ®еӨҡгҒ„жҘӯзЁ®гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢжҺҘйҒҮгҒ®жүӢеј•гҒҚгҒ®дҪңжҲҗгғ»е‘ЁзҹҘгӮ„гҖҒгҖҢиӘҚзҹҘз—ҮгғҗгғӘгӮўгғ•гғӘгғје®ЈиЁҖгҖҚеҲ¶еәҰгҒ®йҒӢз”ЁгӮ’иЎҢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҢиӘҚзҹҘз—ҮгғҗгғӘгӮўгғ•гғӘгғје®ЈиЁҖгҖҚгҒЁгҒҜ

еҮәе…ёпјҡеҺҡз”ҹеҠҙеғҚзңҒгғӣгғјгғ гғҡгғјгӮё
гҖҢиӘҚзҹҘз—ҮгғҗгғӘгӮўгғ•гғӘгғје®ЈиЁҖгҖҚгҒҜгҖҒиӘҚзҹҘз—ҮгҒ®ж–№гҒЁгҒ”家ж—ҸгҒ«е®үеҝғгҒ—гҒҰеә—иҲ—гӮ„гӮөгғјгғ“гӮ№гғ»е•Ҷе“ҒгӮ’еҲ©з”ЁгҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒҶгҒҹгӮҒгҒ®зӨҫдјҡжҙ»еӢ•гҒ§гҒҷгҖӮ ж—Ҙжң¬иӘҚзҹҘз—Үе®ҳж°‘еҚ”иӯ°дјҡгҒҢйҖІгӮҒгӮӢгҖҢиӘҚзҹҘз—ҮгғҗгғӘгӮўгғ•гғӘгғјгҖҚгҒ®еҸ–гӮҠзө„гҒҝгҒ®гҒІгҒЁгҒӨгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒ2022пјҲд»Өе’Ң4пјүе№ҙгҒӢгӮүе§ӢгҒҫгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
дјҒжҘӯгӮ„еӣЈдҪ“зӯүгҒҜгҖҒз”іи«Ӣгғ»зҷ»йҢІгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒиҮӘгӮүWEBдёҠгҒ§гҖҢиӘҚзҹҘз—ҮгғҗгғӘгӮўгғ•гғӘгғје®ЈиЁҖдјҒжҘӯгҖҚгҒЁгҒ—гҒҰе®ЈиЁҖгӮ’иЎҢгҒҶгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
еҜҫиұЎгҒЁгҒӘгӮӢзө„з№”
дјҒжҘӯгғ»еӣЈдҪ“гҒӘгҒ©
иҒ·зЁ®гӮ„иҰҸжЁЎгҒҜе•ҸгӮҸгӮҢгҒҡгҖҒе…ЁзӨҫдёҖжӢ¬гҒ§гӮӮжӢ зӮ№пјҲеә—иҲ—гҖҒж”ҜзӨҫгғ»ж”ҜйғЁгҒӘгҒ©пјүгҒ гҒ‘гҒ§гӮӮз”іи«Ӣгғ»зҷ»йҢІгҒҢеҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖӮ
зҷ»йҢІгҒҷгӮӢгҒЁгҖҢиӘҚзҹҘз—ҮгғҗгғӘгӮўгғ•гғӘгғје®ЈиЁҖгҖҚгҒ®гғӯгӮҙгғһгғјгӮҜгҒҢд»ҳдёҺгҒ•гӮҢгҖҒеҸӮеҠ дјҒжҘӯгғ»еӣЈдҪ“гҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’иЎЁзӨәгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
е®ЈиЁҖеҹәжә–
з”іи«ӢгҒ«гҒҜпј”й …зӣ®гҒ®е®ЈиЁҖеҹәжә–гҒҢжұӮгӮҒгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
|
в‘ зӨҫеҶ…гҒ®гҖҢдәәжқҗиӮІжҲҗгҖҚ в‘Ў иЎҢж”ҝгҖҒд»–жҘӯзЁ®гҒӘгҒ©гҒЁгҒ®гҖҢең°еҹҹйҖЈжҗәгҖҚ в‘ў иӘҚзҹҘз—ҮгӮ’гӮөгғқгғјгғҲгҒҷгӮӢгҖҢзӨҫеҶ…еҲ¶еәҰгҖҚ в‘Ј гҒҠе®ўгҒ•гҒҫгҒҢеҲ©з”ЁгҒ—гӮ„гҒҷгҒ„гҖҢз’°еўғж•ҙеӮҷгҖҚ |
иӘҚзҹҘз—ҮгғҗгғӘгӮўгғ•гғӘгғјгҒ®еҸ–гӮҠзө„гҒҝ

иӘҚзҹҘз—ҮгҒ®ж–№гӮ„гҒ”家ж—ҸгҒ®жҡ®гӮүгҒ—гӮ’зӨҫдјҡе…ЁдҪ“гҒ§ж”ҜгҒҲгҒҰгҒ„гҒ‘гӮӢгӮҲгҒҶгҖҒеӨҡгҒҸгҒ®дјҒжҘӯгӮ„еӣЈдҪ“гҒҢгҖҢиӘҚзҹҘз—ҮгғҗгғӘгӮўгғ•гғӘгғје®ЈиЁҖгҖҚгҒ«еҸ–гӮҠзө„гӮ“гҒ§гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒ“гҒ“гҒӢгӮүгҒҜжҘӯзЁ®еҲҘгҒ®еҸ–гӮҠзө„гҒҝдәӢдҫӢгӮ’гҒ„гҒҸгҒӨгҒӢгҒ”зҙ№д»ӢгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
е°ҸеЈІжҘӯ
ж ӘејҸдјҡзӨҫгӮӨгғҲгғјгғЁгғјгӮ«е ӮгҒ§гҒҜгҖҒиӘҚзҹҘз—ҮгӮөгғқгғјгӮҝгғјгҒ®йӨҠжҲҗгҖҒең°еҹҹгҒ®иҰӢе®ҲгӮҠгғҚгғғгғҲгғҜгғјгӮҜгҒёгҒ®еҸӮз”»гҖҒеҫ“жҘӯе“Ўеҗ‘гҒ‘д»Ӣиӯ·гӮ»гғҹгғҠгғјгҒ®е®ҹж–ҪгҒӘгҒ©гҒ«еҸ–гӮҠзө„гӮ“гҒ§гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒеә—иҲ—гҒ§гҒҜгҖҢгҒҠиІ·гҒ„зү©д»ӢеҠ©гӮөгғјгғ“гӮ№гҖҚгӮ’жҸҗдҫӣгҒ—гҖҒгӮҶгҒЈгҒҸгӮҠгҒҠдјҡиЁҲгҒ§гҒҚгӮӢгҖҢгҒҠгӮӮгҒ„гӮ„гӮҠе„Әе…Ҳгғ¬гӮёгҖҚгӮӮиЁӯзҪ®гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
йҮ‘иһҚжҘӯ
ж ӘејҸдјҡзӨҫдёүдә•дҪҸеҸӢйҠҖиЎҢгҒ§гҒҜгҖҒиӘҚзҹҘз—ҮгҒ®еҹәжң¬з—ҮзҠ¶гӮ„еҝңеҜҫгҒ®гғқгӮӨгғігғҲзӯүгӮ’гҒҫгҒЁгӮҒгҒҹжүӢеј•гҒҚгҒ®дҪңжҲҗгҖҒеҫ“жҘӯе“ЎгҒЁгҒқгҒ®гҒ”家ж—ҸгҒҢд»Ӣиӯ·гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰзӣёи«ҮгҒ§гҒҚгӮӢгҖҢд»Ӣиӯ·зӣёи«ҮгғҮгӮ№гӮҜгҖҚгҒ®иЁӯзҪ®гҒӘгҒ©гҒ«еҸ–гӮҠзө„гӮ“гҒ§гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮеә—иҲ—гҒ§гҒҜгҖҒиӘҚзҹҘз—ҮгҒ®ж–№гӮӮеҲ©з”ЁгҒ—гӮ„гҒҷгҒ„з’°еўғгҒҘгҒҸгӮҠгҖҒгғҰгғӢгғҗгғјгӮөгғ«гғҮгӮ¶гӮӨгғіеҜҫеҝңгҒӘгҒ©гӮ’йҖІгӮҒгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
еҢ»зҷӮ/зҰҸзҘү
зӨҫдјҡзҰҸзҘүжі•дәә敬ж„ӣең’гҖҖд»Ӣиӯ·иҖҒдәәзҰҸзҘүж–ҪиЁӯгӮўгғғгғҲгғӣгғјгғ зҰҸеІЎгҒ§гҒҜгҖҒгҖҢиӘҚзҹҘз—ҮгғӘгғјгғҖгғјз ”дҝ®гҖҚгӮ„гҖҢе®ҹи·өиҖ…з ”дҝ®гҖҚгҒ®еҸ—и¬ӣгӮ’з©ҚжҘөзҡ„гҒ«йҖІгӮҒгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒең°еҹҹгҒ®ж–№гҒҢиӘҚзҹҘз—ҮгҒ«й–ўгҒҷгӮӢеӣ°гӮҠгҒ”гҒЁгӮ’е°Ӯй–ҖиҒ·гҒ«зӣёи«ҮгҒ§гҒҚгӮӢзӘ“еҸЈгҖҢиӘҚзҹҘз—ҮгҒӢгҒ‘гҒ“гҒҝ110з•ӘгҖҚгӮ’иЁӯзҪ®гҒ—гҒҹгӮҠгҖҒзҰҸеІЎеёӮгҒҢеҸ–гӮҠзө„гӮҖгҖҢзҰҸеІЎгӮӘгғ¬гғігӮёгғ‘гғјгғҲгғҠгғјгӮәгҖҚгҒ«еҸӮеҠ гҒ—гҒҹгӮҠгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
й–ўйҖЈиЁҳдәӢ
иҮӘе°ҠеҝғгӮ’еӮ·гҒӨгҒ‘гҒӘгҒ„иӘҚзҹҘз—ҮгҒ®ж–№гҒЁгҒ®гӮігғҹгғҘгғӢгӮұгғјгӮ·гғ§гғіж–№жі•
гғҗгғӘгӮўгғ•гғӘгғјгҒЁгҒҜйҒ•гҒҶпјҹгҒҷгҒ№гҒҰгҒ®дәәгҒ®гҒҹгӮҒгҒ®гҖҢгғҰгғӢгғҗгғјгӮөгғ«гғҮгӮ¶гӮӨгғігҖҚ
家ж—ҸгҒ®д»Ӣиӯ·гӮ’гҒҚгҒЈгҒӢгҒ‘гҒ«д»Ӣиӯ·зҰҸзҘүеЈ«гғ»зӨҫдјҡзҰҸзҘүдё»дәӢд»»з”ЁиіҮж јгӮ’еҸ–еҫ—гҖӮзҸҫеңЁгҒҜгғ©гӮӨгӮҝгғјгҖӮж—ҘгҖ…гҒ®жҡ®гӮүгҒ—гҒ«еҪ№з«ӢгҒӨиә«иҝ‘гҒӘжғ…е ұгӮ’гҒҠдјқгҒҲгҒҷгӮӢгҒ№гҒҸгҖҒд»Ӣиӯ·гғ»еҢ»зҷӮгғ»зҫҺе®№гғ»гӮ«гғ«гғҒгғЈгғјгҒӘгҒ©е№…еәғгҒ„гӮёгғЈгғігғ«гҒ®иЁҳдәӢгӮ’еҹ·зӯҶдёӯгҖӮ

FacebookгғҡгғјгӮёгҒ§
жңҖж–°иЁҳдәӢй…ҚдҝЎпјҒпјҒ
 гғ¬гӮӘгғҸгӮҡгғ¬гӮ№21гӮҜгӮҷгғ«гғјгғ•гӮҡгҒ®д»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ’гӮҷгӮ№
гғ¬гӮӘгғҸгӮҡгғ¬гӮ№21гӮҜгӮҷгғ«гғјгғ•гӮҡгҒ®д»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ’гӮҷгӮ№