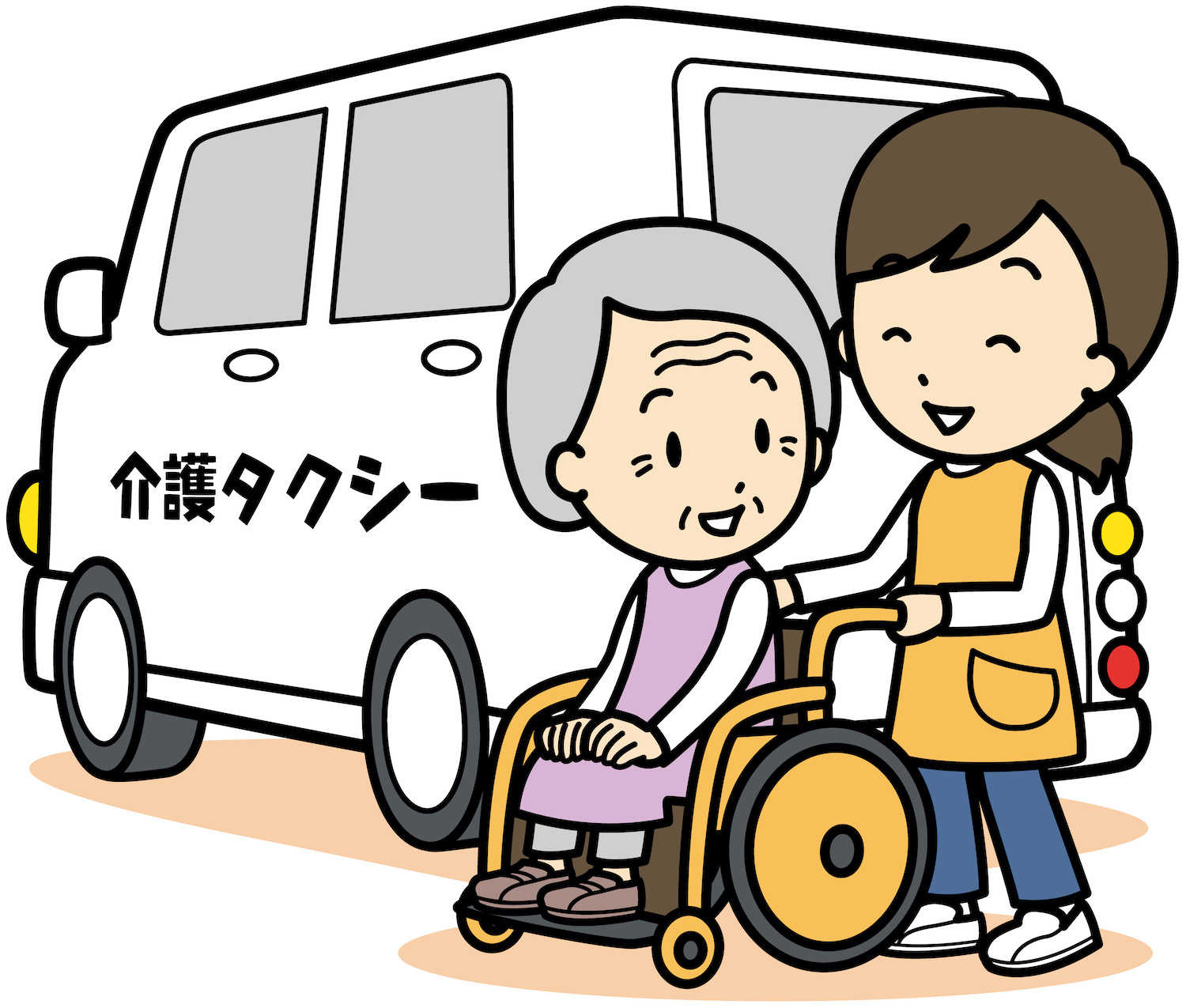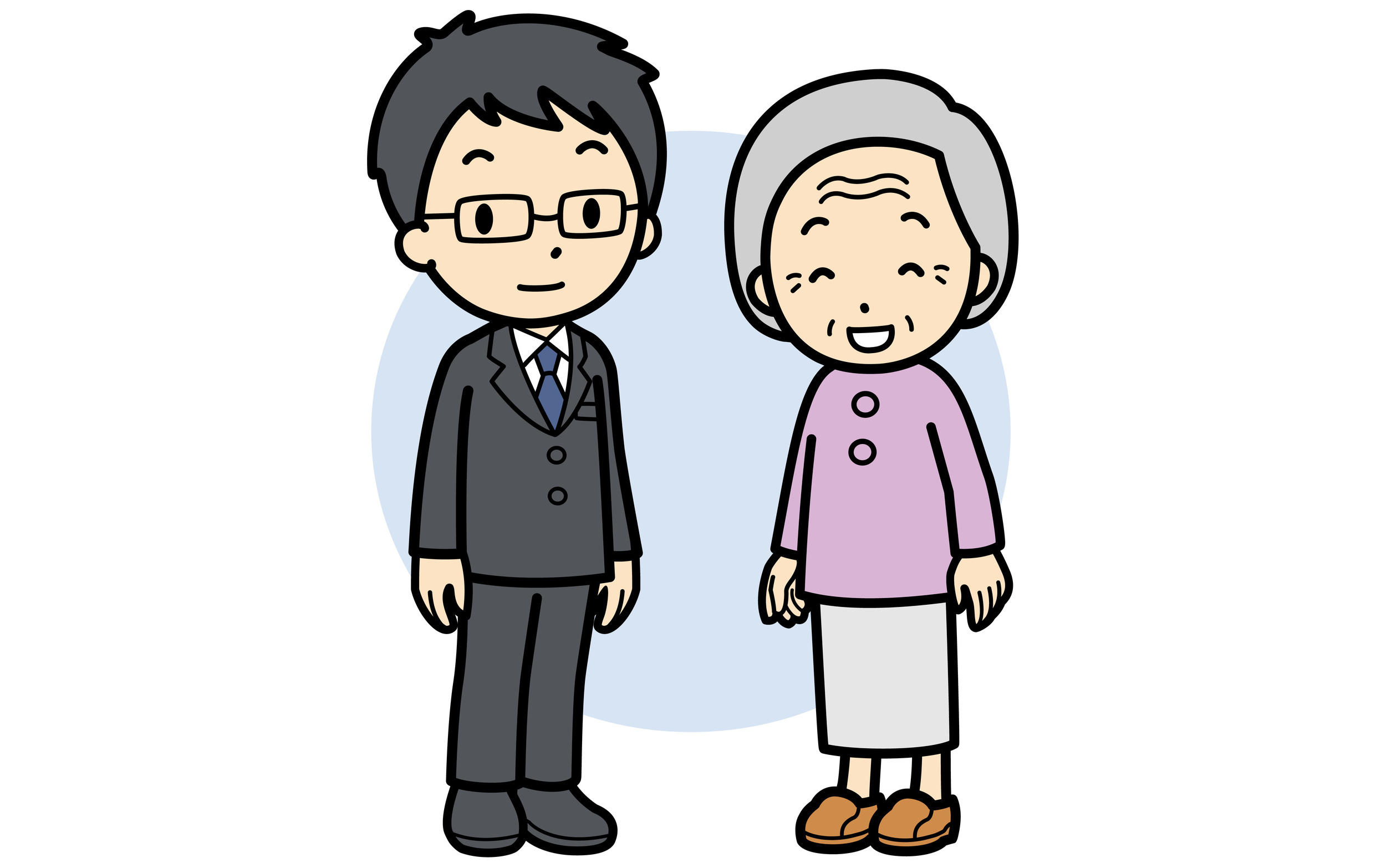д»Ӣиӯ·гҒ®дҫҝеҲ©её–гғҲгғғгғ—гҒёжҲ»гӮӢ
гҖҢе…ұз”ҹгҖҚгҒЁгҖҢдәҲйҳІгҖҚгӮ’дёЎијӘгҒЁгҒҷгӮӢгҖҢиӘҚзҹҘз—Үж–Ҫзӯ–жҺЁйҖІеӨ§з¶ұгҖҚгҒ®5гҒӨгҒ®жҹұ
2019пјҲд»Өе’Ңе…ғпјүе№ҙгҒ«ж”ҝеәңгҒҢгҒЁгӮҠгҒҫгҒЁгӮҒгҒҹиӘҚзҹҘз—Үж–Ҫзӯ–жҺЁйҖІеӨ§з¶ұпјҲгҒ«гӮ“гҒЎгҒ—гӮҮгҒҶгҒ—гҒ•гҒҸгҒҷгҒ„гҒ—гӮ“гҒҹгҒ„гҒ“гҒҶпјүгҖӮгҒ“гҒ®еӨ§з¶ұгҒ«гҒҜгҖҒгҖҢиӘҚзҹҘз—ҮгҒ®зҷәз—ҮгӮ’йҒ…гӮүгҒӣгҖҒиӘҚзҹҘз—ҮгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгӮӮеёҢжңӣгӮ’гӮӮгҒЈгҒҰж—Ҙеёёз”ҹжҙ»гӮ’йҒҺгҒ”гҒӣгӮӢзӨҫдјҡгӮ’зӣ®жҢҮгҒҷгҖҚгҒЁжҳҺиЁҳгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮд»ҠеӣһгҒҜгҖҒиӘҚзҹҘз—Үж–Ҫзӯ–жҺЁйҖІеӨ§з¶ұгҒ®жҰӮиҰҒгҒЁ5гҒӨгҒ®жҹұгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰеҲҶгҒӢгӮҠгӮ„гҒҷгҒҸи§ЈиӘ¬гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
иӘҚзҹҘз—Үж–Ҫзӯ–жҺЁйҖІеӨ§з¶ұгҒЁгҒҜ

гҖҢиӘҚзҹҘз—Үж–Ҫзӯ–жҺЁйҖІеӨ§з¶ұгҖҚгҒҜгҖҒ2019пјҲд»Өе’Ңе…ғпјүе№ҙ6жңҲгҒ«й–ӢеӮ¬гҒ•гӮҢгҒҹиӘҚзҹҘз—Үж–Ҫзӯ–жҺЁйҖІй–ўдҝӮй–Јеғҡдјҡиӯ°гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰзӯ–е®ҡгҒ•гӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ“гҒ®еӨ§з¶ұгҒ®еҹәжң¬зҡ„гҒӘиҖғгҒҲж–№гҒҜгҖҒиӘҚзҹҘз—ҮгҒ®зҷәз—ҮгӮ’йҒ…гӮүгҒӣгҖҒиӘҚзҹҘз—ҮгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгӮӮеёҢжңӣгӮ’жҢҒгҒЈгҒҰж—Ҙеёёз”ҹжҙ»гӮ’йҒҺгҒ”гҒӣгӮӢзӨҫдјҡгӮ’зӣ®жҢҮгҒ—гҖҒиӘҚзҹҘз—ҮгҒ®дәәгӮ„家ж—ҸгҒ®иҰ–зӮ№гӮ’йҮҚиҰ–гҒ—гҒӘгҒҢгӮүпҪўе…ұз”ҹпҪЈгҒЁпҪўдәҲйҳІпҪЈпјҲвҖ»пјүгӮ’и»ҠгҒ®дёЎијӘгҒЁгҒ—гҒҰж–Ҫзӯ–гӮ’жҺЁйҖІгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
иӘҚзҹҘз—ҮдәҲйҳІгҒ«й–ўгҒҷгӮӢгӮЁгғ“гғҮгғігӮ№гҒ®еҸҺйӣҶгғ»жҷ®еҸҠгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«гҖҒдәҲйҳІгӮ’еҗ«гӮҒгҒҹиӘҚзҹҘз—ҮгҒёгҒ®гҖҢеӮҷгҒҲгҖҚгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®еҸ–гӮҠзө„гҒҝгӮ’дҝғгҒҷгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒ70жӯід»ЈгҒ§гҒ®зҷәз—ҮгӮ’10е№ҙй–“гҒ§пј‘жӯійҒ…гӮүгҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӣ®жҢҮгҒҷгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
-
вҖ» пҪўе…ұз”ҹпҪЈгҒЁпҪўдәҲйҳІпҪЈ
гҖҢе…ұз”ҹгҖҚгҒЁгҒҜ
иӘҚзҹҘз—ҮгҒ®дәәгҒҢе°ҠеҺігҒЁеёҢжңӣгӮ’жҢҒгҒЈгҒҰиӘҚзҹҘз—ҮгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«з”ҹгҒҚгӮӢгҖҒгҒҫгҒҹиӘҚзҹҘз—ҮгҒҢгҒӮгҒЈгҒҰгӮӮгҒӘгҒҸгҒҰгӮӮеҗҢгҒҳзӨҫдјҡгҒ§гҒЁгӮӮгҒ«з”ҹгҒҚгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶж„Ҹе‘і
гҖҢдәҲйҳІгҖҚгҒЁгҒҜ
гҖҢиӘҚзҹҘз—ҮгҒ«гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶж„Ҹе‘ігҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒгҖҢиӘҚзҹҘз—ҮгҒ«гҒӘгӮӢгҒ®гӮ’йҒ…гӮүгҒӣгӮӢгҖҚгҖҢиӘҚзҹҘз—ҮгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгӮӮйҖІиЎҢгӮ’з·©гӮ„гҒӢгҒ«гҒҷгӮӢгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶж„Ҹе‘і
иӘҚзҹҘз—Үж–Ҫзӯ–гҒ®гҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гҒЁзҸҫеңЁ
ж—Ҙжң¬гҒ§гҒҜ1980 е№ҙд»ЈеҫҢеҚҠд»ҘйҷҚгҒ«иӘҚзҹҘз—ҮгҒёгҒ®ж–Ҫзӯ–гҒҢжң¬ж јеҢ–гҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
2012пјҲе№іжҲҗ24пјүе№ҙгҒ«гӮӘгғ¬гғігӮёгғ—гғ©гғіпјҲиӘҚзҹҘз—Үж–Ҫзӯ–жҺЁйҖІ 5гҒӢе№ҙиЁҲз”»пјүгҖҒ2015пјҲе№іжҲҗ27пјүе№ҙгҒ«ж–°гӮӘгғ¬гғігӮёгғ—гғ©гғіпјҲиӘҚзҹҘз—Үж–Ҫзӯ–жҺЁйҖІз·ҸеҗҲжҲҰз•ҘпјүгҒҢзӯ–е®ҡгҒ•гӮҢгҖҒ2019пјҲд»Өе’Ңе…ғпјүе№ҙгҒ«гҒҜиӘҚзҹҘз—Үж–Ҫзӯ–жҺЁйҖІеӨ§з¶ұгҒҢгҒЁгӮҠгҒҫгҒЁгӮҒгӮүгӮҢгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
иӘҚзҹҘз—Үж–Ҫзӯ–жҺЁйҖІеӨ§з¶ұгҒ®еҜҫиұЎжңҹй–“гҒҜгҖҒеӣЈеЎҠгҒ®дё–д»ЈгҒҢ 75 жӯід»ҘдёҠгҒЁгҒӘгӮӢ 2025пјҲд»Өе’Ңпј—пјүе№ҙгҒҫгҒ§гҒ§гҖҒзӯ–е®ҡеҫҢ3е№ҙгӮ’зӣ®йҖ”гҒ«ж–Ҫзӯ–гҒ®йҖІжҚ—пјҲгҒ—гӮ“гҒЎгӮҮгҒҸпјүгӮ’зўәиӘҚгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
й–ўйҖЈиЁҳдәӢпјҡ
гҖҢиӘҚзҹҘз—ҮгҒ«гӮҲгӮӢгӮӮгҒ®еҝҳгӮҢгҖҚгҒЁгҖҢеҠ йҪўгҒ«гӮҲгӮӢгӮӮгҒ®еҝҳгӮҢгҖҚгҒ®йҒ•гҒ„гҒЁгҒҜпјҹ
ж—©жңҹзҷәиҰӢгғ»еҜҫеҝңгҒҢйҮҚиҰҒпјҒ65жӯіжңӘжәҖгҒ®дәәгҒҢзҷәз—ҮгҒҷгӮӢгҖҢиӢҘе№ҙжҖ§иӘҚзҹҘз—ҮгҖҚ
иӘҚзҹҘз—Үж–Ҫзӯ–жҺЁйҖІеӨ§з¶ұгҒ®5гҒӨгҒ®жҹұ
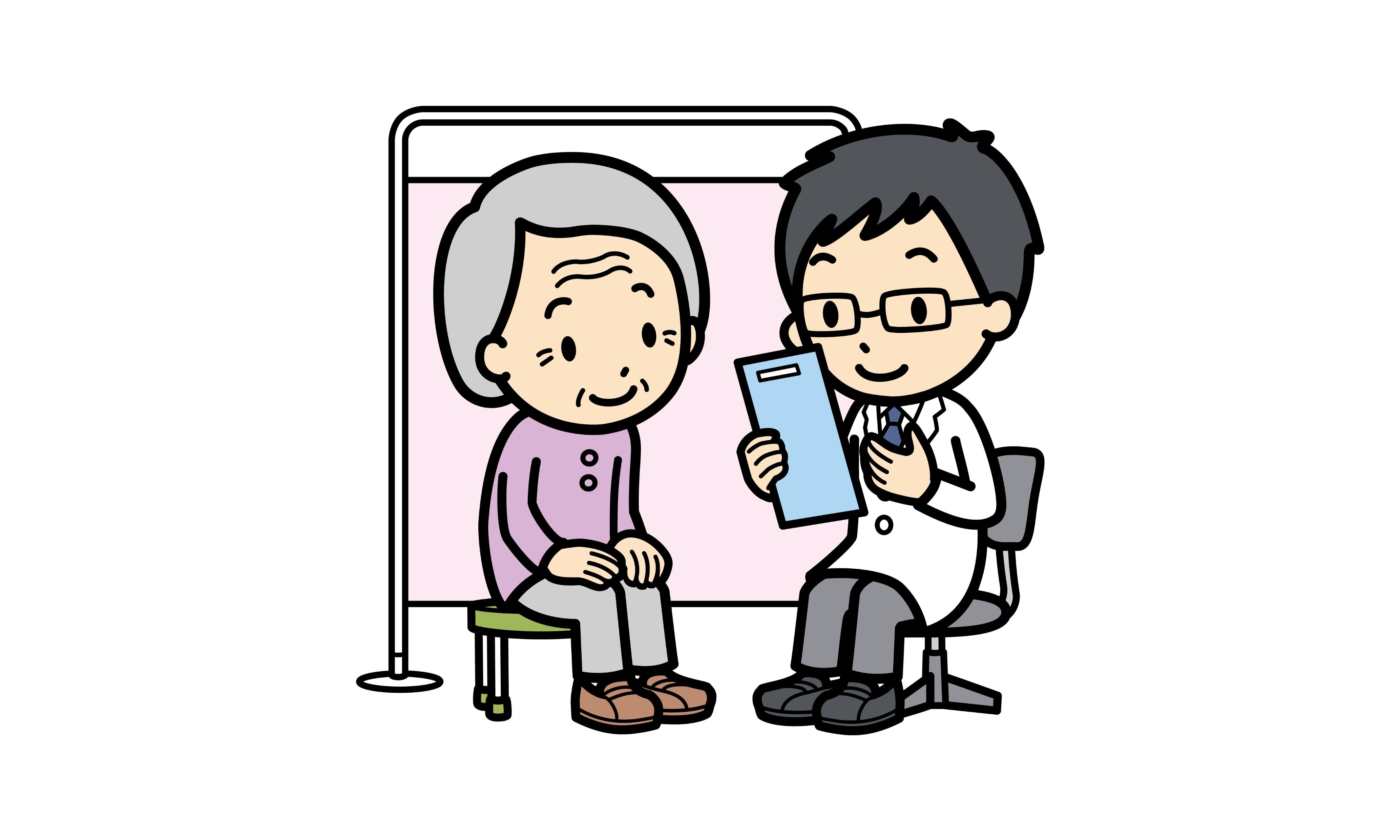
е…·дҪ“зҡ„гҒӘж–Ҫзӯ–гҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒгҖҢжҷ®еҸҠе•“зҷәгғ»жң¬дәәзҷәдҝЎж”ҜжҸҙгҖҚгҖҢдәҲйҳІгҖҚгҖҢеҢ»зҷӮгғ»гӮұгӮўгғ»д»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№гғ»д»Ӣиӯ·иҖ…гҒёгҒ®ж”ҜжҸҙгҖҚгҖҢиӘҚзҹҘз—ҮгғҗгғӘгӮўгғ•гғӘгғјгҒ®жҺЁйҖІгғ»иӢҘе№ҙжҖ§иӘҚзҹҘз—ҮгҒ®дәәгҒёгҒ®ж”ҜжҸҙгғ»зӨҫдјҡеҸӮеҠ ж”ҜжҸҙгҖҚгҖҢз ”з©¶й–Ӣзҷәгғ»з”ЈжҘӯдҝғйҖІгғ»еӣҪйҡӣеұ•й–ӢгҖҚгӮ’5гҒӨгҒ®жҹұгҒЁгҒ—гҒҰжҺІгҒ’гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
в‘ жҷ®еҸҠе•“зҷәгғ»жң¬дәәзҷәдҝЎж”ҜжҸҙ
гғ»иӘҚзҹҘз—ҮгҒ«й–ўгҒҷгӮӢзҗҶи§ЈдҝғйҖІпјҲиӘҚзҹҘз—ҮгӮөгғқгғјгӮҝгғјйӨҠжҲҗгҒ®жҺЁйҖІпјҸеӯҗгҒ©гӮӮгғ»еӯҰз”ҹгҒёгҒ®зҗҶи§ЈдҝғйҖІгҒӘгҒ©пјү
гғ»зӣёи«Үе…ҲгҒ®е‘ЁзҹҘ
гғ»иӘҚзҹҘз—ҮгҒ®дәәжң¬дәәгҒӢгӮүгҒ®зҷәдҝЎж”ҜжҸҙпјҲгҖҢиӘҚзҹҘз—ҮгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«з”ҹгҒҚгӮӢеёҢжңӣе®ЈиЁҖгҖҚгҒ®еұ•й–ӢгҒӘгҒ©пјү
в‘Ў дәҲйҳІ
гғ»иӘҚзҹҘз—ҮдәҲйҳІгҒ«иіҮгҒҷгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒ®гҒӮгӮӢжҙ»еӢ•гҒ®жҺЁйҖІ
гғ»дәҲйҳІгҒ«й–ўгҒҷгӮӢгӮЁгғ“гғҮгғігӮ№еҸҺйӣҶгҒ®жҺЁйҖІ
гғ»ж°‘й–“гҒ®е•Ҷе“ҒгӮ„гӮөгғјгғ“гӮ№гҒ®и©•дҫЎгғ»иӘҚиЁјгҒ®д»•зө„гҒҝгҒ®жӨңиЁҺ
в‘ў еҢ»зҷӮгғ»гӮұгӮўгғ»д»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№гғ»д»Ӣиӯ·иҖ…гҒёгҒ®ж”ҜжҸҙ
гғ»ж—©жңҹзҷәиҰӢгғ»ж—©жңҹеҜҫеҝңгҖҒеҢ»зҷӮдҪ“еҲ¶гҒ®ж•ҙеӮҷ
гғ»еҢ»зҷӮеҫ“дәӢиҖ…гғ»д»Ӣиӯ·еҫ“дәӢиҖ…зӯүгҒ®иӘҚзҹҘз—ҮеҜҫеҝңеҠӣеҗ‘дёҠгҒ®дҝғйҖІ
гғ»д»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№еҹәзӣӨж•ҙеӮҷгҖҒд»Ӣиӯ·дәәжқҗзўәдҝқ
гғ»еҢ»зҷӮгғ»д»Ӣиӯ·гҒ®жүӢжі•гҒ®жҷ®еҸҠгғ»й–Ӣзҷә
гғ»д»Ӣиӯ·иҖ…гҒ®иІ жӢ…и»ҪжёӣгҒ®жҺЁйҖІ
в‘Ј иӘҚзҹҘз—ҮгғҗгғӘгӮўгғ•гғӘгғјгҒ®жҺЁйҖІгғ»иӢҘе№ҙжҖ§иӘҚзҹҘз—ҮгҒ®дәәгҒёгҒ®ж”ҜжҸҙгғ»зӨҫдјҡеҸӮеҠ ж”ҜжҸҙ
гғ»гғҗгғӘгӮўгғ•гғӘгғјгҒ®гҒҫгҒЎгҒҘгҒҸгӮҠжҺЁйҖІ
гғ»з§»еӢ•жүӢж®өгҒ®зўәдҝқгҒ®жҺЁйҖІ
гғ»ең°еҹҹж”ҜжҸҙдҪ“еҲ¶гҒ®еј·еҢ–
гғ»иӘҚзҹҘз—ҮгҒ«й–ўгҒҷгӮӢеҸ–гӮҠзө„гҒҝгӮ’е®ҹж–ҪгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢдјҒжҘӯзӯүгҒ®иӘҚиЁјеҲ¶еәҰгӮ„иЎЁеҪ°
гғ»е•Ҷе“Ғгғ»гӮөгғјгғ“гӮ№й–ӢзҷәгҒ®жҺЁйҖІ
гғ»жҲҗе№ҙеҫҢиҰӢеҲ¶еәҰгҒ®еҲ©з”ЁдҝғйҖІ
гғ»иӘҚзҹҘз—ҮгҒ«й–ўгҒҷгӮӢгҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒӘж°‘й–“дҝқйҷәгҒ®жҺЁйҖІ
гғ»иӢҘе№ҙжҖ§иӘҚзҹҘз—Үж”ҜжҸҙгӮігғјгғҮгӮЈгғҚгғјгӮҝгғјй…ҚзҪ®гҒ®жҺЁйҖІ
гғ»зӨҫдјҡеҸӮеҠ жҙ»еӢ•гӮ„зӨҫдјҡиІўзҢ®гҒ®дҝғйҖІгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҖҖгҒӘгҒ©
в‘Ө з ”з©¶й–Ӣзҷәгғ»з”ЈжҘӯдҝғйҖІгғ»еӣҪйҡӣеұ•й–Ӣ
гғ»иӘҚзҹҘз—ҮгҒ®дәҲйҳІгғ»иЁәж–ӯгғ»жІ»зҷӮгғ»гӮұгӮўзӯүгҒ®з ”究
й–ўйҖЈиЁҳдәӢпјҡ
д»ҠеҫҢгҒ•гӮүгҒ«еҝ…иҰҒжҖ§гҒҢй«ҳгҒҫгӮӢгҖҢжҲҗе№ҙеҫҢиҰӢеҲ¶еәҰгҖҚгӮ’еҲ©з”ЁгҒҷгӮӢгҒЁгҒҚгҒ®гғқгӮӨгғігғҲ
дё»гҒӘж–Ҫзӯ–гҒ®еҶ…е®№
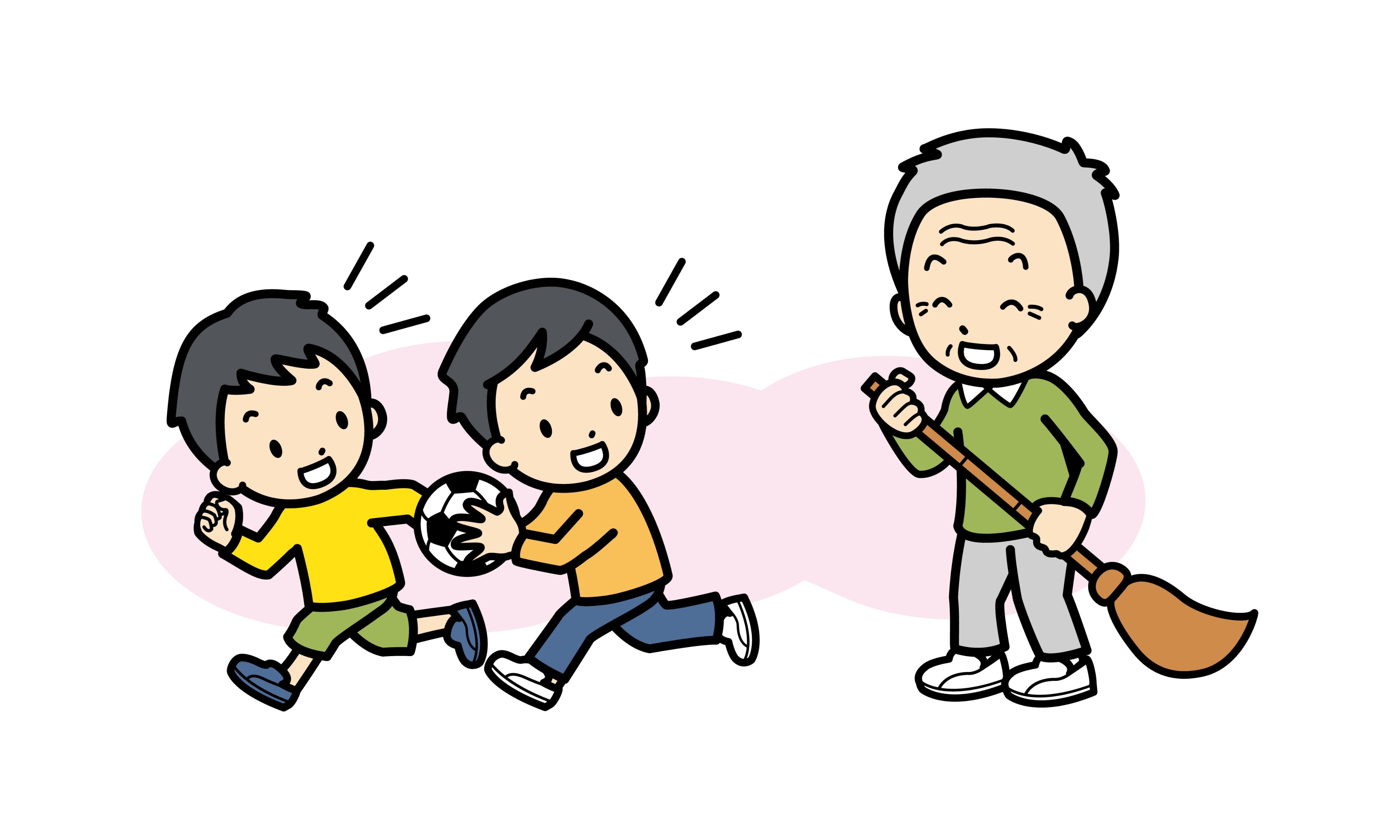
гҖҢиӘҚзҹҘз—ҮгӮөгғқгғјгӮҝгғјгҖҚгҒ®йӨҠжҲҗгҒЁжҙ»еӢ•ж”ҜжҸҙ
иӘҚзҹҘз—ҮгӮөгғқгғјгӮҝгғјгҒЁгҒҜгҖҒиӘҚзҹҘз—ҮгҒ«й–ўгҒҷгӮӢжӯЈгҒ—гҒ„зҹҘиӯҳгӮ’жҢҒгҒЎгҖҒең°еҹҹгғ»иҒ·еҹҹгҒ§иӘҚзҹҘз—ҮгҒ®гҒ”жң¬дәәгӮ„гҒқгҒ®гҒ”家ж—ҸгӮ’гҒ§гҒҚгӮӢзҜ„еӣІгҒ§жүӢеҠ©гҒ‘гҒҷгӮӢдәәгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ
ең°еҹҹгҒ®ж–№гҖ…гҖҒе°ҸеЈІжҘӯгғ»йҮ‘иһҚж©ҹй–ўгғ»е…¬е…ұдәӨйҖҡж©ҹй–ўгҒ®еҫ“жҘӯе“ЎгҒӘгҒ©гӮ’гҒҜгҒҳгӮҒгҖҒеӯҗгҒ©гӮӮгӮ„еӯҰз”ҹгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢйӨҠжҲҗи¬ӣеә§гӮ’жӢЎеӨ§гҒҷгӮӢгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
й–ўйҖЈиЁҳдәӢпјҡ
иӘҚзҹҘз—ҮгҒ®ж–№гӮӮжҡ®гӮүгҒ—гӮ„гҒҷгҒ„ең°еҹҹгӮ’гҒӨгҒҸгӮӢгҖҢиӘҚзҹҘз—ҮгӮөгғқгғјгӮҝгғјгҖҚ
иӘҚзҹҘз—ҮгҒ®ж–№гӮ„гҒқгҒ®гҒ”家ж—ҸгӮ’ең°еҹҹгҒ§ж”ҜгҒҲгӮӢгҖҢиӘҚзҹҘз—ҮгӮ«гғ•гӮ§пјҲгӮӘгғ¬гғігӮёгӮ«гғ•гӮ§пјүгҖҚ
гҖҢиӘҚзҹҘз—Үең°еҹҹж”ҜжҸҙжҺЁйҖІе“ЎгҖҚгҒ®й…ҚзҪ®
иӘҚзҹҘз—Үең°еҹҹж”ҜжҸҙжҺЁйҖІе“ЎгҒЁгҒҜгҖҒй–ўдҝӮж©ҹй–ўгҒЁгҒ®йҖЈжҗәдҪ“еҲ¶гҒҘгҒҸгӮҠгҖҒгҖҢиӘҚзҹҘз—ҮгӮұгӮўгғ‘гӮ№гҖҚгҒ®дҪңжҲҗгғ»жҷ®еҸҠгҖҒгҖҢиӘҚзҹҘз—ҮгӮ«гғ•гӮ§гҖҚзӯүгҒ®й–ӢиЁӯгҖҒиӘҚзҹҘз—ҮгҒ®ж–№гӮ„гҒ”家ж—ҸгҒёгҒ®зӣёи«Үж”ҜжҸҙгҒӘгҒ©гӮ’иЎҢгҒҶдәәгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮең°еҹҹеҢ…жӢ¬ж”ҜжҸҙгӮ»гғігӮҝгғјгӮ„иӘҚзҹҘз—Үз–ҫжӮЈеҢ»зҷӮгӮ»гғігӮҝгғјгҒӘгҒ©гҒ«й…ҚзҪ®гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
й–ўйҖЈиЁҳдәӢпјҡ
иӘҚзҹҘз—ҮгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«з”ҹгҒҚгӮӢж–№гӮ„гҒ”家ж—ҸгҒ®гҒҹгӮҒгҒ®гҖҢиӘҚзҹҘз—ҮгӮұгӮўгғ‘гӮ№гҖҚ
иӘҚзҹҘз—ҮеҲқжңҹйӣҶдёӯж”ҜжҸҙгғҒгғјгғ
иӘҚзҹҘз—ҮгҒҢз–‘гӮҸгӮҢгӮӢж–№гӮ„иӘҚзҹҘз—ҮгҒ®ж–№гҖҒгҒқгҒ®гҒ”家ж—ҸгӮ’иЁӘе•ҸгҒ—гҖҒз—ҮзҠ¶гӮ’жҠҠжҸЎгҒ—гҒӘгҒҢгӮү家ж—Ҹж”ҜжҸҙгҒӘгҒ©гӮ’иЎҢгҒ„гҖҒиҮӘз«Ӣз”ҹжҙ»гӮ’гӮөгғқгғјгғҲгҒҷгӮӢгғҒгғјгғ пјҲзңӢиӯ·её«гғ»дҝқеҒҘеё«гғ»дҪңжҘӯзҷӮжі•еЈ«гҒӘгҒ©пјүгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮгҒ»гҒјгҒҷгҒ№гҒҰгҒ®еёӮз”әжқ‘гҒ«иЁӯзҪ®гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
д»ҠеҫҢгҒҜгҖҒзӨҫдјҡгҒӢгӮүеӯӨз«ӢгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢзҠ¶ж…ӢгҒ«гҒӮгӮӢж–№гҒёгҒ®еҜҫеҝңгӮӮеҗ«гӮҒгҖҒйҒ©еҲҮгҒӘеҢ»зҷӮгғ»д»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№гҒӘгҒ©гҒ«йҖҹгӮ„гҒӢгҒ«гҒӨгҒӘгҒҗеҸ–гӮҠзө„гҒҝеј·еҢ–гҒ®гҒҹгӮҒгҒ«гҖҒе…ҲйҖІзҡ„гҒӘжҙ»еӢ•дәӢдҫӢгӮ’еҸҺйӣҶгҒ—гҒҰе…ЁеӣҪгҒ«жЁӘеұ•й–ӢгҒ—гҖҒгҒқгӮҢгӮүгӮ’гӮӮгҒЁгҒ«гғҒгғјгғ гҒ®иіӘгҒ®и©•дҫЎгӮ„еҗ‘дёҠгҒ®гҒҹгӮҒгҒ®ж–№зӯ–гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰжӨңиЁҺгҒҷгӮӢгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҢиӘҚзҹҘз—Үз–ҫжӮЈеҢ»зҷӮгӮ»гғігӮҝгғјгҖҚгҒ®иЁӯзҪ®
иӘҚзҹҘз—Үз–ҫжӮЈеҢ»зҷӮгӮ»гғігӮҝгғјгҒҜгҖҒиӘҚзҹҘз—ҮгҒ®й‘‘еҲҘиЁәж–ӯгҖҒиЎҢеӢ•пҪҘеҝғзҗҶз—ҮзҠ¶пјҲBPSDпјүгҒЁиә«дҪ“еҗҲдҪөз—ҮгҒёгҒ®еҜҫеҝңгҖҒе°Ӯй–ҖеҢ»зҷӮзӣёи«ҮгҖҒй–ўдҝӮж©ҹй–ўгҒЁгҒ®йҖЈжҗәгҒӘгҒ©гӮ’жӢ…гҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
ж–°гӮӘгғ¬гғігӮёгғ—гғ©гғіпјҲиӘҚзҹҘз—Үж–Ҫзӯ–жҺЁйҖІз·ҸеҗҲжҲҰз•ҘпјүгҒ§гҒҜгҖҢиӘҚзҹҘз—ҮгҒ®дәәгӮ„гҒқгҒ®е®¶ж—ҸгҒ®иҰ–зӮ№гҒ®йҮҚиҰ–гҖҚгҒҢпј—гҒӨгҒ®жҹұгҒ®гҒІгҒЁгҒӨгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгғ—гғ©гғіе…ЁдҪ“гҒ®зҗҶеҝөгҒ§гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮиӘҚзҹҘз—Үж–Ҫзӯ–жҺЁйҖІеӨ§з¶ұгҒ«жІҝгҒЈгҒҹж–Ҫзӯ–гӮӮгҖҒгҒҷгҒ№гҒҰиӘҚзҹҘз—ҮгҒ®ж–№гҒ®иҰ–зӮ№гҒ«з«ӢгҒЎгҖҒиӘҚзҹҘз—ҮгҒ®ж–№гӮ„гҒқгҒ®гҒ”家ж—ҸгҒ®ж„ҸиҰӢгӮ’гҒөгҒҫгҒҲгҒҰз«ӢжЎҲгғ»жҺЁйҖІгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’еҹәжң¬гҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
家ж—ҸгҒ®д»Ӣиӯ·гӮ’гҒҚгҒЈгҒӢгҒ‘гҒ«д»Ӣиӯ·зҰҸзҘүеЈ«гғ»зӨҫдјҡзҰҸзҘүдё»дәӢд»»з”ЁиіҮж јгӮ’еҸ–еҫ—гҖӮзҸҫеңЁгҒҜгғ©гӮӨгӮҝгғјгҖӮж—ҘгҖ…гҒ®жҡ®гӮүгҒ—гҒ«еҪ№з«ӢгҒӨиә«иҝ‘гҒӘжғ…е ұгӮ’гҒҠдјқгҒҲгҒҷгӮӢгҒ№гҒҸгҖҒд»Ӣиӯ·гғ»еҢ»зҷӮгғ»зҫҺе®№гғ»гӮ«гғ«гғҒгғЈгғјгҒӘгҒ©е№…еәғгҒ„гӮёгғЈгғігғ«гҒ®иЁҳдәӢгӮ’еҹ·зӯҶдёӯгҖӮ

FacebookгғҡгғјгӮёгҒ§
жңҖж–°иЁҳдәӢй…ҚдҝЎпјҒпјҒ
 гғ¬гӮӘгғҸгӮҡгғ¬гӮ№21гӮҜгӮҷгғ«гғјгғ•гӮҡгҒ®д»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ’гӮҷгӮ№
гғ¬гӮӘгғҸгӮҡгғ¬гӮ№21гӮҜгӮҷгғ«гғјгғ•гӮҡгҒ®д»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ’гӮҷгӮ№