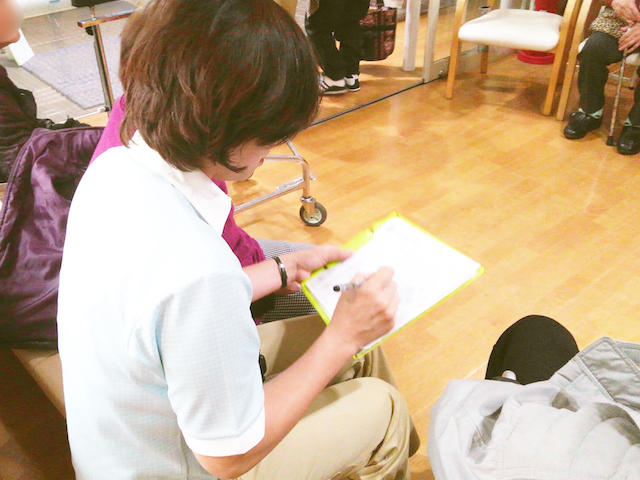С╗ІУГисЂ«СЙ┐тѕЕтИќсЃѕсЃЃсЃЌсЂИТѕ╗сѓІ
С╗ІУГиУЂитЊАуГЅсЂФсѓѕсѓІтќђуЌ░тљИт╝ЋуГЅ№╝ѕсЂЪсѓЊсЂ«тљИт╝ЋсЃ╗ухїу«АТаёжці№╝ЅсЂ«тѕХт║д
жФўжйбУђЁТќйУеГсѓётюет«ЁсЂДтї╗уЎѓуџёсѓ▒сѓбсѓњт┐ЁУдЂсЂесЂЎсѓІТќ╣сЂ»тбЌсЂѕсЂдсЂЇсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓС╗ітЏъсЂ»сђЂтї╗уЎѓуџёсѓ▒сѓбсЂ«сЂфсЂІсЂДсѓѓсђЂсЃІсЃ╝сѓ║сЂ«жФўсЂётќђуЌ░тљИт╝ЋуГЅсЂФсЂцсЂёсЂдсЂіС╝ЮсЂѕсЂЌсЂЙсЂЎсђѓ
сЂЪсѓЊсЂ«тљИт╝ЋуГЅсЂ«тѕХт║дсЂесЂ»
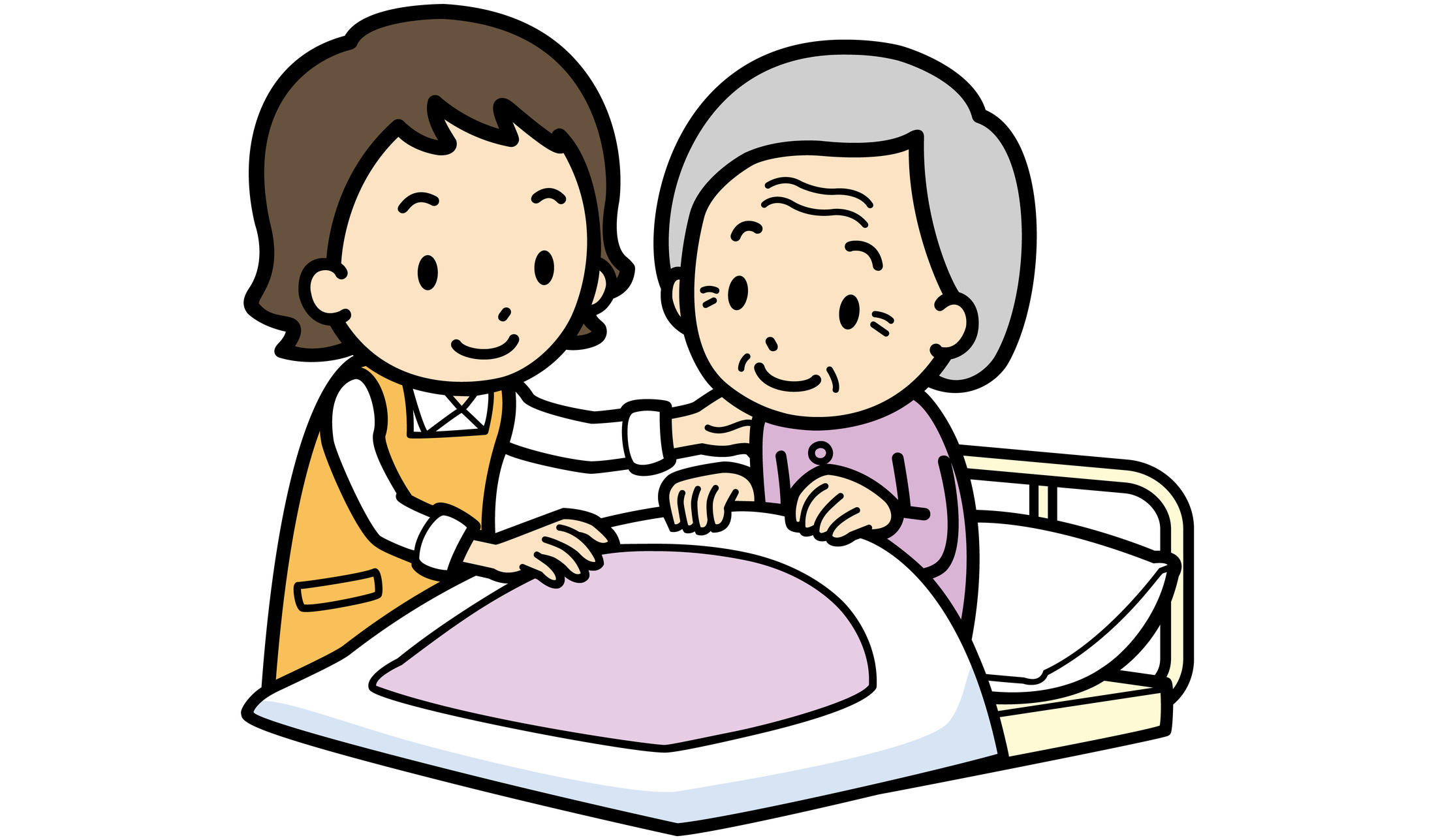
уцЙС╝џудЈуЦЅтБФтЈісЂ│С╗ІУГиудЈуЦЅтБФТ│ЋсЂ«СИђжЃеТћ╣ТГБсЂФсѓѕсѓісђЂ2012т╣┤№╝ѕт╣│Тѕљ24т╣┤№╝Ѕ4ТюѕсЂІсѓЅсђЂСИђт«џсЂ«уаћС┐«сѓњтЈЌсЂЉсЂЪС╗ІУГиУЂитЊАуГЅсЂ»сђЂСИђт«џсЂ«ТЮАС╗ХсЂ«СИІсЂДсђЂсЂЪсѓЊсЂ«тљИт╝Ћсѓёухїу«АТаёжцісЂфсЂЕсЂ«уЅ╣т«џУАїуѓ║сѓњт«ЪТќйсЂДсЂЇсѓІсѓѕсЂєсЂФсЂфсѓісЂЙсЂЌсЂЪсђѓ
сЂЊсѓїсЂФС╝┤сЂёсђЂуаћС┐«сѓњС┐«С║єсЂЌсЂЪС╗ІУГиУЂитЊАуГЅсЂ»сђЂсђїУфЇт«џуЅ╣т«џУАїуѓ║ТЦГтІЎтЙЊС║ІУђЁсђЇсЂесЂЌсЂдУфЇт«џУе╝сЂ«С║цС╗ўсѓњтЈЌсЂЉсђЂсЂЋсѓЅсЂФсђЂУфЇт«џуЅ╣т«џУАїуѓ║ТЦГтІЎтЙЊС║ІУђЁсЂїТЅђт▒ъсЂЎсѓІС║ІТЦГТЅђсЂ»сђЂсђїуЎ╗жї▓уЅ╣т«џУАїуѓ║С║ІТЦГУђЁсђЇсЂесЂЌсЂджЃйжЂЊт║юуюїсЂ«уЎ╗жї▓сѓњтЈЌсЂЉсЂЪСИісЂДсђЂтѕЕућеУђЁсЂФт»ЙсЂЌсЂдсЂЪсѓЊтљИт╝ЋуГЅсѓњт«ЪТќйсЂЎсѓІсЂЊсЂесЂїтЈ»УЃйсЂесЂфсѓісЂЙсЂЎсђѓ
сЂЊсЂ«тѕХт║дсЂФсѓѕсѓісђЂт«ЪТќйтЈ»УЃйсЂесЂфсЂБсЂЪтї╗уЎѓУАїуѓ║№╝ѕтї╗УАїуѓ║№╝ЅсЂ»сђЂсЂЪсѓЊсЂ«тљИт╝Ћ№╝ѕтЈБУЁћтєЁсђЂж╝╗УЁћтєЁсђЂТ░Ќу«АсѓФсЃІсЃЦсЃ╝сЃгтєЁжЃе№╝ЅсЂеухїу«АТаёжці№╝ѕУЃЃсѓЇсЂєсђЂУЁИсѓЇсЂєсђЂухїж╝╗ухїу«АТаёжці№╝ЅсЂДсЂЎсђѓ
| т«ЪТќйтЈ»УЃйсЂфУАїуѓ║ | |
|---|---|
| сЂЪсѓЊсЂ«тљИт╝Ћ | РЉатЈБУЁћтєЁ РЉАж╝╗УЁћтєЁ РЉбТ░Ќу«АсѓФсЃІсЃЦсЃ╝сЃгтєЁжЃе |
| ухїу«АТаёжці | РЉаУЃЃсѓЇсЂєсЂЙсЂЪсЂ»УЁИсѓЇсЂє РЉАухїж╝╗ |
Тћ╣ТГБсЂЙсЂДсЂ«ухїуи»
тї╗уЎѓУАїуѓ║сЂФУЕ▓тйЊсЂЎсѓІсЂЪсѓЊсЂ«тљИт╝ЋсЂеухїу«АТаёжцісЂ»сђЂтї╗тИФ№╝ѕсЂЙсЂЪсЂ»тї╗тИФсЂ«ТїЄуц║сѓњтЈЌсЂЉсЂЪуюІУГитИФуГЅ№╝ЅсЂ«сЂ┐сЂїт«ЪТќйсЂДсЂЇсѓІУАїуѓ║сЂДсЂЌсЂЪсђѓ
Т│ЋТћ╣ТГБтЅЇсЂ«уцЙС╝џудЈуЦЅжќбС┐ѓТќйУеГсЂДсЂ»сђЂС╗ІУГиУЂитЊАуГЅсЂФсѓѕсѓІсЂЪсѓЊсЂ«тљИт╝ЋуГЅсЂ«т«ЪТќйсЂ»сђЂтйЊжЮбсЂ«сѓёсѓђсѓњтЙЌсЂфсЂёТјфуй«№╝ѕт«ЪУ│фуџёжЂЋТ│ЋТђДжў╗тЇ┤№╝ЅсЂесЂЌсЂдсђЂтјџућЪті┤тЃЇуюЂсЂ«жђџуЪЦсЂФтЪ║сЂЦсЂЇсђЂСИђт«џсЂ«УдЂС╗ХсЂ«СИІсЂДт«╣УфЇсЂЋсѓїсЂдсЂЇсЂЙсЂЌсЂЪсђѓтјџућЪті┤тЃЇуюЂсЂ»сђЂт░єТЮЦсЂФсѓЈсЂЪсЂБсЂдсѓѕсѓіт«ЅтЁесЂфТЈљСЙЏсѓњУАїсЂѕсѓІсѓѕсЂєсЂФТ│ЋтѕХтїќсЂФУЄ│сЂБсЂЪсЂесЂЌсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓ
Рќ╝жќбжђБУеўС║І
сЂЕсЂєжЂЋсЂєсЂ«№╝ЪудЈуЦЅсЂ«тЏйт«ХУ│ЄТа╝сђїуцЙС╝џудЈуЦЅтБФсђЇсЂесђїС╗ІУГиудЈуЦЅтБФсђЇ
т«ЪТќйсЂДсЂЇсѓІС╗ІУГиУЂитЊАуГЅ

С╗ІУГиудЈуЦЅтБФтЈісЂ│СИђт«џсЂ«уаћС┐«сѓњС┐«С║єсЂЌсЂЪС╗ІУГиУЂитЊАуГЅсЂ«Тќ╣сЂ»тї╗уЎѓсѓёуюІУГисЂесЂ«жђБТљ║сЂФсѓѕсѓІт«ЅтЁеуб║С┐ЮсЂїтЏ│сѓЅсѓїсЂдсЂёсѓІсЂЊсЂеуГЅсђЂСИђт«џсЂ«ТЮАС╗ХСИІсЂДсђЂсЂЪсѓЊсЂ«тљИт╝ЋуГЅсЂ«УАїуѓ║сѓњт«ЪТќйсЂЎсѓІсЂЊсЂесЂїсЂДсЂЇсЂЙсЂЎсђѓ
<т┐ЁУдЂсЂфТЅІуХџсЂЇ>
С╗ІУГиудЈуЦЅтБФ
[2015т╣┤т║д№╝ѕт╣│Тѕљ27т╣┤т║д№╝ЅС╗ЦжЎЇсЂФтЏйт«ХУЕджеЊсЂФтљѕТа╝сЂЋсѓїсЂЪТќ╣] Рђ╗2016т╣┤№╝ѕт╣│Тѕљ28т╣┤№╝Ѕ№╝ЉТюѕС╗ЦжЎЇсЂ«тЏйт«ХУЕджеЊ
сЃ╗С╗ІУГиудЈуЦЅтБФсЂ«уЎ╗жї▓сѓњУАїсЂёсђїС╗ІУГиудЈуЦЅтБФуЎ╗жї▓Уе╝сђЇсЂїС║цС╗ўсѓњтЈЌсЂЉсѓІ
сЃ╗С║ІТЦГУђЁсЂФт░▒ТЦГтЙїсЂФсђїт«ЪТќйуаћС┐«сђЇсѓњС┐«С║єсЂЌсђЂсђїС┐«С║єУе╝ТўјТЏИсђЇсЂ«С║цС╗ўсѓњтЈЌсЂЉсѓІ
сЃ╗№╝ѕтЁгУ▓А№╝ЅуцЙС╝џудЈуЦЅТї»УѕѕсЃ╗УЕджеЊсѓ╗сЃ│сѓ┐сЃ╝сЂИсђїС╗ІУГиудЈуЦЅтБФуЎ╗жї▓Уе╝сђЇсЂ«тцЅТЏ┤ТЅІуХџсЂЇсѓњУАїсЂє
сЂЮсЂ«С╗ќсЂ«С╗ІУГиУЂитЊАуГЅ
СИіУеўС╗ЦтцќсЂ«С╗ІУГиудЈуЦЅтБФсђЂсЃЏсЃ╝сЃасЃўсЃФсЃЉсЃ╝уГЅсЂ«С╗ІУГиУЂитЊАсђЂуЅ╣тѕЦТћ»ТЈ┤тГдТаАТЋЎтЊАуГЅсЂ«Тќ╣ сЂфсЂЕ
сђїтќђуЌ░тљИт╝ЋуГЅуаћС┐«сђЇсѓњС┐«С║єсЂЌсђїС┐«С║єУе╝ТўјТЏИсђЇсЂ«С║цС╗ўсѓњтЈЌсЂЉсѓІ
жЃйжЂЊт║юуюїсЂИсђїС┐«С║єУе╝ТўјТЏИсђЇсѓњТи╗С╗ўсЂЌсђїУфЇт«џуЅ╣т«џУАїуѓ║ТЦГтІЎтЙЊС║ІУђЁУфЇт«џУе╝сђЇсЂ«ућ│УФІсѓњУАїсЂє
сђїУфЇт«џуЅ╣т«џУАїуѓ║ТЦГтІЎтЙЊС║ІУђЁУфЇт«џУе╝сђЇсЂ«С║цС╗ўсѓњтЈЌсЂЉсѓІ
Т│ЋтѕХтїќтЅЇсЂФСИђт«џсЂ«УдЂС╗ХсЂ«СИІсЂДсЂЪсѓЊсЂ«тљИт╝ЋуГЅсЂ«ТЈљСЙЏсѓњУАїсЂБсЂдсЂёсЂЪТќ╣№╝ѕухїжЂјТјфуй«т»ЙУ▒АУђЁ№╝ЅсЂ»сђЂжЃйжЂЊт║юуюїсЂФУе╝ТўјТЅІуХџсЂЇсѓњУАїсЂБсЂЪсЂ«сЂАсђїУфЇт«џуЅ╣т«џУАїуѓ║ТЦГтІЎтЙЊС║ІУђЁУфЇт«џУе╝сђЇсЂїС║цС╗ўсЂЋсѓїсђЂУфЇт«џсЂЋсѓїсЂЪУАїуѓ║сЂФжЎљт«џсЂЌсЂдт╝ЋсЂЇуХџсЂЇУАїсЂєсЂЊсЂесЂїсЂДсЂЇсЂЙсЂЎсђѓ
т«ЪТќйсЂДсЂЇсѓІС║ІТЦГУђЁ
С╗ІУГиУЂитЊАуГЅсЂїУфЇт«џсѓњтЈЌсЂЉсЂдсЂёсЂдсѓѓсђЂсЂЪсѓЊсЂ«тљИт╝ЋуГЅсѓњсЂЕсЂЊсЂДсѓѓУАїсЂѕсѓІсѓЈсЂЉсЂДсЂ»сЂѓсѓісЂЙсЂЏсѓЊсђѓ
С╗ІУГиУЂитЊАуГЅсЂФсѓѕсѓІсЂЪсѓЊсЂ«тљИт╝ЋуГЅсѓњТЦГсЂесЂЌсЂдУАїсЂєсЂЪсѓЂсЂФсЂ»сђЂС║ІТЦГУђЁсЂїсђїуЎ╗жї▓С║ІТЦГУђЁ№╝ѕуЎ╗жї▓тќђуЌ░тљИт╝ЋуГЅС║ІТЦГУђЁсЃ╗уЎ╗жї▓уЅ╣т«џУАїуѓ║С║ІТЦГУђЁ№╝ЅсђЇсЂесЂфсѓІсЂЊсЂесЂїт┐ЁУдЂсЂДсЂЎсђѓ№╝ѕРђ╗тї╗уЎѓТЕЪжќбсЂ»т»ЙУ▒Атцќ№╝Ѕ
тЙЊС║ІУђЁсЂФС╗ІУГиудЈуЦЅтБФсЂ«сЂёсѓІС║ІТЦГУђЁсѓњсђїуЎ╗жї▓тќђуЌ░тљИт╝ЋуГЅС║ІТЦГУђЁсђЇсђЂтЙЊС║ІУђЁсЂїС╗ІУГиУЂитЊАуГЅсЂ«сЂ┐сЂ«С║ІТЦГУђЁсѓњсђїуЎ╗жї▓уЅ╣т«џУАїуѓ║С║ІТЦГУђЁсђЇсЂесЂёсЂёсЂЙсЂЎсђѓ
ТЅђт▒ъсЂЎсѓІС║ІТЦГТЅђсЂїуЎ╗жї▓сѓњсЂЌсЂдсЂёсЂфсЂёта┤тљѕсЂ»сђЂсЂЮсЂ«С║ІТЦГТЅђсЂДсЂЪсѓЊсЂ«тљИт╝ЋуГЅсЂ«ТЦГтІЎсѓњУАїсЂєсЂЊсЂесЂїсЂДсЂЇсЂЙсЂЏсѓЊсђѓ уЎ╗жї▓С║ІТЦГУђЁсЂесЂфсѓІсЂЪсѓЂсЂФсЂ»сђЂжЃйжЂЊт║юуюїуЪЦС║ІсЂФсђЂС║ІТЦГТЅђсЂћсЂесЂФСИђт«џсЂ«уЎ╗жї▓УдЂС╗Х№╝ѕуЎ╗жї▓тЪ║Т║ќ№╝ЅсѓњТ║ђсЂЪсЂЌсЂдсЂёсѓІТЌесЂФсЂцсЂёсЂдуЎ╗жї▓ућ│УФІсѓњУАїсЂєт┐ЁУдЂсЂїсЂѓсѓісЂЙсЂЎсђѓ
| т»ЙУ▒АсЂесЂфсѓІТќйУеГсЃ╗С║ІТЦГТЅђуГЅсЂ«СЙІ |
|---|
| РЌ»С╗ІУГижќбС┐ѓТќйУеГ №╝ѕуЅ╣тѕЦжціУГиУђЂС║║сЃЏсЃ╝сЃасЃ╗УђЂС║║С┐ЮтЂЦТќйУеГсЃ╗сѓ░сЃФсЃ╝сЃЌсЃЏсЃ╝сЃасЃ╗ТюЅТќЎУђЂС║║сЃЏсЃ╝сЃасЃ╗жђџТЅђС╗ІУГисЃ╗уЪГТюЪтЁЦТЅђућЪТ┤╗С╗ІУГисЂфсЂЕ№╝Ѕ РЌ»жџют«│УђЁТћ»ТЈ┤ТќйУеГуГЅ №╝ѕућЪТ┤╗С╗ІУГисЃ╗сѓ░сЃФсЃ╝сЃЌсЃЏсЃ╝сЃасЂфсЂЕ№╝Ѕ РЌ»тюет«Ё №╝ѕУефтЋЈС╗ІУГисЃ╗жЄЇт║дУефтЋЈС╗ІУГисЂфсЂЕ№╝Ѕ РЌ»уЅ╣тѕЦТћ»ТЈ┤тГдТаА Рђ╗тї╗уЎѓТЕЪжќбсЂ»т»ЙУ▒Атцќ |
ТгАсЂ«сЃџсЃ╝сѓИ№йютќђуЌ░тљИт╝ЋуГЅуаћС┐«№╝ѕсЂЪсѓЊсЂ«тљИт╝ЋуГЅсЂ«уаћС┐«№╝ЅсЂФсЂцсЂёсЂдсђђсђђ
т«ХТЌЈсЂ«С╗ІУГисѓњсЂЇсЂБсЂІсЂЉсЂФС╗ІУГиудЈуЦЅтБФсЃ╗уцЙС╝џудЈуЦЅСИ╗С║ІС╗╗ућеУ│ЄТа╝сѓњтЈќтЙЌсђѓуЈЙтюесЂ»сЃЕсѓцсѓ┐сЃ╝сђѓТЌЦсђЁсЂ«Тџ«сѓЅсЂЌсЂФтй╣уФІсЂцУ║ФУ┐ЉсЂфТЃЁта▒сѓњсЂіС╝ЮсЂѕсЂЎсѓІсЂ╣сЂЈсђЂС╗ІУГисЃ╗тї╗уЎѓсЃ╗уЙјт«╣сЃ╗сѓФсЃФсЃЂсЃБсЃ╝сЂфсЂЕт╣Ёт║ЃсЂёсѓИсЃБсЃ│сЃФсЂ«УеўС║ІсѓњтЪиуГєСИГсђѓ
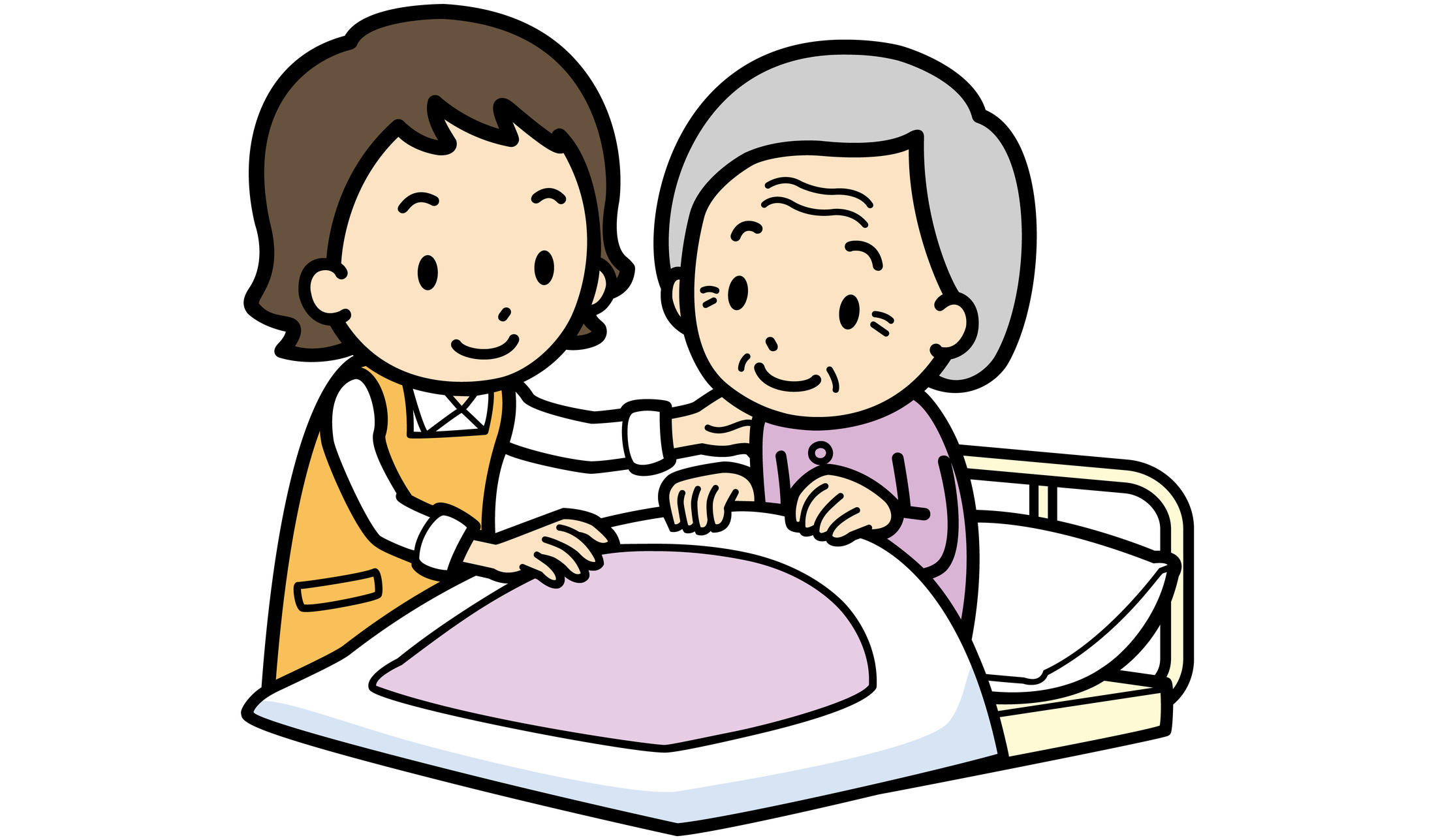
FacebookсЃџсЃ╝сѓИсЂД
ТюђТќ░УеўС║ІжЁЇС┐А№╝Ђ№╝Ђ
 сЃгсѓфсЃЈсѓџсЃгсѓ╣21сѓ»сѓЎсЃФсЃ╝сЃЋсѓџсЂ«С╗ІУГисѓхсЃ╝сЃњсѓЎсѓ╣
сЃгсѓфсЃЈсѓџсЃгсѓ╣21сѓ»сѓЎсЃФсЃ╝сЃЋсѓџсЂ«С╗ІУГисѓхсЃ╝сЃњсѓЎсѓ╣