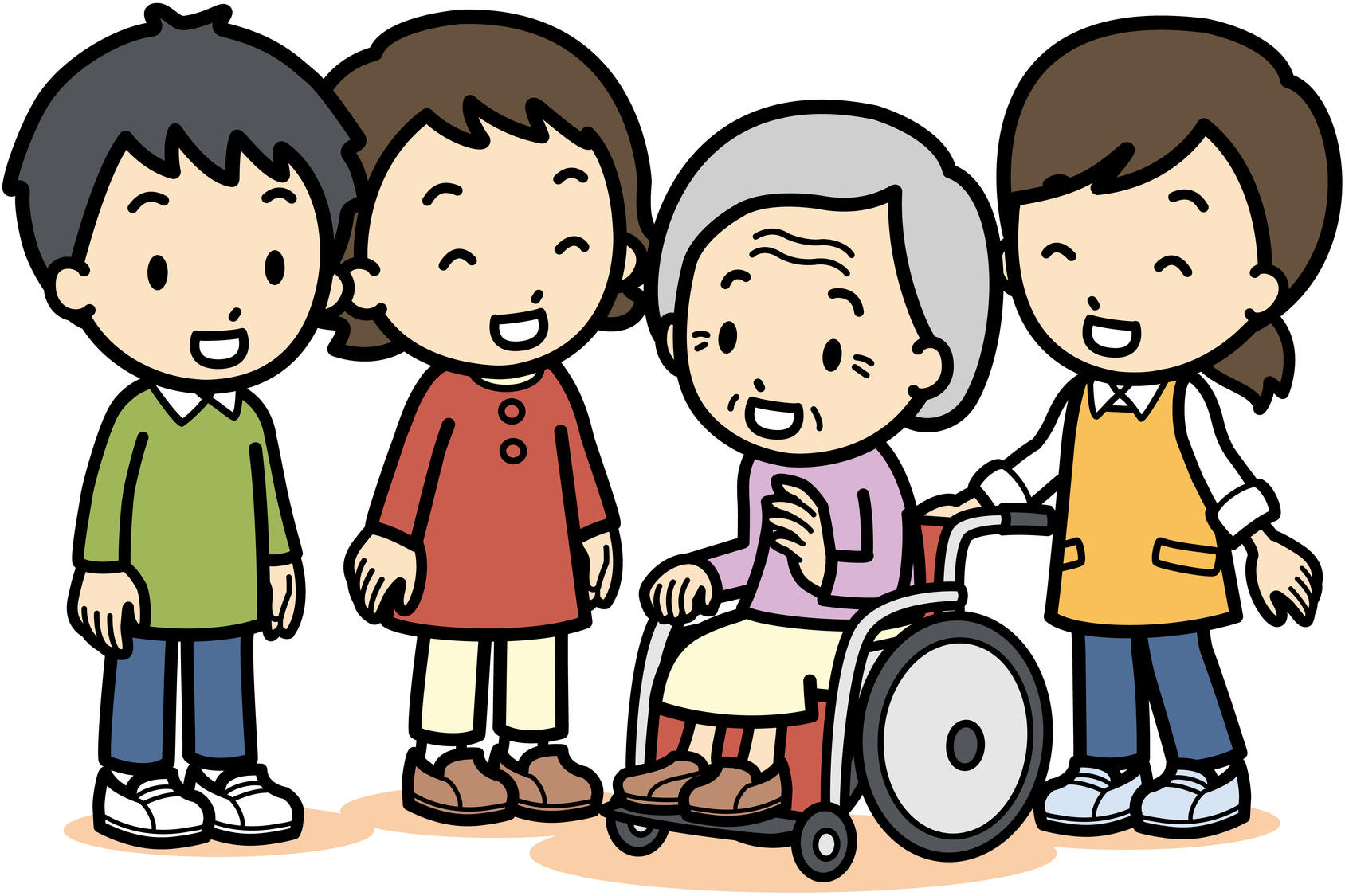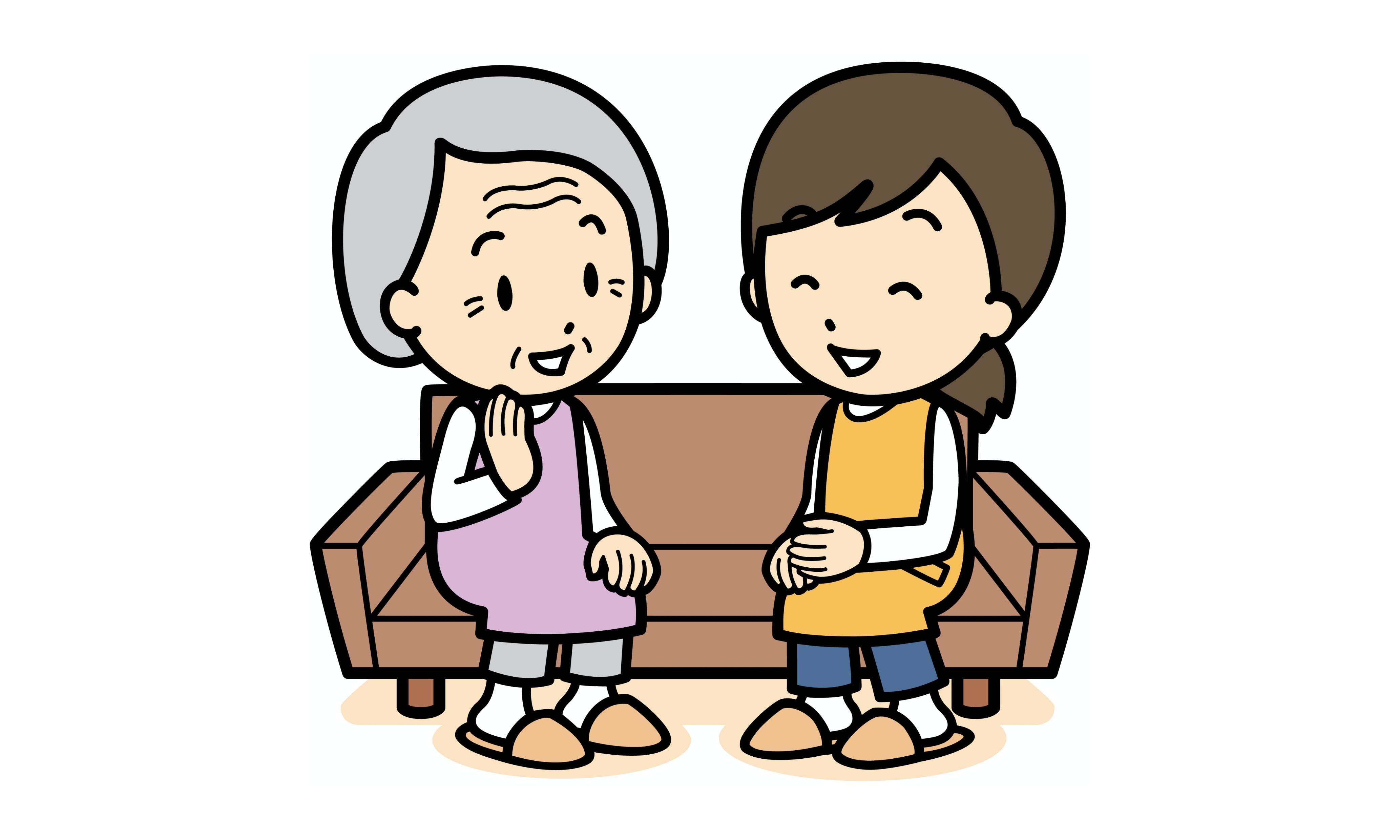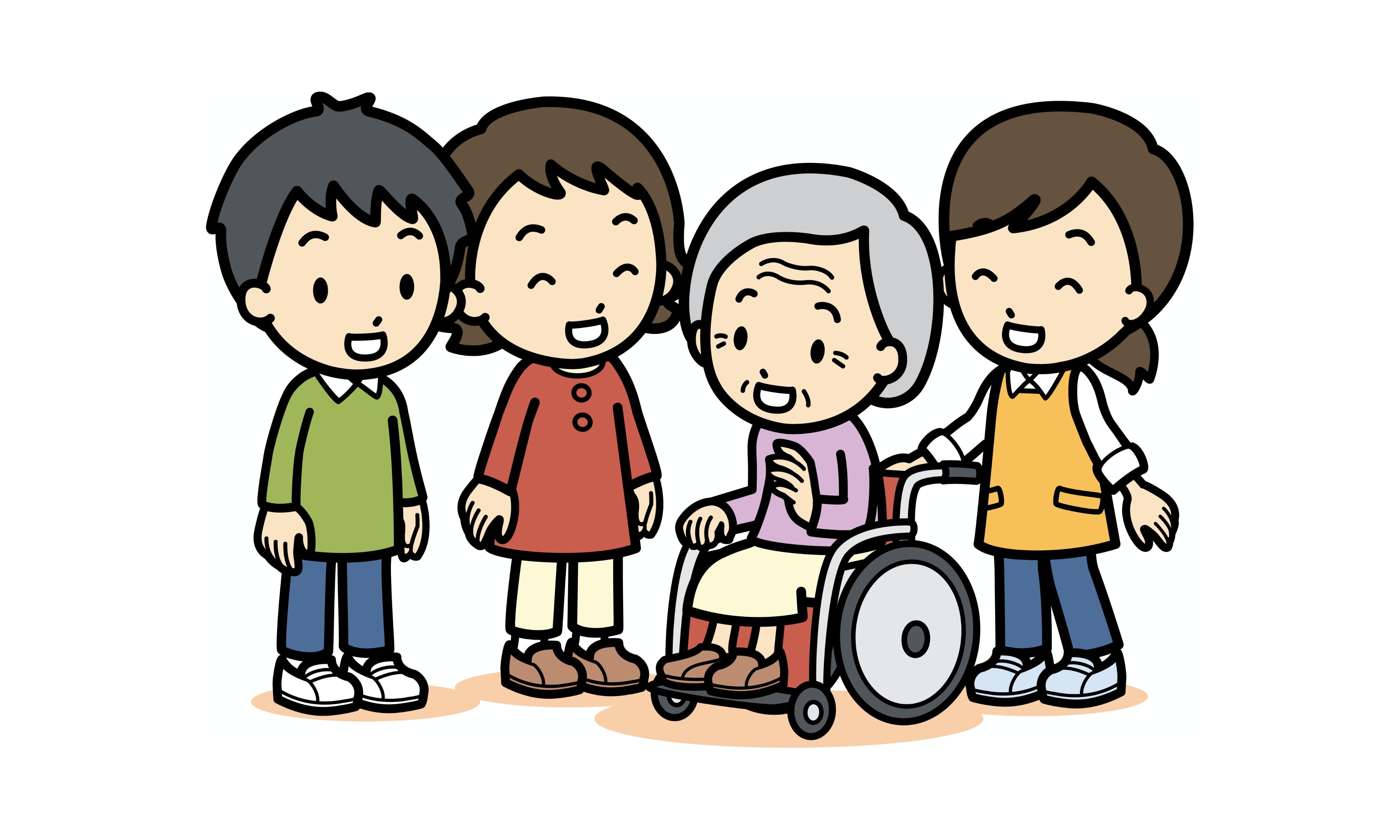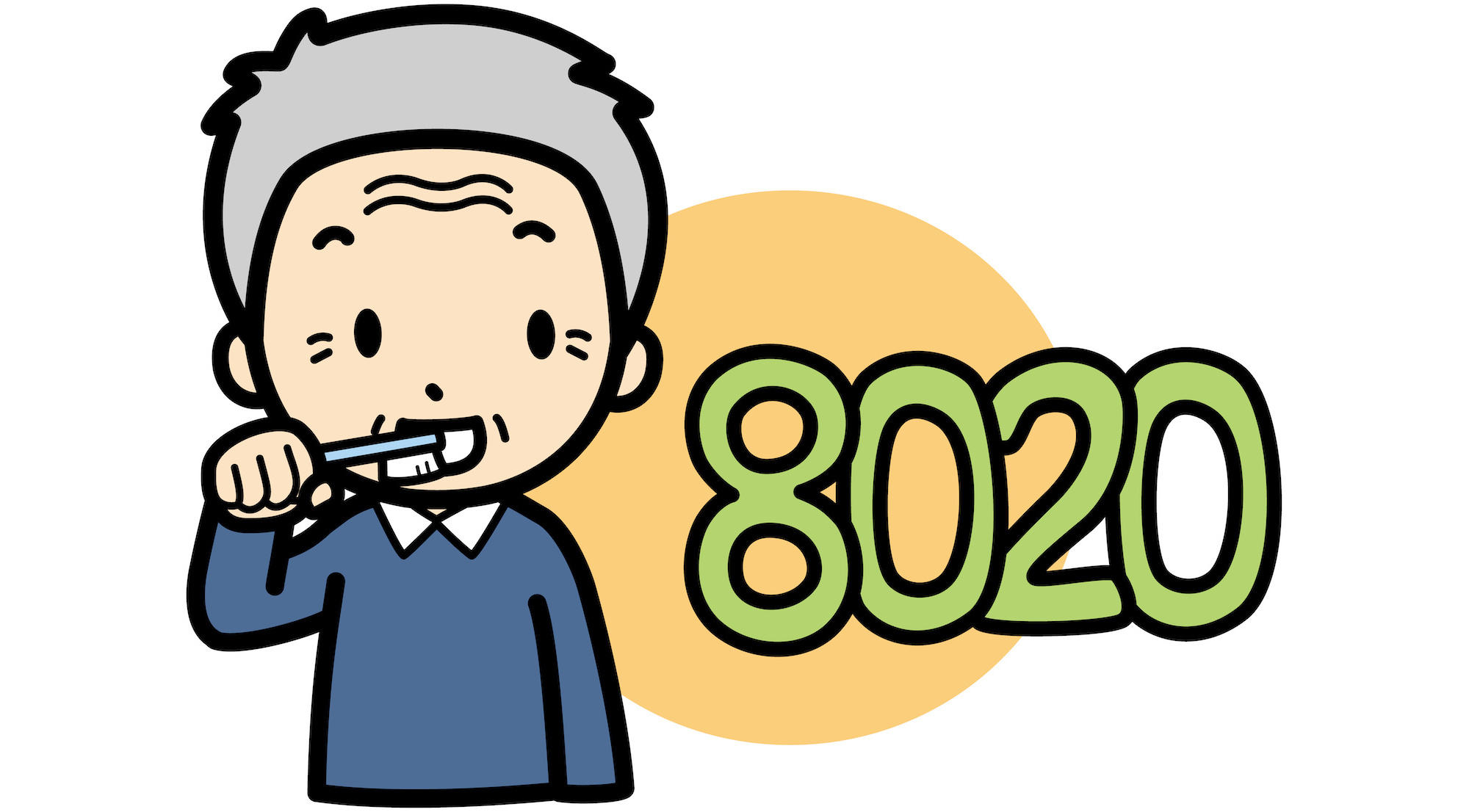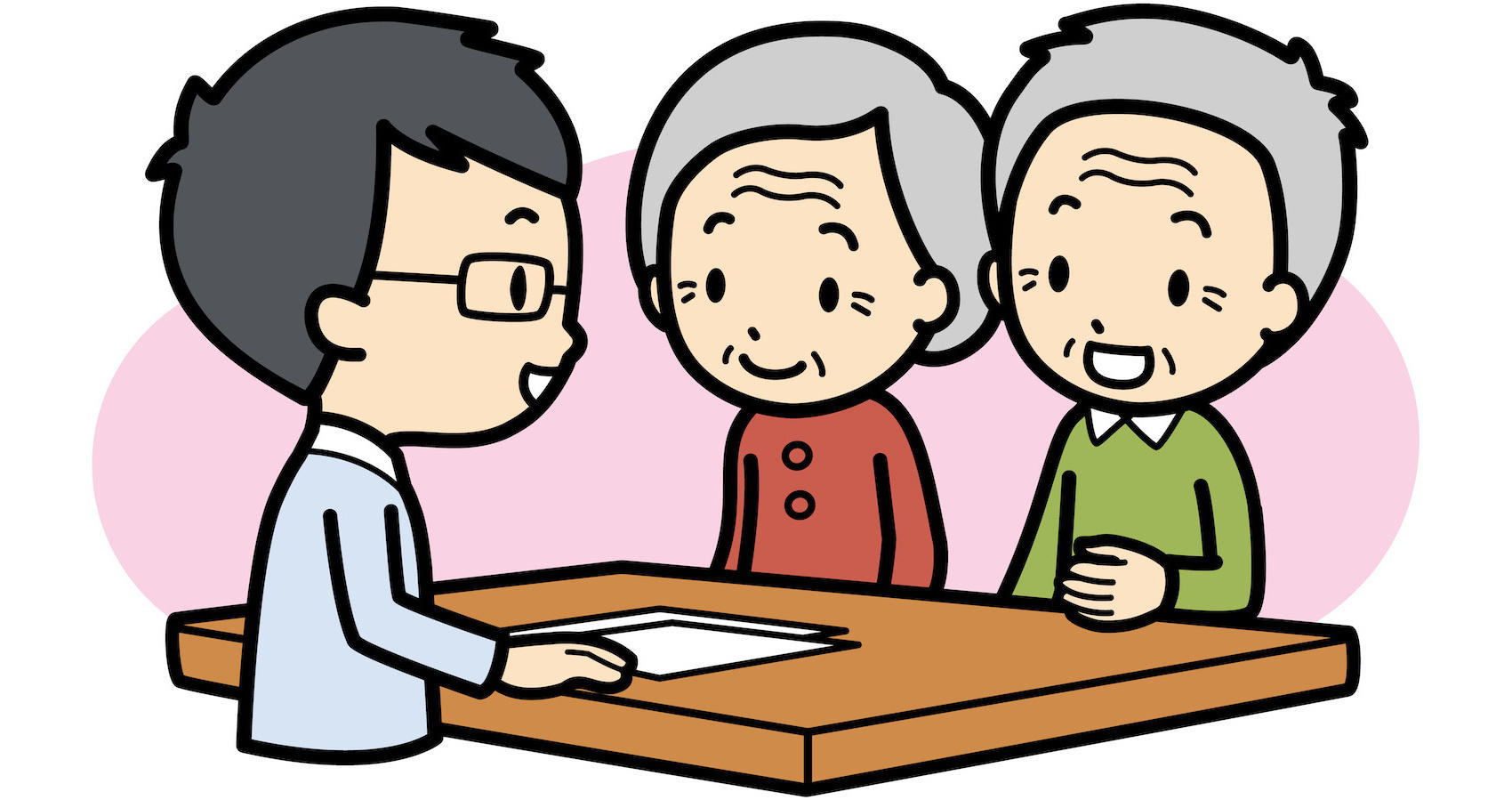дїЛи≠ЈгБЃдЊњеИ©еЄЦгГИгГГгГЧгБЄжИїгВЛ
дїЛи≠ЈдњЭйЩЇгБЂгБКгБСгВЛгАМзЙєеЃЪзЦЊзЧЕгАНгБ®гБѓ
гАМеОЪзФЯеКіеГНе§ІиЗ£гБМеЃЪгВБгВЛзЦЊзЧЕз≠ЙгАНгБ®гБѓ
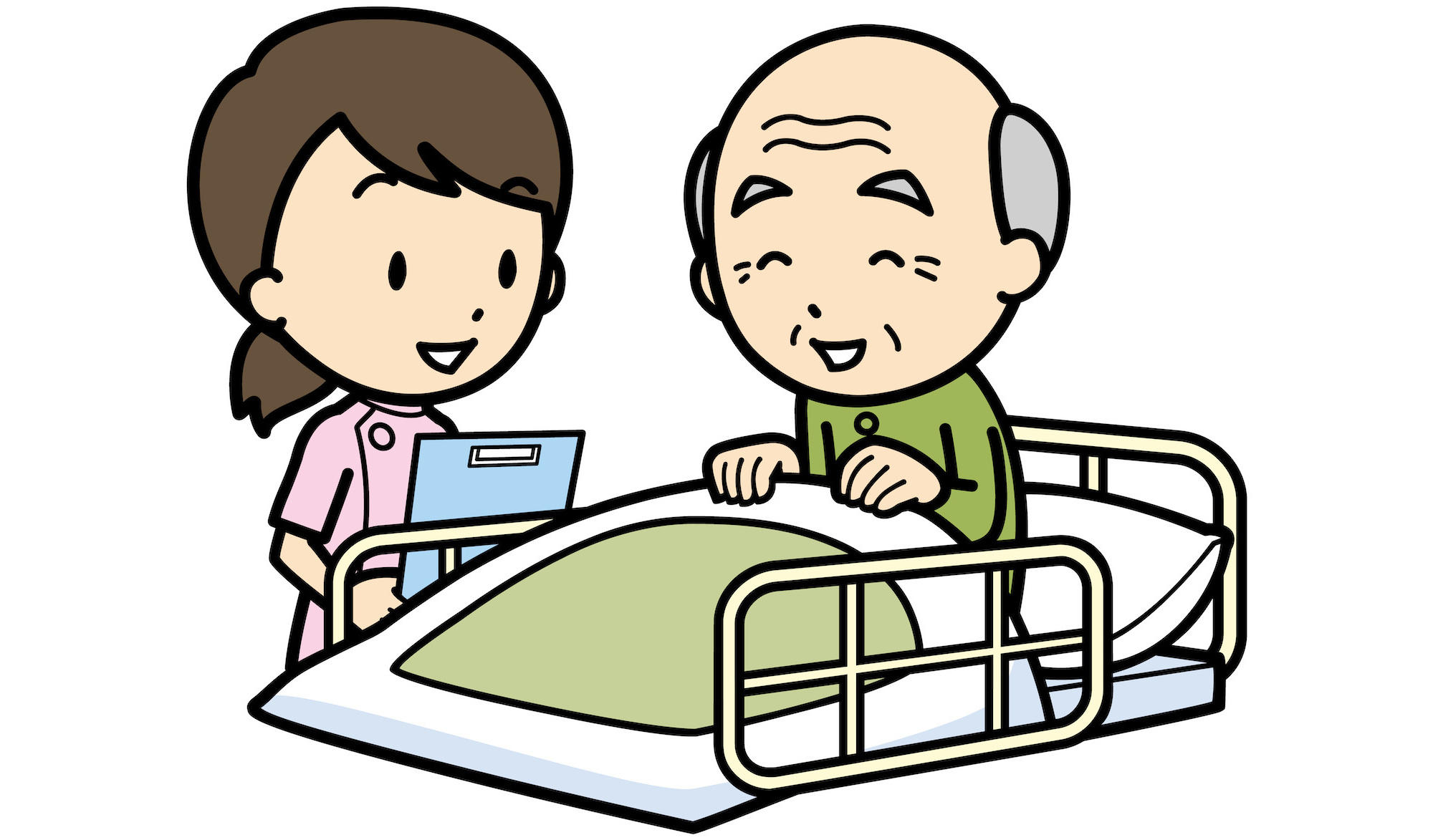
дїЛи≠ЈдњЭйЩЇгБЃеѓЊи±°гБ®гБ™гВЛгАМзЙєеЃЪзЦЊзЧЕгАНгБЃгБїгБЛгБЂгАБгАМеОЪзФЯеКіеГНе§ІиЗ£гБМеЃЪгВБгВЛзЦЊзЧЕз≠ЙгАНгБ®гБДгБЖгВВгБЃгБМгБВгВКгБЊгБЩгАВгАМеОЪзФЯеКіеГНе§ІиЗ£гБЃеЃЪгВБгВЛзЦЊзЧЕз≠ЙгАНгБЃе†іеРИгБѓгАБи®™еХПзЬЛи≠ЈгВТеПЧгБСгВЛгБУгБ®гБМгБІгБНгБЊгБЩгАВ
и®™еХПзЬЛи≠ЈгБЃеИ©зԮ嚥жЕЛгБЂгБѓгАМеМїзЩВдњЭйЩЇгАНгБ®гАМдїЛи≠ЈдњЭйЩЇгАНгБЃ2з®Ѓй°ЮгБМгБВгВКгАБи¶БдїЛи≠Ји™НеЃЪгВТеПЧгБСгБ¶гБДгВЛе†іеРИгБѓгАМдїЛи≠ЈдњЭйЩЇгАНгБЂгВИгВЛи®™еХПзЬЛи≠ЈгВТеИ©зФ®гБЩгВЛгБУгБ®гБЂгБ™гВКгБЊгБЩгАВ
гБЧгБЛгБЧгАБеОЪзФЯеКіеГНе§ІиЗ£гБМеЃЪгВБгВЛзЦЊзЧЕз≠ЙгБЂи©≤ељУгБЩгВЛе†іеРИгБѓгАБи¶БдїЛи≠Ји™НеЃЪгВТеПЧгБСгБ¶дїЛи≠ЈдњЭйЩЇгВТеИ©зФ®гБЧгБ¶гБДгВЛжЦєгБІгВВгАМеМїзЩВдњЭйЩЇгАНгБЂгВИгВЛи®™еХПзЬЛи≠ЈгВТеИ©зФ®гБЩгВЛгБУгБ®гБЂгБ™гВКгБЊгБЩгАВ
гАМдїЛи≠ЈдњЭйЩЇгАНгБЃи®™еХПзЬЛи≠ЈгБЂгБѓеЫЮжХ∞гБ™гБ©гБЃеИ©зФ®еИґйЩРгБМгБВгВКгБЊгБЫгВУгБМгАБгАМеМїзЩВдњЭйЩЇгАНгБЃи®™еХПзЬЛи≠ЈгБЂгБѓеЯЇжЬђзЪДгБЂгАМйА±3жЧ•гБЊгБІгГї1жЧ•гБЂ1еЫЮгГї1гВЂжЙАгБЃи®™еХПзЬЛи≠ЈгВєгГЖгГЉгВЈгГІгГ≥гБЛгВЙгАНгБ®гБДгБЖеИ©зФ®еИґйЩРгБМгБВгВКгБЊгБЩгАВ
гБЧгБЛгБЧгАБеОЪзФЯеКіеГНе§ІиЗ£гБМеЃЪгВБгВЛзЦЊзЧЕз≠ЙгБЂи©≤ељУгБЩгВЛе†іеРИгБѓгАМйА±4жЧ•дї•дЄКгГї1жЧ•гБЂи§ЗжХ∞еЫЮгГї2гВЂжЙАдї•дЄКгБЃи®™еХПзЬЛи≠ЈгВєгГЖгГЉгВЈгГІгГ≥гБЛгВЙгАНгБЃеИ©зФ®гВВеПѓиГљгБІгБЩгАВ
еОЪзФЯеКіеГНе§ІиЗ£гБМеЃЪгВБгВЛзЦЊзЧЕз≠Й
- вС† жЬЂжЬЯгБЃжВ™жАІиЕЂзШН
вС° е§ЪзЩЇжАІз°ђеМЦзЧЗ
вСҐ йЗНзЧЗз≠ЛзД°еКЫзЧЗ
вС£ гВєгГҐгГ≥
вС§ з≠ЛиРОзЄЃжАІеБізіҐз°ђеМЦзЧЗпЉИALSпЉЙ
вС• иДКйЂДе∞ПиД≥е§ЙжАІзЧЗ
вС¶ гГПгГ≥гГБгГ≥гГИгГ≥зЧЕ
вСІ йА≤и°МжАІз≠ЛгВЄгВєгГИгГ≠гГХгВ£гГЉзЧЗ
вС® гГСгГЉгВ≠гГ≥гВљгГ≥зЧЕйЦҐйА£зЦЊжВ£пЉИйА≤и°МжАІж†ЄдЄКжАІйЇїзЧЇгАБе§ІиД≥зЪЃи≥™еЯЇеЇХж†Єе§ЙжАІзЧЗгАБгГСгГЉгВ≠гГ≥гВљгГ≥зЧЕпЉИгГЫгГЉгВ®гГ≥гГїгГ§гГЉгГЂгБЃйЗНзЧЗеЇ¶еИЖй°ЮгБМгВєгГЖгГЉгВЄ3дї•дЄКгБІгБВгБ£гБ¶гАБзФЯжіїж©ЯиГљйЪЬеЃ≥еЇ¶гБМвЕ°еЇ¶гБЊгБЯгБѓвЕҐеЇ¶гБЃгВВгБЃгБЂйЩРгВЛгАВпЉЙпЉЙ
вС© е§Ъз≥їзµ±иРОзЄЃзЧЗпЉИзЈЪжЭ°дљУйїТи≥™е§ЙжАІзЧЗгАБгВ™гГ™гГЉгГЦж©Ле∞ПиД≥иРОзЄЃзЧЗгБКгВИгБ≥гВЈгГ£гВ§гГїгГЙгГђгГЉгВђгГЉзЧЗеАЩзЊ§пЉЙ
вС™ гГЧгГ™гВ™гГ≥зЧЕ
вСЂ дЇЬжА•жАІз°ђеМЦжАІеЕ®иД≥зВО
вСђ гГ©гВ§гВљгВЊгГЉгГ†зЧЕ
вС≠ еЙѓиЕОзЩљи≥™гВЄгВєгГИгГ≠гГХгВ£гГЉ
вСЃ иДКйЂДжАІз≠ЛиРОзЄЃзЧЗ
вСѓ зРГиДКйЂДжАІз≠ЛиРОзЄЃзЧЗ
вС∞ жЕҐжАІзВОзЧЗжАІиД±йЂДжАІе§ЪзЩЇз•ЮзµМзВО
вС± еЊМ姩жАІеЕНзЦЂдЄНеЕ®зЧЗеАЩзЊ§
вС≤ й†ЄйЂДжРНеВЈ
вС≥ дЇЇеЈ•еСЉеРЄеЩ®гВТдљњзФ®гБЧгБ¶гБДгВЛзКґжЕЛ
и¶БдїЛи≠ЈпЉИи¶БжФѓжПіпЉЙи™НеЃЪгБЃзФ≥иЂЛгБЂгБ§гБДгБ¶

дїЛи≠ЈдњЭйЩЇгБЃгВµгГЉгГУгВєгВТеИ©зФ®гБЩгВЛгБЯгВБгБЂгБѓгАБи¶БдїЛи≠ЈпЉИи¶БжФѓжПіпЉЙи™НеЃЪгБЃзФ≥иЂЛгБМењЕи¶БгБІгБЩгАВ
65ж≠≥дї•дЄКгБЃжЦєпЉИзђђпЉСеϣ襀дњЭйЩЇиАЕпЉЙгБМеѓЊи±°гБІгБЩгБМгАБиАБеМЦгБЂдЉігБЖзЙєеЃЪзЦЊзЧЕпЉИ16з®Ѓй°ЮпЉЙгБМеОЯеЫ†гБІдїЛи≠ЈпЉИжФѓжПіпЉЙгБМењЕи¶БгБ®гБ™гБ£гБЯ40ж≠≥дї•дЄК65ж≠≥жЬ™жЇАгБЃжЦєпЉИзђђ2еϣ襀дњЭйЩЇиАЕпЉЙгВВзФ≥иЂЛгБМгБІгБНгБЊгБЩгАВ
зФ≥иЂЛиАЕгБМзђђ2еϣ襀дњЭйЩЇиАЕгБЃе†іеРИгБѓгАБдЄїж≤їеМїжДПи¶ЛжЫЄгБЃи®ШиЉЙеЖЕеЃєгБЂеЯЇгБ•гБДгБ¶гАБеЄВеМЇзФЇжЭСгБ™гБ©гБЂзљЃгБЛгВМгВЛдїЛи≠Ји™НеЃЪеѓ©жЯїдЉЪгБМгАМзЙєеЃЪзЦЊзЧЕгАНгБЂи©≤ељУгБЩгВЛгБЛгБ©гБЖгБЛгБЃзҐЇи™НгВТи°МгБДгБЊгБЩгАВ
и¶БдїЛи≠Ји™НеЃЪгБЃжµБгВМ
вС† зФ≥иЂЛ
гБКдљПгБЊгБДгБЃеЄВеМЇзФЇжЭСгБЂзФ≥иЂЛгБЧгБЊгБЩгАВи¶БдїЛи≠Ји™НеЃЪгБЂгБЛгБЛгВПгВЛи≤їзФ®и≤†жЛЕгБѓгБВгВКгБЊгБЫгВУгАВ
вС° и™НеЃЪи™њжЯїгГїеИ§еЃЪ
и®™еХПгБЂгВИгВЛи™НеЃЪи™њжЯїгВДдїЛи≠Ји™НеЃЪеѓ©жЯїдЉЪгБЂгВИгВЛеѓ©жЯїгБ™гБ©гБМи°МгВПгВМгБЊгБЩгАВ
вСҐ и™НеЃЪзµРжЮЬгБЃйАЪзЯ•
еЄВеМЇзФЇжЭСгБМи¶БдїЛи≠ЈзКґжЕЛеМЇеИЖгВТи™НеЃЪгБЧгБЊгБЩгАВзФ≥иЂЛжЧ•гБЛгВЙгБКгВИгБЭпЉСгВЂжЬИз®ЛеЇ¶гБІи™НеЃЪзµРжЮЬгБМйАЪзЯ•гБХгВМгБЊгБЩгАВ
вС£ гВµгГЉгГУгВєгБЃеИ©зФ®
и¶БдїЛи≠ЈгБЊгБЯгБѓи¶БжФѓжПігБЂи™НеЃЪгБХгВМгБЯжЦєгБѓгАБгВ±гВҐгГЧгГ©гГ≥пЉИдїЛи≠ЈгВµгГЉгГУгВєи®ИзФїпЉЙгВТдљЬжИРгБЧгАБгВ±гВҐгГЧгГ©гГ≥гБЂеЯЇгБ•гБДгБЯдїЛи≠ЈгВµгГЉгГУгВєгВТеИ©зФ®гБЧгБЊгБЩгАВ
вАїдїЛи≠ЈгВµгГЉгГУгВєиЗ™дљУгБѓгАБзФ≥иЂЛжЧ•гБЛгВЙеИ©зФ®гБЩгВЛгБУгБ®гБМеПѓиГљгБІгБЩгБМгАБи™НеЃЪгБХгВМгБ™гБЛгБ£гБЯе†іеРИгБѓ10еЙ≤гБЃи≤†жЛЕгБ®гБ™гВКгБЊгБЩгАВ
и¶БдїЛи≠ЈпЉИи¶БжФѓжПіпЉЙи™НеЃЪгБЃзФ≥иЂЛгБЂгБ§гБДгБ¶и©≥гБЧгБПгБѓгАБгБКдљПгБЊгБДгБЃеЄВеМЇзФЇжЭСгБЂгБКеХПгБДеРИгВПгБЫгБПгБ†гБХгБДгАВ
вЦЉйЦҐйА£и®ШдЇЛ
и¶БдїЛи≠Ји™НеЃЪгБ®гБѓпЉЯдїЛи≠ЈдњЭйЩЇгБЃи™НеЃЪи™њжЯїгВТеПЧгБСгВЛйЪЫгБЃгГЭгВ§гГ≥гГИ
гАМи¶БжФѓжПігАНгБ®гАМи¶БдїЛи≠ЈгАНгБЃйБХгБДгБѓпЉЯгБ©гВУгБ™гВµгГЉгГУгВєгБМеИ©зФ®гБІгБНгВЛгБЃпЉЯ
еЫ≥иІ£гБІгВПгБЛгВЛпЉБдїЛи≠ЈдњЭйЩЇеИґеЇ¶гБЃдїХзµДгБњ
вЦЉеПВиАГ
еОЪзФЯеКіеГНзЬБгАМзЙєеЃЪзЦЊзЧЕгБЃйБЄеЃЪеЯЇжЇЦгБЃиАГгБИжЦєгАН
еОЪзФЯеКіеГНзЬБгАМзЙєеЃЪзЦЊзЧЕгБЂгБЛгБЛгВЛи®ЇжЦ≠еЯЇжЇЦгАН
йЫ£зЧЕжГЕ冱гВїгГ≥гВњгГЉ
еЃґжЧПгБЃдїЛи≠ЈгВТгБНгБ£гБЛгБСгБЂдїЛи≠Јз¶Пз•Йе£ЂгГїз§ЊдЉЪз¶Пз•ЙдЄїдЇЛдїїзФ®и≥Зж†ЉгВТеПЦеЊЧгАВзПЊеЬ®гБѓгГ©гВ§гВњгГЉгАВжЧ•гАЕгБЃжЪЃгВЙгБЧгБЂељєзЂЛгБ§иЇЂињСгБ™жГЕ冱гВТгБКдЉЭгБИгБЩгВЛгБєгБПгАБдїЛи≠ЈгГїеМїзЩВгГїзЊОеЃєгГїгВЂгГЂгГБгГ£гГЉгБ™гБ©еєЕеЇГгБДгВЄгГ£гГ≥гГЂгБЃи®ШдЇЛгВТеЯЈз≠ЖдЄ≠гАВ

FacebookгГЪгГЉгВЄгБІ
жЬАжЦ∞и®ШдЇЛйЕНдњ°пЉБпЉБ
 гГђгВ™гГПгВЪгГђгВє21гВѓгВЩгГЂгГЉгГХгВЪгБЃдїЛи≠ЈгВµгГЉгГТгВЩгВє
гГђгВ™гГПгВЪгГђгВє21гВѓгВЩгГЂгГЉгГХгВЪгБЃдїЛи≠ЈгВµгГЉгГТгВЩгВє