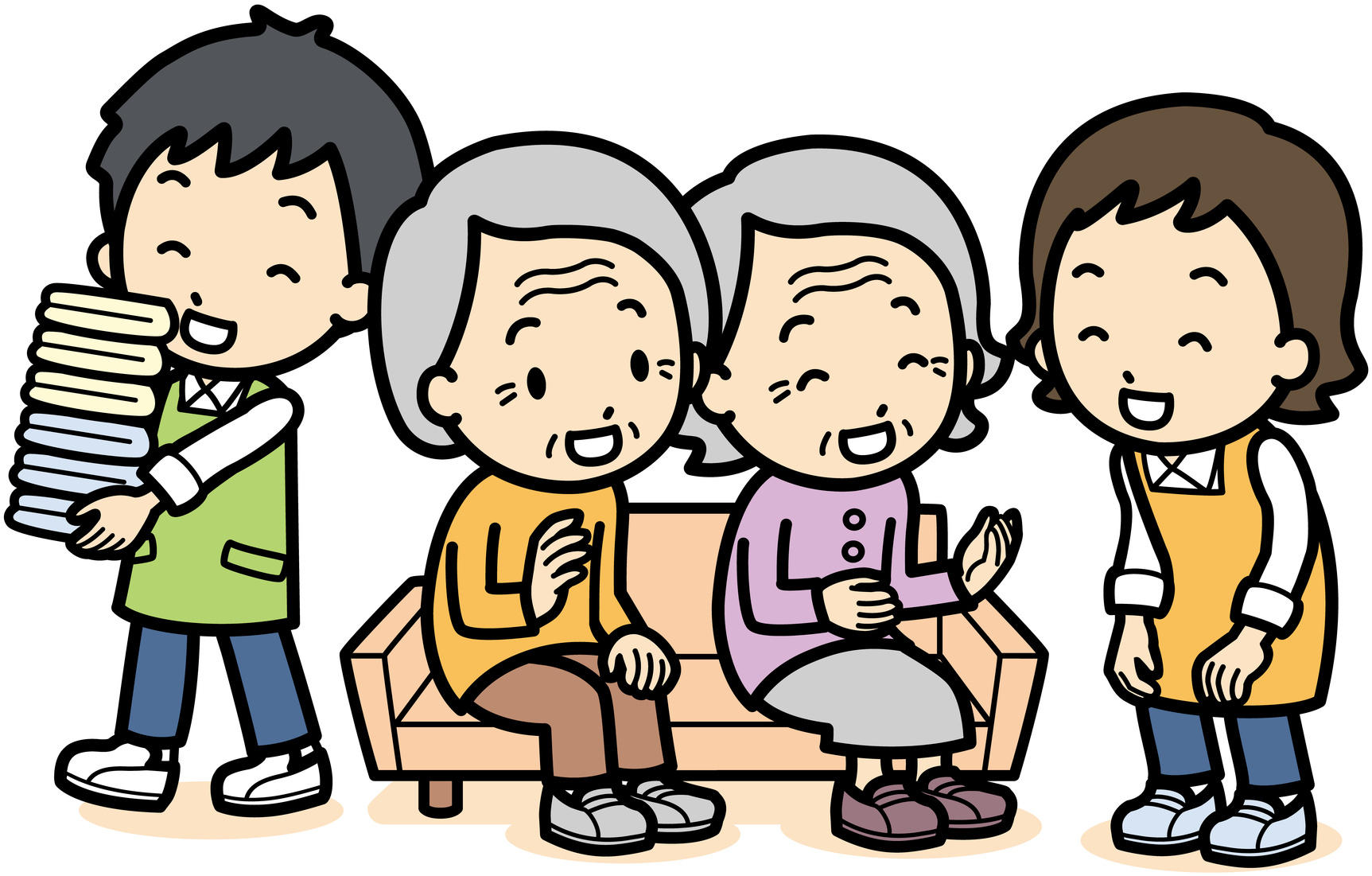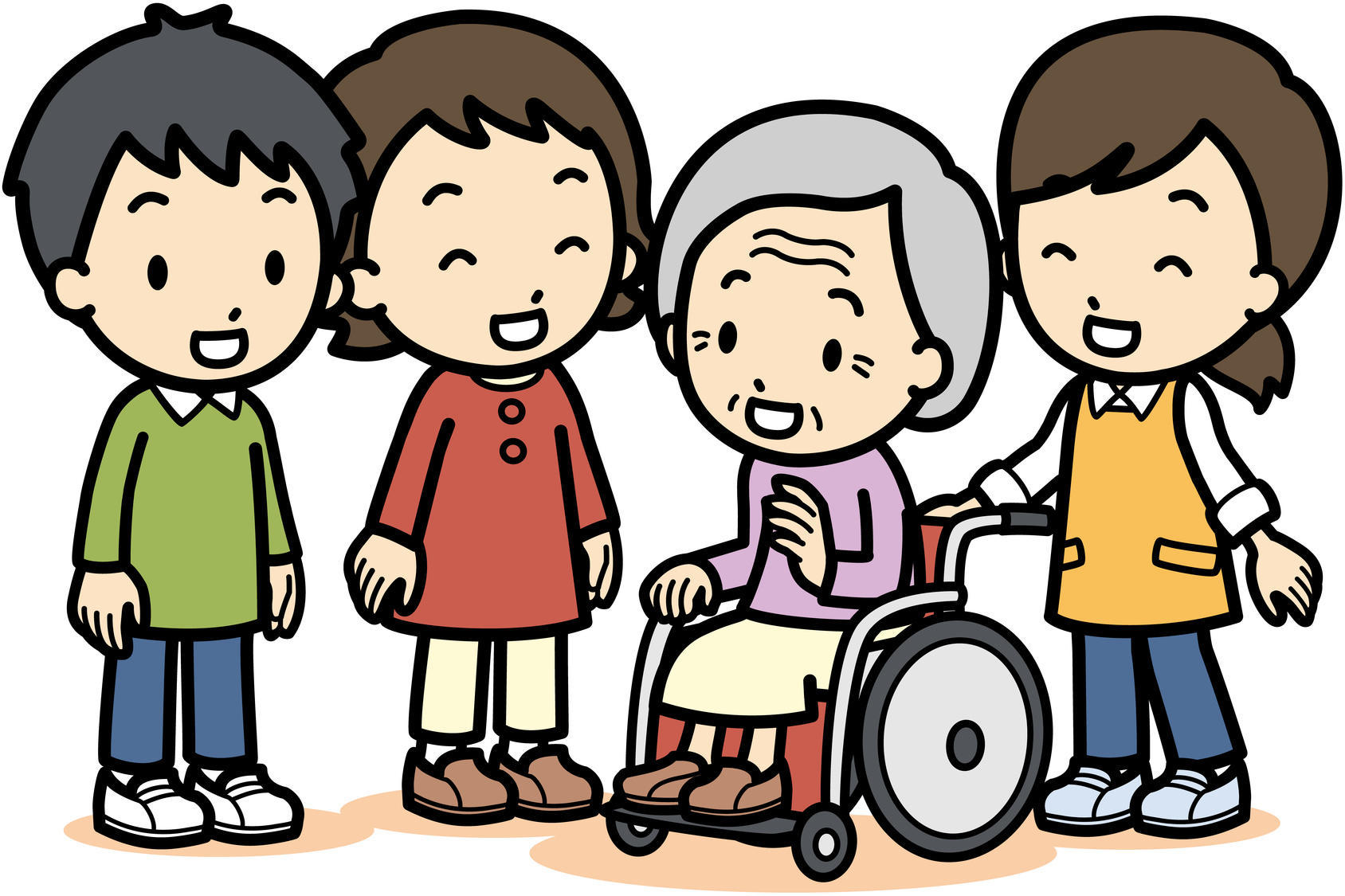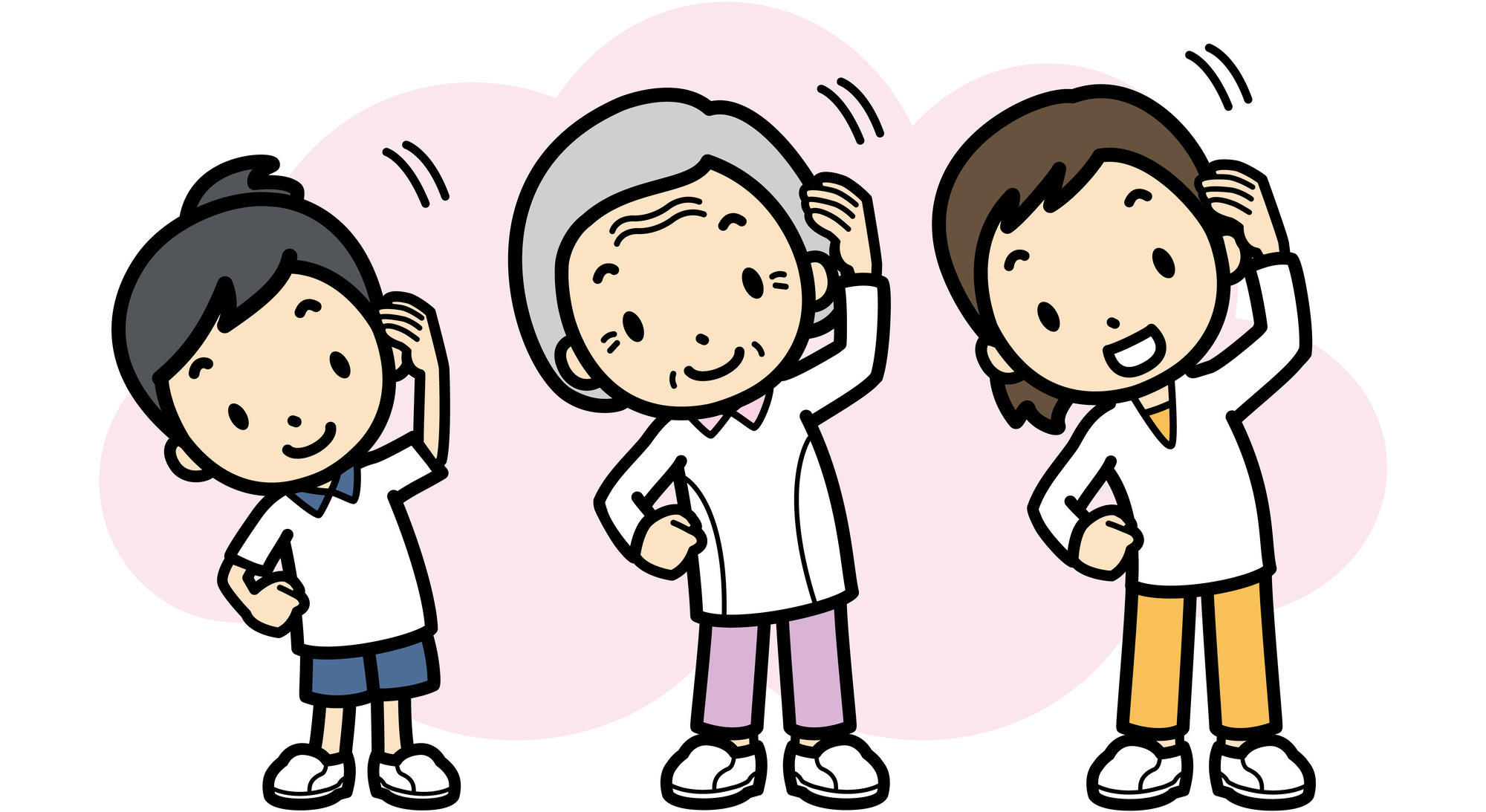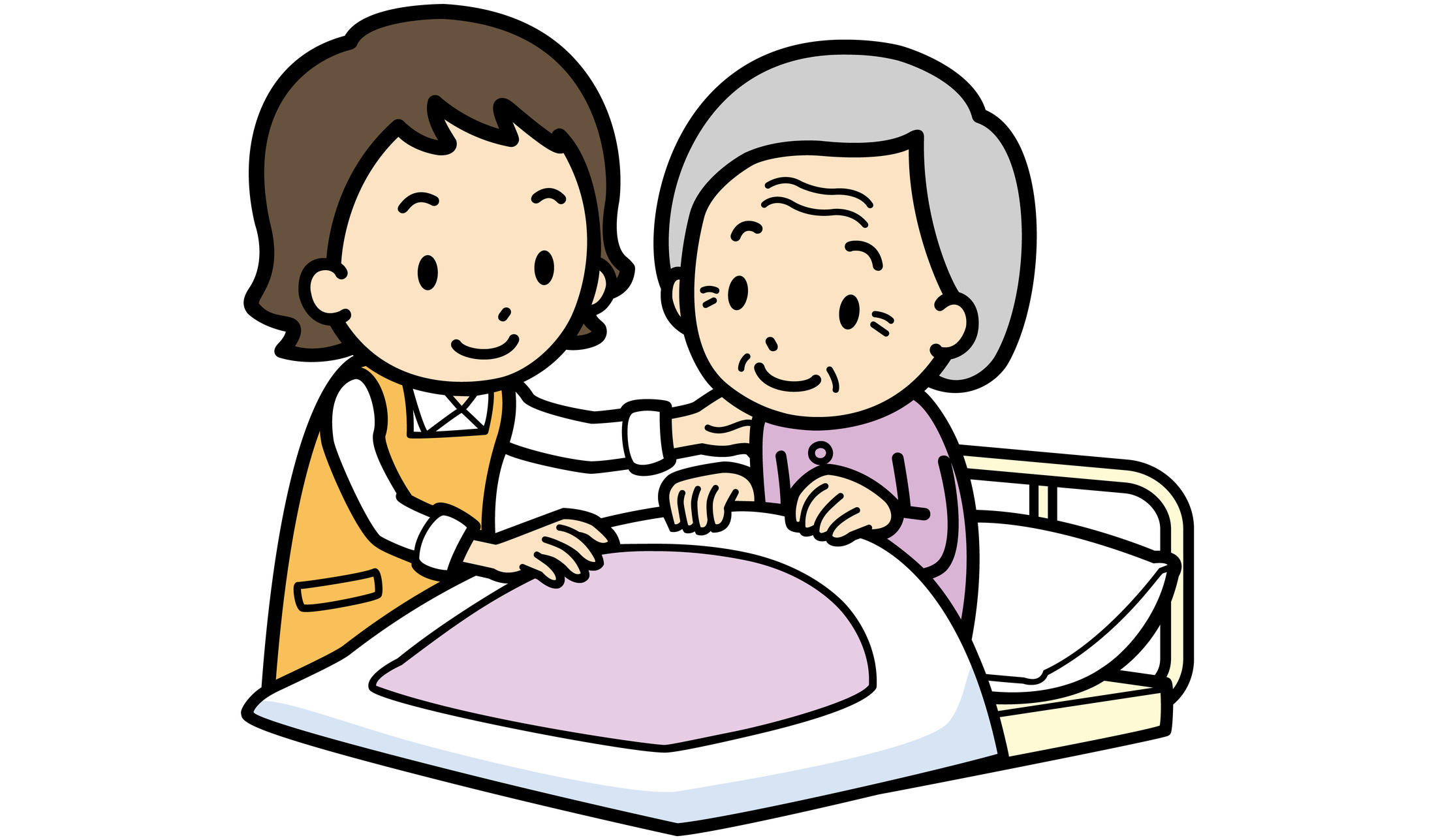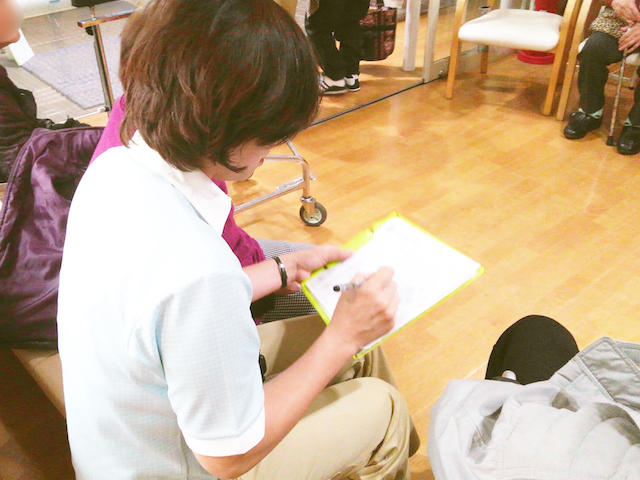С╗ІУГисЂ«СЙ┐тѕЕтИќсЃѕсЃЃсЃЌсЂИТѕ╗сѓІ
С╗ІУГисЂ«уЈЙта┤сЂДсѓѓТ┤╗ућесЂДсЂЇсѓІсѓ▒сЃ╝сѓ╣сЃ»сЃ╝сѓ»сЂ«тЪ║ТюгтД┐тІбсђїсЃљсѓцсѓ╣сЃєсЃЃсѓ»сЂ«7тјЪтЅЄсђЇ
ТЈ┤тіЕжќбС┐ѓсЂФсЂісЂЉсѓІуЏИС║њСйюуће
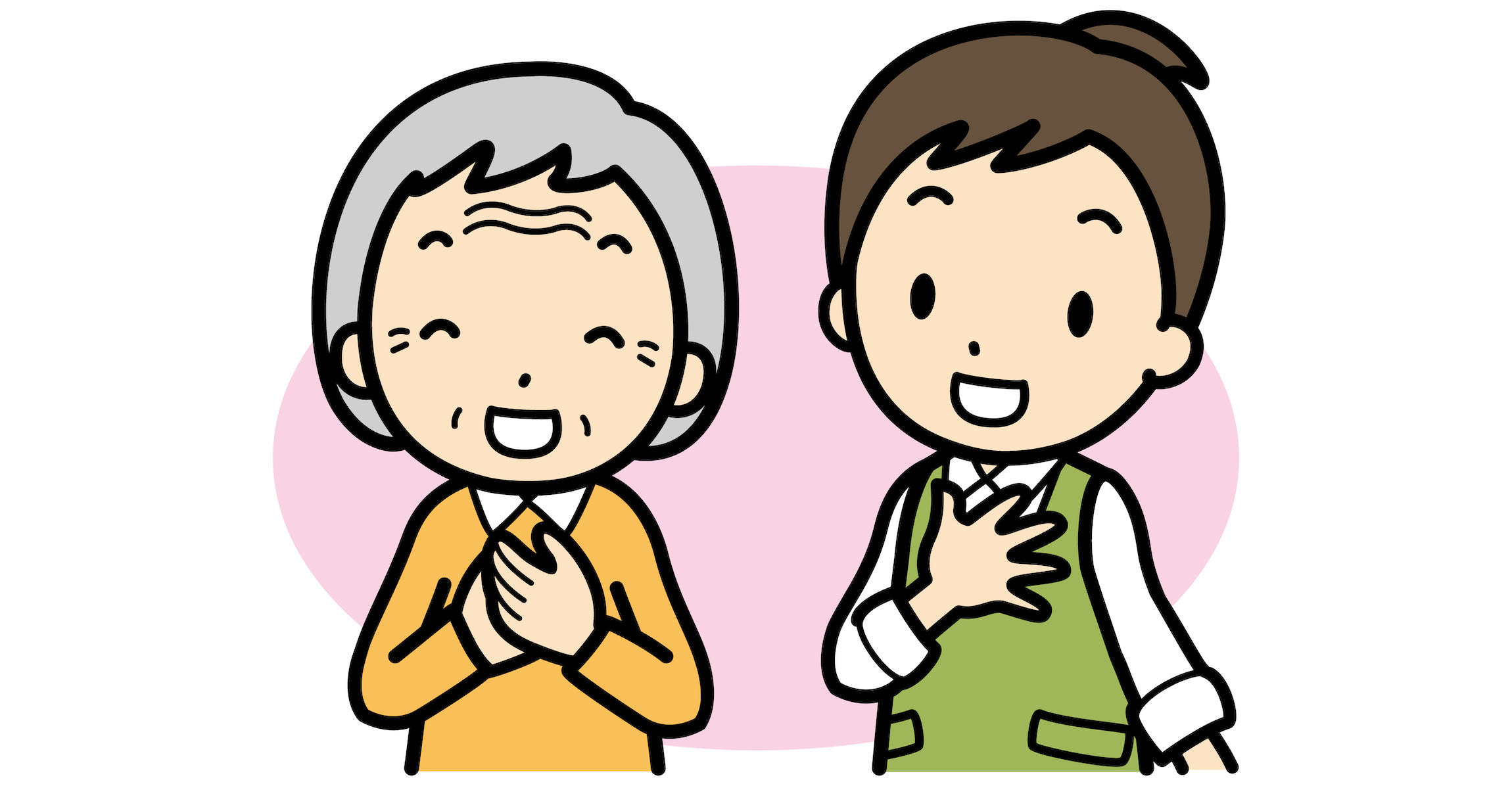
сђїсЃљсѓцсѓ╣сЃєсЃЃсѓ»сЂ«7тјЪтЅЄсђЇсЂ»сђЂтѕЕућеУђЁ№╝ѕсѓ»сЃЕсѓцсѓесЃ│сЃѕ№╝ЅсЂїТ▒ѓсѓЂсѓІ7сЂцсЂ«тЪ║ТюгуџёсЃІсЃ╝сЃЅсѓњжЄЇУдќсЂЎсѓІУђЃсЂѕсЂІсѓЅућЪсЂЙсѓїсЂЪтјЪтЅЄсЂДсЂЎсђѓ
сЂЎсЂ╣сЂдсЂ«С║║сЂ»тЁ▒жђџсЂ«тЪ║ТюгуџёсЃІсЃ╝сЃЅсѓњсѓѓсЂБсЂдсЂісѓісђЂтЏ░жЏБсѓњТі▒сЂѕсЂдТЈ┤тіЕсѓњТ▒ѓсѓЂсѓІтѕЕућеУђЁсЂ»сђЂсЂЮсЂ«сЃІсЃ╝сЃЅсѓњсѓѕсѓісЂёсЂБсЂЮсЂєт╝исЂЈсѓѓсЂцсЂеУђЃсЂѕсѓЅсѓїсЂЙсЂЎсђѓ
сЂЮсЂ«сЂЪсѓЂсђЂТЈ┤тіЕУђЁ№╝ѕсЃ»сЃ╝сѓФсЃ╝№╝ЅсЂїтѕЕућеУђЁсЂ«сЃІсЃ╝сЃЅсѓњт╝исЂЈТёЈУГўсЂЎсѓІсЂЊсЂесЂДсђЂтѕЕућеУђЁсЂесЂ«жќЊсЂФТЁІт║дсЂеТёЪТЃЁсѓњсЂесѓѓсЂфсЂБсЂЪуЏИС║њСйюућесѓњсЂцсЂЈсѓітЄ║сЂЎсЂЊсЂесЂїсЂДсЂЇсЂЙсЂЎсђѓ
ТЈ┤тіЕУђЁ№╝ѕсЃ»сЃ╝сѓФсЃ╝№╝ЅсЂетѕЕућеУђЁ№╝ѕсѓ»сЃЕсѓцсѓесЃ│сЃѕ№╝ЅсЂесЂ«жќЊсЂФућЪсЂЙсѓїсѓІтіЏтІЋуџёсЂфуЏИС║њСйюућесЂ»сђЂ3сЂцсЂ«Тќ╣тљЉТђДсѓњсѓѓсЂБсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓ
| тљётјЪтЅЄсЂ«тљЇуД░ | угг1сЂ«Тќ╣тљЉ№╝џ сѓ»сЃЕсѓцсѓесЃ│сЃѕсЂ«сЃІсЃ╝сЃЅ |
угг2сЂ«Тќ╣тљЉ№╝џ сЃ»сЃ╝сѓФсЃ╝сЂ«тЈЇт┐ю |
угг3сЂ«Тќ╣тљЉ№╝џ сѓ»сЃЕсѓцсѓесЃ│сЃѕсЂ«Т░ЌсЂЦсЂЇ |
|---|---|---|---|
| сѓ»сЃЕсѓцсѓесЃ│сЃѕсѓњтђІС║║сЂесЂЌсЂдсЂесѓЅсЂѕсѓІ | СИђС║║сЂ«тђІС║║сЂесЂЌсЂдУ┐јсЂѕсѓЅсѓїсЂЪсЂё | сЃ»сЃ╝сѓФсЃ╝сЂ»сѓ»сЃЕсѓцсѓесЃ│сЃѕсЂ«сЃІсЃ╝сЃЅсѓњТёЪуЪЦсЂЌсђЂуљєУДБсЂЌсЂдсЂЮсѓїсѓЅсЂФжЂЕтѕЄсЂФтЈЇт┐юсЂЎсѓІ | сѓ»сЃЕсѓцсѓесЃ│сЃѕсЂ»сЃ»сЃ╝сѓФсЃ╝сЂ«ТёЪтЈЌТђДсѓњуљєУДБсЂЌсђЂсЃ»сЃ╝сѓФсЃ╝сЂ«тЈЇт┐юсЂФт░ЉсЂЌсЂџсЂцТ░ЌсЂЦсЂЇсЂ»сЂўсѓЂсѓІ |
| сѓ»сЃЕсѓцсѓесЃ│сЃѕсЂ«ТёЪТЃЁУАеуЈЙсѓњтцДтѕЄсЂФсЂЎсѓІ | ТёЪТЃЁсѓњУАеуЈЙсЂЌсЂдУДБТћЙсЂЋсѓїсЂЪсЂё | ||
| ТЈ┤тіЕУђЁсЂ»УЄфтѕєсЂ«ТёЪТЃЁсѓњУЄфУдџсЂЌсЂдтљЪтЉ│сЂЎсѓІ | тЁ▒ТёЪуџёсЂфтЈЇт┐юсѓњтЙЌсЂЪсЂё | ||
| тЈЌсЂЉсЂесѓЂсѓІ | СЙАтђцсЂѓсѓІС║║жќЊсЂесЂЌсЂдтЈЌсЂЉсЂесѓЂсѓЅсѓїсЂЪсЂё | ||
| сѓ»сЃЕсѓцсѓесЃ│сЃѕсѓњСИђТќ╣уџёсЂФжЮъжЏБсЂЌсЂфсЂё | СИђТќ╣уџёсЂФжЮъжЏБсЂЋсѓїсЂЪсЂЈсЂфсЂё | ||
| сѓ»сЃЕсѓцсѓесЃ│сЃѕсЂ«УЄфти▒Т▒║т«џсѓњС┐ЃсЂЌсЂдт░іжЄЇсЂЎсѓІ | тЋЈжАїУДБТ▒║сѓњУЄфтѕєсЂДжЂИТіъсЂЌсђЂТ▒║т«џсЂЌсЂЪсЂё | ||
| уДўт»єсѓњС┐ЮТїЂсЂЌсЂдС┐Ажа╝ТёЪсѓњжєИТѕљсЂЎсѓІ | УЄфтѕєсЂ«уДўт»єсѓњсЂЇсЂАсѓЊсЂет«ѕсѓісЂЪсЂё |
№╝ют╝Ћуће№╝ъFсЃ╗PсЃ╗сЃљсѓцсѓ╣сЃєсЃЃсѓ»сђјсѓ▒сЃ╝сѓ╣сЃ»сЃ╝сѓ»сЂ«тјЪтЅЄ№╝ЇТЈ┤тіЕжќбС┐ѓсѓњтйбТѕљсЂЎсѓІТіђТ│Ћ Тќ░Уе│уЅѕсђЈУфаС┐АТЏИТѕ┐,1996.1.27p
| угг1сЂ«Тќ╣тљЉ№╝џсѓ»сЃЕсѓцсѓесЃ│сЃѕсЂ«сЃІсЃ╝сЃЅ |
|---|
| тѕЕућеУђЁ№╝ѕсѓ»сЃЕсѓцсѓесЃ│сЃѕ№╝ЅсЂІсѓЅТЈ┤тіЕУђЁ№╝ѕсЃ»сЃ╝сѓФсЃ╝№╝ЅсЂФтљЉсЂЉсѓЅсѓїсѓІуЏИС║њСйюућесЂДсЂЎсђѓ тѕЕућеУђЁсЂ»сђЂУЄфтѕєсЂїТі▒сЂѕсЂдсЂёсѓІтЋЈжАїсѓёт╝▒сЂЋсѓњТЈ┤тіЕУђЁсЂФС╝ЮсЂѕсѓІсЂесЂЇсђЂсђїтђІС║║сЂесЂЌсЂдт░іжЄЇсЂЋсѓїсЂфсЂёсЂ«сЂДсЂ»сЂфсЂёсЂІсђЇсђїжЮъжЏБсЂЋсѓїсѓІсЂасѓЇсЂєсЂІсђЇсђїуДўт»єсѓњС╗ќС║║сЂФТ╝ЈсѓЅсЂЎсЂ«сЂДсЂ»сЂфсЂёсЂІсђЇсЂфсЂЕсЂ«СИЇт«ЅсѓњсѓѓсЂБсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓ |
| угг2сЂ«Тќ╣тљЉ№╝џсЃ»сЃ╝сѓФсЃ╝сЂ«тЈЇт┐ю |
|---|
| ТЈ┤тіЕУђЁ№╝ѕсЃ»сЃ╝сѓФсЃ╝№╝ЅсЂІсѓЅтѕЕућеУђЁ№╝ѕсѓ»сЃЕсѓцсѓесЃ│сЃѕ№╝ЅсЂФтљЉсЂЉсѓЅсѓїсѓІуЏИС║њСйюућесЂДсЂЎсђѓ ТЈ┤тіЕУђЁсЂ»сђЂтѕЕућеУђЁсЂ«сЃІсЃ╝сЃЅсѓњТёЪсЂўсЂесѓісђЂТёЪТЃЁсѓњуљєУДБсЂЌсЂЙсЂЎсђѓсЂЮсЂЌсЂдсђЂтѕЕућеУђЁсЂ«ТеЕтѕЕсѓњт░іжЄЇсЂЌсђЂСИђС║║сЂ«тђІС║║сЂесЂЌсЂдтЈЌсЂЉсЂесѓЂсѓІућеТёЈсЂїсЂѓсѓІсЂЊсЂесѓњуц║сЂЎсЂЊсЂесЂДсђЂтѕЕућеУђЁсЂ«СИЇт«ЅсѓњтњїсѓЅсЂњсЂЙсЂЎсђѓ |
| угг3сЂ«Тќ╣тљЉ№╝џсѓ»сЃЕсѓцсѓесЃ│сЃѕсЂ«Т░ЌсЂЦсЂЇ |
|---|
| тєЇсЂ│тѕЕућеУђЁ№╝ѕсѓ»сЃЕсѓцсѓесЃ│сЃѕ№╝ЅсЂІсѓЅТЈ┤тіЕУђЁ№╝ѕсЃ»сЃ╝сѓФсЃ╝№╝ЅсЂФтљЉсЂЉсѓЅсѓїсѓІуЏИС║њСйюућесЂДсЂЎсђѓ тѕЕућеУђЁсЂ»ТЈ┤тіЕУђЁсЂ«уц║сЂЌсЂЪТЁІт║дсЂФТ░ЌсЂЦсЂЇсЂ»сЂўсѓЂсђЂсЂЮсЂ«Т░ЌсЂЦсЂЇсѓњСйЋсѓЅсЂІсЂ«Тќ╣Т│ЋсЂДС╝ЮсЂѕУ┐ћсЂЮсЂєсЂесЂЌсЂЙсЂЎсђѓ |
сЂЊсЂ«3сЂцсЂ«уЏИС║њСйюућесЂ«Тќ╣тљЉсЂ»сђїТЈ┤тіЕжЂјуеІтЁеСйЊсѓњжђџсЂЌсЂдсђЂС║њсЂёсЂФжЪ┐сЂЇтљѕсЂєсѓѕсЂєсЂФжќбжђБсЂЌсЂфсЂїсѓЅжђ▓сѓђсђЇсЂеУАеуЈЙсЂЋсѓїсЂдсЂёсЂЙсЂЎсђѓ
сЂЊсЂ«сѓѕсЂєсЂфуЏИС║њСйюућесЂ»сђЂУеђУЉЅсЂФсѓѕсЂБсЂдС╝ЮсЂѕсѓЅсѓїсѓІсЂЊсЂесЂ»т░ЉсЂфсЂёсЂ»сЂџсЂДсЂЎсђѓС╗ІУГисЂ«уЈЙта┤сЂфсЂЕсЂДТ┤╗ућесЂЎсѓІсЂесЂЇсЂ»сђЂжЮъУеђУфъуџёсЂфУдЂу┤асѓњТёЈУГўсЂЎсѓІсЂесђЂсѓѕсѓіУЅ»тЦйсЂфсѓ│сЃЪсЃЦсЃІсѓ▒сЃ╝сѓисЃДсЃ│сѓњсЂесѓІсЂЊсЂесЂїсЂДсЂЇсѓІсЂДсЂЌсѓЄсЂєсђѓ
Рќ╝жќбжђБУеўС║І
сЂіт«бТДўсЂесЂ«СИіТЅІсЂфсѓ│сЃЪсЃЦсЃІсѓ▒сЃ╝сѓисЃДсЃ│Тќ╣Т│Ћ
сЂћт«ХТЌЈсЂеС┐Ажа╝жќбС┐ѓсѓњу»ЅсЂЈсЂЪсѓЂсЂ«сѓ│сЃЪсЃЦсЃІсѓ▒сЃ╝сѓисЃДсЃ│Тќ╣Т│Ћ
С╗ІУГисЂФТљ║сѓЈсѓІсЂфсѓЅуљєУДБсЂЌсЂдсЂісЂЇсЂЪсЂёсђїICF№╝ѕтЏйжџЏућЪТ┤╗ТЕЪУЃйтѕєжАъ№╝ЅсђЇ
№╝ютЈѓУђЃТќЄуї«№╝ъ
FсЃ╗PсЃ╗сЃљсѓцсѓ╣сЃєсЃЃсѓ»сђјсѓ▒сЃ╝сѓ╣сЃ»сЃ╝сѓ»сЂ«тјЪтЅЄ№╝ЇТЈ┤тіЕжќбС┐ѓсѓњтйбТѕљсЂЎсѓІТіђТ│Ћ Тќ░Уе│уЅѕсђЈУфаС┐АТЏИТѕ┐,1996.1
т«ХТЌЈсЂ«С╗ІУГисѓњсЂЇсЂБсЂІсЂЉсЂФС╗ІУГиудЈуЦЅтБФсЃ╗уцЙС╝џудЈуЦЅСИ╗С║ІС╗╗ућеУ│ЄТа╝сѓњтЈќтЙЌсђѓуЈЙтюесЂ»сЃЕсѓцсѓ┐сЃ╝сђѓТЌЦсђЁсЂ«Тџ«сѓЅсЂЌсЂФтй╣уФІсЂцУ║ФУ┐ЉсЂфТЃЁта▒сѓњсЂіС╝ЮсЂѕсЂЎсѓІсЂ╣сЂЈсђЂС╗ІУГисЃ╗тї╗уЎѓсЃ╗уЙјт«╣сЃ╗сѓФсЃФсЃЂсЃБсЃ╝сЂфсЂЕт╣Ёт║ЃсЂёсѓИсЃБсЃ│сЃФсЂ«УеўС║ІсѓњтЪиуГєСИГсђѓ
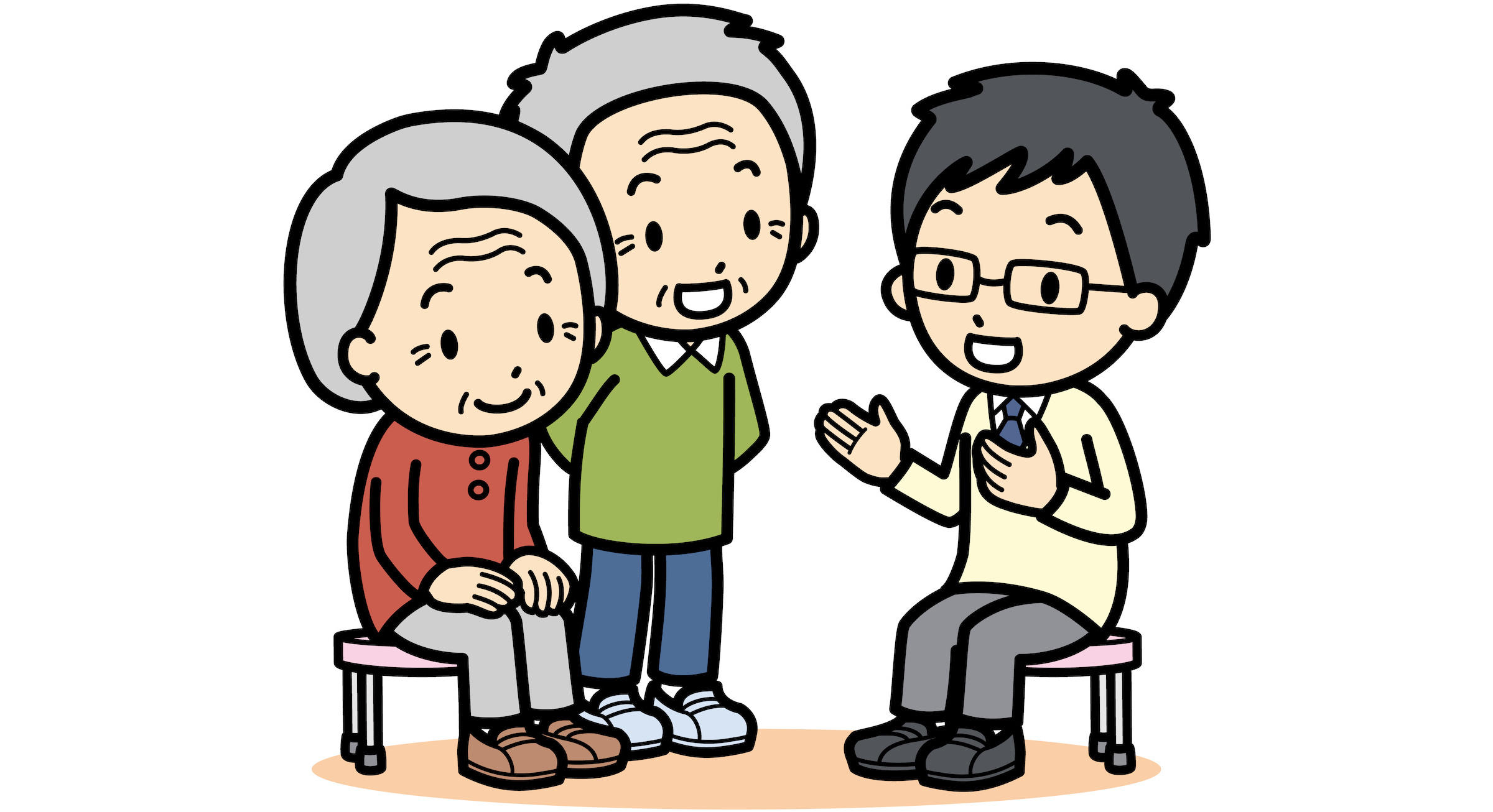
FacebookсЃџсЃ╝сѓИсЂД
ТюђТќ░УеўС║ІжЁЇС┐А№╝Ђ№╝Ђ
 сЃгсѓфсЃЈсѓџсЃгсѓ╣21сѓ»сѓЎсЃФсЃ╝сЃЋсѓџсЂ«С╗ІУГисѓхсЃ╝сЃњсѓЎсѓ╣
сЃгсѓфсЃЈсѓџсЃгсѓ╣21сѓ»сѓЎсЃФсЃ╝сЃЋсѓџсЂ«С╗ІУГисѓхсЃ╝сЃњсѓЎсѓ╣