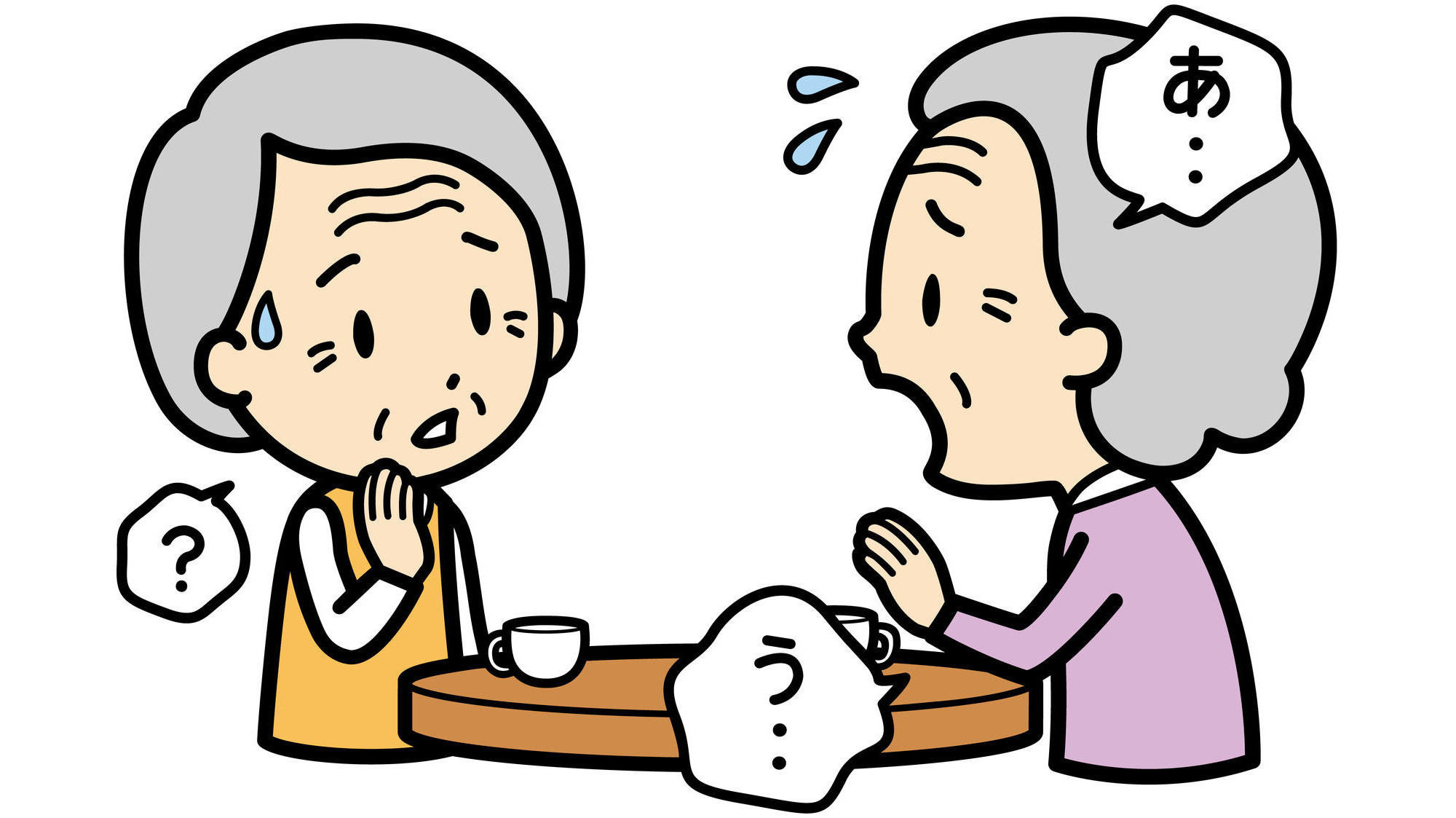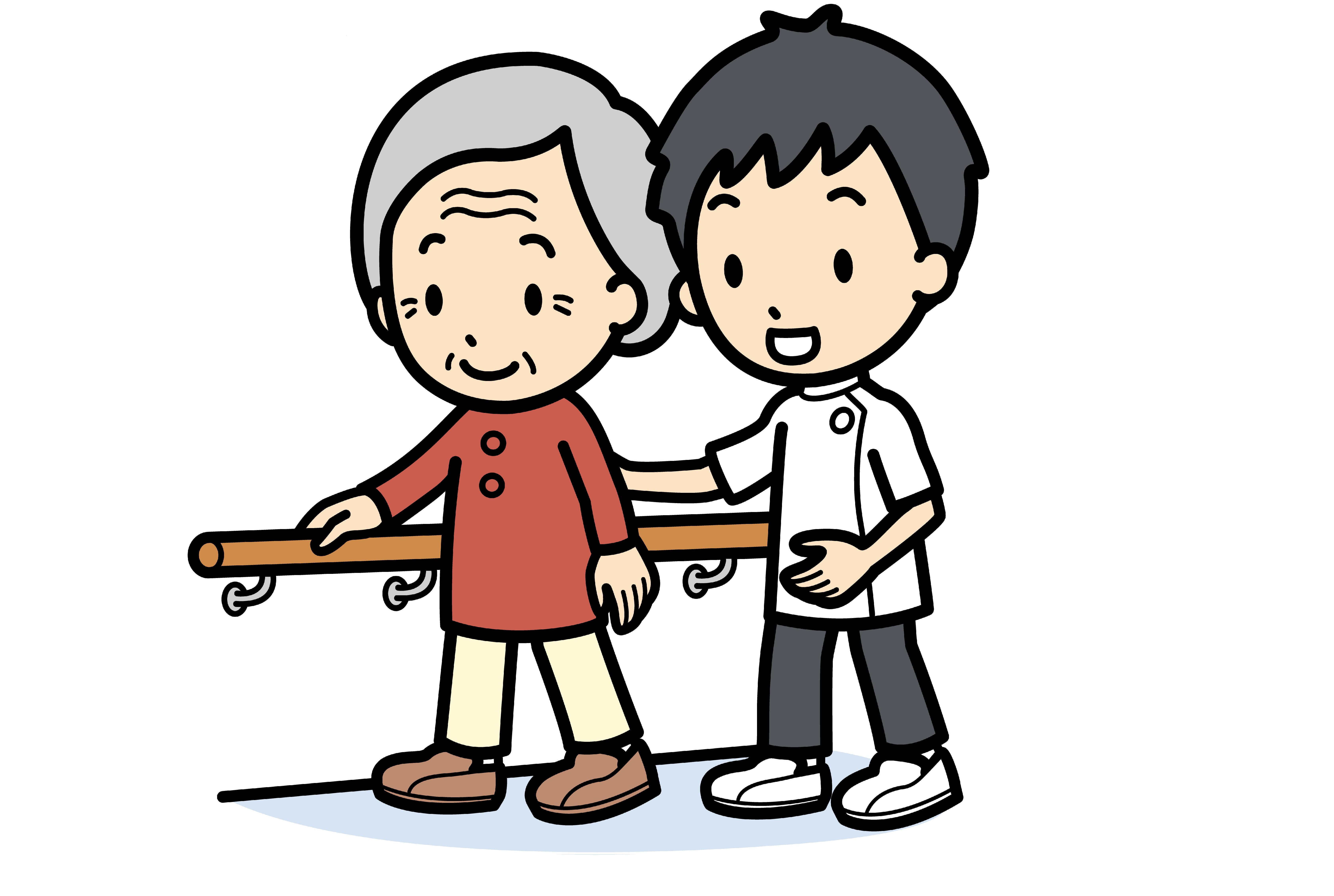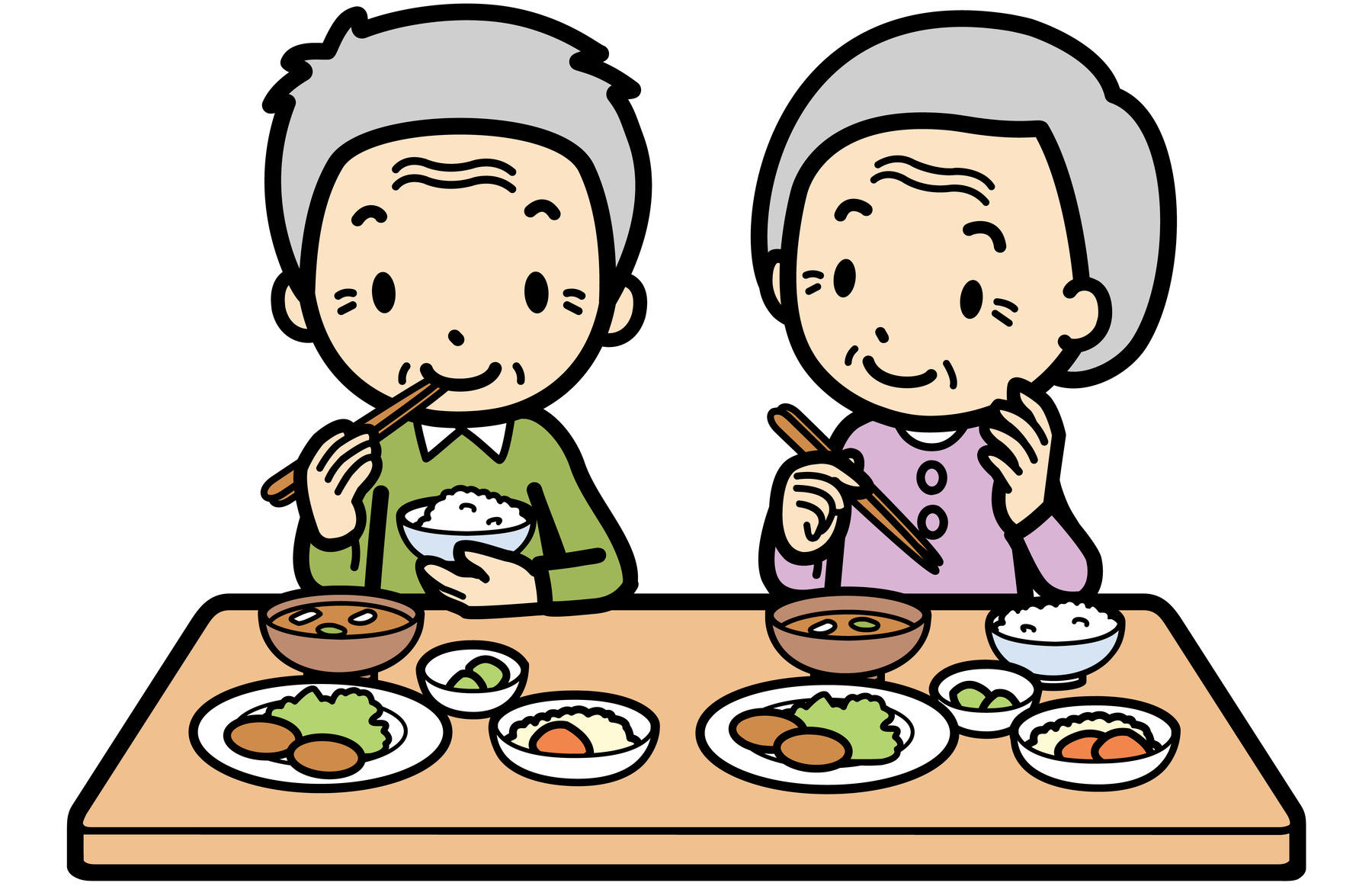д»Ӣиӯ·гҒ®дҫҝеҲ©её–гғҲгғғгғ—гҒёжҲ»гӮӢ
гғӘгғҸгғ“гғӘгғҶгғјгӮ·гғ§гғігҒ®гӮ№гғҡгӮ·гғЈгғӘгӮ№гғҲгҖҢиЁҖиӘһиҒҙиҰҡеЈ«гҖҚгҒ®еҪ№еүІгҒЁдё»гҒӘд»•дәӢеҶ…е®№
иЁҖиӘһиҒҙиҰҡеЈ«пјҲSTпјүгҒҜгҖҒиЁҖиӘһгӮ„иҒҙиҰҡгҖҒж‘ӮйЈҹпјҲгҒӣгҒЈгҒ—гӮҮгҒҸпјүгғ»еҡҘдёӢпјҲгҒҲгӮ“гҒ’пјүгҒӘгҒ©гҒ«е•ҸйЎҢгӮ’гӮӮгҒӨж–№гҒ«гҒ•гҒҫгҒ–гҒҫгҒӘиЁ“з·ҙгӮ„жҢҮе°ҺгӮ’иЎҢгҒ„гҖҒиҮӘеҲҶгӮүгҒ—гҒ„з”ҹжҙ»гӮ’йҖҒгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶж”ҜжҸҙгҒҷгӮӢгғӘгғҸгғ“гғӘгғҶгғјгӮ·гғ§гғігҒ®е°Ӯй–ҖиҒ·гҒ§гҒҷгҖӮд»ҠеӣһгҒҜгҖҒеҢ»зҷӮгӮ„д»Ӣиӯ·гҖҒзҰҸзҘүгҖҒдҝқеҒҘгҒӘгҒ©гҖҒе№…еәғгҒ„й ҳеҹҹгҒ§жҙ»иәҚгҒҷгӮӢиЁҖиӘһиҒҙиҰҡеЈ«пјҲSTпјүгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰи§ЈиӘ¬гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
иЁҖиӘһиҒҙиҰҡеЈ«пјҲSTпјүгҒЁгҒҜ

иЁҖиӘһиҒҙиҰҡеЈ«гҒҜгҖҒиЁҖи‘үгҒ«гӮҲгӮӢгӮігғҹгғҘгғӢгӮұгғјгӮ·гғ§гғігҖҒж‘ӮйЈҹпјҲгҒӣгҒЈгҒ—гӮҮгҒҸпјүгӮ„еҡҘдёӢпјҲгҒҲгӮ“гҒ’пјүгҒӘгҒ©гҒ«еӣ°йӣЈгӮ’жҠұгҒҲгӮӢж–№гҒ«гҖҒиЁ“з·ҙгӮ„жҢҮе°ҺгӮ’иЎҢгҒҶе°Ӯй–ҖиҒ·гҒ§гҒҷгҖӮ
STпјҲSpeech-Language-Hearing TherapistпјүгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
иЁҖиӘһиҒҙиҰҡеЈ«жі•гҒ§гҒҜгҖҒгҖҢеҺҡз”ҹеҠҙеғҚеӨ§иҮЈгҒ®е…ҚиЁұгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰгҖҒиЁҖиӘһиҒҙиҰҡеЈ«гҒ®еҗҚз§°гӮ’з”ЁгҒ„гҒҰгҖҒйҹіеЈ°ж©ҹиғҪгҖҒиЁҖиӘһж©ҹиғҪеҸҲгҒҜиҒҙиҰҡгҒ«йҡңе®ігҒ®гҒӮгӮӢиҖ…гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒқгҒ®ж©ҹиғҪгҒ®з¶ӯжҢҒеҗ‘дёҠгӮ’еӣігӮӢгҒҹгӮҒгҖҒиЁҖиӘһиЁ“з·ҙгҒқгҒ®д»–гҒ®иЁ“з·ҙгҖҒгҒ“гӮҢгҒ«еҝ…иҰҒгҒӘжӨңжҹ»еҸҠгҒіеҠ©иЁҖгҖҒжҢҮе°ҺгҒқгҒ®д»–гҒ®жҸҙеҠ©гӮ’иЎҢгҒҶгҒ“гҒЁгӮ’жҘӯгҒЁгҒҷгӮӢиҖ…гӮ’гҒ„гҒҶгҖӮгҖҚгҒЁе®ҡзҫ©гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
иЁҖиӘһиҒҙиҰҡеЈ«гҒ®еҪ№еүІ
гӮігғҹгғҘгғӢгӮұгғјгӮ·гғ§гғігҒ®е•ҸйЎҢгҒ«гҒҜгҖҒж§Ӣйҹійҡңе®іпјҲе‘ӮеҫӢгҒҢгҒҫгӮҸгӮүгҒӘгҒ„гғ»и©ұгҒ—ж–№гҒҢгҒҺгҒ“гҒЎгҒӘгҒ„зӯүпјүгҖҒеӨұиӘһз—ҮпјҲиЁҖи‘үгҒҢзҗҶи§ЈгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гғ»ж–Үеӯ—гҒҢиӘӯгӮҒгҒӘгҒ„гғ»ж–Үеӯ—гҒҢжӣёгҒ‘гҒӘгҒ„зӯүпјүгҖҒйҹіеЈ°йҡңе®іпјҲеЈ°гҒҢеҮәгҒӣгҒӘгҒ„пјүгҖҒиҒҙиҰҡйҡңе®іпјҲйҹігҒҢиҒһгҒ“гҒҲгҒӘгҒ„гҖҒиҒһгҒ“гҒҲгҒ«гҒҸгҒ„пјүгҒӘгҒ©гҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
иЁҖиӘһиҒҙиҰҡеЈ«гҒҜгҖҒе°Ӯй–Җзҡ„гҒӘзҹҘиӯҳгӮ„жҠҖиЎ“гӮ’з”ЁгҒ„гҒҰгҖҒгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгӮігғҹгғҘгғӢгӮұгғјгӮ·гғ§гғігҒ®е•ҸйЎҢгҒ®ж”№е–„гҖҒиғҪеҠӣгҒ®еӣһеҫ©гҒӘгҒ©гӮ’еӣігӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒйЈҹгҒ№гӮӢгҒЁгҒҚгӮӮи©ұгҒҷгҒЁгҒҚгҒЁеҗҢгҒҳгӮҲгҒҶгҒ«еҸЈгӮ„иҲҢгҒӘгҒ©гҒ®йғЁдҪҚгӮ’дҪҝгҒҶгҒҹгӮҒгҖҒж§Ӣйҹійҡңе®ігҒЁж‘ӮйЈҹпјҲйЈҹгҒ№гӮӢгҒ“гҒЁпјүгғ»еҡҘдёӢпјҲйЈІгҒҝиҫјгӮҖгҒ“гҒЁпјүйҡңе®ігҒҜеҗҲдҪөгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
е’ҖеҡјпјҲгҒқгҒ—гӮғгҒҸпјүгӮ„йЈІгҒҝиҫјгҒҝгҒҢеӣ°йӣЈгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹж–№гҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҖҒиЁ“з·ҙгӮ„жҢҮе°ҺгӮ’иЎҢгҒҶгҒ“гҒЁгӮӮиЁҖиӘһиҒҙиҰҡеЈ«гҒ®еҪ№еүІгҒ§гҒҷгҖӮ
иЁҖиӘһиҒҙиҰҡеЈ«гҒ«гӮҲгӮӢгғӘгғҸгғ“гғӘгғҶгғјгӮ·гғ§гғігҒҜгҖҒеҢ»зҷӮе°Ӯй–ҖиҒ·пјҲеҢ»её«гғ»жӯҜ科еҢ»её«гғ»зңӢиӯ·её«гғ»зҗҶеӯҰзҷӮжі•еЈ«гғ»дҪңжҘӯзҷӮжі•еЈ«гҒӘгҒ©пјүгҖҒдҝқеҒҘгғ»зҰҸзҘүе°Ӯй–ҖиҒ·пјҲгӮұгғјгӮ№гғҜгғјгӮ«гғјгғ»д»Ӣиӯ·зҰҸзҘүеЈ«гғ»д»Ӣиӯ·ж”ҜжҸҙе°Ӯй–Җе“ЎгҒӘгҒ©пјүгҖҒеҝғзҗҶе°Ӯй–ҖиҒ·зӯүгҒЁйҖЈжҗәгҒ—гҖҒгғҒгғјгғ гҒ®дёҖе“ЎгҒЁгҒ—гҒҰиЎҢгӮҸгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
в–јй–ўйҖЈиЁҳдәӢ
иЁҖиӘһйҡңгҒҢгҒ„гҒ®гҒӮгӮӢж–№гҒЁгҒ®гӮігғҹгғҘгғӢгӮұгғјгӮ·гғ§гғігҒ®гғқгӮӨгғігғҲ
иЁҖиӘһиҒҙиҰҡеЈ«гҒ®дё»гҒӘд»•дәӢеҶ…е®№

йҹіеЈ°иЁҖиӘһгҒ®иЁ“з·ҙ
- гғ»иЁҖиӘһйҡңе®ігҒ®гҒӮгӮӢж–№гҒ®зҠ¶ж…ӢгӮ’е•ҸиЁәгғ»жӨңжҹ»гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰиӘҝгҒ№гҖҒзЁӢеәҰгӮ„е•ҸйЎҢзӮ№гӮ’жҳҺгӮүгҒӢгҒ«гҒҷгӮӢ
- гғ»йҹіеЈ°иЁҖиӘһгҒ®иЁ“з·ҙпјҲж§ӢйҹіиЁ“з·ҙпјүгӮ’гҒҷгӮӢ
ж‘ӮйЈҹпјҲгҒӣгҒЈгҒ—гӮҮгҒҸпјүгғ»еҡҘдёӢпјҲгҒҲгӮ“гҒ’пјүгҒ®иЁ“з·ҙгҒӘгҒ©
- гғ»ж‘ӮйЈҹгғ»еҡҘдёӢйҡңе®ігҒ®гҒӮгӮӢж–№гҒ«е•ҸиЁәгӮ„жӨңжҹ»гӮ’гҒ—гҒҰгҖҒйҡңе®ігҒ®зҠ¶ж…Ӣгғ»зЁӢеәҰгӮ’зўәиӘҚгҒҷгӮӢ
- гғ»ж‘ӮйЈҹгғ»еҡҘдёӢйҡңе®ігҒ®зЁӢеәҰгҒ«еҝңгҒҳгҒҰиЁ“з·ҙгӮ’иЎҢгҒҶ
- гғ»йЈҹдәӢеҶ…е®№гҒ«еҗҲгӮҸгҒӣгҒҰйҒ©еҲҮгҒӘйЈҹдәӢж–№жі•гӮ’жҢҮе°ҺгҒҷгӮӢ
- гғ»еҸЈи…”еҶ…гҒ®з’°еўғгӮ’ж”№е–„гҒҷгӮӢ
иҒҙиҰҡгҒ®ж”ҜжҸҙ
- гғ»иЈңиҒҙеҷЁгҒӘгҒ©гҒ®иЈңеҠ©еҷЁе…·гӮ„дәәе·ҘеҶ…иҖігҒ®иӘҝж•ҙгҒӘгҒ©гӮ’иЎҢгҒҶ
гҒқгҒ®д»–
- гғ»жӨңжҹ»зөҗжһңгӮ’гӮӮгҒЁгҒ«еҢ»её«гҒӘгҒ©гҒЁжӨңиЁҺгӮ’иЎҢгҒ„гҖҒжІ»зҷӮж–№йҮқгӮ„иЁ“з·ҙж–№жі•гӮ’жұәгӮҒгӮӢ
- гғ»гҒ”家ж—ҸгҒӢгӮүгҒ®зӣёи«ҮгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰеҠ©иЁҖгҒҷгӮӢ
- гғ»гғ—гғӯгӮ°гғ©гғ гҒ®е®ҹж–ҪзҠ¶жіҒгӮ„йҡңе®ігҒ®ж”№е–„зҠ¶жіҒгӮ’иЁҳйҢІгғ»з®ЎзҗҶгҒҷгӮӢ
- гғ»е°Ҹе…җгҒ®иЁҖиӘһзҷәйҒ”ж”ҜжҸҙгӮ„иӘҚзҹҘз—ҮгҒ®ж–№гҒ«еҜҫгҒҷгӮӢиЁ“з·ҙгӮ’гҒҷгӮӢ
иЁҖиӘһиҒҙиҰҡеЈ«гҒ«гҒӘгӮӢгҒ«гҒҜ
иЁҖиӘһиҒҙиҰҡеЈ«гҒ«гҒӘгӮӢгҒ«гҒҜгҖҒиЁҖиӘһиҒҙиҰҡеЈ«еӣҪ家и©ҰйЁ“гҒ«еҗҲж јгҒ—гҖҒеҺҡз”ҹеҠҙеғҚеӨ§иҮЈгҒ®е…ҚиЁұгӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
еҸ—йЁ“иіҮж ј
- гғ»й«ҳж ЎеҚ’жҘӯеҫҢгҖҒж–ҮйғЁз§‘еӯҰеӨ§иҮЈгҒҢжҢҮе®ҡгҒҷгӮӢеӯҰж ЎпјҲ3пҪһ4е№ҙеҲ¶гҒ®еӨ§еӯҰгғ»зҹӯеӨ§пјүгҒҫгҒҹгҒҜйғҪйҒ“еәңзңҢзҹҘдәӢгҒҢжҢҮе®ҡгҒҷгӮӢиЁҖиӘһиҒҙиҰҡеЈ«йӨҠжҲҗжүҖпјҲ3пҪһ4е№ҙеҲ¶гҒ®е°Ӯдҝ®еӯҰж ЎпјүгӮ’еҚ’жҘӯгҒ—гҒҹж–№
- гғ»дёҖиҲ¬гҒ®4е№ҙеҲ¶еӨ§еӯҰеҚ’жҘӯеҫҢгҖҒжҢҮе®ҡгҒ•гӮҢгҒҹеӨ§еӯҰгғ»еӨ§еӯҰйҷўгҒ®е°Ӯ攻科гҒҫгҒҹгҒҜе°Ӯдҝ®еӯҰж ЎпјҲ2е№ҙеҲ¶пјүгӮ’еҚ’жҘӯгҒ—гҒҹж–№
д»–гҒ«гҖҒиЁҖиӘһиҒҙиҰҡеЈ«гҒ®йӨҠжҲҗгҒ«й–ўгӮҸгӮӢдёҖе®ҡеҹәжә–гҒ®з§‘зӣ®гӮ’гҒҷгҒ§гҒ«зҝ’еҫ—гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢж–№гӮ’еҜҫиұЎгҒЁгҒ—гҒҹжҢҮе®ҡж ЎпјҲ1е№ҙеҲ¶пјүгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒеӨ–еӣҪгҒ®еӨ§еӯҰгҒӘгҒ©гҒ§иЁҖиӘһиҒҙиҰҡгҒ«й–ўгҒҷгӮӢеӯҰжҘӯгӮ’дҝ®гӮҒгҒҹж–№гҒҜгҖҒеҺҡз”ҹеҠҙеғҚеӨ§иҮЈгҒ®иӘҚе®ҡгӮ’еҸ—гҒ‘гӮҢгҒ°еҸ—йЁ“иіҮж јгӮ’еҸ–еҫ—гҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
в–јй–ўйҖЈиЁҳдәӢ
д»Ӣиӯ·дҝқйҷәгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгҒ”й«ҳйҪўиҖ…гҒ®гҖҢгғӘгғҸгғ“гғӘгғҶгғјгӮ·гғ§гғігҖҚгҒЁгҒҜ
гҒ”й«ҳйҪўиҖ…гҒҢе®үе…ЁгҒ«йЈҹдәӢгӮ’гҒЁгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«зҹҘгҒЈгҒҰгҒҠгҒҚгҒҹгҒ„еҹәзӨҺзҹҘиӯҳ
гғӘгғҸгғ“гғӘгҒ®е°Ӯй–Җ家гҖӮзҗҶеӯҰзҷӮжі•еЈ«гҒЁдҪңжҘӯзҷӮжі•еЈ«гҒ®д»•дәӢеҶ…е®№гҒЁгҒҜпјҹ
家ж—ҸгҒ®д»Ӣиӯ·гӮ’гҒҚгҒЈгҒӢгҒ‘гҒ«д»Ӣиӯ·зҰҸзҘүеЈ«гғ»зӨҫдјҡзҰҸзҘүдё»дәӢд»»з”ЁиіҮж јгӮ’еҸ–еҫ—гҖӮзҸҫеңЁгҒҜгғ©гӮӨгӮҝгғјгҖӮж—ҘгҖ…гҒ®жҡ®гӮүгҒ—гҒ«еҪ№з«ӢгҒӨиә«иҝ‘гҒӘжғ…е ұгӮ’гҒҠдјқгҒҲгҒҷгӮӢгҒ№гҒҸгҖҒд»Ӣиӯ·гғ»еҢ»зҷӮгғ»зҫҺе®№гғ»гӮ«гғ«гғҒгғЈгғјгҒӘгҒ©е№…еәғгҒ„гӮёгғЈгғігғ«гҒ®иЁҳдәӢгӮ’еҹ·зӯҶдёӯгҖӮ

FacebookгғҡгғјгӮёгҒ§
жңҖж–°иЁҳдәӢй…ҚдҝЎпјҒпјҒ
 гғ¬гӮӘгғҸгӮҡгғ¬гӮ№21гӮҜгӮҷгғ«гғјгғ•гӮҡгҒ®д»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ’гӮҷгӮ№
гғ¬гӮӘгғҸгӮҡгғ¬гӮ№21гӮҜгӮҷгғ«гғјгғ•гӮҡгҒ®д»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ’гӮҷгӮ№