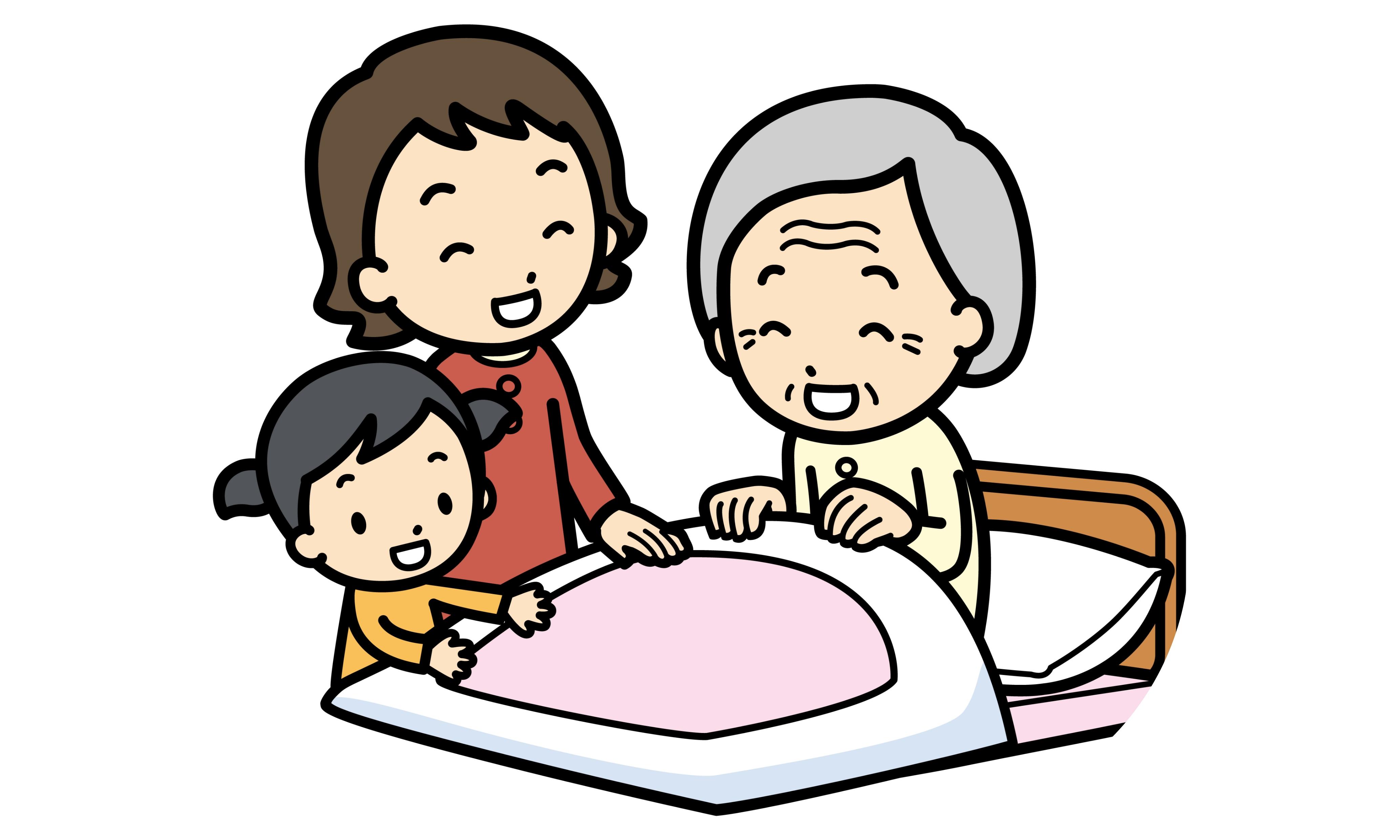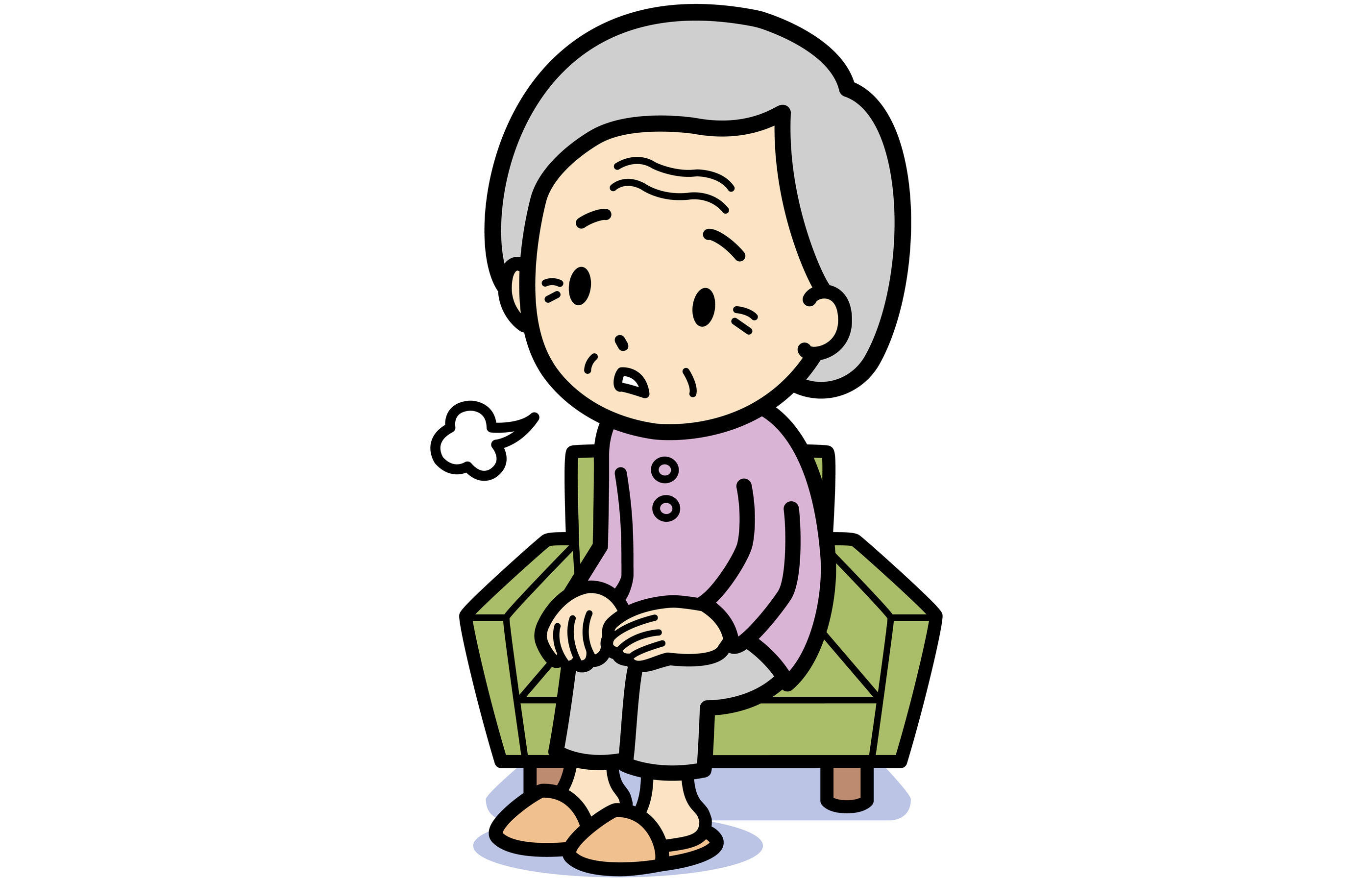д»Ӣиӯ·гҒ®дҫҝеҲ©её–гғҲгғғгғ—гҒёжҲ»гӮӢ
д»•дәӢгҒЁд»Ӣиӯ·гӮ’дёЎз«ӢгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®гҖҢд»Ӣиӯ·дј‘жҡҮгҖҚгҒЁгҖҢд»Ӣиӯ·дј‘жҘӯгҖҚгҒЁгҒҜ
зҸҫеңЁгҖҒеӣҪгҒҜгҖҢд»Ӣиӯ·йӣўиҒ·гӮјгғӯпјҲгҒ”家ж—ҸгҒ®д»Ӣиӯ·гҒ®гҒҹгӮҒгҒ«йӣўиҒ·гҒҷгӮӢдәәгӮ’гӮјгғӯгҒ«гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®еҜҫзӯ–пјүгҖҚгҒ«еҸ–гӮҠзө„гӮ“гҒ§гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ®еҸ–гӮҠзө„гҒҝгҒ®дёҖгҒӨгҒЁгҒ—гҒҰжҢҷгҒ’гӮүгӮҢгӮӢгҒ®гҒҢгҖҢд»Ӣиӯ·дј‘жҡҮгҖҚгҒЁгҖҢд»Ӣиӯ·дј‘жҘӯгҖҚгҒ§гҒҷгҖӮиӮІе…җдј‘жҘӯгҒЁжҜ”гҒ№гӮӢгҒЁгҖҒгҒҫгҒ гҒҫгҒ жөёйҖҸгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒҜгҒ„гҒҲгҒӘгҒ„зҠ¶жіҒгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒдёҠжүӢгҒ«еҲ©з”ЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§д»•дәӢгҒЁд»Ӣиӯ·гӮ’дёЎз«ӢгҒ—гӮ„гҒҷгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
д»ҠеӣһгҒҜгҖҒгҖҢд»Ӣиӯ·дј‘жҡҮгҖҚгҒЁгҖҢд»Ӣиӯ·дј‘жҘӯгҖҚгҒ®йҒ•гҒ„гӮ„д»Ӣиӯ·дј‘жҘӯзөҰд»ҳгҒ®жҙ»з”Ёжі•гҖҒжіЁж„ҸзӮ№гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰи§ЈиӘ¬гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҢд»Ӣиӯ·дј‘жҡҮгҖҚгҒЁгҒҜ

гҖҢд»Ӣиӯ·дј‘жҡҮгҖҚгҒҜгҖҒгҖҢиӮІе…җгғ»д»Ӣиӯ·дј‘жҘӯжі•гҖҚгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰе®ҡгӮҒгӮүгӮҢгҒҹеҲ¶еәҰгҒ®дёӯгҒ«гҒӮгӮӢгҒІгҒЁгҒӨгҒ®д»•зө„гҒҝгҒ§гҒҷгҖӮеғҚгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢдәәгҒ®гҒ”家ж—ҸгҒ®дёӯгҒ«гҖҢиҰҒд»Ӣиӯ·зҠ¶ж…ӢгҖҚгҒ®ж–№гӮ„гҖҒд»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ“гӮ№гҒ®жүӢз¶ҡгҒҚгӮ„з—…йҷўгҒ®д»ҳгҒҚж·»гҒ„гҒӘгҒ©гҒ®гҒҠдё–и©ұгҒҢеҝ…иҰҒгҒӘж–№гҒҢгҒ„гӮӢе ҙеҗҲгҒ«гҖҒдј‘жҡҮгӮ’еҸ–еҫ—гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
д»Ӣиӯ·дј‘жҡҮгҒҜгҖҒ1е№ҙй–“гҒ«гҒӨгҒҚ5ж—Ҙй–“гҖҒд»Ӣиӯ·гҒҢеҝ…иҰҒгҒӘгҒ”家ж—ҸгҒҢ2дәәд»ҘдёҠгҒ®е ҙеҗҲгҒҜ1е№ҙй–“гҒ«гҒӨгҒҚ10ж—Ҙй–“гӮ’йҷҗеәҰгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒ1ж—ҘеҚҳдҪҚгӮ„еҚҠж—ҘеҚҳдҪҚгҒ§гҒ®еҸ–еҫ—гҒҢеҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒҹгҒ гҒ—гҖҒеҚҠж—ҘеҚҳдҪҚгҒ§еҸ–еҫ—гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢйӣЈгҒ—гҒ„жҘӯеӢҷгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢж–№гӮ„1ж—ҘгҒ®жүҖе®ҡеҠҙеғҚжҷӮй–“гҒҢ4жҷӮй–“д»ҘдёӢгҒ®ж–№гҒҜгҖҒеҚҠж—ҘеҚҳдҪҚгҒ§гҒ®д»Ӣиӯ·дј‘жҡҮгӮ’еҸ–еҫ—гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„е ҙеҗҲгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
йӣҮз”ЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢеҠҙеғҚиҖ…гҒ§гҒӮгӮҢгҒ°жҙ»з”ЁгҒ§гҒҚгӮӢеҲ¶еәҰгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒж—ҘйӣҮеҠҙеғҚиҖ…гҒҜжҙ»з”ЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгҒҫгҒҹгҖҒе…ҘзӨҫгҒ—гҒҰ6гғ¶жңҲгӮ’зөҢйҒҺгҒ—гҒҰгҒӘгҒ„еҠҙеғҚиҖ…гӮ„1йҖұй–“гҒ®жүҖе®ҡеҠҙеғҚж—Ҙж•°гҒҢ2ж—Ҙд»ҘдёӢгҒ®еҠҙеғҚиҖ…гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒеҸ–еҫ—гҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
еҸ–еҫ—гҒ§гҒҚгӮӢж—Ҙж•°зӯүгӮ’жӢЎе……гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢдјҒжҘӯпјҲдјҡзӨҫпјүгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒи©ігҒ—гҒҸгҒҜгҒҠеӢӨгӮҒе…ҲгҒ«зўәиӘҚгҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
гҖҢд»Ӣиӯ·дј‘жҘӯгҖҚгҒЁгҒҜ

гҖҢд»Ӣиӯ·дј‘жҘӯгҖҚгӮӮд»Ӣиӯ·дј‘жҡҮгҒЁеҗҢгҒҳгҒҸгҖҒгҖҢиӮІе…җгғ»д»Ӣиӯ·дј‘жҘӯжі•гҖҚгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰе®ҡгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
еғҚгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢдәәгҒ®гҒ”家ж—ҸгҒ®дёӯгҒ«гҖҒгҖҢиҰҒд»Ӣиӯ·зҠ¶ж…ӢгҖҚгҒ®ж–№гҒҢгҒ„гӮӢе ҙеҗҲгҖҒеҜҫиұЎе®¶ж—Ҹ1дәәгҒ«гҒӨгҒҚгҖҒйҖҡз®—гҒ—гҒҰ93ж—ҘгҒҫгҒ§гҖҒгҒҫгҒҹ3еӣһгҒҫгҒ§еҸ–еҫ—гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶеҲ¶еәҰгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒҹгҒ гҒ—гҖҒе…ҘзӨҫгҒ—гҒҰ1е№ҙгӮ’зөҢйҒҺгҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„еҠҙеғҚиҖ…гӮ„д»Ӣиӯ·дј‘жҘӯгӮ’з”іи«ӢгҒҷгӮӢж—ҘгҒӢгӮү93ж—Ҙд»ҘеҶ…гҒ«йҖҖиҒ·гҒҷгӮӢдәҲе®ҡгҒ®еҠҙеғҚиҖ…гҖҒ1йҖұй–“гҒ®жүҖе®ҡеҠҙеғҚж—Ҙж•°гҒҢ2ж—Ҙд»ҘдёӢгҒ®еҠҙеғҚиҖ…гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒжҙ»з”ЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒҠеӢӨгӮҒе…ҲгҒ«зўәиӘҚгҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
д»Ӣиӯ·дј‘жҡҮгғ»д»Ӣиӯ·дј‘жҘӯгӮ’еҲ©з”ЁгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®гҖҢиҰҒд»Ӣиӯ·зҠ¶ж…ӢгҖҚгҒЁгҒҜ
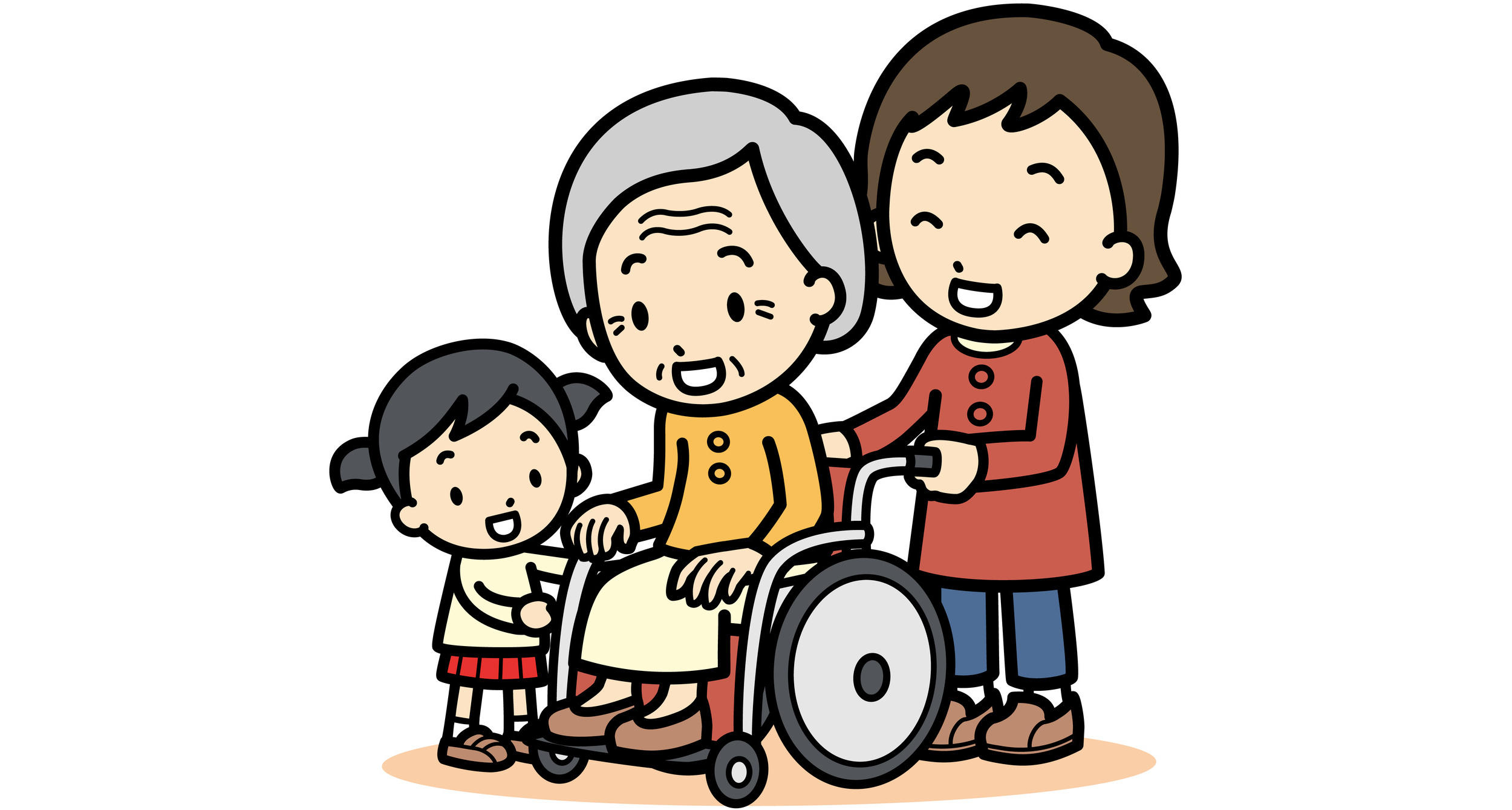
д»Ӣиӯ·дј‘жҡҮгғ»д»Ӣиӯ·дј‘жҘӯгҒҜгҖҒеҺҹеүҮгҒЁгҒ—гҒҰеҜҫиұЎе®¶ж—ҸгҒҢгҖҢиҰҒд»Ӣиӯ·зҠ¶ж…ӢгҖҚгҒ§гҒӮгӮӢе ҙеҗҲгҒ«еҲ©з”ЁгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҢиҰҒд»Ӣиӯ·зҠ¶ж…ӢгҖҚгҒЁгҒҜгҖҢиІ еӮ·гҖҒз–ҫз—…еҸҲгҒҜиә«дҪ“дёҠиӢҘгҒ—гҒҸгҒҜзІҫзҘһдёҠгҒ®йҡңе®ігҒ«гӮҲгӮҠгҖҒ2йҖұй–“д»ҘдёҠгҒ®жңҹй–“гҒ«гӮҸгҒҹгӮҠеёёжҷӮд»Ӣиӯ·гӮ’еҝ…иҰҒгҒЁгҒҷгӮӢзҠ¶ж…ӢгҖҚгӮ’гҒ„гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
дёҠиЁҳгӮ’иҰӢгӮӢгҒЁгҖҒд»Ӣиӯ·дҝқйҷәеҲ¶еәҰгҒ®иҰҒд»Ӣиӯ·гғ»иҰҒж”ҜжҸҙиӘҚе®ҡгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹж–№гҒЁгҒ„гҒҶгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮиҰҒд»Ӣиӯ·гғ»иҰҒж”ҜжҸҙиӘҚе®ҡгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„е ҙеҗҲгҒ§гӮӮгҖҢеёёжҷӮд»Ӣиӯ·гӮ’еҝ…иҰҒгҒЁгҒҷгӮӢзҠ¶ж…ӢгҖҚгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁиӘҚгӮҒгӮүгӮҢгӮҢгҒ°еҸ–еҫ—гҒҢеҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖӮ
д»ҘдёӢпјҲпј‘пјүгҒҫгҒҹгҒҜпјҲпј’пјүгҒ®гҒ„гҒҡгӮҢгҒӢгҒ«и©ІеҪ“гҒҷгӮӢе ҙеҗҲгҒҜгҖҒд»Ӣиӯ·дј‘жҘӯеҲ¶еәҰгӮ’жҙ»з”ЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҒ”зўәиӘҚгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ
пјҲ1пјүгҖҖд»Ӣиӯ·дҝқйҷәеҲ¶еәҰгҒ®иҰҒд»Ӣиӯ·иӘҚе®ҡгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢдәәгҒ§иҰҒд»Ӣиӯ·2д»ҘдёҠгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҖӮ
пјҲ2пјүгҖҖд»ҘдёӢгҒ®зҠ¶ж…Ӣв‘ пҪһв‘«гҒ®гҒҶгҒЎгҖҒ2гҒҢ2гҒӨд»ҘдёҠгҒӮгӮӢгҖҒгҒҫгҒҹгҒҜ3гҒҢ1гҒӨд»ҘдёҠгҒӮгӮӢе ҙеҗҲгҒ§гҖҒгҒӢгҒӨгҖҒгҒқгҒ®зҠ¶ж…ӢгҒҢ2йҖұй–“д»ҘдёҠгҒ®жңҹй–“гҒ«гӮҸгҒҹгҒЈгҒҰз¶ҷз¶ҡгҒҷгӮӢгҒЁиӘҚгӮҒгӮүгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҖӮ
гҖҢеёёжҷӮд»Ӣиӯ·гӮ’еҝ…иҰҒгҒЁгҒҷгӮӢзҠ¶ж…ӢгҖҚгҒ®еҲӨж–ӯеҹәжә–
| 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|
| в‘ еә§дҪҚдҝқжҢҒпјҲ10еҲҶй–“дёҖдәәгҒ§еә§гҒЈгҒҰ гҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢпјү |
иҮӘеҲҶгҒ§еҸҜ | ж”ҜгҒҲгҒҰгӮӮгӮүгҒҲгӮҢгҒ°гҒ§гҒҚгӮӢ | гҒ§гҒҚгҒӘгҒ„ |
| в‘Ўжӯ©иЎҢпјҲз«ӢгҒЎжӯўгҒҫгӮүгҒҡгҖҒеә§гӮҠиҫјгҒҫ гҒҡгҒ«пј•пҪҚзЁӢеәҰжӯ©гҒҸгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢпјү |
гҒӨгҒӢгҒҫгӮүгҒӘгҒ„ гҒ§гҒ§гҒҚгӮӢ |
дҪ•гҒӢгҒ«гҒӨгҒӢгҒҫгӮҢгҒ°гҒ§гҒҚгӮӢ | гҒ§гҒҚгҒӘгҒ„ |
| ③移乗пјҲгғҷгғғгғүгҒЁи»ҠгҒ„гҒҷгҖҒи»ҠгҒ„гҒҷ гҒЁдҫҝеә§гҒ®й–“гӮ’移гӮӢгҒӘгҒ©гҒ®д№—гӮҠ移гӮҠ гҒ®еӢ•дҪңпјү |
иҮӘеҲҶгҒ§еҸҜ | дёҖйғЁд»ӢеҠ©гҖҒиҰӢе®ҲгӮҠзӯүгҒҢеҝ…иҰҒ | е…Ёйқўзҡ„д»ӢеҠ©гҒҢеҝ…иҰҒ |
| в‘Јж°ҙеҲҶгғ»йЈҹдәӢж‘ӮеҸ– | иҮӘеҲҶгҒ§еҸҜ | дёҖйғЁд»ӢеҠ©гҖҒиҰӢе®ҲгӮҠзӯүгҒҢеҝ…иҰҒ | е…Ёйқўзҡ„д»ӢеҠ©гҒҢеҝ…иҰҒ |
| в‘ӨжҺ’жі„ | иҮӘеҲҶгҒ§еҸҜ | дёҖйғЁд»ӢеҠ©гҖҒиҰӢе®ҲгӮҠзӯүгҒҢеҝ…иҰҒ | е…Ёйқўзҡ„д»ӢеҠ©гҒҢеҝ…иҰҒ |
| в‘ҘиЎЈйЎһгҒ®зқҖи„ұ | иҮӘеҲҶгҒ§еҸҜ | дёҖйғЁд»ӢеҠ©гҖҒиҰӢе®ҲгӮҠзӯүгҒҢеҝ…иҰҒ | е…Ёйқўзҡ„д»ӢеҠ©гҒҢеҝ…иҰҒ |
| в‘Ұж„ҸжҖқгҒ®дјқйҒ” | гҒ§гҒҚгӮӢ | гҒЁгҒҚгҒ©гҒҚгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„ | гҒ§гҒҚгҒӘгҒ„ |
| ⑧еӨ–еҮәгҒҷгӮӢгҒЁжҲ»гӮҢгҒӘгҒ„ | гҒӘгҒ„ | гҒЁгҒҚгҒ©гҒҚгҒӮгӮӢ | гҒ»гҒЁгӮ“гҒ©жҜҺж—ҘгҒӮгӮӢ |
| в‘Ёзү©гӮ’еЈҠгҒ—гҒҹгӮҠиЎЈйЎһгӮ’з ҙгҒҸгҒ“гҒЁгҒҢ гҒӮгӮӢ |
гҒӘгҒ„ | гҒЁгҒҚгҒ©гҒҚгҒӮгӮӢ | гҒ»гҒЁгӮ“гҒ©жҜҺж—ҘгҒӮгӮӢ |
| в‘©е‘ЁеӣІгҒ®иҖ…гҒҢдҪ•гӮүгҒӢгҒ®еҜҫеҝңгӮ’гҒЁгӮү гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒ»гҒ©гҒ®зү©еҝҳгӮҢгҒҢ гҒӮгӮӢ |
гҒӘгҒ„ | гҒЁгҒҚгҒ©гҒҚгҒӮгӮӢ | гҒ»гҒЁгӮ“гҒ©жҜҺж—ҘгҒӮгӮӢ |
| в‘Әи–¬гҒ®еҶ…жңҚ | иҮӘеҲҶгҒ§еҸҜ | дёҖйғЁд»ӢеҠ©гҖҒиҰӢе®ҲгӮҠзӯүгҒҢеҝ…иҰҒ | е…Ёйқўзҡ„д»ӢеҠ©гҒҢеҝ…иҰҒ |
| в‘«ж—ҘеёёгҒ®ж„ҸжҖқжұәе®ҡ | гҒ§гҒҚгӮӢ | жң¬дәәгҒ«й–ўгҒҷгӮӢйҮҚиҰҒгҒӘж„ҸжҖқжұәе®ҡгҒҜ гҒ§гҒҚгҒӘгҒ„ |
гҒ»гҒЁгӮ“гҒ©гҒ§гҒҚгҒӘгҒ„ |
еҮәе…ёпјҡеҺҡз”ҹеҠҙеғҚзңҒгҖҖиӮІе…җгғ»д»Ӣиӯ·дј‘жҘӯеҲ¶еәҰгӮ¬гӮӨгғүгғ–гғғгӮҜhttp://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h27_12.pdf
гҖҢеҜҫиұЎе®¶ж—ҸгҖҚгҒ®зҜ„еӣІгҒЁгҒҜ
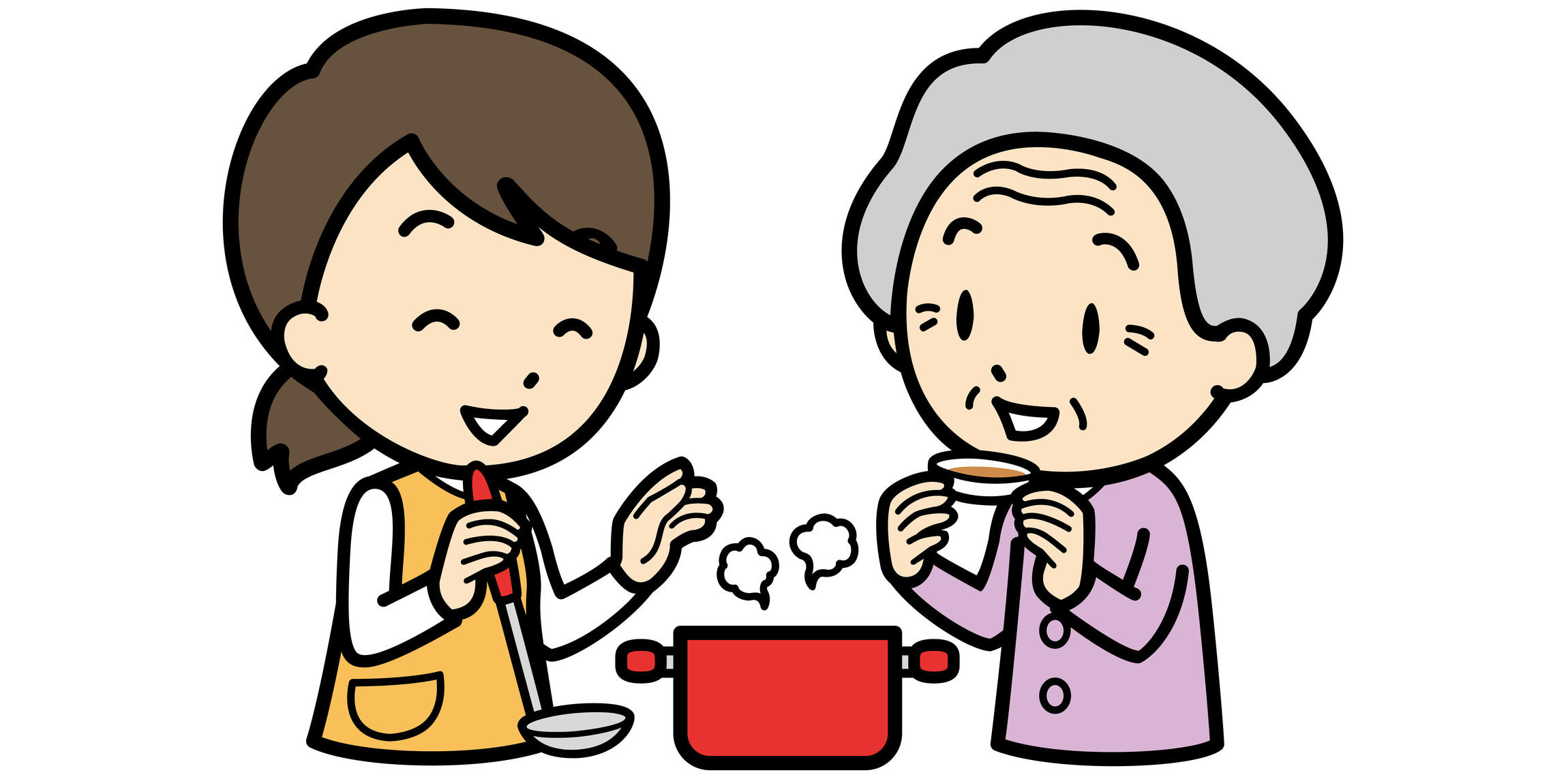
д»Ӣиӯ·дј‘жҡҮгғ»д»Ӣиӯ·дј‘жҘӯгҒ®гҖҢеҜҫиұЎе®¶ж—ҸгҖҚгҒҜгҖҒиӮІе…җгғ»д»Ӣиӯ·дј‘жҘӯжі•гҒ§ж¬ЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«е®ҡгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҢй…ҚеҒ¶иҖ…пјҲдәӢе®ҹе©ҡгӮ’еҗ«гӮҖпјүгҖҒзҲ¶жҜҚгҖҒеӯҗгҖҒй…ҚеҒ¶иҖ…гҒ®зҲ¶жҜҚгҖҒзҘ–зҲ¶жҜҚгҖҒе…„ејҹе§үеҰ№гҒҠгӮҲгҒіеӯ«гҖҚ
вҖ»д»Ӣиӯ·й–ўдҝӮгҒ®гҖҢеӯҗгҖҚгҒ®зҜ„еӣІгҒҜгҖҒжі•еҫӢдёҠгҒ®иҰӘеӯҗй–ўдҝӮгҒҢгҒӮгӮӢеӯҗпјҲйӨҠеӯҗгӮ’еҗ«гӮҖпјүгҒ®гҒҝ
еҜҫиұЎгҒЁгҒӘгӮӢгҒ”家ж—ҸгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒеҗҢеұ…гӮ„жү¶йӨҠгҒҢиҰҒ件гҒЁгҒҜгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒӣгӮ“гҖӮпјҲвҖ»2017е№ҙ10жңҲ1ж—ҘгҒ®ж”№жӯЈгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒгҖҢзҘ–зҲ¶жҜҚгҖҒе…„ејҹе§үеҰ№гҖҒеӯ«гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒ®еҗҢеұ…гғ»жү¶йӨҠиҰҒ件гҖҚгҒҜз„ЎгҒҸгҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮпјүйӣўгӮҢгҒҹе ҙжүҖгҒ«дҪҸгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢгҒЁгҒ—гҒҰгӮӮгҖҒжү¶йӨҠгҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒЁгҒ—гҒҰгӮӮгҖҒд»Ӣиӯ·дј‘жҡҮгӮ„д»Ӣиӯ·дј‘жҘӯгҒ®еҸ–еҫ—гҒҜеҸҜиғҪгҒ§гҒҷгҖӮ
гҖҢд»Ӣиӯ·дј‘жҘӯзөҰд»ҳгҖҚгҒЁгҒҜ
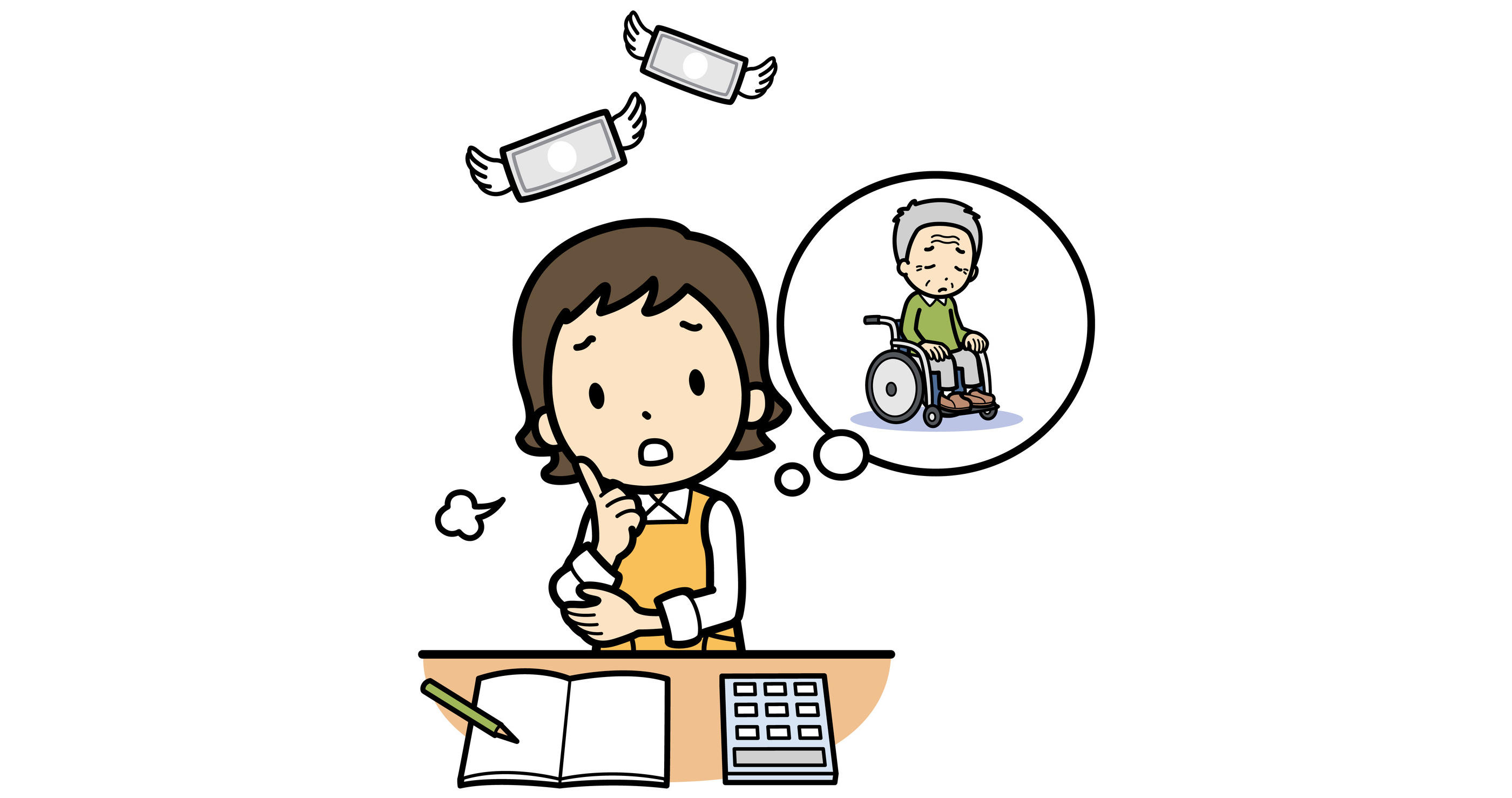
гҒ”家ж—ҸгҒ®д»Ӣиӯ·гҒ®гҒҹгӮҒгҒ«д»•дәӢгӮ’дј‘гӮҖгҒЁгҖҒдәӢжҘӯдё»гҒ«зөҰдёҺгӮ’ж”Ҝжү•гҒҶзҫ©еӢҷгҒҢгҒӘгҒ„гҒҹгӮҒгҖҒеҺҹеүҮгҒЁгҒ—гҒҰгҒҠзөҰж–ҷгҒҜж”Ҝжү•гӮҸгӮҢгҒҫгҒӣгӮ“пјҲгҒҠеӢӨгӮҒе…ҲгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҒҜж”ҜзөҰгҒ•гӮҢгӮӢе ҙеҗҲгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷпјүгҖӮ
гҒқгҒ“гҒ§еҲ©з”ЁгҒ—гҒҹгҒ„гҒ®гҒҢгҖҢд»Ӣиӯ·дј‘жҘӯзөҰд»ҳйҮ‘еҲ¶еәҰгҖҚгҒ§гҒҷгҖӮгҖҢд»Ӣиӯ·дј‘жҘӯзөҰд»ҳгҖҚгҒҜгҖҒд»Ӣиӯ·иІ»з”ЁгҒҢгҒӢгҒӢгӮӢдёҠгҒ«з„ЎзөҰгҒ«гҒӘгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶзҠ¶жіҒгӮ’ж•‘гҒҶгҒҹгӮҒгҒ®жүҖеҫ—дҝқйҡңгҒ®дёҖгҒӨгҒ§гҒҷгҖӮ
йӣҮз”ЁдҝқйҷәгҒ®иў«дҝқйҷәиҖ…пјҲдёҖиҲ¬иў«дҝқйҷәиҖ…гҒҠгӮҲгҒій«ҳе№ҙйҪўиў«дҝқйҷәиҖ…пјүгҒ®ж–№гҒҢгҖҒиҰҒд»Ӣиӯ·зҠ¶ж…ӢгҒ®еҜҫиұЎе®¶ж—ҸгӮ’д»Ӣиӯ·гҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«д»Ӣиӯ·дј‘жҘӯгӮ’еҸ–еҫ—гҒ—гҒҹе ҙеҗҲгҖҒдёҖе®ҡгҒ®иҰҒ件гӮ’жәҖгҒҹгҒҷгҒЁд»Ӣиӯ·дј‘жҘӯзөҰд»ҳгҒ®ж”ҜзөҰгӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
д»Ӣиӯ·дј‘жҘӯзөҰд»ҳгҒ®ж”ҜзөҰйЎҚ
еҗ„ж”ҜзөҰеҜҫиұЎжңҹй–“пјҲ1гҒӢжңҲпјүгҒ”гҒЁгҒ®ж”ҜзөҰйЎҚгҒҜгҖҒеҺҹеүҮгҒЁгҒ—гҒҰгҖҢдј‘жҘӯй–Ӣе§ӢжҷӮиіғйҮ‘ж—ҘйЎҚГ—ж”ҜзөҰж—Ҙж•°Г—67пј…гҖҚгҒ§гҒҷгҖӮж”ҜзөҰгҒҜ93ж—ҘгӮ’йҷҗеәҰгҒ«гҖҒпј“еӣһгҒҫгҒ§гҒ«йҷҗгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
д»Ӣиӯ·дј‘жҘӯзөҰд»ҳгҒҜйқһиӘІзЁҺгҒ§гҖҒз„ЎзөҰгҒ§гҒӮгӮҢгҒ°жүҖеҫ—зЁҺгӮ„йӣҮз”Ёдҝқйҷәж–ҷгҒҜжҺ§йҷӨгҒ•гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
д»Ӣиӯ·дј‘жҘӯзөҰд»ҳгҒ®жүӢз¶ҡгҒҚ
дәӢжҘӯдё»гҒҢгҖҒдәӢжҘӯжүҖгҒ®жүҖеңЁең°гӮ’з®ЎиҪ„гҒҷгӮӢгғҸгғӯгғјгғҜгғјгӮҜпјҲе…¬е…ұиҒ·жҘӯе®үе®ҡжүҖпјүгҒ«гҖҢд»Ӣиӯ·дј‘жҘӯзөҰд»ҳйҮ‘ж”ҜзөҰз”іи«ӢжӣёгҖҚгҒЁгҖҢдј‘жҘӯй–Ӣе§ӢжҷӮиіғйҮ‘жңҲйЎҚиЁјжҳҺжӣёгҖҚгӮ’жҸҗеҮәгҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҢд»Ӣиӯ·дј‘жҘӯзөҰд»ҳгҖҚгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰи©ігҒ—гҒҸгҒҜгҖҒгҒҠиҝ‘гҒҸгҒ®гғҸгғӯгғјгғҜгғјгӮҜпјҲе…¬е…ұиҒ·жҘӯе®үе®ҡжүҖпјүгҒёгҒҠе•ҸгҒ„еҗҲгӮҸгҒӣгҒҸгҒ гҒ•гҒ„гҖӮ
жі•еҫӢгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰе®ҡгӮҒгӮүгӮҢгҒҹгҖҢд»Ӣиӯ·дј‘жҘӯеҲ¶еәҰгҖҚгҒҜгҖҒгҒҠеӢӨгӮҒе…ҲгҒ®е°ұжҘӯиҰҸеүҮгҒ«иЁҳијүгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒҸгҒҰгӮӮеҲ©з”ЁгҒ§гҒҚгӮӢеҲ¶еәҰгҒ§гҒҷгҖӮжӯЈзӨҫе“ЎгҒ®ж–№гҒ гҒ‘гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒеҘ‘зҙ„зӨҫе“ЎгӮ„гғ‘гғјгғҲгҖҒгӮўгғ«гғҗгӮӨгғҲгҒ®ж–№гӮӮиҰҒ件гӮ’жәҖгҒҹгҒӣгҒ°д»Ӣиӯ·дј‘жҘӯгӮ’еҸ–еҫ—гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ еғҚгҒҚгҒӘгҒҢгӮүз„ЎзҗҶгҒӘгҒҸд»Ӣиӯ·гӮ’иЎҢгҒҶгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒгҖҢд»Ӣиӯ·дј‘жҡҮгҖҚгӮ„гҖҢд»Ӣиӯ·дј‘жҘӯгҖҚгӮ’дёҠжүӢгҒ«жҙ»з”ЁгҒ—гҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
зү№еҲҘйӨҠиӯ·иҖҒдәәгғӣгғјгғ иІ¬д»»иҖ…гҖҒеұ…е®…д»Ӣиӯ·ж”ҜжҸҙдәӢжҘӯжүҖгҒ®з®ЎзҗҶиҖ…гӮ’зөҢгҒҰгҖҒзҸҫеңЁгҖҒд»Ӣиӯ·гӮігғігӮөгғ«гӮҝгғігғҲгҒ«еҸ–гӮҠзө„гӮ“гҒ§гҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ дё»д»»д»Ӣиӯ·ж”ҜжҸҙе°Ӯй–Җе“ЎгҖҒзӨҫдјҡзҰҸзҘүеЈ«гҖҒд»Ӣиӯ·зҰҸзҘүеЈ«гӮ’еҸ–еҫ—гҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ

FacebookгғҡгғјгӮёгҒ§
жңҖж–°иЁҳдәӢй…ҚдҝЎпјҒпјҒ
 гғ¬гӮӘгғҸгӮҡгғ¬гӮ№21гӮҜгӮҷгғ«гғјгғ•гӮҡгҒ®д»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ’гӮҷгӮ№
гғ¬гӮӘгғҸгӮҡгғ¬гӮ№21гӮҜгӮҷгғ«гғјгғ•гӮҡгҒ®д»Ӣиӯ·гӮөгғјгғ’гӮҷгӮ№