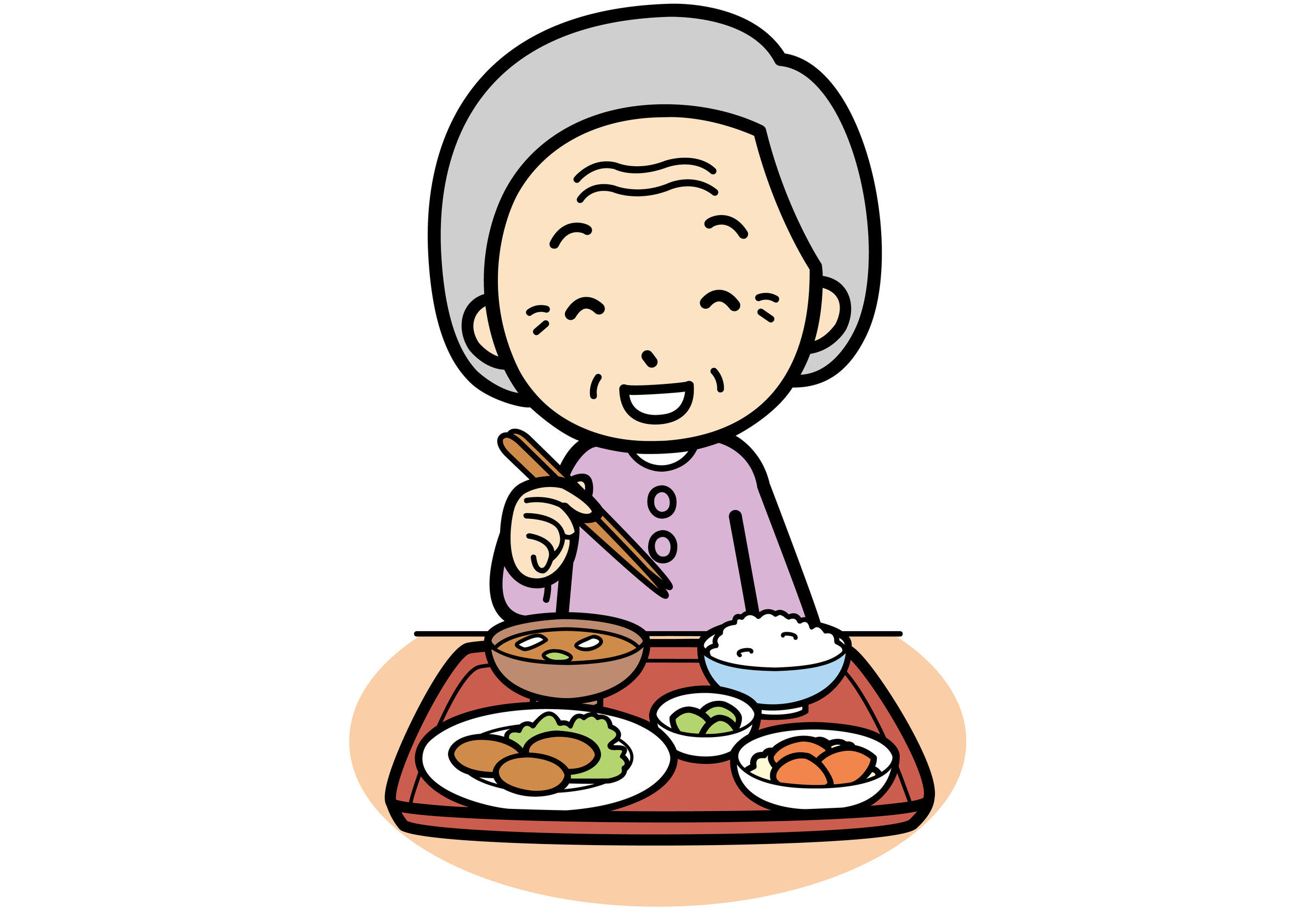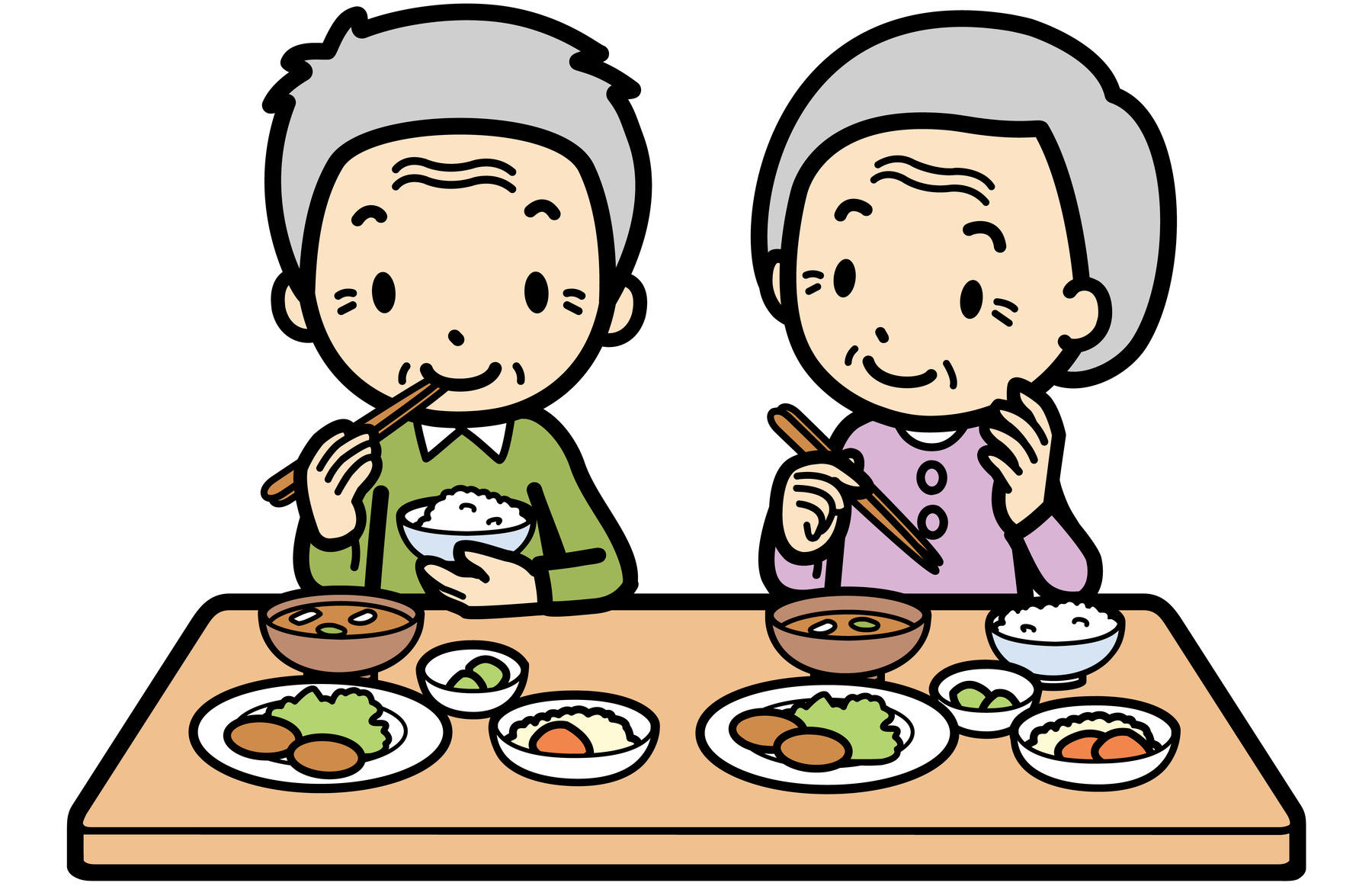дїЛи≠ЈгБЃдЊњеИ©еЄЦгГИгГГгГЧгБЄжИїгВЛ
жШ•гБМжЧђпЉБйѓЫгБ®з≠НгБЃзВКгБНиЊЉгБњгБФй£ѓгАРдїЛи≠Јй£ЯгБЃгГђгВЈгГФ#6гАС
гБУгБЃи®ШдЇЛгВТпЉУи°МгБІиІ£и™ђгБЩгВЛгБ®
- гГї йѓЫгБЃгВҐгГ©гБІгБЖгБЊгБњгБЯгБ£гБЈгВКгБЃгБ†гБЧгВТеПЦгВЛгАВ
- гГї гГЮгВ∞гВЂгГГгГЧгВТдљњгБ£гБ¶еЃґжЧПгБЃеИЖгБ®еРМжЩВгБЂи™њзРЖгАВ
- гГї ж†Дй§Ки±КеѓМгБ™жЧђгБЃзі†жЭРгБМй£ЯгБєгВЙгВМгВЛпЉБ

еЖђгБЛгВЙж°ЬгБМеТ≤гБПжШ•гБЂгБЛгБСгБ¶жЧђгВТињОгБИгВЛйѓЫгБѓгАБгБЭгБЃжЩВжЬЯгВДи¶ЛгБЯзЫЃгБЛгВЙеИ•еРНгАМж°ЬйѓЫгАНгБ®гВВеСЉгБ∞гВМгБ¶гБДгБЊгБЩгАВйѓЫгБМзЊОеС≥гБЧгБПгБ™гВЛй†ГгБѓеНТж•≠еЉПгВДеЕ•е≠¶еЉПгБ™гБ©гАБгБКгВБгБІгБЯгБДгБУгБ®гБМе§ЪгБПгБВгВЛе≠£зѓАгБІгБЩгАВ
дїКеЫЮгБѓгАБгБЭгВУгБ™гБКгВБгБІгБЯгБДеЄ≠гБЂгВВгБігБ£гБЯгВКгБ™йѓЫгБ®з≠НгБЃзВКгБНгБУгБњгБФй£ѓгВТгБФзієдїЛгБЧгБЊгБЩгАВпЉСеМєдЄЄгАЕзФ®жДПгБЧгБ™гБПгБ¶гВВгАБеИЗгВКиЇЂгБ®гВҐгГ©гБМгБВгВМгБ∞зЊОеС≥гБЧгБПдљЬгВМгБЊгБЩгАВ
зВКгБНжЦєгБЂгВВгАБгБ≤гБ®еЈ•е§ЂгБВгВЛгБЃгБІгАБгГБгВІгГГгВѓгБЧгБ¶гБњгБ¶гБПгБ†гБХгБДгБ≠гАВ
вЙ™жЭРжЦЩвЙЂгААеЕ®дљУгБІ3еРИеИЖ
| йѓЫеИЗгВКиЇЂ | пЉТеИЗгВМпЉИ150вДКз®ЛпЉЙ |
| йѓЫгВҐгГ© | пЉСгГСгГГгВѓеИЖ |
| з≠Нж∞ізЕЃ | пЉСжЬђпЉИ170вДКпЉЙ |
| зµєгБХгВД | пЉФжЬђ |
| з±≥ | пЉУеРИпЉИ390gпЉЛ60gпЉЙ |
| ж∞і | 650гПДпЉИйѓЫгБЃиЇЂгБМйЪ†гВМгВЛз®ЛеЇ¶пЉЙ |
| жњГеП£йЖђж≤є | е§ІпЉУпЉИиЦДеП£гБЃе†іеРИгБѓе§ІпЉТпЉЙ |
| йЕТ | е§ІпЉТ |
| гБЩгВКгБКгВНгБЧзФЯеІЬпЉИгГБгГ•гГЉгГЦгБІгВВдї£зФ®еПѓпЉЙ | е∞ПгБХгБШпЉС |

йѓЫгБЂгБѓгАБжњГеОЪгБ™гБЖгБЊгБњгБМгБВгВКгВњгГ≥гГСгВѓи≥™гБ™гБ©гБЃж†Дй§КеИЖгБМи±КеѓМгБІгБЩгАВдїЦгБЃгБКй≠ЪгБЂжѓФгБєгБ¶иДВи≥™гБМе∞СгБ™гБПжґИеМЦгБМгБДгБДгБЃгБІгАБиГГгБЂи≤†жЛЕгВТгБЛгБСгБЯгБПгБ™гБДгБФйЂШ隥гБЃжЦєгБЂгВВгБігБ£гБЯгВКгБ™гБКй≠ЪгБІгБЩгАВ
вЙ™дљЬгВКжЦєвЙЂ
вС† й¶ЩгБ∞гБЧгБХгВТеЗЇгБЩгБЯгВБйѓЫгБЃеИЗгВКиЇЂгБ®гВҐгГ©гВТй≠ЪзДЉгБНгВ∞гГ™гГЂгБІи°®йЭҐгБЂиЦДгБДзДЉгБНиЙ≤гБМгБ§гБПгБЊгБІзДЉгБДгБ¶гБДгБНгБЊгБЩгАВ
пЉИдЄ≠гБЊгБІгБЧгБ£гБЛгВКгБ®зБЂгБМйАЪгВЙгБ™гБПгБ¶гВВе§ІдЄИе§ЂгБІгБЩпЉЙ


вС° йНЛгБЂвЮАгБІзДЉгБДгБЯгВҐгГ©гВТеЕ•гВМгАБж∞і650гПДгВТеЕ•гВМгБ¶еЉ±зБЂгБІгБµгБ§гБµгБ§гБ®15еИЖз®ЛзЕЃгБЊгБЩгАВгБУгВМгБМгБ†гБЧж±БгБ®гБ™гВКгБЊгБЩгАВзЕЃгБЯгБ†гБЧгБ®гВҐгГ©гБѓпЉСеЇ¶гБУгБЧгБ¶гГЬгВ¶гГЂгБЂзІїгБЧгБЊгБЩгАВгБУгБЃгБ®гБНгАБгВҐгГ©гБѓй™®гБЛгВЙиЇЂгВТе§ЦгБЧгБ¶гБКгБНгБЊгБЩгАВ

- гВҐгГ©гБѓдЄАзЈТгБЂзВКгБНгБУгБЊгБЪгБЂгАБдЇЛеЙНгБЂгБ†гБЧгВТеПЦгВКгАБй™®гБЛгВЙиЇЂгВТе§ЦгБЩгБУгБ®гБІгБФгБѓгВУгБЂй™®гБМжЈЈеЕ•гБЩгВЛгБЃгВТйШ≤гБОй£ЯгБєгВДгБЩгБПгБЧгБЊгБЩгАВ

вСҐ з≠НгБѓпЉУгОЭз®ЛгБЃзЯ≠еЖКеИЗгВКгБЂгБЧгАБдїЛи≠Јй£ЯзФ®гБЂгБѓжЫігБЂзі∞гБЛгБПй£ЯгБєгВДгБЩгБДе§ІгБНгБХгБЂеИЗгВКгБЊгБЩгАВзФЯеІЬгБѓгБЩгВКгБКгВНгБЧгБЊгБЩпЉИгГБгГ•гГЉгГЦгБІгВВдї£зФ®еПѓпЉЙгАВ

- з≠НгБѓж†єжЬђгВИгВКгВВз©ВеЕИгБМгВДгВПгВЙгБЛгБПй£ЯгБєгВДгБЩгБДгБІгБЩгАВ


вС£ гГЬгВ¶гГЂгБЂвС°гБЃгБ†гБЧж±БгБЃгБЖгБ°450гПДгВТеЕ•гВМгБ¶гАБйЕТгГїйЖ§ж≤єгГїгБЩгВКгБКгВНгБЧзФЯеІЬгВТеЕ®гБ¶еЕ•гВМгБ¶жЈЈгБЬгБЊгБЩгАВ

вС§ гБКз±≥гВТз†ФгБДгБ†гВЙгАБйЩґеЩ®гБЃгГЮгВ∞гВЂгГГгГЧгБЂдЄЛи®ШгВТеЕ•гВМгБ¶зВКй£ѓеЩ®гБЃзЬЯгВУдЄ≠гБЂзљЃгБНгБЊгБЩгАВ
гГїгБКз±≥3еРИгБЃеЖЕгБЃ60g
гГївС°гБЃжЃЛгВКгБЃгБ†гБЧж±БгБЃгБЖгБ°50ccгБ®гВҐгГ©гБЛгВЙе§ЦгБЧгБЯиЇЂ
гГївСҐгБЃз≠Н
гГївС£гБІдљЬгБ£гБЯи™њеС≥жЦЩеЕ•гВКгБЃгБ†гБЧж±Б
вАїгГЮгВ∞гВЂгГГгГЧгБЂеЕ•гВМгВЛйЗПгБѓгАБгВЂгГГгГЧгБЃ7еИЖзЫЃгБМзЫЃеЃЙгБІгБЩгАВ

- дїЛи≠Јй£ЯзФ®гБЃжЭРжЦЩгВТгГЮгВ∞гВЂгГГгГЧгБЂеЕ•гВМгБ¶зВКгБПгБУгБ®гБІгАБеИ•гАЕгБЂдљЬгВЛжЙЛйЦУгБМзЬБгБСгБ¶жЩВзЯ≠гБЂгБ™гВКгБЊгБЩгАВ

вС• зµєгБХгВДгВТйЩ§гБДгБЯжЃЛгВКеЕ®гБ¶гБЃжЭРжЦЩгВТгГЮгВ∞гВЂгГГгГЧгБЃеС®гВКгБЂеЕ•гВМгБ¶гАБйАЪеЄЄгГҐгГЉгГЙгБІзВКгБНгБЊгБЩгАВ
вС¶ зВКгБНдЄКгБМгБ£гБЯгВЙгАБзБЂеВЈгБЂж∞ЧгВТдїШгБСгБ™гБМгВЙгГЮгВ∞гВЂгГГгГЧгВТеПЦгВКеЗЇгБЧгАБгГЬгВ¶гГЂгБЂдЄ≠иЇЂгВТеЗЇгБЧгБ¶еЕ®дљУгВТжЈЈгБЬгБЊгБЩгАВгБФеЃґжЧПгБЃеИЖгБѓеИЗгВКиЇЂгБЛгВЙй™®гБМеЕ•гВЙгБ™гБДгВИгБЖгБЂиЇЂгВТе§ЦгБЧгАБеЕ®дљУгВТгБЦгБ£гБПгВКгБ®жЈЈгБЬгБЊгБЩгАВ
гБХгБ£гБ®иМєгБІгБЯзµєгБХгВДпЉИйЫїе≠РгГђгГ≥гВЄгВВеПѓпЉЙгВТеЩ®гБЂзЫЫгВКдїШгБСгВМгБ∞еЃМжИРгБІгБЩгАВзµєгБХгВДгБѓгАБдїЛи≠Јй£ЯзФ®гБЃгБФй£ѓгБЂгБѓзі∞гБЛгБПеИЗгБ£гБ¶гАБзЫЫгВКдїШгБСгБЊгБЧгВЗгБЖгАВ

- е∞СгАЕжЈЈгБЬгВЛгБЃгБМе§Іе§ЙгБІгБЩгБМгАБи™њзРЖгБЂдљњгБ£гБЯгВЂгГГгГЧгВТгБНгВМгБДгБЂгБµгБДгБ¶гБЭгБЃгБЊгБЊгБКеПђгБЧгБВгБМгВКгБДгБЯгБ†гБПгБУгБ®гВВгБІгБНгБЊгБЩгАВгБКж∞ЧгБЂеЕ•гВКгБЃгБКй£ЯдЇЛзФ®гВЂгГГгГЧгВТжОҐгБХгВМгВЛгБЃгВВж•љгБЧгБДгБІгБЩгБ≠гАВ

гБКгВПгВКгБЂ
дїКеЫЮгБѓгАБгБФеЃґжЧПгБЃеИЖгБ®гАБдїЛи≠Јй£ЯзФ®гБ®гВТдЄАзЈТгБЂзВКгБНдЄКгБТгВЛжЦєж≥ХгБІзВКгБНиЊЉгБњгБЊгБЧгБЯгАВгГЮгВ∞гВЂгГГгГЧгВТдљњгБДгАБеИЖгБСгБ¶зВКгБНиЊЉгВАгБУгБ®гБІгАБдїЛи≠Јй£ЯзФ®гБѓеЕЈжЭРгБМзі∞гБЛгБПгБ™гВКжЯФгВЙгБЛгВБгБЃгБФй£ѓгБЂдїХдЄКгБМгВКгАБгБФеЃґжЧПгБЃеИЖгБѓе≠ШеЬ®жДЯгБЃгБВгВЛеЕЈжЭРгВТгБКж•љгБЧгБњгБДгБЯгБ†гБСгБЊгБЩгАВ
йѓЫгБ®еРМгБШгВИгБЖгБЂжЧђгВТињОгБИгВЛз≠НгАВдїКеЫЮгБѓеЄВи≤©гБЃж∞ізЕЃгБЃгВВгБЃгВТдљњзФ®гБЧгБЊгБЧгБЯгБМгАБгВВгБ°гВНгВУзФЯгБЃз≠НгВТгВҐгВѓжКЬгБНгБЧгБ¶гВВгБКгБДгБЧгБПгБІгБНгБЊгБЩгАВгВҐгВѓжКЬгБНгБМйЭҐеАТгБ™жЦєгБѓгАБжЧђгБЃжЩВжЬЯгБЂгБѓгВҐгВѓгВТжКЬгБДгБ¶гБВгВЛз≠НгБМгВєгГЉгГСгГЉгБІе£≤гБ£гБ¶гБДгВЛгБУгБ®гВВе§ЪгБДгБЃгБІгАБжШѓйЭЮи¶ЛгБ¶гБњгБ¶гБПгБ†гБХгБДгАВ
е≠¶зФЯжЩВдї£гБЂи™њзРЖеЄЂгАБж†Дй§Ке£ЂгАБдїЛи≠Јй£Яе£ЂгБЃи≥Зж†ЉгВТеПЦгВКгАБгВЂгГХгВІгБЃгГ°гГЛгГ•гГЉйЦЛзЩЇгБ™гБ©зµМй®УгВТйЗНгБ≠гБЊгБЧгБЯгАВе∞±иБЈеЊМгБѓгАБжЦЩзРЖжХЩеЃ§гБІзФЯеЊТгБХгВУгБЂдЉЭгБИгВЛгБЯгБЃгБЧгБХгВТзЯ•гВКгБЊгБЧгБЯгАВзµРе©ЪгВТж©ЯгБЂгАБйААиБЈеЊМгБѓиЗ™еЃЕгБЂгБ¶жЦЩзРЖжХЩеЃ§гВТйЦЛиђЫгБЧгАБзПЊеЬ®гБѓе≠РиВ≤гБ¶гВТж•љгБЧгБњгБ™гБМгВЙгАБжЦЩзРЖжХЩеЃ§гБ®гГХгГ™гГЉгБІгГђгВЈгГФйЦЛзЩЇгВТгБЧгБ¶гБДгБЊгБЩгАВ

FacebookгГЪгГЉгВЄгБІ
жЬАжЦ∞и®ШдЇЛйЕНдњ°пЉБпЉБ
 гГђгВ™гГПгВЪгГђгВє21гВѓгВЩгГЂгГЉгГХгВЪгБЃдїЛи≠ЈгВµгГЉгГТгВЩгВє
гГђгВ™гГПгВЪгГђгВє21гВѓгВЩгГЂгГЉгГХгВЪгБЃдїЛи≠ЈгВµгГЉгГТгВЩгВє